江戸名所図会自転車探訪(圏外の部)
| 最新更新箇所へ |
| 最教寺 |
|
この寺は図会の時代今やスカイツリー人気に沸く北十間川の南にあった。
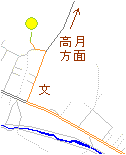 斎藤長秋や長谷川雪旦が歩き回らなかったここ八王子へは戦災を機に移転した。あの3月10日の大空襲に焼かれて多くの檀家や信徒が失われたことが要因だろう。そのほか揺光之部で書いた日の丸曼荼羅のことも尋ねたかったが、住職一家の子ども用ビーチサンダルなどが本堂前の階段に干してあっただけで、寺務所の電気は消えて誰もいなかった。
斎藤長秋や長谷川雪旦が歩き回らなかったここ八王子へは戦災を機に移転した。あの3月10日の大空襲に焼かれて多くの檀家や信徒が失われたことが要因だろう。そのほか揺光之部で書いた日の丸曼荼羅のことも尋ねたかったが、住職一家の子ども用ビーチサンダルなどが本堂前の階段に干してあっただけで、寺務所の電気は消えて誰もいなかった。ここを訪れるルートは選択肢がいくつかある。 JR青梅線拝島駅からのルート: 天権之部「瑞穂町(狭山池)へ」に続けての行程にできるルートである。拝島駅西口からそのまま西に進み睦橋で多摩川を渡って小川交差点で左折する。 小川交差点から寺までは、高月浄水場前交差点を右に行って滝山街道に出る100mほど手前で右に入るのが駅から5kmと短いが、次の二つのルートに比較して高齢者がチャレンジするには坂が急過ぎるのが弱点である。 また、左をとって最教寺から1.2kmほど東の滝山街道丹木町交差点に出るのは、短区間だが自転車を押したくなる区間があるのと、坂の始まりである高月第二橋付近は路外からの植生が路側帯を塞いでいて(都道の管理が良くない)車道本線にかなりはみ出すことになり、次の最短より1.3km延ばして6.8kmかけるメリットはあまりない。 JR五日市線東秋留駅からのルート: 南口から睦橋通りに出て左折して小川交差点を右折するのが最短で3.8km(高月第二橋まわりは5.6km)である。しかし、五日市線に入る電車は少なく電車待ちが多くなるうえに運賃がワンランク上がる。睦橋通りが緩やかな下り坂になることは長所である。 JR八高線小宮駅からのルート: 左入町東第二交差点までは、正面の新しい道をとって宇津木台団地の北を回っても、八高線の線路沿いに八王子方向に進んで右に折れて行っても距離は大差ない。前者は2度ほどのアップダウンがあるが、信号は少なく大型車はあまり走っていない。団地内をショートカットしようとすると道を間違えやすい。後者は信号が多いうえに右折の都度左路側に渡る時間ロスと何より八王子バイパスに絡んで滝山街道に右分岐すのが気を使う。しかし道は間違えようがない。 左入町東第二交差点から丹木町交差点まではほぼ直線で急坂は無いので駅と寺の距離5.9kmは納得できる。しかし、八高線は昼は1時間に2本の運転なので、しっかりと時刻表を調べて臨まねばならない。 JR八王子駅からのルート: 北にまっすぐ進み、ひよどり山道路トンネルを抜けるルートである。450mのトンネル区間の前後とも車道は自転車走行禁止であるので、狭い歩道で我慢することができれば、電車の便は良い。トンネルを抜けた後車道歩道とも余裕のある新滝山街道が完成して創価大学前を抜けて丹木町交差点に出られるようになったので、坂の程度も上二つのルートの中ほどで、7.1kmは苦にならない。 私が最初に訪れたのは、狭山池からのコースだった。帰りは小宮駅に出たが、途中で近道を探して見事に迷った。挙げ句は自転車を畳んで居る間に電車が行ってしまい30分以上駅にいた。 別ページの前駅物語の石神前駅周辺調査の際には、奥多摩道路と東京環状で左入橋交差点から一部完成していた新滝山街道を走り、創価大学手前で旧道を使って戻り、ひよどり山道路トンネルを抜けて八王子駅に出て帰った。 |
| 上行寺 |
|
この寺は、図会が紹介していた高輪に落ち着くまでに3回移転しており、移転癖が付いていたともいえる。
高輪からここ神奈川県伊勢原への移転は東京オリンピックの前年だが、オリンピックに伴う道路工事などに依るものではない。 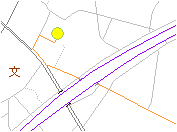 最寄りの電車駅は、小田急小田原線伊勢原駅である。駅北口を出て大山詣での鳥居を抜けて広い道路に合流、1km弱で国道246号との伊勢原交差点に出る。この交差点をそのまま渡って300m余りに「伊勢原高校入口」交差点がある。
最寄りの電車駅は、小田急小田原線伊勢原駅である。駅北口を出て大山詣での鳥居を抜けて広い道路に合流、1km弱で国道246号との伊勢原交差点に出る。この交差点をそのまま渡って300m余りに「伊勢原高校入口」交差点がある。駅からここまでの道は、湘南地域からの大山詣でのルートで、右の伊勢原高校方面の細い道は江戸からの参詣客が往来した道、つまり渋谷に通じる現246国道の原形である。この交差点を左折して緩やかに登っていく。東名高速道の防音壁が視界を遮る(左図右下)が、この下を抜けて側道信号を渡って100mで広い道に出る。 太平洋戦争で廃止されていたケーブルカーが昭和40年に復活して以降は、行楽シーズンになると参詣客というよりもハイカーを乗せたバスがこの道を往復するようになった。右歩道で50mあまり、コンビニの前まで進むと目の前で歩道がなくなり、上行寺の看板が立っている。右へ50mほどの右、つまりコンビニの裏に、図会が芭蕉の高弟宝井其角の墓所として紹介している上行寺がある。駅からは2.7kmの行程である。 寺には高輪から移された其角の墓があり、毎月句会が行われている。平成24年4月に私が訪れた直前に「其角忌」が催され、境内は俳画と俳句に彩られた雪洞が立ち並んでいた。本堂は、高度成長期を迎えた頃の未来にチャレンジする明るい近代的なデザインである。 駅との往復5km余りのサイクリングではもの足りないという向きには、平塚の湘南海岸まで上行寺から約12kmである。広い道を直進して南下すると伊勢原工業団地の東側にそれなりの坂があったりするが、駅へ戻ってのルートは高輪周辺よりも穏やかな相模平野西部の田園地帯でもある。 |
| 等覚院 |
|
この寺は、明治初期に茅場町薬師堂(智泉院)から薬師如来像を引き取った寺として天枢之部で触れた。所在地は天キ之部の五所権現(長尾神社)に最寄りだがその節に無理やり押し込まずにここで紹介する。
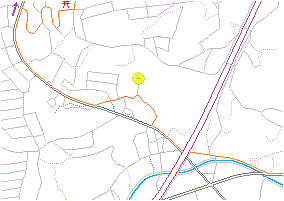 天キ之部で長尾神社南の住宅地内を蛇行して下ったのが左図左上の道ある。同部では↑に向かったが、等覚院へは逆に進む。500mほど左回りに下ると左斜めに等覚院に上がっていく道がある。何の表示もないので、地元の人に確認すると「神木不動ですね」と問い返された。最後は自転車を押して上がりたくなるが200mほどで登りつめ、等覚院不動堂の山門が聳えている(左図イメージマップ参照)。
天キ之部で長尾神社南の住宅地内を蛇行して下ったのが左図左上の道ある。同部では↑に向かったが、等覚院へは逆に進む。500mほど左回りに下ると左斜めに等覚院に上がっていく道がある。何の表示もないので、地元の人に確認すると「神木不動ですね」と問い返された。最後は自転車を押して上がりたくなるが200mほどで登りつめ、等覚院不動堂の山門が聳えている(左図イメージマップ参照)。山門からの境内(一部石段)の両側にはツツジが植えられていて、現代では「つつじ寺」としても知られているようだ。薬師如来像は不動明王像の前に置かれ、不動用王蔵は秘仏となっている。茅場町智泉院と連携した行事が現代も続けられている一方、勤行への信者の参加を受け入れたり、お堂をコンサートや集会に開放し、宗教サミットに日本仏教界の一員として参加するなどいわゆる露出型活動をしている。 帰路はそのまま戻るのも一法だが、左図右半分のように東名高速道路手前の神木交差点から平瀬川に沿った道に入り、殿下橋でバス通りに出て東へ進む。橋の先100m余を左に入ると等覚院が管理している「神木観音」がある。「不動ですね」と念を押された理由はこれであろう。 バス停を辿って東へ進むと寺から3km、橋から2.5kmで上でリンクした天キ之部の同じ節冒頭の東急溝の口駅に着く。寺から↑で戻る場合は、小田急向ヶ丘遊園駅(上でリンクした天キ之部の次の節)2.5km、JR宿河原駅(前同リンク節最後左折せず直進)2km、登戸駅2.6kmである。 |