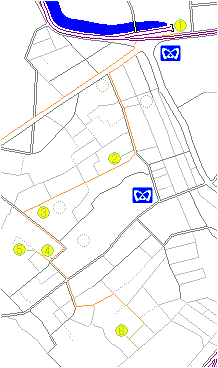江戸名所図会自転車探訪(天
| 最新更新箇所へ |
| 三沢川右岸 |
江戸名所図会天キ之部は、永田町の山王神社に始まって西に進み、甲州街道で多摩川を渡り、多摩川右岸を菅村まで下っている。
そんなわけで、このページは、川崎市の北東の端から始まる。
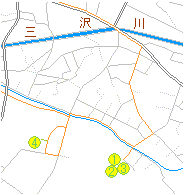
都心からは、京王帝都電鉄相模原線の京王稲田堤駅で降りる。都営地下鉄新宿線と相互乗り入れをしているので、都心から乗り換えなしで到達できる。
南口を出ると川崎(府中)街道である。左折して三沢川を渡るところにJR南武線稲田堤駅から出てきた道が来ている。ここの信号で右歩道に移り、次の右に入る道を採って進む。300mほどの右手前に外壁がオリーブ色のアパートのある十字路を右に入り、旧三沢川を渡って登ったところに法泉寺(左図①)、
法泉寺は図会に簡単な記述があるが、他の2社寺は描かれているだけである。図会以前の寛政年間の奉納という子之神社の石の鳥居の向きと福昌寺の配置は概ねの配置は良いとして、描かれたものと異なっている。鳥居は関東大地震で一度倒れたのではないかと思われ、福昌寺は低地にあって明治の大水害で被災して少し高い位置に移転改築したものだろう。 旧三沢川左岸を上って次に左に入り、少し入って右に上っていくと、薬師堂(左図④)である。図会は、法泉寺に数倍して由緒をコメントしているが、当時から寂れていた様だ。 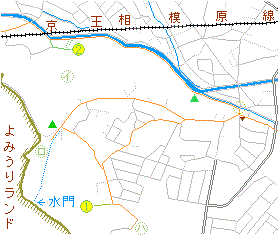 薬師堂を出て旧三沢川右岸を上る。道は川から離れるがそのまま進み、突き当り気味に交差点に出る(右図右)。その左手前(▼)に案内図がある。寿福寺(右図①)への住宅地内の通り抜けは判りにくいので、これを見て良く道順を確認しておくことをお勧めする。整備された道に惹かれてURの団地に入っても戻るしかないので要注意である。
薬師堂を出て旧三沢川右岸を上る。道は川から離れるがそのまま進み、突き当り気味に交差点に出る(右図右)。その左手前(▼)に案内図がある。寿福寺(右図①)への住宅地内の通り抜けは判りにくいので、これを見て良く道順を確認しておくことをお勧めする。整備された道に惹かれてURの団地に入っても戻るしかないので要注意である。そのまま道なりに仙谷の谷を前へ500mほど進むと右手に山が近づいてくる。当初の探訪ではこの辺から左に入って寿福寺へ行ったが、さらに100mほど進んだ右に多摩遊歩道の案内標識(▲)がある。山の中の小澤城址(右図イ)へはこの道と言うことで、再来訪の際に入ってみたが、道も周辺の樹木も殆ど手入れがされておらず、女子供や老人が立ち入るところではないという印象だった。 道の左の水路にはしっかりと水が流れており、左に広がる水田の水源として、
多摩遊歩道の標識の所まで戻り、反対側をのぼっていく。この道が吐玉水の図版中央に描かれている道ではないかと思われる。自転車を押さねばならないほどの急な部分もあるが、70才手前でも何とか自転車で上れるのは、健康な体質に生んでくれた両親とその後の家内の偏らない食事づくり、そして自分自身の努力の成果だから安易にバテていられないと言い聞かせてペダルを漕ぐ。道が左に折れる右に良く整備された境内の寿福寺がある。
図会が「眼界蒼茫として山水の美筆端に尽くしがたし」と記した光照崖は、左の坂を上り詰めた辺り(右図ハ)と思われるが確証はない。 現代の眼界には、URが日本住宅公団の時代に開発した住宅団地が点在している。 浅間(アサマ)山、展翼峰はこの道からよみうりランドにかけての山塊と思われる。帰路は、寿福寺前から150mほど下で右のしっかりした道に入ると、ブレーキのみであっという間に案内板のあったところに降りてくる。 交差点を左折して指月橋(「寿福寺」図版参照)を渡り、すぐ旧三沢川の管理用道路を入っていく。現三沢川との分流地点に来ると、左が小澤城址に至る遊歩道の入口(▲)で、道の先は三沢川サイクリングロードになる。寿福寺に行くときに右に眺めた小澤城址の山(浅間(センゲン)山?)を左に見て進み、都県境を過ぎて150mほどのところに、穴澤天神社の名の由来となった洞窟がある。 図会の時代既に、洞窟は崩れた後新に掘ったものと記されている。洞窟に祀られていた弁天は、神仏分離令で別当だった威光寺(次節)に移されたとのことだが、弁天洞窟として復活している。
なお、図会は穴澤天神社を谷(之)口天神とも書いている。 |
| 京王よみうりランド駅南+JR稲城長沼駅南 |
穴澤天神社から京王線を潜って北に出てすぐ左折、京王線と平行に進む。左に京王よみうりランド駅を見て100mほど先で南北に走る読売ランドへの道にぶつかって左折し、ガード下で狭い右歩道に移る。
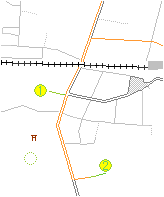 すぐに明覚寺(妙覚寺:当時からこの字で図会が間違えたようだ左図①)の墓地があり、これを過ぎて入口がある。ここの境内は広葉樹が多く、訪れたのは9月だったが晩秋には紅葉が素晴らしくなりそうなことを予感させてくれた。
すぐに明覚寺(妙覚寺:当時からこの字で図会が間違えたようだ左図①)の墓地があり、これを過ぎて入口がある。ここの境内は広葉樹が多く、訪れたのは9月だったが晩秋には紅葉が素晴らしくなりそうなことを予感させてくれた。この道は、信号が少なく逆方向からかなりの速度でトラックなどが下りてくるので自転車の走行にはあまり向いていない。しかし、気をつけてさらに進んで150mの左に威光寺(左図②)がある。
妙覚寺まで戻る手前の左に八雲神社がある。その南の駐車場の奥の位置に、前節穴澤天神社に合祀された 京王線から300m北に三沢川があり、整備されているサイクリングロードを西に進む。 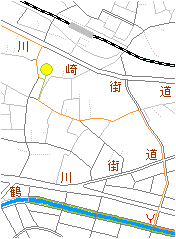 サイクリングロードを1km、5分ほど走ると、右手に赤い消防車が見えてくる。消防署を左に見るように右折し、鶴川街道(稲城市役所入口交差点)を渡り、次の十字路を左に入っていく。この辺はこれから回る府中市などよりも都心に近いのだが、市役所からも稲城長沼駅からも自転車で5分もしないところに梨畑が沢山残っている。
サイクリングロードを1km、5分ほど走ると、右手に赤い消防車が見えてくる。消防署を左に見るように右折し、鶴川街道(稲城市役所入口交差点)を渡り、次の十字路を左に入っていく。この辺はこれから回る府中市などよりも都心に近いのだが、市役所からも稲城長沼駅からも自転車で5分もしないところに梨畑が沢山残っている。曲がって道なりに2分ほど、右手に鳥居と石碑が立っている。青沼明神(現青渭神社:右図)である。社殿までは東側の道に平行して参道があり、途中に改めて鳥居がある。10月始めに訪れたところ、秋祭りに奉納相撲をしたらしく、土俵が荒れたまま残っていた。 境内から1宅地置いて北側には川崎街道(兼府中街道)が走っている。境内の遊具のところから西に抜ける横参道を出て右折し街道に出る。 電車で戻る人用には、街道を渡り、踏切を渡ってのJR南武線の稲城長沼駅(北口だけで南口はない)があるが、その後の都心への乗り換えは楽ではない。いっそ京王線に戻ったほうが料金も安い。右図の「鶴」の字の200mほど南に稲城駅がある。また、近年整備された川崎街道を本篇の出発駅の稲田堤駅まで10分あまり走るのも良い。 次節の関戸へ向かう。幅広く歩道を整備してある川崎街道を5分ほど西へ進むと、多摩川を渡るため府中街道が右に分岐する。この辺から上り勾配が感じられるようになり、以後2.5kmほどひたすら登る。電車での戻りを詳しく書いたのはその伏線である。しかし、速度を上げなければ私でも登りきれるし、広い歩道で市境の市立病院を過ぎると歩行者は少なく、すれ違うのは自転車ばかりである。 図会が次の関戸の一環で記している甚兵衛松があるという平臺は、この坂の南の稲城市の区域と思うが、調べきれていない。 |
| 関戸東西 |
ゴルフ場の間を走る川崎街道を上り詰めると、蓮光寺坂上交差点である。
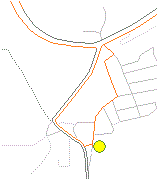 交差点の右は桜ヶ丘カントリークラブの入り口である。左は明治10年代に天皇が兎狩りなどで訪れた里山で、昭和5年に史蹟名勝天然紀念物保存法による聖蹟諸施設が設けられた地域である。交差点名は図会にも記されている地名だが、多摩ニュータウンの区域は「聖ヶ丘」や「桜ヶ丘」と昭和の右翼好みの地名になった。大正14年「関戸」駅として開業した駅(右上図左上隅)の名は昭和12年に現駅名となった。
交差点の右は桜ヶ丘カントリークラブの入り口である。左は明治10年代に天皇が兎狩りなどで訪れた里山で、昭和5年に史蹟名勝天然紀念物保存法による聖蹟諸施設が設けられた地域である。交差点名は図会にも記されている地名だが、多摩ニュータウンの区域は「聖ヶ丘」や「桜ヶ丘」と昭和の右翼好みの地名になった。大正14年「関戸」駅として開業した駅(右上図左上隅)の名は昭和12年に現駅名となった。
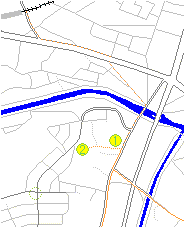 蓮光寺坂上交差点へ戻るのは同じ道を使わず、信号が無くより緩やかな坂の住宅地内を抜けて戻ることもできる。川崎街道は交差点から50m余りで自動車専用道のような構造になるので、左の側道をブレーキのコントロールのみで下る。右の中央車線はやがて高い擁壁状になるが、再びレベルが合ってくると「向ノ岡交差点」に出る。
往時の道筋を広げたような交差点から左を行き、ほぼ降り切って左(南)の多摩ニュータウンから流れてくる乞田川を渡るのが「行幸橋」である。(この間地図を大幅に略し、右図右下は行幸橋手前120mほどからルート図示)
蓮光寺坂上交差点へ戻るのは同じ道を使わず、信号が無くより緩やかな坂の住宅地内を抜けて戻ることもできる。川崎街道は交差点から50m余りで自動車専用道のような構造になるので、左の側道をブレーキのコントロールのみで下る。右の中央車線はやがて高い擁壁状になるが、再びレベルが合ってくると「向ノ岡交差点」に出る。
往時の道筋を広げたような交差点から左を行き、ほぼ降り切って左(南)の多摩ニュータウンから流れてくる乞田川を渡るのが「行幸橋」である。(この間地図を大幅に略し、右図右下は行幸橋手前120mほどからルート図示)図会は、逆方向から関戸より十六七町東の方 蓮光寺村を横切りて赤坂と号く 坂を登れば赤坂台なりと書いている。その道は、都立桜ケ丘公園(聖蹟記念館)前で右に折れて林の間を抜けてルートの向ノ岡交差点から200m程のところに降りてくる旧道である。ハイキングやサイクリングそのものを愉しむ人にはこちらがお勧めである。(逆の登りはどちらも、稲城側より相当きつい)
ところで、稲城からの山越えを回避した人は、府中を回っての京王聖蹟桜ヶ丘駅からになる。右上図左上隅が駅であり、西口広場からでも良いが、図に虎斑で示したのは、高架下商店街を自転車を押して東口に出るルートである。 道路に出て右100mの川崎街道に出たら左(東)に進んで200m余りの信号で街道を渡る。左斜めに入って来ると、旧鎌倉街道の大栗橋になる。橋からは200m足らずで延命寺入口である。 図会は延命寺の裏山が城山と書いている。延命寺の裏の道(桜ケ丘東通り)を登っていき、道が左に曲がって上りつめた感のある十字路になる。郵便ポストのあるこの十字路辺りが図会の時代土中から瓦礫が出ていた城山であろう。とりあえずルートから外す(右上図参照)。 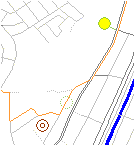 旧鎌倉街道を延命寺入り口から南へ600m足らずの右に熊野神社(左中図)がある。
熊野神社からさらに南へ200mで右に斜めに入っていく坂がある。立て札などの表示はないが、沓切坂とされており、多摩市役所の近くの沿道には小さな祠や地蔵がある。
市庁舎の辺りが古市場と図会が書いた所と思われるが、これまた何の痕跡もないので入らずに右へ右へと道を取る。
旧鎌倉街道を延命寺入り口から南へ600m足らずの右に熊野神社(左中図)がある。
熊野神社からさらに南へ200mで右に斜めに入っていく坂がある。立て札などの表示はないが、沓切坂とされており、多摩市役所の近くの沿道には小さな祠や地蔵がある。
市庁舎の辺りが古市場と図会が書いた所と思われるが、これまた何の痕跡もないので入らずに右へ右へと道を取る。
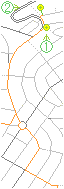 ぶつかって右へ進み、道が左へ曲がると道の両側は高級住宅地風だが、何とも坂のきつい住宅地になる。辻を二つも上がると気分を変えたくなるので右折する(左中図下部参照)。すぐに坂がきつくなるがやがて左に道は曲ってロータリー(右中図参照)が見えると楽になる。交番の東の道に入り、道なりに進んでいくと「いろは坂」のカーブが始まる。その右の急斜面緑地の階段のわきに天守台(左中図①↑先)の標柱がある。樹木が生い繁ったり、住宅に邪魔されて展望は効かないが、突き出した尾根の付け根であり、往時の重要な軍略拠点であったことは容易に伺い知れる。
ぶつかって右へ進み、道が左へ曲がると道の両側は高級住宅地風だが、何とも坂のきつい住宅地になる。辻を二つも上がると気分を変えたくなるので右折する(左中図下部参照)。すぐに坂がきつくなるがやがて左に道は曲ってロータリー(右中図参照)が見えると楽になる。交番の東の道に入り、道なりに進んでいくと「いろは坂」のカーブが始まる。その右の急斜面緑地の階段のわきに天守台(左中図①↑先)の標柱がある。樹木が生い繁ったり、住宅に邪魔されて展望は効かないが、突き出した尾根の付け根であり、往時の重要な軍略拠点であったことは容易に伺い知れる。いろは坂を1街区下った右に
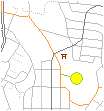 いろは坂を降り切って大栗川と川崎街道を渡ると京王聖蹟桜ヶ丘駅西口になるが、ルートが続かないのでロータリーに戻る。
手前で右に岐れて交番の南の道をほぼ真西に進むとT字路でぶつかる。これを左にとり、100mもしないで右下に降りていく分岐路に入ると、右の家並みの間に寿徳寺(左下図)の本堂が見える。図会の記述では延命寺の北方に寿徳寺があることになっており、移転の経緯の有無を尋ねようと思いながらそのままになっている。
いろは坂を降り切って大栗川と川崎街道を渡ると京王聖蹟桜ヶ丘駅西口になるが、ルートが続かないのでロータリーに戻る。
手前で右に岐れて交番の南の道をほぼ真西に進むとT字路でぶつかる。これを左にとり、100mもしないで右下に降りていく分岐路に入ると、右の家並みの間に寿徳寺(左下図)の本堂が見える。図会の記述では延命寺の北方に寿徳寺があることになっており、移転の経緯の有無を尋ねようと思いながらそのままになっている。寿徳寺から北に道なりに進んでいくと、バス通り(右下図左上端)を経て野猿(やえん)街道に出る。右方向(北)に進んで大栗川を宝蔵橋で渡って川崎街道に出る(左下図一宮交差点)。 川崎街道を戻るように右に向かって200mほどのところに「小野神社入口」と表示されている。これを辿って踏み切りを渡って進むと 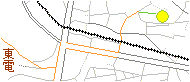 そのまま一宮大明神社(現小野神社:右下図)の鳥居にぶつかる。
そのまま一宮大明神社(現小野神社:右下図)の鳥居にぶつかる。図会は別当を置かずに、独立の宮司がマネージしていた格式の高い神社として書きながら、次節の松蓮(連)寺の建久(12世紀末)の経筒に一宮別当と銘されていることにも触れている。 しかし、図会の評価に反し明治の合祀令では郷社の扱いになった。後に府中で訪れる二つ(六所神社と小野神社)の神社の格付け争いのとばっちりを受けたと思われる。さらに不思議なことに、
小野神社からは一ノ宮交差点で再び信号を2回渡って野猿街道西側に戻る。交差点から100m弱の岐路を右に入っていく。左に直進すると東京電力の研修施設のゲートが待ち構えている。この研修施設の敷地内に二王塚があったと思われる。 右の関戸天守台の図版は左奥(西方向)に二つの山塊を描き、その間に「仁王つか」とキャプションしている。 なお、小野神社から都心に戻るには、神社南の石畳舗装の道を東に行き、バス通りに出て2、3分で聖蹟桜ヶ丘駅である。 |
| 日野市南部(百草+高幡) |
行き交う車も無く、山村の風情すらある前節からの道を進み、「百草地区センター」で左に入る。しばらくは勾配が急だが、ほんの数十メートルだからたいしたことはない。道は一本道で、百草園通りに出る。
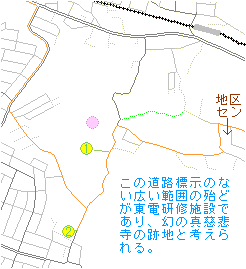
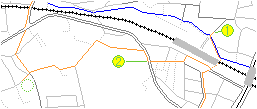
三沢交差点からほぼ1kmで多摩モノレール(絵になっているが、経営はピンチとのこと)の軌道下の高幡交差点に来る。交差点を2回渡って右歩道に移り、そのまま車道を渡ることなく京王高幡駅に向かう(左図右下)。駅ビルの右端に地下道があり、これを潜って北口に出る。
南口の賑わいが嘘のような雰囲気になるが、北口デッキの降り口のところで右に曲がると別旅明神(現若宮神社:右図①)である。金剛寺不動明王(すなわち高幡不動)の脇童子の像を一日で作って立ち去った僧がここで消えたので、この明神を作って「別旅」と名付けて祀ったというこれも習合ならではの言い伝えである。別当は当然金剛寺であった。 南口に戻って広場西の高幡不動参道商店街に入っていく。川崎街道に出ると今も正式名称が高幡山金剛寺(右図②)のパノラマが広がっている。震災や戦災を被らずに700年近く残された堂宇は、宗教を離れても価値のあるものである。後ろの山がさらに数百年前の開基の地とのことで、
右の図版左端に
二王門に向かって左手にある駐輪場に戻って境内に沿って反時計回りに道を辿り、境内から離れるところで右の道に入る。信号を渡って直ぐの左の梨畑が平惟盛之墓(風説)跡である。 図会には、番匠ヶ谷、木切り沢が短く紹介されている。名の由来は高幡不動建立の際の木材供給と大工などに由来するもののようだ。文永之碑のあった梨畑を教えてくれた付近の人のは、これらの沢に古い碑や祠があって将門の時代からの戦の死者を弔ったものと言われていた。しかし昭和30年代半ば、切り倒した山腹の生木や尾根を削った土石とともに沢を埋めて多摩動物公園までの住宅地が出来上がったとの話であった。 先ほどの信号に戻って左折、北に進んで交番のある交差点に出る。川崎街道はここで北に曲がっており、さらに立川に向かってお付き合いをする。 |
| 多摩川 |
図会は、芝崎村(立川市)と高幡(日野市)の間で、多摩川に触れ、右の5枚の図版を描いている。(沿岸の地名等は右図版其二までの付注をご覧いただきたい)
私のページでも「多摩川サイクリング特集」をすべきだろうが、多くの方が私より立派なページをネット上に設けているので、詳しくはそちらをご覧頂きたい。 「タマガワ」について図会がコメントしているポイントを私なりに口語文にする(括弧書きは原文にない)と次のようになる。 * この川は甲州丹波山(タバヤマ)に発し、武蔵国多摩郡丹波(タバ)村を経て流れており、「タバガワ」だったのではないか。 (現在も山梨県北都留郡丹波山村は存在するし、奥多摩湖の北東の山間の字名は丹波である。源流部分は一之瀬川だが、柳沢峠(甲州市塩山へのルート)からくる柳沢川との合流地点から奥多摩湖までは丹波川として河川管理され、小河内ダムで放水されてから下流が多摩川になっている。) * 万葉集で「多麻」、武蔵風土記残篇では「多摩」が(地名に)使われているが、(川は、)日蓮上人の記録では「田波河」、(この地を支配した)北條家の記録は「多波川」である。 * (歌人が)山城(野田)、摂津(三島)、紀伊(高野)、近江(野路)及び陸奥(多賀)にある玉川に合わせて(調布の)玉川とし、「六玉川」と称したので字を変えたのではないか。 万葉集に「多麻河泊爾 左良須・・・・・」というのがあり、麻布を川でさらしている(平地、最上流でも調布市付近の)情景を詠んだものである。これが多摩川(タマガワ)正統を主張する人の論拠になっている。 前々節の「多摩丘陵の地名」で書いたように「玉の横山」は具体的には八王子市域か多摩市域かの主張はあるものの、より下流の稲城市や川崎市から声は上がっていない。 上流から下流に進むに従って川の名前が変わっている例はいくらでもあ。地域名との関係では、下流の地域で上流の地域の名をつけて呼ぶのが通例である。代表例はわが国最長の信濃川で、信濃の国では千曲川など別の名で、下流の越後の国に入って「信濃から来た川」として呼ばれたものである。 歴史的には、地域社会の広域化や河川改修によって名称を変えることになり、その際に地誌的な意義よりもアピール効果を優先したものにしてきた例がある(代表例は江戸川)ことも考慮しなければならなくなっている。 |
| 立川駅南 |
前々節での交番付交差点を直進し、上って京王線を越えるとそのまま浅川を渡る。渡り終わって川崎街道は左斜めに入っていく。自転車向きでないこの道路とはここでお別れをして真っ直ぐ進む。国道20号(日野バイパス)を横切り、中央道を潜り、モノレールのある道に出てモノレール沿いに左折する。
左折して200mほどで甲州街道を横切って同じほど走ると道は右へ湾曲し、立日橋南という広い合流交差点に出る。鋭角な左折専用車道が分岐しているうえに橋を渡らない自動車が前方左分岐するので、自転車にはリスクが大きい交差点である。安全性重視で右歩道をルート紹介しようと思ったが、堤防道路から下りてくる道と分離している壁、歩道の大部分を占めているモノレールの橋脚が邪魔をしていて先の見通しは良くない。 橋の名は「タッピバシ」と読む。竣工して20年を越えたようだが、私のパソコンは津軽海峡の岬の名前しか変換してくれない。
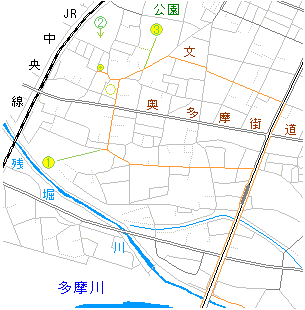 ひとつ下流の甲州街道の橋は日野橋、上流の新奥多摩街道のが立川橋だったのでこの名になったらしい。
ひとつ下流の甲州街道の橋は日野橋、上流の新奥多摩街道のが立川橋だったのでこの名になったらしい。 モノレール主体の設計のせいか工事がバブル経済破綻直後のせいか、
入口に戻って20mほどの左への道を辿る。奥多摩街道を横切った左手あたりに
戻って左寄りに道を採ると鳥居があり、諏訪社(現諏訪神社:左図③)である。参道も長く広い境内には、既述の八幡宮(現八幡神社)のほか稲荷神社、金毘羅宮、浅間神社、目の神様が合祀されている。境内北側の諏訪の森公園も第二次大戦前は境内であった。 諏訪神社東の道をいけば約1kmでJR中央線立川駅南口になる。継続ルートは神社東の小学校の南の道を進んでモノレール道に出て立日橋の袂へ戻り、多摩川添いのサイクリングロードを下流に向かう。 |
| 谷保へ |
多摩川サイクリングロードは、立日橋から日野橋までは堤防上、日野橋からは立川公園でもある河川敷を抜け、青柳地区で一般道に少し出てすぐに右の堤防道に入っていく。中央道の下を潜ると日野バイパスの石田大橋が見える。橋の手前で左に堤防を降りて石田大橋北交差点からバイパスの側道、歩道を進む。再び中央道の下を潜って進むと国立府中ICのランプが歩道を塞ぐ(左図左下)。
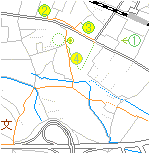 左には道が3本分かれているが中の道を進む。間もなく前方の集落の向こうに杜が見えてくる。谷保天神社(現谷保天満宮:左図④)の境内林である。昔農業用だった面影のある水路を渡ってすぐ右折して東へ150mほど進んで左に入る。
左には道が3本分かれているが中の道を進む。間もなく前方の集落の向こうに杜が見えてくる。谷保天神社(現谷保天満宮:左図④)の境内林である。昔農業用だった面影のある水路を渡ってすぐ右折して東へ150mほど進んで左に入る。もうひとつ用水路を渡って進むと右に谷保天神境内への裏木戸があるが、甲州街道に回って参拝することにして通過する。図会は、そこから50mの左からの丁字路のところに谷保天神の別当の
甲州街道を潜る地下歩道に入り、左の出口から出て八王子方面に100mほど下った所の右の窪地(左図②)に 坂を戻って地下歩道出口を通り過ぎて左の小路を上がると右手に瀧の院(左図③)がある。図会では天神の僧坊の一つが残ったものとしているが、掲示板にあった説明では廃寺となった安楽寺の坊としている。境内は無住で共同墓地に経蔵風の建物があるだけである。 甲州街道を少し都心方向に戻ってJR南武線谷保駅(左150mほど)からの道が出てきたところの信号を渡り、谷保天神社境内に入っていく。図会が本社右の岡に描いた稲荷神社と観音の位置には稲荷神社が残っており、その左の急な坂の下に本殿がある。杖を持った旅人が歩いている道は本殿と同じレベルに描かれている。つまり、この時代は先ほどの裏木戸もしくは現裏門辺りに甲州街道と神社入り口があったような配置である。先ほどの清水立場跡の状況からすると、甲州街道は低い位置にあったと考えられる。 裏木戸は、関係者出入り口のようなので裏門を出て先ほどの道を戻り、左にに道を採り、昔からの道独特のうねりを感じながら原則東南東に進む。これが往時の甲州街道だったかもしれない。 |
| 府中(西南部) |
前節の図の右端からすぐ日野バイパスの下を抜ける。300m余りでの幼稚園の先で小川(用水路)の左側の道に移る。右手の水田のはずれに風景に違和感を与えている4階建ての図書館がある。
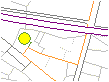 図書館を右にクランクして東南に進むと広い道になり、右がNECの社宅や工場の敷地になる。
図書館を右にクランクして東南に進むと広い道になり、右がNECの社宅や工場の敷地になる。NEC敷地に沿って走り続けると、六節前の関戸から北に延びてきた新鎌倉街道に出る。そのまま右歩道で関戸方面、南へ進み、中央道を潜る(左上図右上)。潜って100mほどを右に入って突き当たりの右に小公園があり、小野神社(左上図)が見える。図会は、小野県、小野牧の往時に比較すると僅に茅祠一宇で旧址と言うしかないと書いている。現状の方がまし? 図会は、多摩川を渡ってここと一宮大明神とを結ぶ神道が田畝の古道になっていると書いている。近年府中市が石碑を立てた「一の宮の渡」を経ていたのだろうが、両岸ともまともな道筋を辿りようもないほど耕地整理や区画整理がされている。
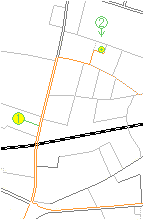 中央道を再び潜って進み、分梅駐在所交差点で鎌倉街道を右に見送る。ここから先が右の図版の陣街道である。坂を上がってJR南武線を渡って左の八雲神社の境内林が図会の天王森(左下図①)である。
中央道を再び潜って進み、分梅駐在所交差点で鎌倉街道を右に見送る。ここから先が右の図版の陣街道である。坂を上がってJR南武線を渡って左の八雲神社の境内林が図会の天王森(左下図①)である。塚状に盛り上がって描かれている部分は八雲神社本殿裏に残っているが、天王の森の背景である異形の神である牛頭天信仰が神仏分離令で排斥され、素盞雄神に置き換えて八雲神社を設けた際に、碑は北の街区道路際に移されたようだ。図会の時代には判読されていなかった碑の文面が豪族の墓であることを示すものと判り、文化財という扱いになっているようだ。 右の陣街道の図版に天王森とともに描かれ、次の三千人塚の項で記されている首塚(左下図②)は、一つ先の信号を右に入った住宅地内に祠として残されている。いつのまにか弁財天の碑が持ち込まれたり白狐の奉納があって、国家神道から外された神々の集結場所のようで、府中市の説明板も立っていない。 同じく胴塚は、陣街道を挟んで対称的な位置と思われるが、はっきりしない。信号から150m余り西を北に入った突き当りに篠竹の密生した塚風のものがあるが、これがそうかもしれない(自信が無いので地図表示しない)。 東に行くと十字に線路が交わるJR・京王乗り換えの分倍河原駅に自ずとぶつかる。行き止まり風になって左クランクで京王線のホーム北側踏切を渡って反対側に回り込んで北東側の改札になる。この駅の南側はJR南武線の定期券専用口だけで、バスはこちらで発着している。 バスでこの駅に来た老人や車いすの人は、三つ折りになっている斜路で南武線を越えて北東の改札に行かねばならない。 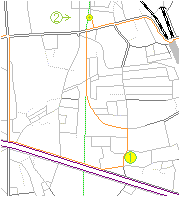 とにかく駅付近で自転車で南に渡る術は無いので、ここで電車に乗る人以外は分梅駐在所交差点まで戻って左折、鎌倉街道を東へ京王線を潜って税務署角交差点を右折する(右図左上部)。
とにかく駅付近で自転車で南に渡る術は無いので、ここで電車に乗る人以外は分梅駐在所交差点まで戻って左折、鎌倉街道を東へ京王線を潜って税務署角交差点を右折する(右図左上部)。ひたすら南へ進んで中央道の北側道を左折する。矢崎遊歩道という交差点を過ぎて間もなく左に岐れる道を採り、次の十字路を左折する。右手の小さな塚と青い石の碑が三千人塚(右図①)である。 これらの塚について図会は、新田義貞以来3度に及ぶ分倍河原の戦いで討たれた人の墓と考察している。府中市の立札には、昭和30年の発掘調査の結果、江戸時代の記録が出たので伝承されていた戦国時代のものではなく、江戸時代のものだと書いてあるが、私は江戸時代の新田開発などの際に、分倍河原のあちこちにあった戦死者の墓をまとめたのではないかと考察する。平和な江戸時代に新たにこのように塚を設ける動機はほとんど考えられないし、高幡不動の裏山を荒っぽく造成した昭和30年代よりは死者への弔いの気持ちは強かったろうから。
三千人塚から北に進んで最初の十字路を左折すると、道は右に湾曲し、南北一直線の緑道と一緒になる。そのまま北に進んで200m余りで鎌倉街道に出る。これを渡って右20mにある道を左に入る。左の緑道との間の狭い緑地帯の中に津保の宮(現坪宮:右図②→先)がある。図会は六所の宮(現大国魂神社)大祭の際には神官が乗馬して訪れると書いているが、いまでも続いているのだろうか。
鎌倉街道通りに戻って左折、次の信号で右歩道に移って府中本町駅の橋上駅前に漕ぎ上がる。往時の街道は、武蔵野線のトンネル入り口付近を通って左に曲がっていたのだろう。 |
| 府中(競馬場周辺) |
府中本町駅を東に降りきると府中街道である。これを右折して100mほどの左に金毘羅神社の階段がある。
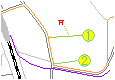 この位置は図会が観音堂を描いている。神社から明光院(左図①:現妙光院。図会のミス?)へは階段が付いており、習合の形態を残している。その明光院の入口は、府中街道をさらに50mほど下ったところにある。裏に広がる墓地は大国魂神社境内に達している。
この位置は図会が観音堂を描いている。神社から明光院(左図①:現妙光院。図会のミス?)へは階段が付いており、習合の形態を残している。その明光院の入口は、府中街道をさらに50mほど下ったところにある。裏に広がる墓地は大国魂神社境内に達している。明光院の直ぐ南は、用水路を隔てて安養寺(左図②)になっている。境内には小さな鳥居があるが何を祀っているかは明確でなかった。
ぐるっと(境内を通り抜けて)東側に回り、明光院裏までいくと、ハケ下遊歩道というような道がある。この遊歩道と競馬場周りの広幅員道路とが一緒になる所に「天神橋」という案内板がある。前節の谷保天神下から辿ってきた用水路が図会で代小川(しろこかは)と書かれているもので、これに蓋をしたものが遊歩道であることを説明している。しかしなぜか「ダイショウガワ」とカナを振っている。 代(シロ)掻きと密接な関係のあったもので、音読みされるべきものではない。国立市内では「下の川(シモノカワ)」と「ハケ下の川」あるいは「(上流の)矢川から分流した川」の意味で使われていたようだ。 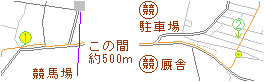 この南側に有ったと思われる石塚社は、競馬場を設けた際に、交差点から左上のハケ上に上がったところの日吉神社(右図①)に合祀されたとのことであるが、神社の表示は明確でなかった。なお、次節で紹介する図版の六所宮田植の現地はこの南の競馬場用地そのものと思われるが、手掛かりは得られていない。
この南側に有ったと思われる石塚社は、競馬場を設けた際に、交差点から左上のハケ上に上がったところの日吉神社(右図①)に合祀されたとのことであるが、神社の表示は明確でなかった。なお、次節で紹介する図版の六所宮田植の現地はこの南の競馬場用地そのものと思われるが、手掛かりは得られていない。競馬場通りを東に進み京王線府中競馬場正門駅からも設けられている立体歩道の下を抜けて600mほど進むと、道の向こう(右)は厩舎、左は駐車場になる(右図)。 ここで通りは京王線東府中駅に向けて上る競馬場通りと下って多摩川に近づいていく道とに分かれる。後者を辿り、300mほどで左に入って突き当りが石塚社と並べて記されている瀧の社(現瀧神社:右図②↓先)である。前節の坪宮よりはやや広いが、ハケに設けられた小さな神社で、町内会が管理しているらしい注意書きがいくつかある。 直ぐ裏のハケ上の道に出て左にある住宅地内を右に抜けている道を入っていく。 |
| 府中(甲州街道逆戻り) |
道は東府中駅にぶつかるので、左折する。駅西では踏切を渡らずに競馬場通りを右クランク気味に渡って線路に沿って西へ進んで、次の踏切で旧甲州街道に出る。
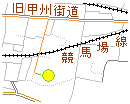 350mほどのところに「武蔵国八幡宮」の大きな石碑と、その手前に銅製の碑板がある。八幡宮(現八幡神社:左上図)の入口である。
350mほどのところに「武蔵国八幡宮」の大きな石碑と、その手前に銅製の碑板がある。八幡宮(現八幡神社:左上図)の入口である。 図会は、甲州街道八幡宿の道より左にありと書いている。八幡宿は、旧府中町の時代から平成元年まで旧甲州街道沿いの地名になっていた。宿場があったのではと思っていたが、明治初年の府中町の字名が地図で示されている入口手前の碑板で謎は解けた。
それによれば旧甲州街道から離れた八幡神社周辺の境内だけが「八幡宿」で、この長い参道を図会は「宿の道」と書いたのである。
京王競馬場線に沿って左上図の左外に出れば、府中競馬場正門前駅である。(左上図下部の広幅員道路は、前節右図で省略した部分である。)
旧甲州街道に戻って西へ800mで武蔵国総社六所明神社(現大国魂神社:右図①)になる。
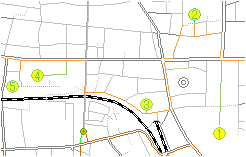 ここから左右に脇参道があるので、境内通り抜けの町の人が左右に往来している。図会はこの参道の樹林が渡り鳥のねぐらになっていると書いているが、現在では甲州街道の北側に整備されたケヤキ並木が初夏には境内以上に鮮やかな緑を提供している。
ここから左右に脇参道があるので、境内通り抜けの町の人が左右に往来している。図会はこの参道の樹林が渡り鳥のねぐらになっていると書いているが、現在では甲州街道の北側に整備されたケヤキ並木が初夏には境内以上に鮮やかな緑を提供している。 図会は馬市と馬場に触れている。
左右の脇参道それぞれの外に1条ずつと正面の鳥居(華表)の外に2条の馬場が設けらていた。馬市の開催を五月三日の駒くらべから九月晦日までと定めた制札は正面に残っているが、今は浅草と麻布の馬市がその役割を担い、担当の馬口労がセレモニーとして参拝にくるだけだと書いている。
でもこのセレモニーが競馬場を目黒からここへ移させた重要な動機になっている。ケヤキ並木はその2条の馬場跡である。 旧甲州街道を渡ってケヤキ並木に入り60mほどを左に曲がる。右手の2基の立体駐車場の向こうが称名寺(右図②)の正面である。寺の直前から右に抜けて旧甲州街道に出る。
すぐ右の市役所前交差点を南に入ると左に市役所があり、ここに 次の信号を右に渡って左先が鎌倉街道の旧道と思われるが、行き止まりに等しくなっている。直進する狭い道を上った右に善明寺(右図③)がある。寺の真下はJR武蔵野線のトンネルである。図会で六所明神社の項に書かれている恋ヶ窪由来の阿弥陀如来銕像は、神仏分離令でこの寺に移されている。 寺から先は遊歩道になっているが、JR南武線沿いに通り抜けると前々節で走った南北の遊歩道併設道路に出る。ここに高安寺(右図④)の裏木戸からの道があるが、普段は門は開いていない。右折して旧甲州街道に出て左折すると100mも行かない左にちゃんとした入口がある。 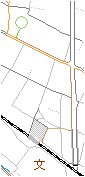 入ってそのままの突き当りに図会が描いている七観音(現観音堂:正面は裏木戸側)がある。この位置も含め、観音堂手前の右に山門が有ってその奥に寺の本堂が有る配置は江戸時代からのもののようだ。
入ってそのままの突き当りに図会が描いている七観音(現観音堂:正面は裏木戸側)がある。この位置も含め、観音堂手前の右に山門が有ってその奥に寺の本堂が有る配置は江戸時代からのもののようだ。藤原秀郷霊祠(現秀郷稲荷神社:右図⑤)へは、一般参拝人が入り難い左(南)側の墓苑内に参道風の直線の通路が残されている。習合と言われるのを避けた工夫とも感じられる。なお高安寺入口から180mほどにある高安寺保育園入口の未舗装の細い道を入っていくと秀郷大明神社の前に出る。 保育園入口から西へ1km足らずで現甲州街道に合流し、本宿交番前交差点で関戸からの新鎌倉街道を渡って200m余りの右に熊野神社(左下図)がある。左車道で行くと一旦通り過ぎて西府2丁目の信号で戻ることになるが、右歩道は狭いのでやむをえない。 図会に記されている弥勒寺がこの神社の別当で、右の図版「総図」には共に描かれている。方位は合っているものの善明寺や高安寺との距離は間に霞をたなびかせて描いてあっても腑に落ちないし、石張りドーム状のカバーを掛けた神社裏の古墳との関係も理解できない。本当に図会が描いた弥勒寺と熊野神社がこの辺だったのか心配になっている。 次節の国分寺へ出なおす人には、本宿交番交差点から右歩道で南200mの新鎌倉街道西にJR南武線の西府駅がある(虎斑のルート)し、さらに戻って高安寺保育園手前を右折すれば分倍河原駅である。続けて走るには神社西の交差点を北へ進む。 |
| (西)国分寺 |
この地域は前節で京王府中駅から都心に戻り、別の機会にJR中央線西国分寺駅からアクセスするのが無理がない。
ところで図会は、国分寺と府中の間で古今の詩歌、紀行を引用して武蔵野に紙面を割いている。江戸の街を含む東西十三里南北十里は曠野蒼茫だったが、開発が進んで往古の風光これなしと書いている。そんな中紫草と逃水を項立てし、 紫草は最上の色である紫の原料で江戸むらさきの名もあることを述べ、逃水は2説あるが蜃気楼とするのがよろしかるべきと書いている。 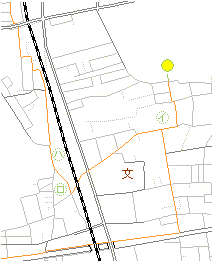
前節熊野神社西の道を600m余り北へ進み、左に高圧線の鉄塔が建っている信号に来たら右折し新鎌倉街道に出て左折する。東八道路の暫定終点の交差点である次の西原一丁目交差点で右折、東八道路を東へ進む。
600mを過ぎると前方で東八道路がJR武蔵野線の下を深く潜っているのが判る。手前の信号のところからの左歩道が潜らずに高架下を抜けているのでこれを進んで府中街道の信号を渡る。(左上図下部中央)次の左に入る道を北に進む。
右クランクで進むと国分寺(左上図)の山門になる。左奥の仁王門と薬師堂は石段込みで図会がが描いた配置で残っている。薬師堂前から細い道で通じている西隣りの八幡神社もほぼ同位置だが東向きから南向きになっている。その周りに合祀(?)されていた疱瘡神などの痕跡はなく、忠魂碑や戦勝の碑が目立ち、村を挙げて郷社からの社格昇進に努めたつとめた痕跡が見えるだけである。 国分寺は、図会の時代には再建されて6,70年の比較的新しい寺だったせいか、往古を懐かしむ記述が多く当時の状況描写は乏しい
国分寺旧跡に戻り、そのまま西(南)へ進んで府中街道とJR武蔵野線を渡ると右手が開けている。この区域が国分尼寺跡(左上図ロ)とのことだが、図会は全く触れていない。
そのまま道を進むとミニ開発的な住宅地に入る。とにかく北へ進むと武蔵野線を跨ぐ東西の高架道路にぶつかるが、その下を抜けてさらに進むと西国分寺駅南口に出る(左下図下部:冒頭に書いた無理のないルートはここからスタート)。  駅前広場の手前で右折してJR武蔵野線を潜って府中街道に出て左折する。駅北口からの信号を東に渡り、そのまま進み、階段を下りる。この階段までの間に
駅前広場の手前で右折してJR武蔵野線を潜って府中街道に出て左折する。駅北口からの信号を東に渡り、そのまま進み、階段を下りる。この階段までの間にこの道は右50mほどで中央本線で断たれているが、この辺が阿弥陀坂と考えられる(図会の記述富士見塚より十三町あまりと北へ向て下る坂と一致する。) 階段を降りたついでに、自転車をぶらさげて向かい側の林に入っていく。父の後に付いて山へ入っていた頃、林は空が見えなくなったら手入れが必要と教えられたが、富士見塚と言いここと言い、ひょろひょろの木が天空を覆っているのは本来の里山の姿ではないことは若い人たちに伝えたい。 林の東寄りにある北に出る踏み分け道を出ると、右に姿見の池(左下図①)がある。
北へ進んで緩やかに坂を上がった信号の右に熊野神社(左下図③)がある。西のほうから拡幅された道路が来ており、ただでさえ短冊状の境内がさらに細くなりそうである。 右の恋ヵ窪の図版ではさらにその後ろに八幡宮、傾城(ヶ)松そして富士見坂が描かれている。そして牛頭天がタイトルに列記されていて記述でも注記されているが、いずれも現状(場)を確認できない。 熊野神社の北の坂を東へ上がり、西武国分寺線の踏切を過ぎると、右は日立の中央研究所の広い敷地になる。描かれているほどの小高い岡ではないが、上記中この中に取り込まれたものも有りそうだがパスする。研究所の敷地が終わる所を右折して南に進んでJR中央本線を渡り、左折すると国分寺駅南口に出る。 |
| 多磨霊園周辺 |
前節国分寺駅駅前からは、広場左(東)の銀行ところから南に入り、道の左の公園が終わる辺りから道は右に曲がるとともに下っていく。下りきったところを右から左に流れているのは、武蔵野を代表する川、野川である。野川を渡って1km足らずで、前節で走った東八道路に出るので左折する。東八道路を走ること3km手前の前原一丁目交差点で道の右手は多磨霊園小金井門入口になる。
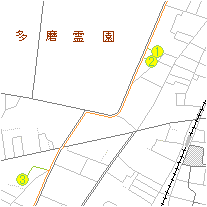 多磨霊園周辺は関東大震災以降の移転寺院ばかりで、図会の時代には耕されてもいない武蔵野の森林であった。幡随院を天権之部から外して本節に含めて移転寺院巡りとすることも考えたが、改めて武蔵小金井駅からスタートする場合の参考に留める。駅から南への小金井街道の前原坂下交差点(幡随院前から東200mの立体交差から南100mあまり)を左にとると、上述の前原一丁目交差点多磨霊園に出る。
多磨霊園周辺は関東大震災以降の移転寺院ばかりで、図会の時代には耕されてもいない武蔵野の森林であった。幡随院を天権之部から外して本節に含めて移転寺院巡りとすることも考えたが、改めて武蔵小金井駅からスタートする場合の参考に留める。駅から南への小金井街道の前原坂下交差点(幡随院前から東200mの立体交差から南100mあまり)を左にとると、上述の前原一丁目交差点多磨霊園に出る。多磨霊園の中を抜けていくこともできるが、オーソドックスに公道を行くとする。多磨霊園の北東の角の多磨2丁目交差点を右折して直線約800mの左に、揺光之部の本所から移転してきた 引き続き南に進み、道なりに右に曲がると多磨霊園の正面である。正面で参道を南に進み、次の信号で右歩道に移る。70mほど先にブロック塀が道に突き出すように立っていて、その裏側に浅草(新寺町)から移転してきた誓願寺(左図③)への入口がある。 「多磨霊園」という駅は南参道の先1kmあまりの京王線にあり、左図右端の駅は西武多摩川線多磨駅である。2001年までは「多磨墓地前」と言っていた。前年に東200mに東京外語大学が移転してきて、「外語大前」と変更しようとしたが、駅周辺に多い墓石業者の反対で実現しなかった。一般市民は「もう墓地前は勘弁してくれ」と言い、住居表示地名の今の名に落ち着いた。
参道を南に向かい、甲州街道に出たら左、都心方向に進む。(そのまま南へ行くと多磨霊園駅になる。左図右に出て外語大学の東の道を行き、味の素スタジアムのところで甲州街道に出る方法もある。)
|
| 調布市内 |
前節で二つのルートを紹介したが、その合流地点である甲州街道味の素スタジアム前交差点(スタジアムの客がと京王飛田給駅に行くための大型デッキが国道を蔽っている)から70mほどが東京オリンピックのマラソン折り返し点で、ポールと碑がある。この辺りから街路樹は歩道の幅を狭めるほどになっている。
1960年のローマオリンピックに殆ど無名で初出場し、アッピア街道の石畳をはだしで走って世界最高記録で優勝したアベベ・ビキラは、世界中からの重圧に負けたかのように東京オリンピックに向けて調子を落としていた。東京オリンピックで、アベベは後方からスタートしたが、この折り返し地点ではトップに立ち世界最高記録を更新して優勝した(オリンピック連続優勝はその後チェルピンスキーが果たしたが、世界最高ではなかった)。
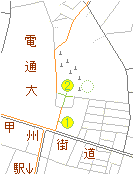 甲州街道を走るアベベの映像は今でもしばしば使われる。映像で折り返し付近は家並みが途切れて農地が広がっている。沿道には群集が写っているが並木は見えない。並木が無かったのではなく、人波に隠れるほどの若木だったのである。
甲州街道を走るアベベの映像は今でもしばしば使われる。映像で折り返し付近は家並みが途切れて農地が広がっている。沿道には群集が写っているが並木は見えない。並木が無かったのではなく、人波に隠れるほどの若木だったのである。 味の素スタジアム前から2kmに調布駅入口交差点がある。再出発の人は駅北口から400m足らずである。その一つ都心寄りの信号を北(左)に入って右に
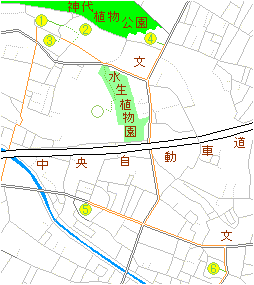 図会は、布多天神社は多摩川の岸頭にあって洪水に遭遇してここに移転した。そこには元天神という小祠があるとのことだと、旧地を訪れていないことを明かす記述をしている。左図下端から1kmほど南にオイルショック後に開発されたタウンハウス団地があり、その西側が「古天神公園」となっているので、この辺であろう。(ルート紹介略)
図会は、布多天神社は多摩川の岸頭にあって洪水に遭遇してここに移転した。そこには元天神という小祠があるとのことだと、旧地を訪れていないことを明かす記述をしている。左図下端から1kmほど南にオイルショック後に開発されたタウンハウス団地があり、その西側が「古天神公園」となっているので、この辺であろう。(ルート紹介略)図会はまた、布多里の項を立て、布田邑補陀郷という表現を示したうえで、(新田)→爾布多(ニフタ)→布多と変遷したのではないかと考証している。 布多天神西出入り口を出て北へ向かう。右の大正寺墓地が終わる所から右に入って進むと次の交差点で道は広くなる。400m程の中央高速手前の信号を渡ると再び狭くなるがそのまま高速を潜り(右図左端)、突き当ったら右のミラーのある道から緩やかな坂を上がる。左が修道院の無粋なブロック塀になると、正面に深大寺の境内林が見える。 バス通りを渡った先に深砂大王社(右図①)がある。東照権現と八剣権現を相殿と図会は書いているが、そんな風情はない。 本殿の右後ろからの境内連絡道を東へ行くと、神代植物園公園(図会はここに深大寺城址があったとしている)の深大寺出入り口から下りてくる道に出ると前は深大寺(左図②)の乾門である。入って右に天平時代の釈迦如来像と梵鐘(いずれも重文)を展示してある。宗教心の無い人でも歴史や文化を感じられる良い展示である。この境内は殆どの堂宇が図会描くまま残されている。 山門を出た左右には「深大寺そば」の店がひしめいている。図会は現在のバス通りから南に家並みを描き、高床の客間から水田を見はらすそば屋の様子を描いているので、明治以降そば屋グループに押し切られて寺が土地を貸したように思える。
一方、東へ進んで右の水生植物園は毘沙門天吉祥天社が描かれていた場所と思われる。また、水生植物園西の小高い所は、城山と呼ばれていた場所で、図会は難波田弾正城址としているが、調布市の調査ではこちらが北條氏綱に抗した上杉氏の出城の深大寺城の跡としている。
三鷹通りを下って中央高速を潜ってから最初の交差点の名は、図会にも出てくる旧村名の佐須町である。これを右折して200m先の左に虎柏(神)社(右図⑤)がある。 鳥居前は歩車分離のガードレールが塞いでいる。
佐須町交差点から300mほど東に柏野小学校があり、ここから南へ100mに祇園寺(右図⑥)がある。明治時代に板垣退助がこの寺で自由党員犠牲者の合同葬儀を行った際に植えた「自由の松」が立派に育っている。 柏野小学校の東北東300mの晃華学園内に狛江入道旧館地を示す祠が残っているとの市の資料を見たが、授業中でもあったので中に入らず、ここでもルートに乗せない。 というわけで、祇園寺前を南下し、野川サイクリングロードで甲州街道(馬橋西信号)に出る。 |
| 甲州街道沿いは移転寺院だらけ |
甲州街道に出て都心方向に1.2km、信号のあるつつじヶ丘交差点を右折し、商店街を抜けて京王線の踏切を渡って突き当たり、右折する。道なりに左に曲がった左が関東大震災後に上野広小路(アメヤ横丁)から移転してきた
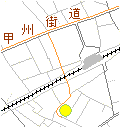 建物はしもた屋風で、道路向いが墓地でなければ通り過ぎてしまいそうである。入口には、終戦後の住職本多秋麿が作曲した「思い出のアルバム」の碑が建てられて現代の名所になろうとしているように見える。
建物はしもた屋風で、道路向いが墓地でなければ通り過ぎてしまいそうである。入口には、終戦後の住職本多秋麿が作曲した「思い出のアルバム」の碑が建てられて現代の名所になろうとしているように見える。 常楽院は調布市内なので、一旦は前節で紹介したが、甲州街道沿いの移転寺院として本節に移した。
御用とお急ぎの向きには踏切からホームの見えるつつじヶ丘駅がある。 甲州街道に戻って、都心に向かう。1.5kmほどで世田谷区に入り、さらに1kmほどにある左角がガソリンスタンドの烏山交差点を北(左)に入る。600mのところに中央自動車道があり、これを越えると右も左も寺院ばかりである。右上図のピンクで塗った範囲が寺の境内、墓地、斎場の用地である。
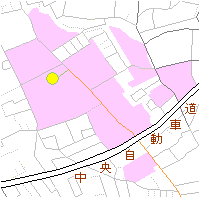 この地域は、関東大震災後旧地を区画整理事業に提供して移転してきた20余りの寺の団地である。
この地域は、関東大震災後旧地を区画整理事業に提供して移転してきた20余りの寺の団地である。新住居表示になるまでは烏山寺町と呼ばれ、甲州街道から入ってきた通りは寺町通りと呼ばれている。図会に登場した寺がいくつも移転して来ていて不思議でないのだが、 把握できたのは、地域のほぼ中央にある上野合羽橋から移転してきた
寺町通りを都合1km、再び甲州街道に戻る。信号を渡って真っ直ぐ旧甲州街道をさらに渡れば千歳烏山駅である。 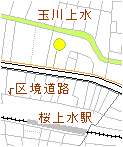 左折して都心に向かって2.5kmのところで中央自動車道からバトンタッチを受けた首都高速道路が、甲州街道の中に入ってくる。2、3分で交番があり、横断歩道橋があり、そして左先に覚蔵寺(左中図)がある。図会は、寺の名前よりも祀られている本尊の「鬼子母神」をタイトルにし、「下高井戸の道」と書いている。ここは旧甲州街道ではなかったかと思わせる。江戸時代末期この辺では、北から覚蔵寺裏の玉川上水沿いの道、現甲州街道、世田谷区と杉並区の境界になっている道と東西の道が三筋あり、図会が並べて書いている高井戸駅舎は南の道にあったようだ。
左折して都心に向かって2.5kmのところで中央自動車道からバトンタッチを受けた首都高速道路が、甲州街道の中に入ってくる。2、3分で交番があり、横断歩道橋があり、そして左先に覚蔵寺(左中図)がある。図会は、寺の名前よりも祀られている本尊の「鬼子母神」をタイトルにし、「下高井戸の道」と書いている。ここは旧甲州街道ではなかったかと思わせる。江戸時代末期この辺では、北から覚蔵寺裏の玉川上水沿いの道、現甲州街道、世田谷区と杉並区の境界になっている道と東西の道が三筋あり、図会が並べて書いている高井戸駅舎は南の道にあったようだ。覚蔵寺から都心方向500mあまりの下高井戸駅入口の信号で駅とは逆に左折する。すぐ甲州街道に平行な道があるのでこれを右折すると、ここにも都心から移転してきた寺が立ち並んでいる。 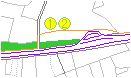 一番手前にあるのは永昌寺である。この寺を図会では名所と取り上げてはいないが、このページの最終節のひとつ前の麹町から杉並区和田に移転した寅薬師の開祖が住んでいたのが四谷塩町の
一番手前にあるのは永昌寺である。この寺を図会では名所と取り上げてはいないが、このページの最終節のひとつ前の麹町から杉並区和田に移転した寅薬師の開祖が住んでいたのが四谷塩町の この地域は明治初期から大正にかけて火薬庫が置かれていたとのこと。図会に登場しないのはもちろんだが、ひょっとすると米軍は古い地図に基づいて空襲をしたのかもしれない。
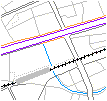
そのまま200mほど東へ進み、松原2丁目交差点で甲州街道に戻ってさらに都心へ2kmあまり、京王線代田橋駅の近くにその名のとおり代太橋があったはずである。
しかし、都心に向かって甲州街道を来て、玉川上水の交差部は完全に暗渠化していて気付かない。代田橋駅入口すら横断歩道橋が目印とあらかじめ言われていないと判りにくい。
この地域は図会でも五箇村の入会地(松原、赤堤、泉廻、代太)と書いていて、現在でも世田谷、杉並、渋谷の三区の境界点が環七の東にあり、そこから北東400m余のところに中野区の最南端がある。
甲州街道と環七との大原交差点まで行って街道の反対側を100mほど戻ると、左の並木とビルが途切れて玉川上水があり緑が残されている。このへんに代太橋があったようである。 図会が名所とした理由は、橋の上に土が盛って道幅を広くし、交通の賑わいを助けていることに注目したようだ。つまり当時「暗渠」の実例が珍しく、表す言葉も無かったためではないかと思われる。 引き続き甲州街道を都心に向かう。 |
| 山手通り(環六)南下 |
大原交差点から都心方向1kmほどに笹塚交差点があり、さらに進むこと1kmほどに甲州街道地下を走るようになっている京王線の初台駅入口があり、左向こうが新国立劇場になる。
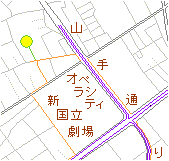 ここを左折(左図下部)して次の幡ヶ谷不動尊入口を右折してクランクに次の路地を抜けると、幡ヶ谷不動明王・荘厳寺(左図)の正面に出る。天権之部で現杉並区の名所の間に記載したのは整理ミスだとしたあの寺である。
ここを左折(左図下部)して次の幡ヶ谷不動尊入口を右折してクランクに次の路地を抜けると、幡ヶ谷不動明王・荘厳寺(左図)の正面に出る。天権之部で現杉並区の名所の間に記載したのは整理ミスだとしたあの寺である。門前を東西に走るいかにも昔からの雰囲気の残る道を山手通りに出て右(南)に向かう。山手通りは、地下に首都高速道路の環状線が平成20年に完成しているが、地上の歩道や側溝は平成23年10月現在まだあちこちで工事中である。 そんな山手通りを1.5kmほど走ってやや上りにかかった左に代々木(野)八幡宮(右図①)の鳥居と石碑がある。通りに面して立つ鳥居の後の急な石段を自転車を下げて上り、直進30mの左に再び鳥居が立ち、本殿正面からの参道になる。
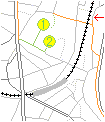 別当だった福泉寺(右図②)はぴったりと境内を接し、神社の二つ目の鳥居の脇から出入りできるようになっている。図会が描いた東の石段は自動車用の通路になっていて近代的なデザインになっている寺の本堂は南を向き、表札が南側の狭い道路側にある。神社本殿裏の自動車用通用路を使って北の坂を下りて東(右に)向かってさらに坂を下りる。
別当だった福泉寺(右図②)はぴったりと境内を接し、神社の二つ目の鳥居の脇から出入りできるようになっている。図会が描いた東の石段は自動車用の通路になっていて近代的なデザインになっている寺の本堂は南を向き、表札が南側の狭い道路側にある。神社本殿裏の自動車用通用路を使って北の坂を下りて東(右に)向かってさらに坂を下りる。小田急線の踏切を渡っての南北の道は暗渠化した河骨川の流路であり、すぐ北(右図←)には小学唱歌「春の小川」の碑がある。ここは右の図版右端の位置に相当し、福泉寺前で左から冨ヶ谷川(現代々木八幡商店街)が合流して宇田川になって手前(渋谷方面)に流れる様も描かれている。 代々木公園西側の道路に出て右に進み、代々木公園交番前交差点を左折して公園内を抜けてJR山手線原宿駅に向かう。 |
| 千駄ヶ谷 |
代々木公園を抜け、大正年間造営の明治神宮をやり過ごし、原宿駅前で左折して300mあまり山手線に沿って走る。
二つに岐れる右の広いほうの道(50年前に国立霞ヶ丘競技場と代々木体育館とを結ぶために整備したオリンピック道路)を進む。明治通りに出、左折して「千駄ヶ谷三丁目」交差点で右折して緩い坂を登っていく。この千駄ヶ谷駅に向かう道は、往時原宿村と大窪村を繋いでいた古道でもある。
ほぼ上りきった信号の無い交差点を右折(左図左)するとすぐ右に将棋会館があり、その先左手が千駄ヶ谷八幡宮(現鳩森八幡神社:左図①)経営の幼稚園になる。 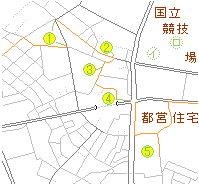 さらに進んでの交差点左側に神社の鳥居があり、走ってきた道を戻るかのように参道がある。
さらに進んでの交差点左側に神社の鳥居があり、走ってきた道を戻るかのように参道がある。境内には、本殿はもちろん図会が描いた浅間神社と富士塚、甲賀稲荷さらには神輿蔵が移改築されたとはいえ残されている。
その先の裏門を出ると「鳩森八幡神社前」という名の五叉交差点で右向こうが千駄ヶ谷駅への道である。交差点右の広くない方を入って坂を下って行く。この道が往時は江戸から千駄ヶ谷村の中心地の千駄ヶ谷八幡宮への道だった。 現れる左の築地塀は聖輪寺・千駄ヶ谷観音堂(左図②)のものである。聖輪寺の先10m余りのところから右に入って戻るように上がって直ぐ左に入る。右手が千駄ヶ谷八幡宮の別当だった瑞円禅寺(左図③)である。 瑞円寺の駐車場入口の向いの小路を入って道なりに進むと、新日暮里・仙寿院(左図④)の境内に横からぶつかる。この名所名は、「シンヒグラシノサト」と言い、図会はゆったりした庭中図を描いている。寺の縁起を記した立て札には「火災とオリンピック道路で見る影も無くなった」と書いてある。しかし、図会の絵と突き合わせると、現在墓地下を潜っているオリンピック道路は鬼子母神などがあった場所で、新日暮里は瑞円禅寺との間の土地である。 新日暮里の部分の消滅は明治以降の火災の際に土地を売らざるを得なかったのと、東京の人口増加に伴う墓地の拡大ではなかったろうかと感じられる。 仙寿院を正門から出て下りると外苑西通りである。この地下にある下水道幹線が新宿御苑を水源とする渋谷川の姿である。聖輪寺から東へ来ての交差点の名は「観音橋」で、空襲で焼失した千駄ヶ谷観音の名残となっている。一つ南のオリンピック道路との交差点の「仙寿院前」で、対角の街区に渡る。 この街区には都営住宅があったが、2020年東京五輪に向けての新国立霞ヶ丘競技場用地として撤去された。街区の南に6,70m回り込んで右に上がって100mほどに竜岩寺(現龍巌禅寺:左図⑤)がある。境内参道には古木が残り、図会描くところに似ている芯留めの松があったりするが、墓石の海に浮かぶ松島といった風情である。
さらに100m余り南に、原本でひとつ後の分冊で紹介されている青山熊野神社がある。
「仙寿院前」に戻った向こうの国立霞ヶ丘競技場の西側部分(渋谷川沿い)には、
なお、図会は権太原(現権田原)の
オリンピック道路の公園内終点の日本青年館前交差点を左折し、国立霞ヶ丘競技場に沿って絵画館裏の道(マラソンのゴール前走路)で信濃町駅に向かう。 本節と次節を繋ぐルートは、都営住宅跡地を含め2020年東京オリンピックに向けての国立競技場の解体、新築が完了するまで使えなくなっている。
|
| 南元町・若葉・須賀町 |
絵画館付近から信濃町駅へは歩道橋でないと渡れない。自転車はJR中央線の北に渡って慶応病院角の信号で渡る(左図左端)。
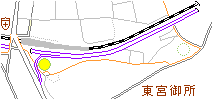 信濃町駅の南直ぐにある首都高速道路の信濃町ランプ下を抜ける道を下りていく。高架の真下から左に入るのが一行院(左図)である。現代は千日谷会堂といったほうが通じる。昭和30年代にここの墓苑のビル化を提案したと言っていた役所の先輩はここで告別式が行われ、自ら関与したビルの中で永眠している。その先輩から聞かされた「信濃町」「千日谷」の由来も図会にみんな書いてあった。
信濃町駅の南直ぐにある首都高速道路の信濃町ランプ下を抜ける道を下りていく。高架の真下から左に入るのが一行院(左図)である。現代は千日谷会堂といったほうが通じる。昭和30年代にここの墓苑のビル化を提案したと言っていた役所の先輩はここで告別式が行われ、自ら関与したビルの中で永眠している。その先輩から聞かされた「信濃町」「千日谷」の由来も図会にみんな書いてあった。微妙にうねっている道を東へ進み、右へ分岐して少し上って権田原交差点からの道に出て下る。右の向こうは東宮御所である。御所と迎賓館の間の鮫が橋門のところで左折した先の公園あたりに
江戸時代でも重要拠点は町普請が行われ、直線の広小路や火除け地が整備された。その他の区域は自然地形を大きく変えることなく、庶民が住み着いて世界最大の江戸の街が出来上がった。本節は谷を中心としたそんな街がそのまま残っている地域である。  現代では公明党本部と創価学会の聖教新聞本社のある地域となっている。
現代では公明党本部と創価学会の聖教新聞本社のある地域となっている。首都高速道路とJR中央線の下を潜って進む。道の左右は、建築基準法の都市計画規定を構造規定なみに厳密に適用すれば建て替えが認められない狭い路地によってのみ奥に入れる漁村集落のような密集地である。 左から坂を下ってくる真っ直ぐな道との丁字路を過ぎると、正面に4階建ての各階に幟旗がはためいているビルが見える。汐干観世音菩薩・真成院(右図①)である。江戸時代から境内の小さかったこの寺は、現東宮妃の先祖が世話になった越後村上藩主が関が原の合戦に出向く際にこの寺に預けた観音像が本尊となっている。 丁字路に戻り、右折して坂をほぼ上がりきった右が妙典山戒行寺(右図②)である。図会は、真成院前の観音坂から真っ直ぐの道がこの寺の石段に通じているように描いているが、その位置に現在する小路は行き止まりである。 西へ進むと整備された寺町が始まるが、最初の寺の勝興寺の角を右折すると下り階段の手前左に鳥居があり、駐車場になっている。その向こうにまた鳥居があり、奥に(四谷)牛頭天王社(現須賀神社:右図③)がある。図会が付注しているみこし蔵は複数の住宅と合築された有効利用(?)になっている。 また別当の
右図左上端から新宿通り(甲州街道)に出る50m余りの坂が津之守坂でである。 |
| 新宿〜四谷 |
図会の第九分冊(天キ編3冊目)は、四谷の概略を述べた後、前節右図を巡って本節に入り、天龍寺から前節鮫河橋へ行っている。
しかし、現代の道路ではそのようなルートは採りにくいうえに、都心勤務者が新宿副都心への仕事で本節の区域を通ることが多い。というわけで、自転車探訪のルートとしての連続性は切れるが、3節前の荘厳寺からそのまま甲州街道を東進するルートとして紹介する。 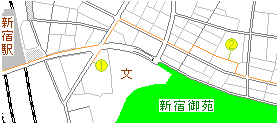
初台交差点から1.5km、甲州街道はJR山手線などを越えるため高架になり、その橋上に台風などで通勤電車が乱れるとTV各社がカメラを据える新宿駅南口がある。東へ坂を下るところは、自転車de雑学Ⅰの終着点である。
下りきって明治通りを右折して直ぐ左に護本山天龍寺(左図①)がある。境内に 明治通りを伊勢丹の角(ここが甲州街道と青梅街道の追分。現在は非北東角の交番名に名残)まで行き、新宿通りを右折する。新宿二丁目の大きな交差点を渡って次の信号で左折し直ぐの辻を右折して進むと霞関山大宗寺(現太宗寺、図会が点を付け忘れ?:左図②)の前に出る。境内に入って直ぐ右に江戸六地蔵のひとつがある。
伊勢丹の角から四谷四丁目交差点までが(四谷)内藤新宿と呼ばれた地区である。由来は自転車de雑学第Ⅰ篇で書いた。図会は芭蕉の「節季候の来ては風雅を師走かな」をキャプションにして、歳末の江戸の動きのある風俗・情景を描いており、駅馬がピタッと静止している広重の内藤新宿図と対照的である。  新宿通りに出て東へ進み、右手に新宿御苑の大木戸門がある次が複雑な交差点の四谷四丁目交差点である。
新宿通りに出て東へ進み、右手に新宿御苑の大木戸門がある次が複雑な交差点の四谷四丁目交差点である。気長に信号が変わるのを待って右(南)歩道に渡り、二つ目の小路が篠寺・四国山長善寺(現笹寺:右図)への入り口である。 笹寺から東、四谷三丁目交差点を過ぎて右二つ目に右に入るのが前節の日宗寺から上がって来る津之守坂である。 図会は、この四谷通周辺を忍原と言うのは、行田の忍城が廃されて御家人がここに移り住んだためと説明している。またこの間の北側は昭和18年まで四谷塩町と呼ばれていた。南側は図会が地名を残している石切町や伝町であった。 また、800m東の四谷見附橋を渡った左側に四谷御門跡があるが、図会は四谷という地域の説明に用いているだけで、御門を名所としては紹介していない。 |
| 加瀬山から新丸子 |
図会の第八分冊は、祐天寺から西南に進んで狛江で多摩川を渡り、南岸流域を辿って加瀬山まで行って丸子の渡に戻っている。
本節から新ルートとし、JR東京駅地下ホームから横須賀線で20分の新川崎駅を出発点にし、橋上の新川崎駅前広場から左に操車場を渡って直ぐの信号で左折、南下する。
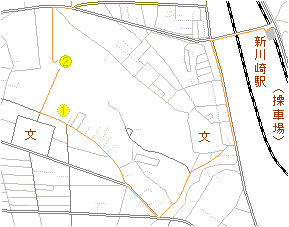
昭和55年に旅客駅が開業するまでここは広大な貨物列車専用の新鶴見操車場だった。操車場の周囲をマンション用に処分して併せ新駅を作るという国鉄の赤字解消策としての鉄道用地処分のモデルプロジェクトになった。
しかし、破格の処遇だった鉄道年金の是正にはOB労組一体の政治圧力で手を付けられず、このようなプロジェクトはしりすぼみになって清算事業団は赤字を殆ど埋められず(「事業団が無かったらもっと税金の注ぎ込みは増えていた」というのが政府答弁)、結局もっと大きな年金問題へのすり替えや国有地借用型の分割民営化で一般国民負担は不明確なままになっている。 道の左のマンション街(上記の操車場処分地)の途切れるところの信号で右の道に入り、小学校にぶつかったら左に直進する。川崎市の合同出張所を右に見て進むと「夢見ヶ崎動物公園入口」交差点に出る。これを直角に右折して北東に進む。
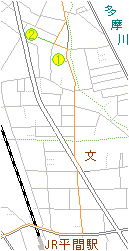 山の北東側に古い社寺があるが、図会は取り上げていない。
山の北東側に古い社寺があるが、図会は取り上げていない。社殿の裏から一旦南に回って北に下りる道は、かなり急だが自転車に乗ったまま降りることができる。 降りきって新川崎駅から西に伸びている道に出、右40mの信号で工場の左の道に入り、ガス橋通りに出て横須賀線を越える。府中街道を横切ってJR南武線平間駅北の踏み切りが右図下である。 踏み切りを過ぎて最初の信号を左折し、南武沿線道路を渡って小学校の脇を同じ北方向に進む。道路の右側が公園風になって直ぐ右が無量寺(右図①)である。図会では羽黒権現(現神明大神社:右図②)の別当と書いているが、絵では現在緑道となっている水路までを描きながら表されていない。その神明大神社は、無量寺の角を曲がって突き当たりにあり、描かれたとおりに脇参道もある。 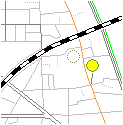 元の道に戻って北上を続ける。1km余りで左下図の下に出てくる。この辺の地名の「山王町」交差点から真北に参道がついているのが地名の由縁でもある山王権現社(現日枝神社:左下図)である。
元の道に戻って北上を続ける。1km余りで左下図の下に出てくる。この辺の地名の「山王町」交差点から真北に参道がついているのが地名の由縁でもある山王権現社(現日枝神社:左下図)である。次節で紹介する図会の図版「最明寺」に描かれている天神は、日枝神社に合祀されたとのことであるが、痕跡は見当たらなかった。 すぐ北の道路西側に新しい日枝神社社殿(左下図破線の○)がある。どうやら本来の境内はここまで広く、むしろ道が境内を分断したようである。せっかくだから地名として残されている天神を分祀しても良さそうだが、地名とのギャップが生ずるので許されないのだろう。 その先の東海道新幹線を潜って進む。 |
| 中原街道 |
日枝神社から400mほどで多摩川の堤防下道路に出る。右の最明寺の図版に描かれている丸子渡口の位置を眺めるには、堤防上の道路に上がる。渡し口は眼下の児童公園の辺りにあり、対岸はやや下流の真東の方向の東急多摩川線の沼部駅に近いところ(大田区多摩川丸子橋緑地)であった。現在代替して役割を果たしている丸子橋はこれより少し上流で多摩川に直角に架かっている。
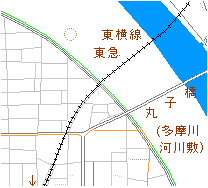 東詰めと異なり丸子橋の西詰めは信号が無く、堤防上の道路は一旦途切れる。
東詰めと異なり丸子橋の西詰めは信号が無く、堤防上の道路は一旦途切れる。
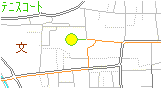 川に沿ったサイクリングは、堤防下道路か河川敷内を走ることになる(左上図参照)。
川に沿ったサイクリングは、堤防下道路か河川敷内を走ることになる(左上図参照)。
最明寺の図版に天神が描かれているが、左上図の点線の○の位置にあったようで、明治以降の多摩川改修に伴い、前節の日枝神社に合祀された。なお、「上丸子天神町」という付近の地名は残っている。 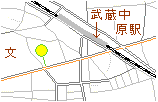 西明寺参道の途中から細い小路で中原街道に出て西へ1km、JR南武線武蔵中原駅南の高架下を過ぎて200mの右に大戸神社(左下図)がある。右の図版に描かれている天王の位置である。
西明寺参道の途中から細い小路で中原街道に出て西へ1km、JR南武線武蔵中原駅南の高架下を過ぎて200mの右に大戸神社(左下図)がある。右の図版に描かれている天王の位置である。実は次節で取り上げる橘明神社の西にあると書かれている大戸明神は見当たらない。牛頭天王を祀った神社が明治政府によって廃されたり変貌させられた経緯からすると、山中からここに大戸明神を遷座し、「牛頭天隠し」とでもいう措置をしたのではないかと推測される。 次節から以後登戸で多摩川を渡るまで山また山である。齋藤幸雄・長谷川雪旦がこの山また山を踏破したことを思い、時には自転車を押して上りながら負けじと頑張るしか無い。次節をスキップする人や一旦帰る人には、左下図のJR南武線武蔵中原駅か左上図↓先の東横線下丸子駅をご紹介する。 |
| 橘樹郡の中心地 |
中原街道を進み、高津区に入る表示があって間もなく千年交差点出る。渡って右歩道で左折し、左側がNTTのビルになったら右折する。中原街道からこの間の市民プラザ通が図会の府中道であり、右折する前後に舟田があったのだろうが、現在は家が立ち並んでしまっている。
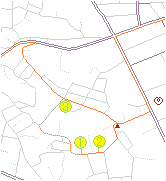 この地域の道は判り難いので、右折後100mほどのところ(▲)にある案内図で再確認するのが良い。左に上がって祠があるところを右に降りていくと橘明神社(祠)(現橘樹神社:左上図①)と前節でとりあげた大戸明神の別当だった蓮乗院(左上図②)があり、その向こうに橘樹神社がある。神社の西に少し林があるが、周囲の新興住宅地から苦情が来たのか墓に追われたのか地形の割りに境内林が乏しい。
この地域の道は判り難いので、右折後100mほどのところ(▲)にある案内図で再確認するのが良い。左に上がって祠があるところを右に降りていくと橘明神社(祠)(現橘樹神社:左上図①)と前節でとりあげた大戸明神の別当だった蓮乗院(左上図②)があり、その向こうに橘樹神社がある。神社の西に少し林があるが、周囲の新興住宅地から苦情が来たのか墓に追われたのか地形の割りに境内林が乏しい。
地図で見ると、橘姫神廟(現富士見塚:左上図③ 図会は橘明神より東としているが、立札や市の資料はこことなっている。)へは左回りが順路(虎斑で表示)だが、これが難物であった。橘樹神社の西で道は一旦低くなり、少し上ると建築基準法の厳格運用では建て替えのできないような狭い道幅になり、大人が寄りかかったら倒れそうな塀が道の左に立ててある。右手の急坂は南斜面で陽当りが良いので子供が遊んでおり、転げ落ちてもさきほどの塀までで止まるのだと理解した。ふうふう言いながら自転車を押して上がって行ったら、子供の母親に怪訝な顔で見られた。とにかく地形的に頂上の位置に富士見塚はあった。図と里程表は、最初の案内板に戻ってこの住宅地のメイン道路(これも決して楽な坂ではない)を辿るようにした。 図会は稲毛薬師堂と橘明神の間に十三塚を配し、この篇の府中の三千人塚や高幡の平惟盛之墓と同様に野戦で戦死した無名の武士達を弔った墓と推定している。 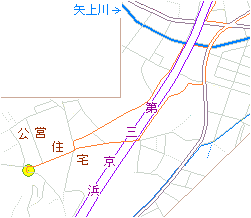 描かれた風景と記述の「耕地の中」から、当初の探訪で平坦な広がりの範囲と考えて中原街道・矢上川沿いを探したが発見できず、3年後の再訪でも諦めていた。
描かれた風景と記述の「耕地の中」から、当初の探訪で平坦な広がりの範囲と考えて中原街道・矢上川沿いを探したが発見できず、3年後の再訪でも諦めていた。
富士見塚から北西に進み、右に曲がる急坂を下って中原街道の峠の部分に出る。ここから中原街道を南西に進んで尻手黒川道路との野川交差点を過ぎ、矢上川を渡った次の信号で右歩道に移る(右図右上)。1店舗南の道を入って第三京浜に沿って坂を200mほど上がって第三京浜を渡る。そのまま西南西へ向かって200m足らずでのX型交差を過ぎて200mほどの左に十三塚の唯一の名残塚と言われている塚がある。 塚が崩れてこないように高さ50cmもないトタンと2・3mおきの鉄杭で裾周りを補強してあるだけで、市の教育委員会の標識などもない。矢上川からだいぶ上った水の便が悪かったこの地にスズメオドシがそこここにあって集落もある風景など江戸時代に存在したのだろうかという私の疑問と同じ疑問を教育委員会も抱いているのかもしれない。あるいは隣接する県営住宅が殆どを潰してしまったことを秘しているのかもしれない。 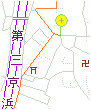 大した成果でもないので、同じ道を戻らず先ほどのX型交差点を左に入って、次を右折して矢上川まで下り、野川交差点で尻手黒川道路北側の歩道を行き、第三京浜の東側道に入る。(以上右図、以下左下図)
大した成果でもないので、同じ道を戻らず先ほどのX型交差点を左に入って、次を右折して矢上川まで下り、野川交差点で尻手黒川道路北側の歩道を行き、第三京浜の東側道に入る。(以上右図、以下左下図)
図会は、聖武天皇に縁起があることは説明しているが、鎌倉時代の御家人稲毛氏の名が付いていることのコメントはしていない。 律令制当初に現川崎市域から横浜駅にかけての地域が橘樹郡とされ、その郡衙が影向寺付近に設けられたという。他の郡衙や国分寺がアクセスの良いところに置かれたのと異なって直ぐ南の能満寺との間も急坂であり、郡の中心としては不便すぎるように思う。本節は地域の歴史認識を確立しにくい典型になってしまった。
|
| 溝の口駅南部〜長尾山 |
前節をスキップした人など改めて本節に出向く人は、東急田園都市線溝の口駅南口から旧府中街道を左に進むと左図上部の広い分岐型交差点に出る。
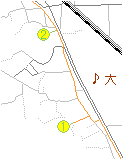
前節から続く人は、前節の図で示したように、影向寺の裏に回って谷筋の道を下る。初めは「上りはゴメン」という急坂だが、直ぐにブレーキもペダルもきしませることない緩やかに下る道になり、旧府中街道の「橘」交差点に出る。そのまま信号を直進して1km余りで右に「川崎北税務署」の看板があるあたりから接近している左の脇道(たぶんこれが昔の府中街道)に入る(左図右下)。 50mも行かない左に龍臺寺(図①)がある。この寺の由緒案内板には、図会が1行足らずで杉山明神祠の別当であることに触れていることをしっかりと紹介している。 脇道が旧府中街道に合流した先すぐ左に、久本神社(図②)がある。神奈川県神社庁のサイトに「杉山社二社、神明社、八幡社の・・・・四社を合祀し、社名を久本神社と改め、祭神を天照大神とした」と書いてあることから図会の杉山明神祠の現在の姿ががこれである。図会に星川邑・・・・杉山神社の模なるへしとあるので、星川杉山神社に尋ねたが、久本神社のことを知らなかった。 旧府中街道の東側は、学校法人洗足学園のキャンパスである。私は学生時代目蒲線(現目黒線)洗足駅近くに下宿していた。近くに女子高の洗足学園高校があり、童謡歌手だった由紀さおりが通っていた。戦前に洗足で学校を始めたのが法人名の由来だが、敗戦後陸軍の溝の口演習場が廃されて、衰退した溝の口駅南部の土地を取得して今日の発展を見ている。
この節のアップから半年も経たない平成21年5月、この大学は新インフルエンザの初期患者を出し、一躍全国に名を馳せた。再編した23年12月には、前述した由紀さおりが、米欧で再評価されて60才台半ばで海外公演を続けている。 溝の口駅南口先で田園都市線を潜って右折し、JR南武線の踏切を渡り、栄橋交差点を左折してJR南武線に平行に進む。久地駅を過ぎたら左折して府中街道に入り、500mほどで東名を潜り、左図右端に出て来る。府中街道から左折のポイントは、妙楽寺の通称である「あじさい寺入口」交差点である。途中津田山駅と久地駅の間で右手に川崎市の斎場が設けられている山が、図会で妙楽寺と共に描かれている
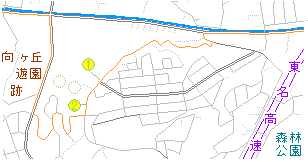 景色を眺める余裕もなく只管ペダルを漕いで坂を上がるのを繰り返すと、上りきって修行とはこんなものだろうかと思う。私の菩提寺の宗派でいえば「行禅」の一形態である。戦後の開発で長尾団地の真中を抜けて上る道が出来ているが、府中街道から入って4,50mで右折する旧道のほうが禅行向きであるし、ばてて自転車を押して上がっても周囲の視線は殆どない。
景色を眺める余裕もなく只管ペダルを漕いで坂を上がるのを繰り返すと、上りきって修行とはこんなものだろうかと思う。私の菩提寺の宗派でいえば「行禅」の一形態である。戦後の開発で長尾団地の真中を抜けて上る道が出来ているが、府中街道から入って4,50mで右折する旧道のほうが禅行向きであるし、ばてて自転車を押して上がっても周囲の視線は殆どない。妙楽寺の山号である本節のタイトルは、ここの地名でもある。図会は高幡と日野の間の多磨川4図幅の2番目に狛江上空から宿河原の後に長尾山を描き、遠景に大山の稜線を描いている。 妙楽寺(図①)の紫陽花は、毎年6月中旬から地域の観光イベントになっていて賑わう。境内の南の墓地の上に薬師堂とかねが、その西斜面には大師巌室が描かれ記述されているが、現在はその地域は私有地になっている。
その南にある神社が五所権現社(現長尾神社:図②)である。図会は、「祭神詳ならず」と書いているが、由来が道を挟んで南の公園の塚群であろうこと、元来塚は五つあったろうこと、塚は前々節の十三塚と同種だろうことが容易に推察される。 神社と公園(ここに塚らしき盛り土がある)との間の道を進み、修行で上った分を蛇行して下りる。下りて出た広い道路を右折する。この左手の樹の繁っている所は、川崎市が買い取ったバラ園を含み小田急グループの向ヶ丘遊園が2003年まであった。ここも長尾の地名だからもしかすると大師巌室はこの区域にあるかもしれない。坂を下って府中街道長尾橋交差点に出て左折、次節へ向かう。 なお、蛇行して下り切ったところで左折すると、600m余に明治初期に茅場町薬師堂(智泉院)から薬師如来像を引き取った等覚院がある。この節で補遺更新を検討したが、一続きのルートとしては無理が感じられたので、圏外の部に収録した。 |
| 向ケ丘遊園駅南部(東生田〜枡形) |
本節のタイトルの駅名は、今や幻を意味している。郊外遊園地華やかな時代に、新宿と小田原箱根を結ぶ特急電車までもがこの駅に停車した。そして駅前から遊園地直結のモノレール線まであった。左図左上の←の先は向ヶ丘遊園駅である。
ここのモノレール線が廃止された年に開業した舞浜ディズニー線を除いて、日本中の鉄道駅直結型の郊外遊園地線は全て廃止されている。 前節で府中街道を左折して250mに藤子・F・不二雄ミュージアムがある。廃業した遊園を川崎市が買い取り、遊園地施設であったボウリング場を改造して平成23年秋に開業した。
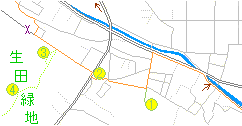 さらに350m先に、図会が右の図版で描き「頗る美景の地」と紹介している雪ヶ坂の名の付いたバス停がある(左図→)。
さらに350m先に、図会が右の図版で描き「頗る美景の地」と紹介している雪ヶ坂の名の付いたバス停がある(左図→)。
本村橋信号から100mあまり先の左に、図会が長森稲荷明神の別当として記述している安立寺(左図①)への小路がある。門前の参道両脇に墓地があり、週間出演時間数でギネスブックに載ったTV司会者のM2家の立派な墓石が参道に直面して立っている。
稲荷前の広い道を渡って右クランクで入っていくと、200m程の左に生田緑地北口がある。自転車を提げて右の階段を上がってすぐに長者穴(現長者穴古墳:左図③)がある。古墳が暴かれて宝物が出たので「長者」と呼ばれたのだろう。 さらに丸太や板張りで滑らないようにしてある階段を10分余り上ると四阿の休憩所の先に飯室山の山頂(左図④)がある。
山越えは自転車なしで別途民家園視察を兼ねてのハイキングという人が多いだろうから、ルートは街中の道とする。
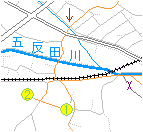 寺の門を入って駐車場を抜けて石段を上がると、西向きの本堂がある。参拝して振り向くと、境内の向こうが低くなってその先に鳥居が見える。かつて寺が別当をしていた韋駄天宮(山)(現北野天神社:右図②)である。自転車を下げて階段を下り、再び北野神社の階段を上がる。正月の関東大学対抗箱根駅伝に度々出場している専修大学や明治大学のチームが韋駄天を守護神にしている痕跡でもあるかと探したが見当たらなかった。
寺の門を入って駐車場を抜けて石段を上がると、西向きの本堂がある。参拝して振り向くと、境内の向こうが低くなってその先に鳥居が見える。かつて寺が別当をしていた韋駄天宮(山)(現北野天神社:右図②)である。自転車を下げて階段を下り、再び北野神社の階段を上がる。正月の関東大学対抗箱根駅伝に度々出場している専修大学や明治大学のチームが韋駄天を守護神にしている痕跡でもあるかと探したが見当たらなかった。神社前を左に進んで先ほどの踏切を渡って府中街道に出て信号を渡る。続いて二ヶ領用水を渡る橋が次節の「登戸宿」図版中央に描かれている太鼓橋の現在の姿である(右図↓先)。橋の西の府中街道とその手前が図版付注の「榎戸」であった。 |
| 登戸〜狛江駅西 |
左図でレモン色に塗ってあるところは、前節と重複している。
この地区は長年かけて少しずつ土地区画整理事業をしており、区役所東の交差点付近が工事中で迂回ルートとして小泉橋から300m弱で一旦向ヶ丘遊園駅北口広場に出る方法を紹介していた。 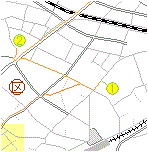 平成26年度には関連工事が終わり左図左端から道なりに進むルートを紹介するが、向ヶ丘遊園駅から一旦出直す場合の参考として左図はそのままの範囲を表示している。
平成26年度には関連工事が終わり左図左端から道なりに進むルートを紹介するが、向ヶ丘遊園駅から一旦出直す場合の参考として左図はそのままの範囲を表示している。区役所東の交差点で進行方向の右向こうに渡り、一つ先の一方通行出口を入る。斜めにぶつかった道のすぐ右の交差点を左折して40mほどの右の奥まったところに右の登戸宿図版の左端に描かれている善立寺(左図①)がある。
図会に右の「登戸宿」と「登戸渡」の図版はあるが、記述が無い。しかも、綴じ込み箇所が三つ前と二つ前の節で紹介した中原街道沿いのものの中に紛れている。つまり、雪旦は訪れて絵を描いたが、長秋は訪れなかったか無視したかである。
信号に戻って右折、津久井道(都内世田谷通りの続き)に出た向こうに光明院(左図②)の屋根が見える。②のクリックで判るように門は固く閉ざされていた。
右図版の登戸宿で見ると、当時の津久井道は善立寺前の道であったようだ(つまり、区役所南からここまでの旧道がズタズタになった)。 登戸の渡については、光明院前から始まる多摩川水道橋を都側に渡ったところにこの辺にあったとの銘板があるが、図会の描く風景のような松林があったとは考えられない。
多摩川水道橋を渡って250m、小田急線を潜らずに西側の側道に入って行く(右図左下)。 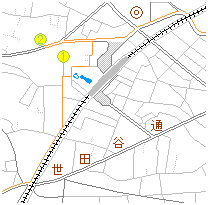 左前方への分岐道路の突き当たりに泉龍寺(右図①)山門が見える。大きな災害に遭わずに江戸時代の原形を残してきた寺院建築であり、都心からの交通の便も良いので、学生や研究者が調査に訪れることの多い寺である。
左前方への分岐道路の突き当たりに泉龍寺(右図①)山門が見える。大きな災害に遭わずに江戸時代の原形を残してきた寺院建築であり、都心からの交通の便も良いので、学生や研究者が調査に訪れることの多い寺である。門前を東へ曲がった突き当りには、注連縄を張った様子が図会に描かれた和泉村霊泉(右図水色部分)が一度は枯れたものの導水して復元され、図会同様古木が池を取り巻いている。池には往時のままの弁天祠がある。寺と地域(村)の名の由来であることは言うまでもない 小田急線狛江駅北口駅前広場を目の前にして、アパートの間の細い道を通って、駅と西河原を結ぶ道へ出て左折、200m弱の右(道路の反対側)の2棟のマンションの間に柵があってその向こうに十本ほどの木の繁った塚がある。図版泉龍寺で中遠景に描かれている経塚(右図②)である。マンション用地として買収されたが、②をクリックして出る写真の電柱の左の位置に、行政の要請があって保存されたとの説明とともに図会の図幅も示された銅製の銘板がある。 北口駅前広場から狛江市役所(図◎)前に出て、信号そのままで広い道を進み、図の右外で世田谷通に出て都心方向に向かう。 |
| 世田谷南西部 |
前節から世田谷通りに出た交差点が新一の橋交差点である。直ぐ一の橋交差点があり、次いで二の橋交差点になる。この交差点から右に枝分かれするように伸びている道が江戸時代の喜多見中心部への道である。(左図左上)
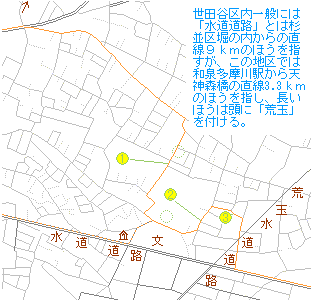 前節で狛江から都心に戻った人は、喜多見駅南口に出て都心方向に戻って線路を潜っているバス通りを右に進み、100mほどにある100円ショップの角を右に曲がるとこの交差点に出てくる(左図左上↑矢印のほうから)。(和泉多摩川駅まで行ってのアプローチは後で述べる)。
前節で狛江から都心に戻った人は、喜多見駅南口に出て都心方向に戻って線路を潜っているバス通りを右に進み、100mほどにある100円ショップの角を右に曲がるとこの交差点に出てくる(左図左上↑矢印のほうから)。(和泉多摩川駅まで行ってのアプローチは後で述べる)。左図のように世田谷通りから岐れて入った道を700mの左にまとまった農地が残っていて、電柱を挟んでカーブミラーが二つ立っている。 ここを右に入って左カーブが終わった先を右に入ると左前方に見える大きな銀杏の樹が見える。その下に そのすぐ南の辻に氷川明神社(現氷川神社:左上図①)の鳥居がある。境内は奥深く、木々の樹高も高い。下で説明する 鳥居の前の道を少し進むと左側が慶元寺(左上図②)の塀になり、裏門がある。そのまま下り気味に鍵の手に進むと寺経営の幼稚園がある。
太田道灌によって現在の皇居付近からこの地へ移らされた江戸氏がこの三つの寺社を設けた。江戸氏は絶えたが、寺社は戦乱にも着込まれず明治を迎えた。別当ビジネスや修行主体の祷善寺は神仏分離令で廃寺になり、檀家を抱えていた慶元寺は生き残ったようだ。 慶元寺の幼稚園の部分は、右の図版では北見陣屋址と付注されている。しかし記述では、須賀神社のあるあたりに天神森があって天王(たぶん牛頭天)を相殿していると書いている。明治の神祇官が牛頭天と天神との間で線を引いていたのが判る。
元来の地名は北見だったが、木田見とも表記した。江戸氏は封ぜられて当初北見と名乗り、家康入府に際して喜多見姓に変えたが暫くしてお家廃絶になった。喜多見で地名を表すようになったのは、明治以降である。
須賀神社の前をそのまま進んで突き当りを右折し、「荒玉水道道路」を斜めに渡って「水道道路」に出て左折する。この水道道路が和泉多摩川駅からのアプローチ手段である。
(駅を出て線路の高架に沿って都心方向に戻ると世田谷通りに出る。通りを右歩道で都心方向に行って信号から右に伸びている直線道路が左上図の左下に出てくる。「こまえ苑」という老人ホームと喜多見中学の間の道を入る。)須賀神社という名称は、若葉・須賀町で書いたように、牛頭天社が名乗り変えたものが多い。 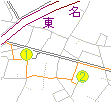
水道道路を東へ向かい、東名高速道路手前の信号で右歩道に移る。高速道路の下を抜けて直ぐにあるバス停のところから右に入り、突き当たって左折すると観音寺(右上図①)の正面に出る。200mほど南にある(宇奈根)氷川神社の別当だったようだが、図会はこの氷川神社は取り上げていない。
観音寺前を南に進み最初の左折を入っていって突き当たると常光寺(右上図②)である。図会は、次節の浄光寺の所在とを混同して書いている
水道道路に戻って東へ進むと野川にぶつかって曲がり、天神森橋を渡ると多摩堤通である(左下図)。これを横切って小さな坂を上がり、左折する。 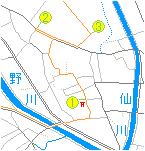 道左の鎌田天神社の向こうに吉祥院(左下図①)がある。両寺社は別当関係があったのではと思わせる。図会が、今は僅かの草堂一宇と書いている状況に変化はない。
道左の鎌田天神社の向こうに吉祥院(左下図①)がある。両寺社は別当関係があったのではと思わせる。図会が、今は僅かの草堂一宇と書いている状況に変化はない。吉祥院から北へ道なりに進むと広い道路に出る。左折してしばらくで道が細くなる交差点の右に公孫樹の高木が目を引く永安寺(左下図②)がある。長年栄え続けている檀家に支えられ、現在でも風格を保っている。 永安寺からUターンして真っ直ぐ進み、最初の左折できる道の奥に永安寺が別当をしていた(大蔵)氷川明神社(現氷川神社:左下図③)がある。 江戸氏−石井(イワイ)氏と地域の有力者庇護のもとに、一時は別当抜きの運営もしていたと図会は書いている。石段の上の境内の樹木の間からは仙川越しに岡本の台地が見渡せる。 橋を渡って右へ50m余りを左に入るのが古来からの道である。これを進むと左右は「石井」という姓だらけである。 東名高速から600m弱の右に、図会には書かれていない妙法寺(右下図)という寺がある。山門を潜ってすぐ左に、石井戸稲荷大明神という扁額を掲げた鳥居があり、その後ろにさらに鳥居が少し向きを変えて建てられている。 図会が「祭神詳ならず」と書き稲荷と合祀とも記していることから、一応同一の神社と扱うしかない。でも、図会は石井氏の鎮護の神としているが、妙法寺は安藤家の菩提寺のようで、石井氏の影は薄い。図会に石井氏の先祖として安藤姓が記されているので、明治以降に石井氏の一部の人達が改姓したようにも思える。(彼岸明けに訪れたが、唱和会が行われていた。神仏分離をどう乗り越えたかも伺いたかったが、いずれも微妙な話でもあるので早々に退散) 山門を出て右の分岐を左に取ると、世田谷通りの「砧小学校交差点」に出る。ここは本節始めに触れた荒玉水道が横切ってもおり、複雑な交差点である。都心に向かって仙川まで下り切って右後ろを振り返ると、先程の妙法寺が平成2年に設けた露座の「おおくら大仏」が見える。 なお、砧小学校交差点から西北1kmほどに成城学園前駅があり、自転車探訪を一区切りすることもできる。 また、て来るキンタ小学校世田谷通りを渡るに出て、都心方向に右折する。 |
| 世田谷中央部 |
砧小学校交差点から世田谷通りを3.5kmほどで松ヶ丘交番交差点になり、次の交差点を右折して世田谷通りを離れる。この右折の交差点の内角には1階はハンディキャップド用で健常者用は2階という公衆トイレがある。御用の向きはどうぞ(左図左端上寄り)。
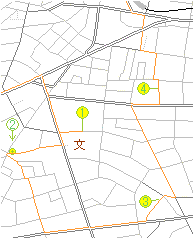 桜新町へ抜けるこの通りに入って200m、松丘(交番と表記が違うが共にマツガオカである)小学校信号の手前を左に入った先の左に実相院(左図①)の正面がある。平成21年2月に訪れた時工事中だった本堂は、無事落慶を迎えたようだ。
桜新町へ抜けるこの通りに入って200m、松丘(交番と表記が違うが共にマツガオカである)小学校信号の手前を左に入った先の左に実相院(左図①)の正面がある。平成21年2月に訪れた時工事中だった本堂は、無事落慶を迎えたようだ。
信号の直ぐ南を左に入り、狭い通路を南へと進んで弦巻通りに出たら左折する。次の信号の先を左折すると、道は少し高くなっている境内に沿って右に曲がる。変形した辻のすぐ手前左に鳥居が立っているのが上で予告した弦巻神社(図③)である。立札に経緯が書いてあるが、社務所は行くたびに閉まっていた。 神社のすぐ東の通りは西へ戻ってしまうので、右斜めに進んで次の通りを北上する。この道の直線区間が終わる交差点の右に前節で触れた浄光寺(左図④)があり、図会の書いた世田谷上宿の南である。しかし、図会が記した「常」と「浄」が異なるのみならず、「日蓮宗、天正13年草創」は前節の常光寺で、こちらは開基は100年以上古く、浄土宗である。 東向きの浄光寺前から北へ少し鍵の手に進んで出た通りでは、12月と正月の中旬に「ボロ市」が行われる。
150mほどの左路傍に石碑があり、左前方に直線で参道が伸びている。勝光禅院(右図①)である。 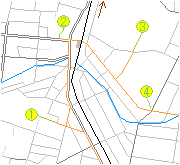 電車と平行な道に戻って進むと、信号の左向こうに叢林が見えてくる。信号を左折すると宮坂八幡宮(現世田谷八幡宮:右図②)の赤い大きな鳥居がある。潜るともう一つの鳥居との間が広場になっていて右手は厳島神社があり、その手前の立て札に現代の名称は、戦後になって使うことになったと書いてある。
電車と平行な道に戻って進むと、信号の左向こうに叢林が見えてくる。信号を左折すると宮坂八幡宮(現世田谷八幡宮:右図②)の赤い大きな鳥居がある。潜るともう一つの鳥居との間が広場になっていて右手は厳島神社があり、その手前の立て札に現代の名称は、戦後になって使うことになったと書いてある。
東に向かって宮坂駅踏切を渡って道なりに進むと、左手に豪徳寺(右図③)への広い入口がある。境内の墓地には彦根藩主だった井伊家の墓域がある。 豪徳寺の南、建て替えて洒落た雰囲気になっている都公社の住宅団地の南に吉良氏古城跡(現世田谷城址公園:右図④)がある。上町駅からの道との交差点にある入口から入って一休みした後、東に向かう。 なお、右図上部↑の先400m足らずが小田急線豪徳寺駅である。 |
| 上馬・下馬 |
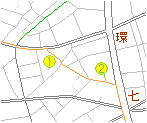
前節をそのまま東へ進む。世田谷税務署前交差点を右クランク気味に細い道を抜けると世田谷通りと松蔭神社を結ぶ商店街に出る。右折して世田谷通りに出たら左折、都心方向に進む。最初の信号の左の下駄ばきマンションと自動車販売ビルの間に緑道があり、「防災緑道」との説明板が立っている。
どのような災害を防ぐものか不明だが、水路の機能を失ってから長らく無主地として国有地扱い(いわゆる「青線」)しているうちに、国の役人は自分の権限を振るい、
都庁と区役所の役人は世田谷通りの反対側に設けられた2車線道路が北側には抜けそうもないのでお互いの役人同士が面子の立つレッテルを貼ったように見える。
常盤橋から二十歩にあると書かれている常盤塚(左上図①)は、この信号で右歩道に渡って100mの「若林三丁目」バス停のところから右に入って30mの右にある。
常盤塚から東南に進んで環七に出る他前左の石垣に囲まれた境内が若宮八幡宮/駒留八幡宮(現駒留八幡神社:左上図②)である。この境内の左奥、地形的には池の作り難い位置に田中弁天(現厳島神社)がある。 図会は常盤橋と若宮八幡宮の項の中で、「常盤伝説」を説明して常盤塚と田中弁天を紹介している。吉良頼康(吉良家最後の代)の妾の常盤が不義をして逃げる途中ここで死んで塚に葬られた。崇りを恐れた里人は霊を弁天とし身ごもっていた嬰児を若宮八幡とした、と簡潔に書いている。また、隣村若林の曹洞宗の香林寺(現存しない)は常盤が開創し、ここに墓があるとも書いている。
しかし常盤塚から800mほど西に現存する日蓮宗の常在寺(前節浄光寺の東南東300m)は、常盤の支援のもと開基されたとのことでここにも常盤の墓があるとのことである。  世田谷区内に残る伝説も、不義は、妬みによる作り話だったので頼康が真実を知って噂を広めた側室らを処刑したというもの(この場合常盤の身の潔白を示した辞世の句まである)と信心の食い違い(頼康は曹洞宗で常盤は日蓮宗)というものがあるし、崇りも里人の禍ではなく頼康に跡目の出来なかったことというものがあり、真実は藪の中である。
世田谷区内に残る伝説も、不義は、妬みによる作り話だったので頼康が真実を知って噂を広めた側室らを処刑したというもの(この場合常盤の身の潔白を示した辞世の句まである)と信心の食い違い(頼康は曹洞宗で常盤は日蓮宗)というものがあるし、崇りも里人の禍ではなく頼康に跡目の出来なかったことというものがあり、真実は藪の中である。
駒留八幡神社の別当だった宗円寺(右上図)へは、環状七号道路を右歩道のまま行き、国道246号との交差点である上馬交差点を渡る。246を郊外方向40mで左に入ったところにある。
右歩道のまま都心方向に戻り、交差点を過ぎても右歩道のまま進む。 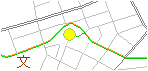 500m先の世田谷郵便局前の世田谷警察署信号で駒留通りへと右折する。近年整備されたこの道路は、自転車レーンが着色表示されていて沿道の商店が少ないので路側駐車も殆どないので自転車にとって快適である。700m先の信号を過ぎて次の左への道を入り、すぐ右へ折れてそのまま蛇崩通りを突っ切ると左下図左端である。
500m先の世田谷郵便局前の世田谷警察署信号で駒留通りへと右折する。近年整備されたこの道路は、自転車レーンが着色表示されていて沿道の商店が少ないので路側駐車も殆どないので自転車にとって快適である。700m先の信号を過ぎて次の左への道を入り、すぐ右へ折れてそのまま蛇崩通りを突っ切ると左下図左端である。この道の右には蛇崩川緑道が設けられている。駒繋中学を右に見て(左下図左端)進むと、やがて右にカーブして赤い欄干の太鼓橋が現れる。ここから、自転車をぶら下げて正一位子明神社(ねのみょうじん。現駒繋神社:左下図)の境内に上がる。 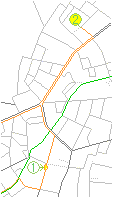
明治になって七曜暦が定着するまで月齢の次の短い生活サイクルとして十二支が使われていた。最初の子の日にこの12日間の無事平穏を願って行われていたのが子の神信仰で、いわばキリスト教の日曜礼拝みたいなものであった。明治になって週が用いられてすっかり廃れてしまい、この神社も祭祀の形態を変えてしまっている。
現在の神社名は、前節の駒留八幡で源頼朝が葦毛の馬を選んで乗り、ここ子明神で降りたという説から駒繋と称されていたものが明治以降正式名称になった。 引き続き緑道沿いの道を進むと500mあまりでついには緑道だけになる。ここで緑道に入らず右折し、次の十字路を左折すると、道の真ん中に樹木が3・4本の中央分離帯のようなものがある。源頼朝が乗った葦毛の馬を葬ったという足毛塚(現葦毛塚:右下図①)である。
ところで図会は、馬牽澤旧跡の項を立て、この地名は目黒に及ぶ広い地域に使われ、上、中、下に別れている。由来は頼朝の奥州征伐成就の祈願の際に東絛蘆毛の馬を献上しようと牽いていったが、この地で躓(たふれ)たことに由来すると子明神の項の記述とは異なるニュアンスで書いている(祈願用の馬が足を躓(くじ)くだけでも縁起でもない話)。また注記では、祈願ではなく狩りの際に馬がびっくりして沢に落ちで死んだ。そのため今でもこの地の人は葦毛を飼わなくなったとの説も書いている。 前段に関しては、明治の市町村制でも「馬牽澤」が使われ、合併後略して「上馬」や「下馬」になったし、「駒沢」というのも同じ源である。 緩やかな坂を登り続けて、蛇崩交差点に出る。さらに右方向に上っていき、350mほどに子明神の別当だった寿福寺(右下図②)の入口がある。
次の北沢川両岸へは、蛇崩交差点へ戻って直進し、下馬一丁目交差点を右折して三宿交差点で左折する。 なお、寿福寺からの最寄り駅は、東急田園都市線池尻大橋駅なのだが、その間は旧陸軍用地が自衛隊用に残された部分、国家公務員住宅として各省庁に割り振られた部分それぞれが独立的閉鎖的に造られてきたので、2、3度訪れただけではとても道を覚えられない。ましてランドマークを殆ど示していない私の地図では誤解されるばかりなので省略する。 |
| 三茶〜池尻 |
三宿交差点から800mあまりで三軒茶屋の交差点である。地下には都心の地下鉄駅から20分前後の東急田園都市線三軒茶屋駅があるので、前節ともここを起点駅とすることができる。
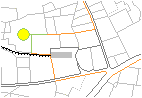 右分岐なので予め道路の右歩道を行きたいが、首都高速のランプが邪魔しているのと歩行者が多いので、三軒茶屋交差点まで行って我慢して歩行者信号で渡って左へ行き、150mほど先で同様に右折する。新しい舗装の道を入っていくと、東急世田谷線(昔の玉電)の踏切があり、その右は三軒茶屋駅のホームで電車が止まっている。
踏切を渡って線路沿いに左折して数十mの右に青山から移転してきた
右分岐なので予め道路の右歩道を行きたいが、首都高速のランプが邪魔しているのと歩行者が多いので、三軒茶屋交差点まで行って我慢して歩行者信号で渡って左へ行き、150mほど先で同様に右折する。新しい舗装の道を入っていくと、東急世田谷線(昔の玉電)の踏切があり、その右は三軒茶屋駅のホームで電車が止まっている。
踏切を渡って線路沿いに左折して数十mの右に青山から移転してきた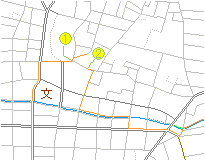 境内東側の道を出て、三軒茶屋交差点から北に伸びる茶沢通りに出て左折する。茶沢通りを1km余り進んでの右手に代沢小学校(右図文マーク)があり、この1街区向こうを右折して100mほどに北澤粟(淡)島(明神)社を置いていた森巌寺(右図①)がある。
右折せずに進んで、左寄りの道を選んで行くと小田急線と井の頭線の下北沢駅である。
境内東側の道を出て、三軒茶屋交差点から北に伸びる茶沢通りに出て左折する。茶沢通りを1km余り進んでの右手に代沢小学校(右図文マーク)があり、この1街区向こうを右折して100mほどに北澤粟(淡)島(明神)社を置いていた森巌寺(右図①)がある。
右折せずに進んで、左寄りの道を選んで行くと小田急線と井の頭線の下北沢駅である。図会の記すところでは、住職が積年悩んでいた腰痛の治癒を紀州加太の淡島明神に祈願していたところ、夢の霊示に従って灸治療をしたら直ったので、礼として淡島明神社を設け、灸の治療を普及したとある。図会に描かれている粟島社本殿は、現在森巌寺の境内にある針供養堂と淡島幼稚園にかけての位置である。 森巌寺が粟島神社に加えて別当をしていた北澤八幡宮(現北澤八幡神社:図②)は、森巌寺の通用口を出ると神社の駐車場に通じる道の向こうに本殿が見え、かつての別当道がこの間の道路になっている。
 その池尻稲荷神社へは、北澤八幡神社の前から真っ直ぐ南へ伸びる道で北沢川緑道に出て左折する。左岸の道は旧郵政省宿舎で行き止まりになるのでここで右へ迂回して淡島通りに出て交差点を渡り、すぐ左に入って(右図右端)再び北沢川緑道を辿る。700mほどで、烏山川(緑道)との合流点になる(左下図左上)。
その池尻稲荷神社へは、北澤八幡神社の前から真っ直ぐ南へ伸びる道で北沢川緑道に出て左折する。左岸の道は旧郵政省宿舎で行き止まりになるのでここで右へ迂回して淡島通りに出て交差点を渡り、すぐ左に入って(右図右端)再び北沢川緑道を辿る。700mほどで、烏山川(緑道)との合流点になる(左下図左上)。 北沢川・烏山川合流点付近は、江戸初期には池があり、「池ノ尻」、「池ノ上」は池を挟んで対の地名だった。図会の時代には低湿地状態になり、池の大部分は池尻村の地籍になっていったようである。
烏山川緑道を遡り、右手が行き止まり気味の広い道路に出たら左折し、次の信号を再び左折すると玉川通りの池尻交差点に出る。この信号を渡った右に池尻稲荷神社(左下図)の脇参道がある。本殿の左右に小さな観音堂があるが、社務所の話ではこれも地域からの働き掛けで昭和年代に設けられたものである。
境内を抜けて南の旧二子街道(大山道)に出て(こちらが正面)左折し、玉川通りに出ると田園都市線池尻大橋駅がある。ここで信号を渡って都心方向に向かう。 |
| 目黒川上流部 |
玉川通りに出て都心方向に400mの大橋信号のところの左に石の鳥居があり、継ぎ目はモルタル詰めしてあるものの「寄りかからないでくれ」と張り紙がある。
その先も手すりはあるものの高齢者にはきつい急な石段がある。道路の反対側にある自動車専用道のダイナミックなジャンクションとは対極の感が強いが、これが氷川明神祠(現上目黒氷川神社:左上図①)の入口である。 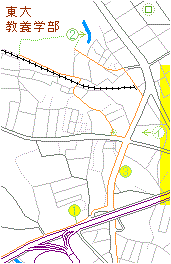 神社の北の僅かな民家の向こうには転勤族でもある国家公務員住宅が立ち並んでいる。西の池尻の商店街は世田谷区、東の山手通りの向こうは渋谷区松涛であり、氏子のサポート体制が弱いのであろう。川崎市内に「地震時には近づくな」という張り紙の社殿もあった。避難地と受け取られがちな神社境内が危険性を孕んでいるとは考えさせられることである。
神社の北の僅かな民家の向こうには転勤族でもある国家公務員住宅が立ち並んでいる。西の池尻の商店街は世田谷区、東の山手通りの向こうは渋谷区松涛であり、氏子のサポート体制が弱いのであろう。川崎市内に「地震時には近づくな」という張り紙の社殿もあった。避難地と受け取られがちな神社境内が危険性を孕んでいるとは考えさせられることである。すぐ東にある山手通りへの坂を下って、山手通りを左(北)に向かう。次の信号が淡島通りとの「松見坂」交差点である。
とアップしながらも右図版の左右の遠近感が腑に落ちなかった。機会があって松濤公園(左上図ロ)を訪れた際公園北側の松濤中学がこの辺で最も標高が高いと判り、ここならば右図版の景色が描けたと確信している。
空川の暗渠の上は通路になっており、これを辿っていくと途中西からの流れと北からの流れが合流するポイント(写真)を経て京王井の頭線のガードになる。潜って線路の北を左へ行くと、東京大学教養学部の東門である。
斎藤親子が蛇池を訪れなかったとは言い切れない。幕府の直轄地で一般町人は立ち入りできないのであえて伝聞としての記述したかもしれない。しかし、続けて「御猟地になった翌夏、ここに栖んでいた蛇が嵐を起こしてこの池から立ち去った」との記述は、加えられた何らかの圧力への反発のようにも読める。
池のすぐ南西に大学関係者の通用門がある。キャンパスを去る分には構わないだろうとこれを出て道なりに山手通りに向かう。通りの手前40mほどを左から右に横切る直線状の道は、三田用水跡であり、目黒区と渋谷区の区界でもある。これを辿って井の頭線神泉トンネル西出口の上を通って山手通りに出て右歩道で松見坂交差点に戻り、左歩道に移る。
100mほど下ると左の擁壁に鉄骨の階段がへばりついている。少し先には大きな標柱が立っていて「大教寺」の文字がある。この階段が本篇世田谷南西部の常光寺「図会の混同」で触れた イメージマップの写真は山手通りの反対側から撮ったもの。明治後期に駒沢からの移転ということから、戦後の新山手通り整備で緩やかな上り道がごっそり道路用地になったと推察する。
平成20年の探訪では以上のように旧山手通りを戻った。その後5節後の「赤坂」で不明としていた松泉寺が現恵比寿南に移転していたことが判り、猿楽神社から旧山手通りを南下する。
 猿楽神社から150mほどの鎗ヶ崎交差点で駒沢通りに出る。これを恵比寿方面に左折するが、この交差点の信号を含む3つの信号のいずれかで右歩道に渡り、左下図左上に出る。セブンイレブン、ローソンとコンビニが続いた先を右に入り、猿楽神社から1kmほどの左下図の位置に1900年に赤坂円通寺坂から
猿楽神社から150mほどの鎗ヶ崎交差点で駒沢通りに出る。これを恵比寿方面に左折するが、この交差点の信号を含む3つの信号のいずれかで右歩道に渡り、左下図左上に出る。セブンイレブン、ローソンとコンビニが続いた先を右に入り、猿楽神社から1kmほどの左下図の位置に1900年に赤坂円通寺坂から松泉寺からJR山手線の恵比寿駅改札へは左下の図のように500mほどで到達し、メトロ日比谷線の恵比寿駅はその先50に入り口がある。 また、左下図右下部の→先の交差点を左歩道南下200mで、目黒駅周辺の節の冒頭で紹介する千代ヶ崎の図の茶屋坂になる。 |
| 渋谷駅周辺 |
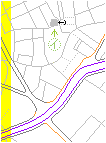
|
| 渋谷区東 |
渋谷川は、旧広尾村の高台の裾を反時計回りに流れており、明治通りはその山側を辿った道になっている。渋谷区東地区は、旧広尾村の西半分の岡である。
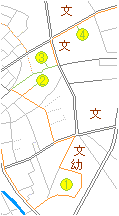
広尾幼稚園側に出て左に進んで右折し、明治通りと平行に戻っていくと、広尾高校前交差点に出る。これを左、明治通り方向に100m弱戻って右に入って行く。250mほど進んだ右は宝泉寺(図②)への参道として広くなっている。この宝泉寺が別当をしていたのが氷川明神社(図③)で、連続した樹林の中を塀で仕切った北隣にある。
さらに境内の東にも鳥居の立つ入口があり、これを出て左に行き、國學院大學前交差点を右折、右歩道で行く。100m余りに鶴ヶ谷・羽沢にと書かれている吸江寺(図④)がある。 そのまま進むと、常陸宮邸の角の東四丁目交差点が谷筋になっている。この辺が図会がどこか判らなくなっていると書いている鶴谷かもしれない。六本木通りへ出て道の反対側に渡り、都心方向(右)に進むと高樹町交差点になる。 |
| 笄町〜上渋谷 |
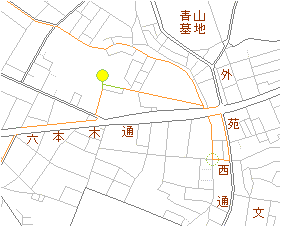
高樹町の交差点は首都高速道路の出入り口にもなっており、ここで六本木通りを渡るのは容易でない。ひとつ渋谷寄りの信号で渡っておくのが無難である。さらに鋭角に左折する南青山の通りを渡る歩行者信号は六本木通りの停止信号で青になるのであるが、これを渡った左に長谷寺(左上図)への道がある。
長谷寺は戦災で一切が焼け失せたが、四半世紀を経て曹洞宗永平寺の東京別院として再興された。図版の惣門の参道は安政大地震以降閉鎖され、再興までは東に参道が出来ていた。
交差点から外苑西通りを南へ200mの信号を右に入る道が当時の道で、直ぐの十字路を右から左に流れていたのが笄川で、ここに右の図版の笄橋はあった。現在「笄」の地名は左上図右下の小学校(文マーク)とその西の小公園に付けられており、公園の小学校寄りに由来を書いた案内板がある。 川筋を戻って六本木通りに出ると、丁度反対側が先ほど通りに出た場所である。そこまで戻って笄川西岸だたと思われる道を青山方向に上がっていくと根津美術館の築地塀になる。築地塀の向こう側に笄川の水源の泉(長谷寺境内にあると書かれている文献が多い)が今も美術館庭園内に池として残っている。 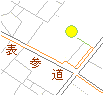
表参道交差点を都心に向かって100mあまりの左に青山善光寺(右図)がある。山号の南命山は、「台命により谷中より移転」を示しているかのようである。自動車用に開放している門の右通路に面して寺のものとは思えないビルがあるが、寺が土地かビルを貸しているのだろう。
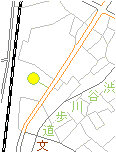
長泉寺は、二つ前の節の「渋谷駅周辺」で訪れた渋谷八幡宮ゆかりの金王丸(麿)が尊信した観音像(運慶作)を祀る寺として図会は紹介している。しかし、戦災などのせいか、今は石仏が残されているだけである。 明治通りを北へ戻り、神宮前交差点をそのまま進む。 |
| 外苑前駅周辺 |
若い人には、「ラフォーレ前交差点」といったほうが通じる神宮前交差点から3つめの信号の「神宮前一丁目」交差点を右に曲るのだが、車道の中のほうを走らないと曲がり難い。ここまでの信号で右歩道に移って曲がったほうが安全である。
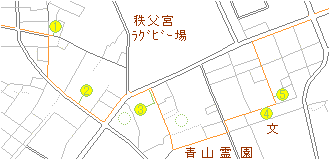
龍巌寺とは逆に進んで外苑西通りに出る。
青山通りを左折、外苑前交差点を南(右歩道)に渡って左に進んで、地下鉄駅への出入り口を過ぎると右に泰平観音堂・梅窓院(図③)の入口がある。竹林をデザインしているが、こちらも本堂ともどもビル化している。交差点から逆の西にも竹林があって入口があり、図会では紹介していない「祖師堂」が墓地の真ん中にある。 梅窓院の西のブロックは、三軒茶屋に移転した 梅窓院東の道を南に進み、青山霊園の北端の道を左折、赤坂消防署の所に出たら、左鍵の手に曲がって消防署の北側の道に入る。150mほど進んでの左に赤い門の 龍泉寺の東20mの丁字路を左折すると、 青山通りに戻って都心方向へ進む。次の青山一丁目交差点で左に移ると、赤坂御所である。南通用口付近の警備員以外人影の殆どない広い歩道が続くので、これを気楽に走っていく。 |
| 赤坂 |
| 世田谷区南部 |
等々力駅のある東急大井町線は、上京直後から9年間沿線に下宿していたので土地勘のある懐かしい場所である。
東急田園都市線二子玉川駅からJR京浜東北線大井町駅までのこの路線は、都心から南下する東横線、目黒線、池上線(この3線も東急)を東西に繋いでいる乗換え乗客の多い路線である。

満願寺図版で二子街道等々力村道(現目黒通り:図版では目黒道)沿いに描かれているくまのは、現玉川神社(図②)である。図会に記述はないが、満願寺が別当だったと玉川神社の説明板に書かれている。 目黒通りを50mほど都心に向かっての信号を右に渡り、通りと直角(東)に入っていく。
図会で一番奥に描いている開山堂(現開基堂)は、仁王門の東に移転し、描かれたところは墓苑になっている。また、図会は縁日の風景なのだろうか、境内に延々とヨシズ張りの出店を描いているが、現状は霊場的な雰囲気を漂わせている。
浄真寺仁王門から真っ直ぐの東門を出て左折、北に進んで目黒通りに向かう。 |
| 目黒区南西部〜中部 |
途中上り坂になって右に曲がったところで左折(前節図右上端)しなくても、600mほど先で自由が丘駅から北に伸びる自由通りに出るのでそれを左折して目黒通りに出る。

都立大学駅前交差点に戻ってそのまま目黒通りを横切り、駅南側の広場から左へ入る。緩やかな坂を上がりきると、道は右へ右へと曲がり直線になる。
300mほど先にあるバス停先を左に曲ると白い鳥居があり、碑文谷八幡宮(右図①)である。 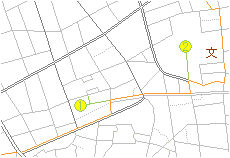
この寺は元々は天台宗だったが、日蓮宗に改宗して法華寺と名乗った。現代風に言えば原理主義的な日蓮宗の修行の場になっていたのを危惧した徳川幕府が元禄時代に元の天台宗に戻させた。法華寺という名は、天台宗の寺には無い筈だが、図会は宗旨替えの経緯を書くとともに日蓮宗の寺名で記し、描くに留め、寺名のギャップには触れていない。一方で、神宮院という名の寺の子院が八幡宮の別当をしているとも書いているので、巷間の受け止めや実態は幕府の目的どおりになっていたということだろう。
円融寺の門前を左(東)に進んで、突き当って左折すると、明治12年開校という碑(いしぶみ)小学校があり、その北に円融寺の通用門がある。その次の十字路で左クランクに進んで(右図右上)道なりに前へ進んで目黒通りに出る。直ぐの分岐で左を選び、後はほぼ同じ方向に1.5kmほど進めば駒沢通りである。これを都心方向に進むと祐天寺(左下図①)の立派な境内が右に見えてくる。駒沢通りに出る前に間違えて中町通りに入ってしまっても、そのまま進んで「祐天寺裏」という交差点をほぼ直角に左に曲がれば祐天寺の境内である(図のピンクのルート)。
当初訪問時の本堂改修工事は完工し、続いて会館等の建築が進んでいる。
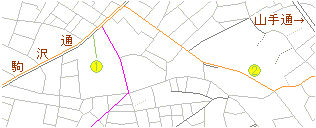
東南の鞍部のような十字路へ出て左へと下っていくと山手通りに出る。 |
| 目黒駅周辺 |
山手通りを右手の横断歩道で渡り、そのまま入っていくと、目黒川に出て左向こうが清掃工場になる(左図左端中央)。
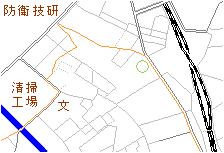
茶屋坂は急坂で、自転車を押して上るが、ぶつかって左折すると再びサドルを跨ぐ気になる。切通しの道の上に出ると遮断された向こうに防衛省の公務員住宅群があり、これを取り巻いて自衛隊基地と防衛技術研究所になっている。
跳ね返されたように向きを変えて緩やかに登りきった右手の児童公園(左上図○)に「千代ヶ崎」の名が付いているのを確認してそのまま進む。目黒駅北のバスターミナルのところで左折(右歩道)してJR山手線を渡り、駅東口からの道の一つ先を右に入って、目黒通りに出る。そのすぐ左に誕生八幡宮(右図①:現誕生八幡神社)がある。 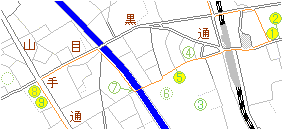
JR目黒駅東口広場のところの信号で目黒通りの南側に渡って山手線の西に出る。東急発祥の路線である目蒲線の目黒駅が地下鉄南北線・東急線の総合駅として立派になったのに感慨を覚えながら、メインの権之助坂ではなく、左に入る。 ここから下る行人坂とその周辺を鳥瞰した右の夕日岡・行人坂の図版は、どんな古地図にも勝る表現で、描写力において余人の及ばぬ水準を示している最高傑作ではないかと私は思っている。 夕日岡は、右図の③にある杉野服飾大学の学生会館にその名を留めている。また、行人坂の左に描かれている石垣は別の図版の
図会で一番はっきりと描かれている 目黒川上流に向かい、目黒新橋で目黒通りを左折する。次の信号で山手通りを渡ったところが大鳥大明神社(現大鳥神社:右図⑦)である。別当だった隣の大聖院(図⑧)も健在である。千代ヶ崎の南にあった松平主殿の別荘跡から出土してそれぞれに寄進されたという「切支丹灯篭」なるものが大鳥神社に1基、大聖院に3基ある。これまでも天権之部の月桂寺や本篇の太宗寺で見かけたが、いずれも明治以降に「発見」されたもので往時の記録などがあるはずは無く、真偽のほどは定かでない。(全国あちこちにあるらしい) 金毘羅(大権現)社は、大鳥神社の西(右図左端○)にあったようだが、その別当の高幢寺とともに現存しない。大鳥神社横から碑文谷方面に向かって緩やかに登る目黒通りの坂を「金毘羅坂」と呼ぶのがこの神社由来であることは言うまでもない。 |
| 目黒不動の周りは移転してきた寺だらけ |
大聖院から右手歩道のまま150m、歩道橋の手前に蟠龍寺(左図①)の入口がある。境内は奥まっており、その右奥の岩窟が弁財天(窟弁天)を祀っているというのだが、その上は中学校のグランドになっていて生徒の声がにぎやかである。右の図版に描かれている丈六の阿弥陀如来の銅像は、廃仏毀釈でこの寺が無住になっていた明治初期に、フランスの蒐集家が檀家総代に金を渡してパリへ運んでしまった。
さらに100m南の「羅漢寺」という信号付き交差点の分岐の角に松雲禅師の彫像が置かれている。ここを斜めに入って100mに
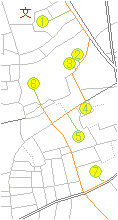
五百羅漢寺の前から右へ目黒不動への遊歩道があるが、真正面の方向の蛸薬師如来・成就院(左図④)に向かう。「デビルフィッシュが信仰の対象などとは、毛唐どもにゃあ判るめぇ」と見栄を切りたいところである。格式はさておいての賑わいが有りそうである。
7、80m西に進んだところに長い参道の安養院・能仁寺(左図⑤:右図版「寝釈迦堂」)の入口がある。山号の臥龍山は本尊の涅槃釈迦像をイメージさせるものである。 安養院は、明治初期に麻布薬園坂にあった東福寺を合併している。当初訪問時、境内の南に移転してきた墓を受容れた広い墓苑が広がっていたのと、寺には北インド・チベット美術を中心としたが美術館が併設されていた。その後、墓苑の参拝の無い墓石を整理して、納骨堂と本堂を合築する5階建ビルの工事が行われ、平成24年再訪時の話では美術館は廃止、本尊も一般参拝の計画はないとのことだった。(中華人民共和国の圧力かな?) 西へ進んで交差点を右折した突き当りが目黒不動堂・瀧泉寺(左図⑥)である。広い境内の踏み固められ様は、年間を通じて多くの参詣者が訪れていることを示している。主要な伽藍の配置はほぼ右図版のとおりである。しかし、図会が記し描いた堂宇を私なりにチェックしてみたら下のような表になった。段崖の直ぐ南側の大きくないものを除いて米軍の空襲で焼け落ちたとのことで、米軍が北から襲来したことを示している。 左側の表は石段から上、右側は石段のある崖面から南である。
道を戻ってそのまま南へ上っていく、ほぼ上り詰めた交差点の東西の桜並木が「かむろ坂」で、これを左へ降りていって100mに目立たない2本の石柱の間へと上がっていく道がある。石柱の寺の名も目立たず、本堂らしきものも見えないが、これが明治40年に神楽坂から移転してきた 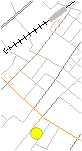
交差点に戻って東南へ(左折して)進む。城南の地の大型斎場、桐ヶ谷斎場が左に右が霊巌寺になる手前の右の小路を入る。そこにはがピカピカに光っている真新しい というわけで、本節は寺ばかり8ヶ所、しかもそのうち4寺は明治40年代に都心から移転し、1寺は都心からの合併を受容れた寺ということになった。 ここで一旦都心に帰るには、行元寺のほうへ戻って最初の信号を右に入ると東急目黒線不動前駅である。次節へは、南へ進んで専修寺が明治末から平成20年まであった首都高速ランプ付近で桜田通り(国道1号線)に出て都心に向かう。 |
| 五反田駅から高輪 |
五反田駅付近の信号で右歩道に移って桜田通り、相生坂を登る。駅前広場を出て150mのところの交差点で坂を離れて右に入る道を採る。突き当る東西の道は、国道下がガードになっていて、右の雉の宮図版に描かれている水路沿いの土手道である。
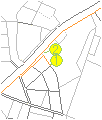
そのまま道を戻って再び桜田通りを右歩道で上がって、右下に先ほどのガードから出た道と右先の雉子宮(現雉子神社:左図②)の鳥居を眺めると、やはり揃って南を向いている図会の描く様が自然で、
右手、教会の先に高野山宿寺・正覚院(現高野山東京別院:右図①)が広い境内を構えていて、続いて建っている高輪警察署のパトカーが並んでいる。高輪署の位置は、宿坊の一つ無量院があったところである。敷地の一体利用は往時からの伝統か。そのほかに宿坊と思われる宝性院、明王院を注付きで描いているが、丹生高野(両)神祠とともに痕跡はない。 交差点の斜向いには、宝井 円真寺(右図②)と黄梅院(右図③)は上行寺とともに、通りの西の傾斜地に並んで左の「覚心寺ほか」の図版に描かれているが、現況は図版より両寺の間隔が小さいようだ。 
通りの東側は西より台地が広い様は図会に描かれているが、現代までに街は細分化されている。その間を抜けて辻に出た右に承教寺(右図⑤)がある。承教寺の背中は、天枢之部で登場する泉岳寺である。江戸時代の絵師で戯作者でもあった英一蝶の墓がこの寺にあることの説明板は、二本榎通りに戻ったところにある。 通りの100m北の左に広い道があり、突き当りが広岳院(図⑥)である。図会は、この寺の末寺である龍吟山興雲院が次の覚林寺の坂の上(図・)にあって、奈良時代以来の本尊の十一面観音に上杉謙信にかかわる由緒があると書いているが、見当たらない。 広岳院前の丸山神社横の小路を北へ抜けて出ると、天神坂である。坂を下りきる50m手前左に花城天満宮の図幅に背景として描かれている光臺院(右図⑦)がある。光臺院より低い位置に天満宮を描いていることと坂の道標に「坂の南」と書いてあることから、坂を下りきって左の辺(図・)に天満宮はあったのだろう。 近代デジタルライブラリーの天キ之部第七分冊第38コマには本節「花城天満宮」の半紙サイズの図版と次節「松秀寺」の左半分の図版とが組み合わされて収録されている。国会図書館は原本の乱丁自体が真実としてそのままのデジタル化を発注したと考えられる。 下りきって信号を渡った左が覚林寺(右図⑧)である。自転車de雑学第Ⅰ篇で調べてあるのでリンクで済ませる。 この北側の目黒通りの北に右の図版の 次節へは目黒通りを西へ進む。 |
| 目黒通り南と北 |
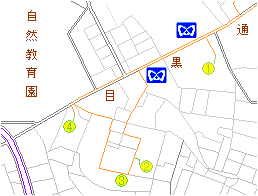
なお、落合(天権之部)にあった 目黒通りに出て西へ200m、地下鉄白金台駅入り口を過ぎて左の小路に入る。道なりに進み、ひとつ十字路を過ぎ、次の十字路のところに九つの寺への方向を示す標識が立っている。これを左折した突き当たりから右三つ三つ目が天枢篇高輪神社の南から移転してきた
両寺とも日露戦争のころの移転である。その他の寺もたぶん同時期に造成された寺団地へ移転したきたものであろう。 ここから目黒川へはかなり下るのだが、一段下の地区が「池田山」で、皇后がお育ちになった正田邸跡地(ねむの木の庭)はこの一角にある。 池田山へは下りずに進んで右折、つまりぐるっと一回りして先ほど目黒通りから入ってきて最初に横切った道へ出て左折する。 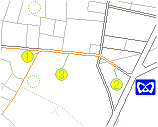
目黒通りに戻って左600mに2節前で通ったJR目黒駅だが、逆に戻って、日吉坂上の信号の先80mのマンションとマンションの間の道を左に入っていく。路面にスリップ防止リングが付いている坂が三鈷坂(現三光坂)である。坂の途中右側に 右の図版の
道を逆に戻って通り過ぎてきた鳥居手前左の自動車用の坂を上がると氷川明神社(現白金氷川神社:右図③)である。ネットサーフィンで「鷺森神明宮はここに合祀された」と見かけたが、とりあえず境内の配置や説明からは確認できていない。 なお、右の図版は氷川神社の西隣に鷺森神明宮の別当の 400m西に北里大学と病院・研究所があるので「北里通り」と呼ばれているこの通りを外苑西通りへ向かって進む。 |
| 明治通りから麻布 |
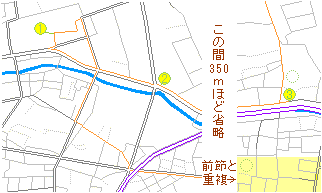
そのまま明治通りを渡って進むと道は直角に右折するが、祥雲寺(左図①)へはこの角の左を入って行く。
これも描かれている南へ抜ける通用口を出ると、明治通りのすぐ東なので、明治通りに出て左折し、外苑西通を渡る天現寺橋交差点を渡ったところに毘沙門堂・天現寺(左図②)がある。図会初版後まもなく毘沙門堂は焼失し、大正初期に再建されるも空襲で烏有に帰した。本堂のほうは平成21年の当初訪問時は更地だったが2年あまりで落慶し、新しい木材の色が輝いている。図会が光孝帝御陵石塔と紹介しているものは、その後東アジア各地にある「育王塔」と考証されて残されている。 続いて明治通りを東へ800m進み、「四の橋交差点」を渡った左に前節の鷺森神明ほかの図版に描かれている明称寺(左図③)がある。その北隣にあった
交差点に戻って右折、東福寺跡と思われる右手のイラン人学校(左手はイラン大使館)などを確認しながらゆっくりと薬園坂を登る(左図右上)。 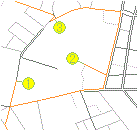
仙台坂上に戻って左折して坂を下り、麻布山入り口の名がついている交差点を左折する。麻布山は善福寺(右図②)の山号で、仙台坂上の台地を山と言っているわけではない。前節の祥雲寺同様、善福寺も塔中だったと思われるいくつかの寺に囲まれている。 寺の東の道を北に進み、パティオ十番のところを左折、大黒坂を登る。
図の番号をクリックして表れるいずれの写真の背景にもドイツビールのジョッキのような高層マンションが写る。この3箇所の中心に聳えるフォレストタワーで、パティオ十番とともに現代の麻布のランドマークである。 次節へは、一本松前の複雑な交差点を西に入る。 |
| 六本木ヒルズの南 |
狸坂という急坂を下りきって向いの比較的緩やかな坂を登っていくと、麻布消防署のところ(中国大使館北)に出る。
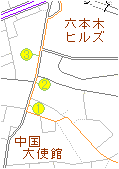
なお、新撰組の沖田総司は、今戸神社の別当寺松林院で亡くなったが、松林院が廃寺になった際に専称寺に移された。浅草のほうは、若者誘致に熱心だが、こちらはセキュリティに腐心して立ち入りを制限している。 専称寺の前の交差点で反対側の歩道に移り、次の信号の手前の左に霞山稲荷明神祠(図③:現桜田神社)がある。
この南北の通りは「テレビ朝日通り」と呼ばれているが、六本木ヒルズプロジェクトのためにテレビ朝日がこの通りから移転したのは1986年である。プロジェクトの完成でテレ朝が落ちついたのは、この通りでなく六本木ヒルズを挟んで反対側の位置である。桜田神社の名は移転してきた住民や末裔である氏子の気持ちの現れであるが、公共施設がランドマークでもない企業名を引きずっているのは、雑学としても低レベルではないだろうか。 なお、専称寺の前の交差点を西へ入って坂を下りて外苑西通りに出ると、10節ほど前に紹介した笄橋跡の東の交差点である。 六本木ヒルズ周りの六本木通りは自転車には不向きである(ように設計した?)。反対側の車道へは左折の多いヒルズ出庫の車の間に強引に割り込むしかない。次節が六本木通の東側なので歩道を行っても、トンネル寄りの横断歩道は、平行してデッキを設けてあるためか信号間隔を絞っていて、車椅子の人は地上からアクセスするな(地下鉄駅からの長い地下道とエレベータには支障はない)ともとれる。
あえて評価すれば、ライブドア事件の報道の際に見られたように、六本木ヒルズの超セレブが事件を起こしても、公衆道徳を持ち合わせていたない取材陣がうろうろするスペースが排除されいていることであろうか。
六本木通りを北へ進み、六本木交差点に出る。
|
| 溜池堰堤跡から霞が関 |
六本木交差点を渡って右折し、同じくらい進んで六本木五丁目の信号を左に入る。突き当たり気味に右折し、首都高速目黒線の下を抜けて向こう側に入っていく。突き当たって左折すると左図の左下に出てくる。
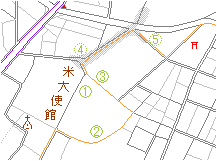
下りきったら左折して進む。しばらくは平だがホテルオークラ本館入口付近から上りになる。これが汐見坂(左図③)である。
溜池の堰堤は図の草色の網掛けをした区域にあったが、明治になってその東端に工部大学校(東大工学部の前身)を設けた際に一部が取り除かれたのをきっかけに全体が除却、平地化された。その結果、白山祠から西に下っていた 溜池の由来は、左図左上の溜池交差点の▲の位置にある石碑に詳しい。ビジネス、観光のついでにお読み頂くとして今回のルートから外す。金毘羅神社(左図鳥居マーク:なぜか図会は取り上げていない)東の区域に葵畑があったのがそもそもの坂の名の発祥ということだけ書いて雑学ボタンも設けない。 虎ノ門交差点を経て霞ヶ関官庁街へ入る。 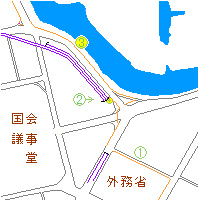
財務省と外務省の間を左に上がる坂に「潮見坂」という道標が立っている。
この坂を上がりきっての突き当たりは国会議事堂の修景公園である。渡り難いが国会前交差点でお濠端に出て歩道で坂を上がっていく。250mほど登って右の水面近くに大きな木(柳?)があり、その袂(右図③)になにか遺構があるように見える。柳ノ井らしい。でも右図②→先の位置に彦根藩邸前の石垣が首都高工事の際移されており元来の位置かどうかは明確でない。また、柳の水と言われた清水谷の彦根藩邸前の櫻ノ井もともに図版付きで項立てされており、混同しやすい。 三宅坂交差点で左歩道に移って半蔵門方面に向かう。 |
| 麹町から南(天キ之部上がり) |
最高裁の北には国立劇場があり、さらにその北には首都高速道路の補修基地が置かれている。この地下は高速道路のトンネルである。このトンネルは左に曲がっていて、北の敷地にまではみ出し、グランドアーク半蔵門ビルの壁面が弧を描いているのは、トンネルの上を避けたためである。
この北を左に入り(左図右端)、東京メトロ半蔵門線の半蔵門駅南出口のある次の交差点をそのまま進んで次の角を左折する。左折後1ブロック先に平川天満宮(左図①:現平河天満宮)がある。 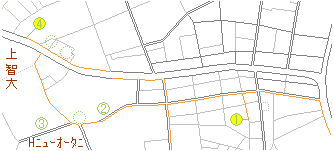
先ほど左折したところに戻って、さらに300m弱西の紀尾井町交差点を過ぎると、道は下り始める。ここにもあったかの富士見坂(左図②)である。現在冨士の方角にはホテルニューオータニなどが聳えていて、どんなに天候が良くても冨士は見えない。 図会は、清水坂は尾州公御館と井伊家の間と書いており、図③の位置になるのだが、別の切絵図では、その手前であったり、図会が注記している麹町八丁目へ出る坂であったりしている。さらにこの坂下つまり富士見坂との行き合い付近に櫻ヶ井(柳の水)があると書いている。加えて前節の柳ノ井も彦根藩邸近くであり、混同しやすい。 自転車を押しながら上智大学の東の麹町八丁目へ出る坂を上がって新宿通りに出、やや右よりの麹町六丁目信号で反対側に渡る。渡って歩道を四谷方向に100m進んで右に心法寺(左図④)があるが、図会が項立てした千手観世音は戦災で焼失したとのことである。 道を戻って先ほど渡った付近に明治末に杉並区和田に移転した 大正9年に杉並区永福に移転した 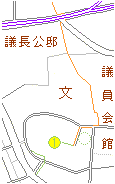
渡りにくい平河町交差点を議長公邸の側に渡り(右図上端)、その東の坂を下っていく。国会の直近でありながら最後は建築基準法の最低幅4mも満たしていない道になるが、道の線形は切絵図とほとんど同じである。左手の議員会館が豪華に整備し直されたが、この道はそのままである。 抜け出た左から下りてくる道は衆議院の二つの議員会館の間を下ってきた道である。往時はここに日吉山王神社(右図:通称日枝神社)の二の鳥居があり、鳥居を潜ると参道が左鍵の手になっていた。 図会が描いたとおりの左鍵の手で神社の正面にたどり着く。神社の前に別当の観理院があったが、現在はマンション(実態は個人事務所群?)である。さらに東には太田道灌が神社とともに設けた第六天祠もあったようだが、すでに同時代の切絵図にすら痕跡がない。 神社の外堀通り側は、自転車de雑学Ⅱで書いた山王パークタワープロジェクトで整備された参詣者用デッキがあるので、地下鉄の駅へもそのまま都心の他の拠点へも便利である。 日吉山王神社は、埼玉県川越の東郊外の仙波にあったが、太田道灌が江戸城内に移し、天満宮とともに祀っていた。その後江戸初期に城内平川寄りに両社は移設され、家光の頃にともに現平河神社付近に移された。
|
| 天キ之部を走り終えて |
|
この部は、図会の分冊が4冊に及んでいる大篇である。地理的には東京の城南地域で、私的には東京に出てからの勤めも含めての生活圏そのものでもあった。 若い日の思い出などもあり、喜々として臨んだのであるが、当初のアップを再編してみると思い込みが走ってとんでもないミスがいくつかあった。レベルの高い閲覧者にはがっかりさせてしまったであろうし、関心を持ちはじめたばかりの人には誤解を与えてしまったのではないかと気になっている。 一方で、図会自体がミスしていると思わざるを得ないところもこの部の中で見つかったりしているのと、所詮は雑学集と割り切ってこれからも適宜更新をしていく。 |
 池尻での姿に較べると急に成長して両岸に桜並木ができている目黒川の左岸に入る。前々節の寿福寺前から都心方向に下りてきた野沢通りは50mあまり左の信号まで行って戻る(右図左端)のがルールだろうが、歩行者も山手通りの信号に合わせて渡っている。
池尻での姿に較べると急に成長して両岸に桜並木ができている目黒川の左岸に入る。前々節の寿福寺前から都心方向に下りてきた野沢通りは50mあまり左の信号まで行って戻る(右図左端)のがルールだろうが、歩行者も山手通りの信号に合わせて渡っている。