江戸名所図会自転車探訪(天枢之部)
| 最新更新箇所へ |
| 高輪海岸 |
図会天枢之部巻末は谷山(現八ッ山)である。目黒の南より(現西五反田から)仙台侯別荘の地の辺へかけて(JR大井駅東部まで)の広い村の名前だったが、今は品川入口の海に面した丘の名になったと図会は書いている。現大崎駅付近の「居留木村」を含まないと大井の仙台坂まで一体にならないので、疑問点である。
八ッ山から北は海岸へ降りる磯の旧坂を経ての磯伝いの道であり、天キ篇で紹介した「高縄の道」が家康が入府前の東海道だったようだ。日本最初の鉄道敷設にトンネルは不可能で、海の中に堰堤を築いて品川駅などを設けたものであるから、線路より海側には図会の名所はない。 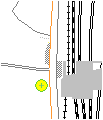
道の左端を走ると、薩摩藩邸跡のパシフィックホテル前の品川バスセンターに入り込むので、そのまま車道を500mほど進むと、左に東禅寺(右図①)へまっすぐ入っていく参道が一般道路化した道がある。この突き当たりの山門の左右に、大田区西糀谷に移転した安泰寺(右図(イ))と品川区上大崎に移転した 第一京浜に戻り、北へ200m余り、左の桂坂を上がっていくと天キ之部で訪れた高輪警察署と高野山東京別院の間に出る。桂坂の出会いの信号から100mほどの左に高輪神社(右図②)がある。図会は一つの鳥居の中に太子堂(常照寺)・稲荷社・庚申堂が並んで祀られている姿を描いているが「高輪神社」の名は使っていない。高輪神社はたぶん「稲荷社」の現在の姿だろう。それらの別当をしていた 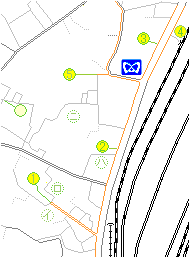 第一京浜を北300mにある泉岳寺の信号からさらに100mあまりの左に願生寺(右図③)があり、図会が記している牛町(現泉岳寺駅付近)で飼育されていた牛の供養塔がある。角(ツノ)が前に出ておらず、躾の行き届いた牛が1000頭以上飼われていることを牛小屋という項を立てて讃えている。図会初版後10年余り後にこの辺から出火した火事は、浅草寺の裏まで帯状に延焼した。強風下の破壊消防技術の頂点ともいうべく、江戸の大火の中で最も延焼帯が細い記録になっている。
第一京浜を北300mにある泉岳寺の信号からさらに100mあまりの左に願生寺(右図③)があり、図会が記している牛町(現泉岳寺駅付近)で飼育されていた牛の供養塔がある。角(ツノ)が前に出ておらず、躾の行き届いた牛が1000頭以上飼われていることを牛小屋という項を立てて讃えている。図会初版後10年余り後にこの辺から出火した火事は、浅草寺の裏まで帯状に延焼した。強風下の破壊消防技術の頂点ともいうべく、江戸の大火の中で最も延焼帯が細い記録になっている。この先の信号は「 この道を抜けたあたりが、右図版の高輪海辺ではなかったかと思われる。日暮里の台地には江戸町民が夕涼みをするスペースがあったが、高輪の台地はそのスペースが無く、右図版のキャプションにあるように、夏の盛りの旧暦七月二十六日は、東の空が白む頃迄高輪台地からの夜風を浴びての月の出(続く日の出も?)を待つイベントが定着していた。 図会が諸書に詳なるを以ってこれを省くとして記述の少ない泉岳寺(右図⑤)へは、さらに戻って泉岳寺の信号で右に渡って入っていく。図会が描いている質素な総門はこの交差点にあった。と当初訪問時に書いたら、「質素な総門」は寺領が狭かったためのようで、その後ここにマンション計画が出てひと騒動になった。 境内左奥の義士の墓の後ろの丘(これが図版如来寺の臥龍岡だろう)にそびえるマンション群の南側にあった 次節へは、泉岳寺前から北に上がる坂を上って行く。 |
| 三田寺町・台町 |
前節から上がる坂が伊皿子坂で、左へくの寺に折れる所から右に高輪大木戸跡へ降りる坂が潮見坂(左図下端)である。その途中左に伊皿子薬師堂・福昌寺が明治中ごろまではあったが、現状は痕跡もないし移転先等も不明である。
伊皿子坂の上で高輪通りと交差し、直ぐ下るのが魚籃坂である。坂を右歩道で下って行く途中に赤い山門があり、坂の名前の元となった魚籃観音堂・浄閑寺(現魚籃寺:左図①)がある。魚籃観音のことは、自転車de雑学Ⅰで紹介した。 当初訪問の頃は「浄閑寺は移転し、魚籃寺という名になった」と理解していた。実は元禄のころからずっと浄閑寺と魚籃寺の呼称が二つある状態が続いていて、図会の出版が許される少し前に寺社奉行の裁きで魚籃寺が正式名称になっていた。
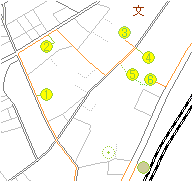 混乱のきっかけは、大分県中津の円応寺で「魚籃院」を名乗っていたこの寺の開祖の称誉上人が元禄になる前に三ノ輪の浄閑寺に移ったことではないかと思う。
混乱のきっかけは、大分県中津の円応寺で「魚籃院」を名乗っていたこの寺の開祖の称誉上人が元禄になる前に三ノ輪の浄閑寺に移ったことではないかと思う。
坂を降り切って国道一号に出、右歩道で右折して100m足らずに図会と同じく荻生徂徠の墓を標榜している長松寺(左図②)の入り口がある。
隣の寺の先右に昔ながらの二間道路を舗装しただけの道があり、これを入って坂を上り直す。「三田寺町」の中心地とも言えるところで、幽霊坂と言うそうだが細長く漂ってくる香からは線香坂が相応しい。坂上は伊皿子坂上からの三田台町で、左折して300mあまり先から少し急になる坂が聖坂である。150m先の左には右の聖坂の図版右端に描かれている大増寺(左図③)への入口と済海寺(左図④)の門とが向かい合っている。
済海寺は近代的な建築になっている一方、墓所に鳥居が建てられているなど訪ねたいことがあるが、入り口にある立て札を見るとセキュリティにピリピリしている感じであるのでそっと立ち去る。 坂を戻って済海寺の隣の公園の中に亀塚(左図⑤)がある。塚の上からは先ほどの済海寺境内が良く見えるが、公園との境には2m近い塀が張り巡らされている。竹芝寺旧地との伝説の地ではあったが、当時既に大名屋敷になっていて明治以降は某財閥の邸宅だったようで、港区の説明板も「よく判らん」と言いたげである。 図会はこの公園の地について、右図版の「竹芝寺古事」で皇女を連れて逃げた衛士の家に天皇の使いが詔を伝えている様子を描き、更級日記の竹芝寺の旧址との説と更級日記のそのくだりを紹介している。しかし、絵の皇女は更級日記での毅然とした言いぶりに較べ怖気づいているように見える。なお、更級日記の記述とは地形や規模が合致しないとの消極説も紹介している。
亀塚の直ぐ東の急斜面には、東隣の御(三)田八幡宮(現御田八幡神社:左図⑥)に通じる階段が設けられている。自転車を下げてこの階段を下りると右の図版とは逆の位置に別殿合祀の稲荷神社と御嶽神社がある。図会が記した
|
| 田町駅から赤羽橋 |
前節末から300mで札の辻交差点を過ぎ、500m余りでJR田町駅前(左図左下)になる。
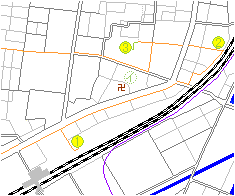 右側の歩道に移り、150mほどの三菱自動車工業本社(江戸無血開城の勝・西郷会談が行われた場所との碑がある)角を右折すると、JRの線路の手前の本芝公園の一部のようになった鹿島神社(現御穂鹿島神社:左図①)がある。今の名前から判るように御穂神社(旧地:左図(イ))を合祀している。なお、図会は両神社とも別当は正福寺としているが、ひょっとすると御穂神社旧地の南にある「正念寺」の誤記かもしれない。
右側の歩道に移り、150mほどの三菱自動車工業本社(江戸無血開城の勝・西郷会談が行われた場所との碑がある)角を右折すると、JRの線路の手前の本芝公園の一部のようになった鹿島神社(現御穂鹿島神社:左図①)がある。今の名前から判るように御穂神社(旧地:左図(イ))を合祀している。なお、図会は両神社とも別当は正福寺としているが、ひょっとすると御穂神社旧地の南にある「正念寺」の誤記かもしれない。 私は中高生のころ年末恒例の落語「芝浜」をラジオで何度か聞いた。主人公が財布を拾った魚河岸は、鹿島神社から公園を挟んだ東の超高層マンションのところにあった。この河岸を支えたのは、室町時代末期に静岡の三保からここに移り住んだ漁民の集団で、合祀された御穂神社は彼らが郷里の三保の本社(現存している)から勧請したものであった。
第一京浜に戻って北東に進み、芝4丁目交差点を渡って右折、ガードの手前を左折して次の十字路を右折して線路沿いに進む。円珠寺という寺の先を曲がったところが毘沙門堂・正伝寺(左図②)の入り口がある。図会は寅の日の縁日の賑わいに「毘沙門天」を奉祝する幟が立てられている様を描いている。現在幟は年中立てられており、田町から浜松町に向かう山手線の電車の左窓からも見ることができる。
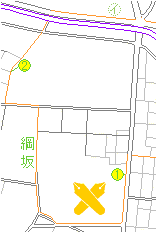 寺前をそのまま西に行き、第一京浜を渡ってもそのまま進むと西応寺(左図③)にぶつかる。本堂は洗練された近代的な建築になっている。境内右手は幼稚園である。
寺前をそのまま西に行き、第一京浜を渡ってもそのまま進むと西応寺(左図③)にぶつかる。本堂は洗練された近代的な建築になっている。境内右手は幼稚園である。戻って最初の十字路を右折、芝4丁目交差点からの道に出たら右折して西に向かい、日比谷通りを渡って日本電気ビルの北側の道に入る。 日本電気ビルのブロックを過ぎると道幅が少し狭くなるが、すぐに国道一号(桜田通り)に出る(右図右下部)。信号を渡り左折(右歩道)、7、80mのところに春日明神社(現春日神社:右図①)がある。後ろは慶応大学のキャンパスで、ここに月波楼があった。 月波楼は、当時の一般木造では珍しい3階建で、ここからの眺望が良いことは、下からはランドマークになっていた。福沢諭吉が慶応義塾を開いて図書館として使い、老朽化に伴ってゴシック風のレンガ張りの建物にした。受験生向けの大学案内などには必ず登場するこの建物は重要文化財となっていて使われていない。最上階には犬養毅揮毫の「月波楼」の額が掲げられているとのことである。
三田2丁目交差点を右折、大学正門を過ぎて右へ道をとり、北へ向かう。慶応のキャンパスが終わる辺りからの坂が綱坂で、大江山の酒呑童子と羅生門の鬼をやっつけた渡辺綱の由緒が残っている。図会は渡辺氏が封じられたのは「箕田(ミダ:現埼玉県鴻巣市)」で、「三田」(ミタ)は聞き違いとの説が有力と断った上で書いている。 突き当たって左折、次の信号で右に下って100mあまり、右にある鳥居が小山神明宮(現天祖神社:右図②)である。図会には描かれていない稲荷が狭い境内をやりくりして合祀されている。別当の不動院は見当たらない。
坂を下りきって中ノ橋交差点をそのまま進み、首都高速道路の下で赤羽川(現古川:ともに渋谷川の下流部)を渡る。さらに信号を渡って右折して次の赤羽橋交差点の手前左(右図(イ))に 赤羽橋交差点を含んで芝公園の一部に渡る区域が右の図版「赤羽」に描かれている広い勝手が原と推測されるが、港区の史跡標などはない。 東に渡り、芝公園の南の歩道をのんびりと行く(右図右上端)。 |
| 芝大門から飯倉 |
芝公園の東南の角の芝公園交差点を直進して進んでいくと、第一京浜国道に出る。左折して400m、大門交差点を過ぎて50mに芝大神宮の石標があり、ここから左が飯倉神明宮(現芝大神宮:左図①)の参道である。
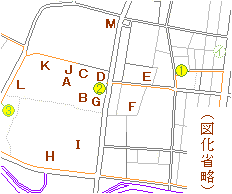 この位置に右の図版(続)の惣門、次の十字路に鳥居と楼門があったと考えられる。現在の境内までは、さらに一般市街地になっているが、安政、関東の二つの大地震と米軍の空襲の後で境内を開放してきたものだろう。別当の金剛院は、左図(イ)の位置に描かれているが、ひしめき合うビルのどこまでが跡地かは判らない。
この位置に右の図版(続)の惣門、次の十字路に鳥居と楼門があったと考えられる。現在の境内までは、さらに一般市街地になっているが、安政、関東の二つの大地震と米軍の空襲の後で境内を開放してきたものだろう。別当の金剛院は、左図(イ)の位置に描かれているが、ひしめき合うビルのどこまでが跡地かは判らない。図会は、頼朝の時代に栄えていたのを小田原北條氏が荒廃させ、家康から家光が神威を復したと社記にあると書いている。
図会は境内のいくつもの名所を記している。それらの明治以降の推移の概況は以下の表のような状況である。
東京タワー前交差点に戻ってタワー方向に入り、東京タワーの真下に上がった右に金地院(現金地禅院:右図①)がある。東京タワーの土地の大部分はこの寺が家光の計らいで与えられた寺領であった。寺の本堂は近代的デザインである。 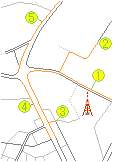 金地禅院の100m西を右に入って道なりに右クランクに進んだ丁度金地禅院の裏に、幸稲荷神社(右図②)がある。上のリストで「転出」とした
金地禅院の100m西を右に入って道なりに右クランクに進んだ丁度金地禅院の裏に、幸稲荷神社(右図②)がある。上のリストで「転出」とした 廃仏毀釈は明治政府の御膝下の増上寺に関しては「廃神毀社」だったようだ。あえて勘案すると伊勢神宮に縁遠い神社だったからか。でも熊野三所権現は「ユヤ天」と言い換えてまでして残したと言うから何らかの権力の横車があったとも思われる。 戻って西100mにある鞍状の飯倉交差点を左折して土器坂(桜田通り:国道一号)を下る。歩道橋を過ぎて直ぐの道を左に入り、次の辻の左先に前節の赤羽橋付近から移転してきた
桜田通りに戻って70m下の信号で反対側に渡り、坂を上る。200mほどの左にささやかに熊野権現宮(現熊野神社:右図④)がある。
飯倉の交差点から200mの左に西窪八幡宮(現八幡神社:右図⑤)がある。家光の母(淀君の妹)が関ヶ原の勝利を祈願し、家光の時代になって宮社を建立したとの記録からはそれまで茅屋だったことが推察される。この神社は、桜田通りから小高くなった所にあり、北側の急傾斜の下に西に向かう500mほどの谷筋の道がある。この谷が西窪の地名の源と思われるが、住居表示変更までは我善坊の谷と呼ばれていた。 谷の北の岡は図会の時代仙石家宅であった太田道灌城跡で、その北が城山であった。「仙石」「城山」はマンションやビルの名として現代に残されている。 さらに200mほど先の神谷町交差点で右折する。 |
| 愛宕山界隈~新橋駅南 |
前節で右折して二つ目の左へ入る道を進むと、突き当たる手前左に天徳寺(左図①)がある。不断念仏など浄土宗の教義を高め、増上寺より前に紫衣を得ていた称念上人が出生の地に開いた寺とのことで、格式は高かった(今も?)。
今回は神社の前にトンネル先の交差点を右折した右にある青松寺(左図②)へまず行く。江戸開幕の頃に麹町から移転したと図会は記している。麹町に負けない都心になった結果、ビルデベロッパーはこの大型の寺が高層化しない空中権を買い取って寺の両側に愛宕山より高いビルを建築した。 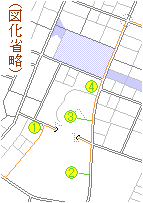 突き当たって右折すると愛宕山トンネルである。できれば右歩道で行きたいが、歩行者もあり左が無難。トンネルの入り口左に愛宕神社への急な階段(裏参道?)があるが、自転車を下げて上がるのは困難である。
突き当たって右折すると愛宕山トンネルである。できれば右歩道で行きたいが、歩行者もあり左が無難。トンネルの入り口左に愛宕神社への急な階段(裏参道?)があるが、自転車を下げて上がるのは困難である。戻って200m北に愛宕山権現社(現愛宕神社:左図③)参道がある。曲垣平九郎が馬を操って上り下りしたという正面急階段を自転車を下げて上るのはリスクが大きい。先ほどトンネルを抜けた右の階段は広く、自転車を下げて上がると頂上の放送博物館前に出る。図会では別当の円福寺がこの階段に向かって左に描かれているが、現地にある寺は円福寺とは全く無関係である。
この道の北隣に真福寺(左図④)がある。近代的な7階建てのビルになっており、入り口左には英訳付きの由緒説明が金属製のプレートに彫られて掲示されている。図会が描いたような神仏習合の諸堂は整理されて薬師に特化している。 青松寺からここまでの道沿いには桜川が溜池(天キ之部参照)から引かれていたが、今は下水道に置き換わっている。 当初アップ時真福寺の北東地区で始まっていた環状2号道路(新外堀通り)の地下トンネル工事に併行して、東京都庁を凌ぐ高さのビルが建築された。 この道路は、進駐してきた米軍が東京湾とアメリカ大使館とを結ぶものとして要求したもので「マッカーサー道路」とも言われている。同様の経緯を持つ話は天セン篇陽光院の節(横浜)でも登場した。当時郊外だった横浜のほうは直ぐ着手して10年足らずで完成したが、こちらは当のアメリカがシャウプ勧告で公共事業を抑えたなどで工事着手できなかった。
その間にびっしりと復興市街地が形成されて補償額は膨大なものとなり、60年間東京都は着手できなかった。長年の都市計画制限による補償されない地権者の損失は、八ッ場ダムの場合と比にならないほど大きい。それでも工事区域内に形成された補償対象の権利の量は膨大で、超高層ビルを道路上に設けることによって権利を移し替えるという仕組みが取られた。
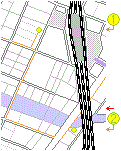
環状2号の北、歩道橋の一つ先の信号を左に入って虎の門病院前で新外堀通りに合流する通りが右の図版の藪小路である。震災復興・戦災復興で拡幅され、「小路」とは呼べなくなっている。 ここでコースは逆に右折して新橋駅へ向かう。この通りは当時「佐久間小路」と言われていたが現在は「烏森通り」と呼ばれている。新橋駅前の再開発ビルの手前のブロック内小路の突き当りに烏森稲荷社(現烏森神社:右図①←先)がある。
新橋駅西の再開発ビルの街区の角で右折、南下する。新外堀通りに出て左折し、第一京浜との交差点の対角の位置に |
| 新橋、(銀座)、築地 |
右歩道のまま第一京浜を北へ進んでJR東海道線などの下とゆりかもめ新橋駅の下を抜けて行くと、新橋交差点に出る。図会の時代に新橋があったのは、直進して高速道路(厳密には高速道路ではない。参照)の下(左図(イ)↑先)である。
これから先は、江戸時代も商家が立ち並ぶ地区で、図会も名所よりも江戸文化の象徴を描いたり、記述することが主体になっている。現在も誰でも知っている場所なのでイメージマップを省略する。 新橋交差点を直進して入っていく通りは中央通りである。金六町は最初の右側街区で、ここ(左図(ロ)↓先)に右の図版の
以下、右の里程表を含め銀座地区をパスしたルートで進める。 昭和通りの起点でもある新橋交差点の一つ東で複雑な歩道橋がかかっている蓬莱橋(明治になって汐留橋から名称変更)交差点の南側に汐留橋(左図①)はあった。 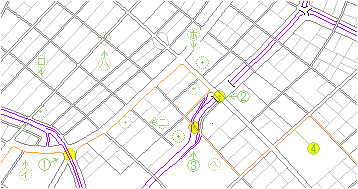 昭和通りを進むのだが、この交差点南部の旧汐留駅周辺の開発が自転車を認めないことの前提となったとも思えるこの交差点は、自転車を下げてこの複雑な歩道橋で渡るしかない。
昭和通りを進むのだが、この交差点南部の旧汐留駅周辺の開発が自転車を認めないことの前提となったとも思えるこの交差点は、自転車を下げてこの複雑な歩道橋で渡るしかない。蓬莱橋交差点から信号二つめを右に新橋演舞場へ入る道の前後が木挽町で、図会が故ありて止められたと書いている山村座はこの辺(左図(ニ)←先)にあった。「故」は絵島生島事件で、アイドルスター生島をまっとうに管理できなかったとして山村座は取りつぶされた。図会初版のころ(天保年間)残りの歌舞伎三座は浅草へ移転させらていたはずだが、森田座が木挽町にあると書いている。森田座の木挽町復帰は安政大地震より後だが、別の座の名義を借りての運営が常態化していたというので、図会は実態に即して書いたのかもしれない。 晴海通りとの三原橋交差点まで行き、そのまま右歩道で右折する。道の向うは、平成25年4月新装開場した歌舞伎座である。こちら側は雑然とした市街地だが、ここは当時采女が原と言って馬場があった(右図版参照)。馬場の向こうに描かれている築地川を渡る萬年橋(左図②←先)は、下の川は流れなくなっても存続している。
そのまま橋を渡って首都高内回りの銀座出口ランプ入口先の幼稚園や小公園のある場所(左図(ホ))に 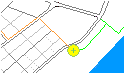 その東は築地市場への観光バスの駐車場になっており、小公園のトイレはバス客が順番待ちをしていた。
その東は築地市場への観光バスの駐車場になっており、小公園のトイレはバス客が順番待ちをしていた。築地市場手前の新大橋通りに出て左折、築地四丁目交差点を対角に渡って右歩道で北に進んで70mに西本願寺(現築地本願寺:左図④)がある。毎日のように葬儀案内が掛かっているのに加えて観光バスも停まっているなど、人の出入りが多い寺である。 寺の北側の道を東、隅田川方向に進むと突き当る。左折して次の信号で右折しする。行く手の信号の先で築地川からの北水路(現存しない)が隅田川に注いでいた。ここで川を渡って明石河岸に入る橋は橋脚が高く、吹き曝したのでだれも正式な明石橋とは言わなくなったという寒橋(右図)だった。水路は埋立てられてポンプ場ができているし、描かれた河岸の角地はには今や老舗となった高級料亭がある。 アパート裏から川岸の遊歩道に出て上流に向かい、首を痛めないように聖路加タワーをチラッと見て佃大橋へと進む。 |
| 佃島~八丁堀西 |
佃大橋は、東京オリンピックのドサクサに地元説明も不十分なまま造られたので、地元の評判は必ずしも芳しくない。車道さえできればという工事だったので歩道のアクセスは両側とも階段で雑だったから何度も補修を繰り返しているようだ。両岸の橋詰めとも潜れるので、楽な南歩道で上がって月島に渡る。 東詰の階段を下りて堤防沿いに北に進んで突き当り付近で堤防に上がっての上流は、佃島とは別扱いだった鎧島で、いわゆる大川端の高層住宅群が聳えている。右に曲がっての突き当りが住吉神社(左図①)でがある。鳥居には明治期の進取のデザインを感じさせる陶器製の有栖川宮の献額が掛けられている。 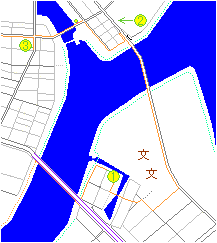
境内を右に抜けて左折して進み、左に抜けられる道で北の幹線道路に出る。この道は左へ向うと2kmほどで東京駅八重洲中央口にぶつかる道である。大川端高層住宅の間を抜けると隅田川で一番新しい斜張橋の隅田川中央大橋である。渡り終えると堤防側に戻る歩道を辿ってそのまま右に進み、道が右に直角に曲がって最初の信号を渡って右歩道で左折する。亀島川に架かる南高橋の袂に恵比須前稲荷社(現徳船稲荷神社:左図②←先)がある。図会では、右の湊稲荷社の図版左端に付注なしに描かれている鳥居がこれと思われる。また、他所から移転してきたと書いているが、明治以降も移転続きで、平成になっても今渡ってきた中央大橋の工事でここに移された。 そのまま南高橋(同じ図版に「いなり橋」と付注されている橋であろう)を渡り、湊に移って最初の信号で左折すると右に湊稲荷社(現鉄砲洲稲荷神社:左図③)がある。同じ稲荷神社でも今見てきた徳船稲荷神社よりもはるかに立派な構えである。境内左には八幡神社ほか5社を合祀ししてあり、いわば総合神社である。図会の時代には現代の南高橋西詰にあり、神社の北の桜川(八丁堀)を挟んで稲荷橋で徳船(恵比須前)稲荷と向かい合っていた。 信号に戻って西(都心方向)へ進む。 三ツ橋は、京橋ジャンクション(右図:紫表示の自動車道の分岐)付近で、堀が十字になっており、区切られた4つの土地を繋ぐ橋がコの字に三本架けられていた(右図版参照)のでこの地域を指す名称となった。三ツ橋から東の堀は桜川と言い、亀島川への合流地点までほぼ八町あったので沿川地域は「八丁堀」と呼ばれていた(町名として公式だったのは昭和初期から30年ほど)。 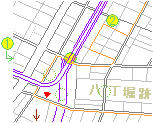 桜川の上流の三ツ橋から西の堀は外堀から引かれる京橋川、北は茅場町付近の日本橋川から引かれる楓(もみじ)川、三ッ橋から南は築地までの三十間堀と呼ばれていた。明治以降いち早く京橋川が埋め立てられ、楓川と三十間堀が首都高速道路用地になるのと併せて桜川も大部分が埋め立てられ、亀島川の合流付近は蓋で覆われた。道路にならなかった桜川(八丁堀)は、公園など公共施設になっている。
桜川の上流の三ツ橋から西の堀は外堀から引かれる京橋川、北は茅場町付近の日本橋川から引かれる楓(もみじ)川、三ッ橋から南は築地までの三十間堀と呼ばれていた。明治以降いち早く京橋川が埋め立てられ、楓川と三十間堀が首都高速道路用地になるのと併せて桜川も大部分が埋め立てられ、亀島川の合流付近は蓋で覆われた。道路にならなかった桜川(八丁堀)は、公園など公共施設になっている。進んできたルートは三十間堀跡の首都高速道路を新金橋で渡る。この橋の位置から少し北に三十間堀最北の 右折100mあまりで鍛冶橋通りを右折すると なお、この国産第一号鉄橋が「八幡橋」として移転活用されていることは、揺光之部で紹介した。
弾正橋の東の交差点は桜橋で、明治になって架けられた桜川最西の橋がこの南にあった。この交差点を左折し(北へ)すぐ左の小路を入り、首都高速道路の手前を右折して100mあまりを右に入ると左のビルの敷地内通路のような参道の奥に伊雑太神宮(現天祖神社:右図②)がこじんまりと建っている。 そのまま東へ出て桜橋交差点からの道を左折して北上する。 |
| 霊巌島 |
前節から200m弱で八重洲通りになる。これを右折して進み、八丁堀交差点で新大橋通りを横切り、50mあまりの亀島橋で亀島川を渡って(左図左端)再び新川地区(霊巌島)に入る。
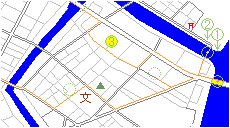 直ぐの交差点亀島橋を直進し、次の信号で左折する。1街区先の右側の小学校から東が越前藩邸跡で、左側が円覚寺で、ここに薬師堂と橋本稲荷社があったことは古地図などで判ったが。どうなったかは区のサイトにも書いてない。
その先越前堀公園(▲)に出たら右折する。公園の北1宅地をおいて亀島川と隅田川を結ぶ水路があり「新川」とか「越前堀」と呼ばれた。鍛冶橋通りに出たら左折する。
直ぐの交差点亀島橋を直進し、次の信号で左折する。1街区先の右側の小学校から東が越前藩邸跡で、左側が円覚寺で、ここに薬師堂と橋本稲荷社があったことは古地図などで判ったが。どうなったかは区のサイトにも書いてない。
その先越前堀公園(▲)に出たら右折する。公園の北1宅地をおいて亀島川と隅田川を結ぶ水路があり「新川」とか「越前堀」と呼ばれた。鍛冶橋通りに出たら左折する。
図会は記していないが、図会初版の30年ほど前に死者1500人という永代橋の落橋事故が起きた。タイタニック号沈没と並ぶ世界最大級の事故である。明治30年の架け替えに当って交通需要の大きさから、旧橋を残しつつ日本橋川の南に外国から最先端の技術を導入して構造体の強度を最高水準にして我が国最初の鉄道(市電)併設橋としたのが現永代橋である。関東大震災では橋板が損傷して改築したが、第二次大戦の空襲には耐え、2007年には国の重要文化財に指定された。
西詰めの信号に戻って右に入ったところにある日本橋川に架かる橋が豊海橋(左図②↓先)で、右の永代橋の図版に付注で示されている。同じ図版の永代橋西詰めに注なしで描かれている鳥居は、左図鳥居印にある「高尾稲荷」である。
永代通りを西、茅場町方面に右歩道で進み最初の交差点を左に渡って(右歩道で)入っていく。この左側(東)が随見屋鋪(図会は「川村随見」としているが、「河村瑞賢」のほうが知られている)のあったところである。図会の時代、次の十字路の左右は右の図版のように酒問屋がひしめいていて随見屋舗跡はその中に埋もれていたようだ。 その十字路を右折して50mほどの右に伊雑太神宮(新川大神宮)(左図③)がある。戦災に遭ったが、商売の復興に併せて酒問屋街の肝いりで再建された。牛頭天、天神、弁天、三峯を備えていた総合神社としての俤は無いが、これが地震、空襲という歴史の試練や市民の幸福追求意識の変化の結果であろう。主要な寄進主体であった問屋街の風情は今や酒問屋(右図版新川酒問屋参照)の組合のビルが残っている程度である。 西に進んで右折して永代通りに出て茅場町のほうに渡る橋が霊岸橋である。 霊巌島と霊岸橋は、図会の時代既に使い分けられていた。霊巌上人がここを埋めて霊巌寺を建立したことに由来するが、寺は明暦の大火後深川に移された(揺光之部参照)。
|
| 茅場町から江戸橋 |
霊岸橋を渡って150mで、メトロ日比谷線と東西線が交わっている新大橋通りとの交差点になる。ここで右歩道に移って進むと、俳仙其角と図会が書いている其角住居跡の碑が100m先の右に(左図←先)のビルの犬走りに設置されている。この先の茅場町交差点を右折する。 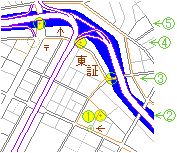 50m先の小さな灯明台が両脇にある小路(参道)を入ると永田馬場山王御旅所(現日枝神社摂社:左図①)である。二つ遥拝所を設けて、神主と別当が別々の役割で祀っていると図会は書いてあり、現在も2社殿よりなっている。別当の観理院は、永田町にあったが廃寺になっていることは天キ之部で書いた。
50m先の小さな灯明台が両脇にある小路(参道)を入ると永田馬場山王御旅所(現日枝神社摂社:左図①)である。二つ遥拝所を設けて、神主と別当が別々の役割で祀っていると図会は書いてあり、現在も2社殿よりなっている。別当の観理院は、永田町にあったが廃寺になっていることは天キ之部で書いた。右の図版では境内左隣に描かれている
南の永代通りへ出たところが先ほどの其角の碑がある場所である。其角とともに徂徠先生が住んでいたのもこのへんのはずだと図会は書いているが、フォローしていない。 北へ進むと左側に東京証券取引所があり、その前の信号を過ぎると鎧之渡跡(現鎧橋:左図←③先)である。 右の山王祭の図版其二を見ると、手前の祭列の最後尾がさらに図の右外まで続いているように描いている。鎧之渡から江戸橋にかけての日本橋川左岸の小網町も氏子町内であったようだ。
また同図版左端手前では祭列がはこさきはし(現在の箱崎交差点)を渡って箱崎の島に入り、其三の図版で湊橋で霊巌島に入り、れいかんはしを渡って其二中景を経て同図版左上の薬師堂から本社に到達している。 東証の北の道を入っていくと、首都高ジャンクションの下に入ってしまいそうな場所に兜塚(現兜神社:左図④←先)がある。
20世紀末にはニューヨークのウォール街と並び称せられた兜町だが、この地名は明治になってこの塚から付けられた。前々節の楓川はこの西側から引かれていたが、現在は首都高都心環状線の高架基礎を支えている。 首都高を抜けて一街区先の郵便局までの間(左図↑先)に当時の江戸橋は架かっていたようだが、現在は昭和通りの橋となっている(左図⑤←先)。
という訳でルート図は省略し、江戸橋を渡って右折、高速道路で風情の無くなった日本橋川に近い道を辿って鎧橋東詰へ戻る。 |
| 隅田川右岸 |
前節から引き続き日本橋川左岸の道を行く。前節の山王祭の図版其二の手前に描かれた祭列のルートであるが、新大橋通りを横切るなど信号待ちは多くなる。
同じ図版で描かれた「はこさき橋」のあった箱崎交差点で首都高速道路が日本橋川から離れるのであるが、ルートは右折して頭の上の自動車走行音を感じながら進む。  首都高速道路が道の正面に見えてくるのは左図右下のように隅田川沿いに向きを変えるからで、その手前右側に「浜町敬老館」というバス停が立っている。ここから隅田川沿いの中洲公園に入る。車いす用の長い斜路もあるが、階段もあるので余分な荷物が無ければ自転車を提げて上り下りして川沿いの遊歩道まで下りて一休みする。
首都高速道路が道の正面に見えてくるのは左図右下のように隅田川沿いに向きを変えるからで、その手前右側に「浜町敬老館」というバス停が立っている。ここから隅田川沿いの中洲公園に入る。車いす用の長い斜路もあるが、階段もあるので余分な荷物が無ければ自転車を提げて上り下りして川沿いの遊歩道まで下りて一休みする。ここから対岸に当時の
戻って橋に上がると、橋の中央部でほどが膨らみベンチが置かれているのでここからもゆっくり川を眺めることができる。 新大橋西詰の信号で新大橋通りを渡って直進、浜町公園にぶつかったら左折して(以下ルート図なし)公園の角で右折して進む。公園を過ぎて信号付き交差点を渡って右折する。もう一つ後ろの信号が久松町交差点でその西に賀茂真淵翁閑居地の表示板が張られているビルがあるが、省略する。 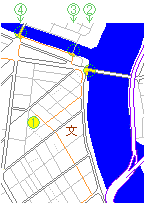 隅田川にぶつかる手前(右図下)を左折して250mほどの日本橋中学校(右図文マーク)がある。隅田川から掘り込まれた薬研堀はこの学校の北側で直角に北西に向かってさらに掘られていた。隅田川への出口には袂に柳の大樹のある橋が架けられていて元来の柳橋だった。図会の時代既に場末感が生じていて、右の両国橋の図版右端に
隅田川にぶつかる手前(右図下)を左折して250mほどの日本橋中学校(右図文マーク)がある。隅田川から掘り込まれた薬研堀はこの学校の北側で直角に北西に向かってさらに掘られていた。隅田川への出口には袂に柳の大樹のある橋が架けられていて元来の柳橋だった。図会の時代既に場末感が生じていて、右の両国橋の図版右端に道を渡って直進すると左に華やかに塗られた不動堂(右図①)が見えてくる。 図会は、右の薬研堀の図版に金毘羅、歓喜天(聖天)及び妙見とともに一見神社仏閣に見えない建物に描いている。 一つ手前の十字路に戻って左折、堤防下道路に出る。左200mで靖国通りの両国橋西詰交差点に出る。橋上に新大橋のようなスペースはないので両国橋(左図②↓先)の橋標を確認したら戻る。図会が描く両国橋は、広重の錦絵の芸術性には及ばないが、周辺の街並みに船宿や土弓場がひしめいている様を描いているのは地誌として貴重である。 靖国通りを北に渡り、神田川に出たところに神田川最下流の柳橋(左図③↓先:右図版其二右手前)がある。一つ上流が浅草橋(左図④↓先)である。図会は千住方面への交通の節目と紹介している。ともに自転車de雑学Ⅱの神田川シリーズで触れた。 浅草橋の大きな交差点を丁寧に渡って、靖国通りとは45度左の江戸通り(水戸街道)を(右歩道で)入っていく。 |
| 大門通東西 |
江戸通りに入って最初の右角を曲がり、そのまま進むと60m程で郵便局にぶつかる。この郵便局の手前(左図(イ))から郵便局にかけての前後30mほどを幅として左右100m余りの長さで最も古しと書いている
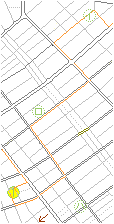 中央遠景に
中央遠景にそのまま進んで清洲橋通りに出て左折し、馬喰町交差点を過ぎて次の信号で横山町問屋街(南半分)に右折する。この通りが当時は日本橋からのメインストリートだった。100mほど先の浜町川に架かっていた緑橋を渡った先の右側(左図(ロ))に錦絵の総合販売店の
次の交差点を左折して進む通りは大門通である。150mほどの右に税務署があり、その先の信号を右折する。直進して次の信号付近(左図(ハ))が右の大門通りの図版の場所で、銅屋(かなものや)が複数あって其角が「鐘一つ売れぬ日もなし江戸の春」を詠んだ場所でもあるがこれまた何の痕跡もないのでルートから外して右折する。この通りが、がくや新道かもしれない。 さらにルート外をコメントすると、この信号から左前方(東)の街区が、明暦の大火まで吉原遊郭のあったところで、走ってきた通りの名もこれに由来する。旧吉原遊郭跡から西南の堀留にかけて右図版の堺町・葺屋町が形成されていたようだが、具体的な痕跡を確認できないでいる。 右歩道で右折して水天宮通りを堀留町交差点で渡る。すぐ先に右図版に描かれた参道の半分もないほどに狭くなった杉森稲荷神社(現椙森神社:左図①)への参道がある。 鳥居が見えないので一つ先の角を右に回っていく(これがいなり新道のようだ)とこちらに鳥居がある。図版と照らしてみると、現在の境内は白狐神の前で取っ組みあっている子どもを母親(?)がなだめている広場くらいしかないことが判る。 左図下部の←先が右図版の堺町・葺屋町の戯場で、歌舞伎の原点の一つである猿若狂言を主体とした市村座・中村座のみならず複数のあやつり座がここで賑わっていることを図会は説明しているのだが、現地にはその雰囲気は全くないので割愛する。 水天宮通りに出て北に進み、メトロ日比谷線の小伝馬町駅のある交差点で右折する。 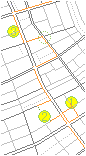 一つ目の小路を入って十字路を過ぎた右に千代田稲荷(現千代田神社:右図①)がある。
一つ目の小路を入って十字路を過ぎた右に千代田稲荷(現千代田神社:右図①)がある。 図会は、千代田村旧跡の項でこの神社を紹介し、太田道灌の弟の『千代田某』ゆかりで『忍ヶ岡の麓から移した』という俗説を紹介するとともに「道灌にそんな弟はいない」と疑問を提案している。道灌以前千代田村は現在の丸の内にあった。太田道灌が江戸城を整備する際に千代田村は村民ともども日比谷入り江の東(図会は鉄砲町(現日本橋本町3丁目)としている)に移され、千代田稲荷は城内に(図会は深追いしていない。)移された。
千代田稲荷は、家光によって城内から現在の渋谷区宮益坂に移転され、さらに明治初期に渋谷区道玄坂に移されたことは天キ之部で紹介した。小伝馬町のほうは、道灌に拉致された鎮守稲荷の替わり(摂社)として村民が祀ったのが始まりではないだろうか。
小伝馬町交差点に戻り、水天宮通りを渡って北に図会の時代にはなかった大安楽寺がある。その北の十思公園にある鐘楼が図会の時代にこの場所から昭和通りを挟んで対称的な位置の旧石町(現室町4丁目)に設けられていた
水天宮通りに戻って信号を渡り、ひとつ北の角を左に入ったところに於玉稲荷(現繁栄お玉稲荷大明神:右図③)がある。図会は旧名桜が池にお玉が身を投げたため「於玉が池」となった古事を記し描いているが、すでに池は無いことも書いている。地名としての「於玉ヶ池」を冠して評判になっていたはずの千葉周作の玄武館道場(跡地は首都高を挟んで北東200m)のことは書いていない。於玉稲荷は、安政大地震をきっかけに新小岩に移された。つまり、こちらは地元が明治以降改めて祀り直したものである。 水天宮通りに戻って次の岩本町三丁目交差点を右折して靖国通りの大和町交差点に向かう。 |
| 神田川沿岸 |
大和町交差点に出て両国橋方向に戻り、東神田交差点で靖国通りを渡る。100m先にある神田川に架かる美倉橋(左上図①↑先)は、右の図版の遠景にあたらしはしとキャプションされている。
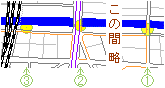 明治以降の架け替えで名称が変わったが、南の神田美倉町とは昭和通りを越えて南西1kmも離れており、何故の橋の名かは不明である。
明治以降の架け替えで名称が変わったが、南の神田美倉町とは昭和通りを越えて南西1kmも離れており、何故の橋の名かは不明である。50m戻って右折、西へ進む。この通りの北の宅地が神田川右岸(南)の堤で柳が植えられていたため柳原堤(封彊)と呼ばれていた。
昭和通りは和泉橋南詰から水天宮通りの分岐を始めており、西へ渡るには岩本町交差点まで南下して渡るしかない。橋南詰め西に戻って150m西へ進むと、右のやや低いところに柳森神社(左上図③↑先)があり、このへんだけ街路樹が柳になっている。 図版の「柳原堤(土扁でなく小里扁が使われている)」は現在の線路上空から神田川の東のほうを鳥瞰して描き、 柳森神社西のガードを潜って次の交差点万世橋南詰を渡りたいが、できない。右歩道で一旦橋を渡って信号まで行って右歩道で戻り、ちょうどJR中央線の下から右に分岐した道に入る。この右は大宮に移転した交通博物館跡である。 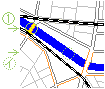 ここに
ここに この広場は明治時代には昌平橋駅とその駅前広場になり、明治末年に辰野金吾設計の万世橋駅が改めて建設された。甲武鉄道の東端の駅だったが、中央線としての東京駅乗り入れ計画があったこと、運転管理の機能は飯田町駅に残されていたことから関東大震災被災後、仮設駅舎のままにされていた。
中央線と東北線が神田駅で合流するに至ってさびれ始め、昭和11年に東京駅舎の一部を使っていた鉄道博物館を移して駅は廃された。戦後交通博物館として総合化を図ったが、地下鉄は別の博物館ができるなどして平成18年にはさいたま市の鉄道博物館に役割を移した。
次の角を右折するが、この道路が場違いな感じで広いのは、交通博物館時代に修学旅行バスがひしめいていたからである。
神田郵便局の前の本郷通が神田川を渡る昌平橋(右上図①→先)は、図会は玉衡之部の書き出しの聖堂で触れているが描かれておらず、筋違八ッ小路の図版の右端ギリギリに描かれている。「昌平」は、聖堂に祀られている孔子の生地の名で、綱吉が聖東の坂に名付け、その後に橋の名にもなった。 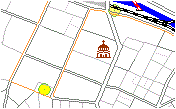 本郷通を渡ってJR御茶ノ水駅に向かって線路沿いに上がっていく坂が淡路坂である。ほぼ上り詰めた左に淡路坂の説明の標柱があり、併せ一口坂とも呼ばれると書いてある。右にはJR御茶ノ水駅の臨時出札口があり、その隣の欅(左下図中央上)に
本郷通を渡ってJR御茶ノ水駅に向かって線路沿いに上がっていく坂が淡路坂である。ほぼ上り詰めた左に淡路坂の説明の標柱があり、併せ一口坂とも呼ばれると書いてある。右にはJR御茶ノ水駅の臨時出札口があり、その隣の欅(左下図中央上)に坂の上は、聖橋交差点で、右向こうはJR御茶ノ水駅の聖橋口である。聖橋の名は、神田川を北に渡った先が玉衡篇のゴールの湯島聖堂であるからであることは言うまでもない。交差点を渡ると御茶ノ水駅の昇降客に巻き込まれるが、気をつけて直進し、直ぐ左折する。 100mほどで左がニコライ堂、右が駿河台予備学校1号館になる。ともに書きたいことはあるが、そのまま400m足らずの直線道路が終わる手前右に淡路坂から移転した 西へ進んで明大通りを右折、再び坂を上がってJR御茶ノ水駅西口の御茶ノ水橋を渡る。(左下図左上)
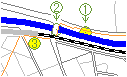 この北東300mの順天堂大図書館裏に東京都の水道歴史館があり、この地域が神田への給水地になっていたことなどを説明している。
この北東300mの順天堂大図書館裏に東京都の水道歴史館があり、この地域が神田への給水地になっていたことなどを説明している。右の図版で懸樋の下の空間にはめ込んだように描かれている水道橋(右下図②↓先)は、ほぼ現在地と同じ位置にあった。現在は東京ドーム最寄りのJRの駅名として知られている。 坂を下って白山通りとの水道橋交差点を左歩道のまま左折、JRのガードを潜って直ぐの信号で白山通りの反対側に渡り、線路沿いの狭い道に入ると左の樹の間から三崎稲荷神社(右下図③)の社殿の裏が見える。正面鳥居は次の角を左折したところにある。 一旦駅寄りに戻り、直ぐ西を左折して南西に進む。 |
| 九段北~猿楽町 |
前節から首都高速道路池袋線の側道(左図右上)に出るまで400mほどの間の交差点は、斜め交差ばかりなので要注意である。高速道路の下には日本橋川が流れていて橋の名は新川橋である。
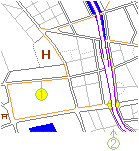
現在の日本橋川の最上流部である神田川の三崎分水口から新川橋下流までは、江戸初期から280年近く埋立てらていた。明治36年に川は復活したのだが、地域住民にとっては「新川」だったからこのような名が付けられた。
橋を渡って進むと専修大学通りが飯田橋から南下してきた目白通りにぶつかる少し手前に出る。右歩道で行き、目白通り向こうのホテルグランドパレス側へ渡って右歩道で南下し、
中坂のちょうど中間の左に戦災後市谷船河原町から戻ってきた津久土明神社(現築土神社)の幟が立っており、ビルのピロティを通り抜けた先(左図①)に社殿がある。
坂を上がって信号を左折、靖国神社前に出る。神社前の道路が堀に向かって下る坂で幅員が広いのは当時の図面にも描かれているがその理由は未調査である。靖国神社については、本サイト内合祀と習合で述べてある。神社に向きあっている建物は、旧日本住宅公団本社だったが、現在は東京理科大学が使っている。 靖国通りに出て真正面の内堀を渡って田安門から皇居外苑に入ると武道館である。ここから右への内堀が現在の桜の名所千鳥ヶ淵である。 靖国通りを左折して下る坂が九段坂である。大八車などの上り下りで、車夫が緩急の間をとるためと躓いた途端に車が一気に坂を転げ落ちるのを防ぐため、九段に分けて勾配を緩和してあったことから名付けられ、今や元来の地名の飯田町や田安台を押しのけての地名になった。 目白通りの起点でもある九段下交差点を過ぎ、首都高速道路の下で日本橋川を渡るのが魚名板橋(現在の橋の銘板は「俎橋」。図会も併用。左図②↑先)である。橋の手前左の小公園は、路上禁煙条例に加えて禁煙ビルが増えたため、昼休みなどは愛煙家が集まっている。 橋を渡って左折、北へ50mほどの道が最も低くなっている位置に右の飯田町図版の右端にとんとん橋とキャプションされた橋があり、その下は東に引かれた水路だったようだ。この辺が日本橋川から分岐した菰が淵の最上部で、舟運のターミナルの「飯田町河岸」として機能していたようだ。 とんとん橋の後ろに細い水路から水が落ちていて、その水路を跨ぐ橋が描かれている。これが、菰が淵の項にある
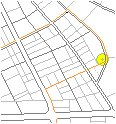
堀切橋東詰(西神田ランプ入口)で右折して西神田交差点を真っ直ぐ渡り、さらに白山通りをも渡って(右図左端)進むと明治大学の猿楽町キャンパスに突き当る(右図上部)。右折して道は右に弧を描いて正面に幼稚園が見える。その道路反対側に、図会に描かれた鎌倉町(現内神田2丁目)から大正年間の美土代町移転を経て戦後現在地移転をした |
| 一ツ橋・錦町そして芝崎村 |
白山通を南下して神保町交差点を渡って300m足らずの交差点の左先に野球ボールを握った手首のモニュメント(左上図(イ)↓先)が立っている。詳しくは右の雑学タブ「野球発祥の地」をクリックして頂くとして、そこに建つレトロな感じを残すビルは東大ほか旧七帝大系卒業生の社団が運営している学士会館の敷地である。この敷地から南日本橋川までの間の東西600mほどの幅の区域が、護持院(旧地)原であった。
 江戸城が市街地から延焼を受けたのがいずれも神田方面からであったので、幕府は機会あるごとに建築禁止区域(火除け地)を日本橋川の北に設けた。
江戸城が市街地から延焼を受けたのがいずれも神田方面からであったので、幕府は機会あるごとに建築禁止区域(火除け地)を日本橋川の北に設けた。
学士会館南の交差点を左歩道で西へ進む。左の街区が一番小さい四番原(右図①下)だったようだが、ここに幕府が設けた蕃書調所があり、東京大学の前身の前身のさらに前身である(「野球発祥の地」参照)。 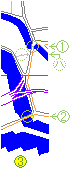 直ぐにややこしい交差点になる。まずひとつ横断歩道で渡ると日本橋川左岸である。右(上流)へと進むとまた横断歩道が右と左にある。左の横断歩道の下に道の向こうから日本橋川が流れ込んでいる。そしてここが現在の雉子橋(右図①)で、前節で触れた菰が淵はここから上流だった。図会当時の日本橋川は清水濠(現水路から40m西)から流れ出していて、そこ(右図(ハ)←先)に当時
直ぐにややこしい交差点になる。まずひとつ横断歩道で渡ると日本橋川左岸である。右(上流)へと進むとまた横断歩道が右と左にある。左の横断歩道の下に道の向こうから日本橋川が流れ込んでいる。そしてここが現在の雉子橋(右図①)で、前節で触れた菰が淵はここから上流だった。図会当時の日本橋川は清水濠(現水路から40m西)から流れ出していて、そこ(右図(ハ)←先)に当時文章だけでは伝えにくく、普通に地図に書いても首都高が隠してしまってやはり判りにくいので、右図のピンクの線から上(北)は首都高を消してみた。なお、雉子橋跡から次の竹橋方面へは自転車では戻るしかなく、訪れても感慨を及ぼしてくれる何ものもないので写真も撮らなかった。 南へ進んで清水濠と平川濠の接点に架かる橋が竹橋(右図②←先)である。竹橋の平川濠側で内堀通りの西、紀国坂の近代美術館前で濠の向こうを眺める。皇居石垣の向こう右手に屋根の見える宮内庁書陵部に東南のほうから登っていく坂が梅林坂(右図③)である。このへんに天キ篇で紹介した平河天満宮と浄土寺、揺光篇で紹介した法恩寺があったと図会は記している。図会も記述だけで御城内の見取り図は控えている(立ち入っていない?)ので私も遠望に留める。自転車でなければ入苑券を買うことによって散策などは可能なようである。 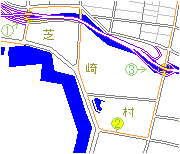 内堀通りを平川濠側歩道で戻り、次の平川門交差点で東側の横断歩道で北、白山通りに入る。首都高速の下で日本橋川に架かるのが一橋(左下図①↑先)である。
内堀通りを平川濠側歩道で戻り、次の平川門交差点で東側の横断歩道で北、白山通りに入る。首都高速の下で日本橋川に架かるのが一橋(左下図①↑先)である。橋を渡って一ツ橋河岸交差点の左向うが三番原で右が一番原(図会は三番の東は二番にと描いているがここが一番との資料もある。)だったようだ。そのまま歩道を右折してみ錦町交差点で同様に北をを向いての右先が二番原だったようだ。しかし、その安政の資料では、騎馬当番所となっている。 錦町交差点で右折して錦橋を渡った所が一橋家の屋敷が広がっていた区域で現在は大手町一丁目である。外神田へ移転した神田大明神や西浅草へ移転した日輪寺があり、太田道灌が江戸城を築くまでは地域の中心地であった。気象庁前で内堀通りに合流し、次の信号で左に入ると60m先に神田明神旧地(将門塚:左下図②)がある。休日だけでなく平日でもパワースポットとして、ビジネス街に場違いな姿の訪問者が多い。 東の交差点を左折して神田橋(左下図③↑先)で本節だけで四たび日本橋川を渡ると、本郷通りの起点の神田橋交差点である。北上して、江戸名所図会を著した齋藤家が町名主を務めた神田雉子町へ向かう。 |
| 旧神田雉子町 |
本郷通り美土代町交差点の次の信号で右歩道に移る。次の右斜めに入る通りが丹後殿前の通りである。
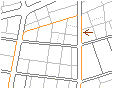 図会は、「神田川」の項と「藍染川」の項との間で説明している。
図会は、「神田川」の項と「藍染川」の項との間で説明している。 図会が記しているのに他の文献から補足して説明すると、沢庵禅師らと親交のあった堀丹後守直寄が村上藩主を隠居後この通りに住んだので本文のように呼ばれるようになった。しかし同時代地域には湯女風呂(現代のトルコ風呂・ソープランド)が林立して、幕府公認の新吉原が寂れてしまうほどであった。しかも、その客は旗本崩れの無法者が多かった。彼らは湯女が羽織っていた丈の長い綿入半纏姿でこの通りを徘徊した。
江戸の人々はこの集団の姿を「丹(後殿)前六法風」と呼んで眉を顰めていた。そんな中幡随院長兵衛が六法の一つ白柄組に暗殺される事件が起こり、幕府はその三年後に湯女風呂を禁止する。しかしこのファッションは関西に伝わり、くつろいだ部屋着の「丹前」として現在も定着している。東京周辺では、初期のイメージの悪さから「どてら」と呼ばれているが、語源は不明である。 通りの南側(現美土代町)から東の現神田司町にかけてが神田雉子町で、その町名主を代々務めてきたのが図会を著した幕末の齋藤家3代だった。居宅跡は、この通りを東へ出た外堀通りを右折して50mの左だったようで、歩道の植樹マスに碑が立てられている(左図←先)。当初の探訪で発見できずそのままアップしたら何人かの愛読者からお知らせいただいた。言い訳だが、明治20年の地図の雉子町は、江戸時代の範囲より北にシフトしており、居宅跡の碑は三河町の区域になっている。江戸時代は、ご公義の事業での替地先を従前の地名として従前通りの祭祀を続けることが認めらていたようで、雉子町付近は異なる町名が敷地単位で入り乱れていた。明治になって雉子町がシフトしたのもそのせいとも思われる。 そのまま外堀通りを南下して本節スタートの神田橋交差点の一つ東の鎌倉橋交差点へ戻る。 |
| 神田堀界隈 |

鎌倉橋交差点を左折して二つ目のビルのところ(左図(イ)↓先)に右図版の
さらに東へ進んで龍閑橋交差点で外堀通りと岐れて左に入り、JR神田駅南のガードを東に抜け、鉄道東の側道を左折する。微妙なアンジュレーションだが、次の鋭角なT字路付近(左図(ロ))が最も低いので、この辺を藍染川(神田堀)が東北東に流れていたと思われる。
そのまま今川橋交差点と西福田交差点とを過ぎて首都高速道路のある昭和通りに至る。昭和通りは渡らずに右折、つまり右歩道で行き、歩道橋直前を右に入る。この道は、神田堀(龍閑川)跡で、千代田・中央の区界である。昭和通りの向う側も同様で、川は5節前の「大門通り東西」で紹介した浜町川に合流していた。 小路に入って直ぐ左(千代田区側)に、福田稲荷神社(現左図①↑先)がある。図会は大久保主水屋敷内にと書いてあり、その屋敷は左図(ハ)→先とのことで、200mほど移動している。震災と戦災の二度の区画整理が実施された地域であるので、その時の換地計画の産物だろう。
西へ進んで中央通りへの出口(左図(ニ)↓先)に「今川橋あと」の碑がある。図版では舟運があるように描かれているが、現在までの経緯は右の雑学でどうぞ・・・・・。南の室町四丁目交差点を使って反対側に行くと、歩道内に右図版を銅板にした橋の説明板がある。 一つ北の道を西へ入った北(左図(ニ)→先)に当時の高級和菓子製造の大久保主水の家があり、門前の井戸が主水井と呼ばれた名水だったようだ。何の痕跡もないことを確認するだけで通り抜け、次の十字路から左クランクに進んでJRガードを抜ける。ガード下からしばらくは、昭和レトロの居酒屋街の最後の姿のような「西今川小路」である。 外堀通りに出ると車道との間が公園になっていて、龍閑橋の親柱がモニュメントとして置かれている。左折して再びJRを潜って左折し、次の右に入る道を入っていくと、左に白旗稲荷神社(左図②→先)がある。 この神社は、図会の時代には先ほどの「西今川小路」左にあったのだが、新橋と上野を鉄道で繋いだ際に跡地を呑屋に譲ってたぶん同じ区内のここに移転したのだと思う。 主水井と白旗稲荷は福田村旧跡の項で書いており、この辺を指している。東へ向かって走った際の「西福田町」交差点は「西福田稲荷」交差点の省略名なのだろうか? 東に出て右折、江戸通り(中央通りから先は国道6号で、言問橋を渡ると水戸街道になる)に出たら左折して室町三丁目交差点を渡る。右歩道で1街区先の右への入口に 一つ先の十字路で南の国道6号に出て室町四丁目交差点に戻り、日本橋方向(南)に向う。 |
| 日本橋川左岸 |
図会は、須田町の交差点から金杉(現芝四丁目)まで間を通り町としている。東京都は上野駅前から新橋駅前までの道路を「中央通り」と呼ぶよう公告した。両者とも広(長)過ぎて、実際には細分して「日本橋通り町」「金杉通り町」「秋葉原の中央通り」「銀座の中央通り」などと呼ばれてきている。
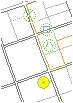
室町3丁目交差点から30mほどのところ(左図(イ))に そしてその先の交差点の東西が本町通りで、6節前の冒頭に書いたように当時は浅草御門へのメインストリートだった。交差点を左に曲って100mほどのあたり(左図(ロ))から先は右図版の本町薬種店が何軒もあり、しかも暖簾分けシステムで「鰯屋」の看板の店がいくつもあったとのことである。
次の交差点の中央から当時の西を描いたのが、右図版の駿河町三井呉服店で、江戸の繁栄を示すものとして教科書などに最も引用されている。図の右側は三井住友銀行になっているが、左側(左図①)の三越は当時の家業を引き継いでいると言えよう。 ここで左折してさらに次の左に入る道を入る。 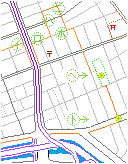 十字路を過ぎたあたりに浮世小路が左から出てきたのだがもちろんなにも痕跡はない。次の角を右に入っていく。
十字路を過ぎたあたりに浮世小路が左から出てきたのだがもちろんなにも痕跡はない。次の角を右に入っていく。当時は次の十字路付近まで西堀留川が掘られており(右図版「伊勢町河岸通」の左遠景霞下に相当)、この手前あたりから河岸だった。この通りも昭和通りで行く手を阻まれるが、その手前から昭和通り向う側にかけてが堀北側の伊勢町河岸だった(右図(イ))。 昭和通りを南100mの本町2丁目交差点(此の辺が伊勢町河岸通図版の米河岸、江戸橋寄りに堀の東西を結ぶ この十字路で左折して次の十字路の東西の道が何度も書くが日本橋から浅草橋御門への道で、この右が当時の大伝馬町一丁目(現在は日本橋本町:右図(ハ))だった。ここに
南へ戻ってぶつかる辺り(右図(ホ))が塩河岸であった。左クランクで出た通りが、本町2丁目交差点から入ってきた通りで、東堀留川の堀留の河岸で、右の同図版の火の見櫓とほぼ同じ位置に日本橋保険センタービルが聳えている。なお、6節前に訪れた椙森神社は右図の赤い鳥居マークである。 そのまま通りを渡って進むと、左に堀を埋めて作った児童公園(右図(ヘ)→先)がある。右の小舟町祇園会御旅所の神事は現在ここで催されている。  公園の中を南に出て細い通りを直進する。この通りは、埋められた堀の中心線である。通り抜けた左右の道は日本橋と人形町を結んでいる通りで、6節前にルートを割愛した堺町・葺屋町の図版で、中央手前に描かれている
公園の中を南に出て細い通りを直進する。この通りは、埋められた堀の中心線である。通り抜けた左右の道は日本橋と人形町を結んでいる通りで、6節前にルートを割愛した堺町・葺屋町の図版で、中央手前に描かれている右折して江戸橋の北詰で交差点を渡ると、
次の信号左が図会の時代から街道の起点となっていた日本橋で、道路元標のことなどは自転車de雑学Ⅰで触れた。 |
| 東京駅東西 |
図会は、日本橋から八重洲通までの間について、江戸橋と茅場町の間で取り上げている。私の編纂順からすると8節前に続けることになるが、何とも中途半端なルートになるのと、現代の地域認識に合わせてここでフォローする。
しかし、この間の図版に関する痕跡は、前節にもまして残されていない。そんな訳で左図はイメージマップの体をなしていないことを御理解いただきたい。 
日本橋中央通りへ出て左折して京橋までの間に順次右の残りの図版ゆかりの場所がある。あくまで場所であって描かれた形も風俗も今は伝わっていない。 日本橋のすぐ南、左手が広くなっているところ(左上図↑先)は、右図版の
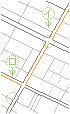 南の永代通りとの交差する日本橋交差点から400m弱で八重洲通りと交差する(左中図(イ)↓先)。ここが右図版の中橋(広小路)である。
南の永代通りとの交差する日本橋交差点から400m弱で八重洲通りと交差する(左中図(イ)↓先)。ここが右図版の中橋(広小路)である。交差点の東京駅側の中央分離帯に、「ヤンヨーステン銘板」とモニュメントがある。
さらに京橋交差点まで進んで鍛冶橋通りに右折、鍛冶橋交差点で外堀通りを右折する。下線が右図版八見橋の左端に付注されている
外堀通りの東京駅側が走りにくい状況は私が自転車を事務所に置いた時から9年経っても変わっていないので、右歩道のまま進む。 500m余り北上して永代通りに戻る40m手前の反対側の鉄鋼ビルの敷地にかけて 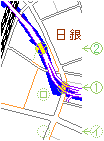 (遠山金四郎が務めた北町奉行所は呉服橋を渡って左。)永代通りとの呉服橋交差点を渡るとすぐの日本橋川を渡るのが一石橋(右図①←先)である。渡る手前の右が西(檜木)河岸と呼ばれたことは前節の日本橋図版にも付注されている。
(遠山金四郎が務めた北町奉行所は呉服橋を渡って左。)永代通りとの呉服橋交差点を渡るとすぐの日本橋川を渡るのが一石橋(右図①←先)である。渡る手前の右が西(檜木)河岸と呼ばれたことは前節の日本橋図版にも付注されている。次の常盤橋交差点で道の左に移り、80mほどの所に常磐橋(右図②←先)があり、その先に常磐橋御門が現存している。御門を抜けると小公園になっている。小公園の南に出て信号を渡って右の歩道に 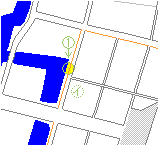 信号を渡った先は、ビルとビルとの敷地内通路のようだが、関係者以外も通り抜けている(車はダメなようだ)のでそのまま通り抜け、永代通りを右折する。
信号を渡った先は、ビルとビルとの敷地内通路のようだが、関係者以外も通り抜けている(車はダメなようだ)のでそのまま通り抜け、永代通りを右折する。JRのガードを抜け大手町交差点の50mほど手前に 国道一号をなぞって永代通りを大手町交差点で左折する際に右歩道に移る(左下図上部)。右側のビルが途絶えてお濠になったところ(左下図①↓先)に
 和田倉門交差点の左には復元なった東京駅が見える。八重洲口広場に屋根をかけたりデッキを設ける工事の工事用クレーンが見えていて、街の景色としてはいまひとつだが、2013年の秋までは完成するらしい。
和田倉門交差点の左には復元なった東京駅が見える。八重洲口広場に屋根をかけたりデッキを設ける工事の工事用クレーンが見えていて、街の景色としてはいまひとつだが、2013年の秋までは完成するらしい。南へ800mで日比谷交差点である。お濠と別れて南に渡った日比谷公園の入口にある石垣が日比谷御門跡である(右下図)。図会で項立てされていないが、先ほどの「八見橋」の最遠景に付注とともに小さく描かれている。
図会のチームは岩倉山を訪れていないと考えられる。岩倉が現青梅市小曽木の岩蔵であることには異論が無い。岩陰を住居にした痕跡のある巨岩があり、現代では古代遺跡(青梅市は「史跡」としている)として扱われている。ここには4里山奥に入った御岳山(奥の院)の神社(蔵王権現:現武蔵御嶽神社)の摂社が置かれていた。 武蔵の地名の起源や言い伝えの「日本武尊武具収蔵の地」を確かめようとする動きは同時代盛んだった。その中に摂社の別当を訪れた記録があり、「宝蔵を蔵王院の奥の院と当方とで共同管理していたが、昔争いが起こって当方は手を引いた」という趣旨の説明を受けている。図会のチームが訪れていればこの別当に会って何らかの記述をしたはずである。あるいは会った結果論争のどちらかを加担することになるのを避けて伝説に留め置いたのかもしれない。
|
| 完走の感想 |
|
このシリーズに取り組むきっかけは、「靖国問題での分祀不能論」を神社当局が主張したことへの疑問だった。明治以降の政治的な神道国家形成が軍部中心に推進されたのだが、その影響を受けていない時代の日本人の宗教観を知ろうとしたものである。たまたま手元にある江戸名所図会が社寺の創建の経緯を記しているのを思い出し、とりあえず机上で神社だけ簡単に調べて別ページの「合祀と習合」をアップした。 リストを眺めていて社寺の立地・配置が神仏分離令などでどう変わったかを見て歩くことを種切れになっていた「自転車de雑学」の新シリーズにすることに思い至った。巻末から始めて玉衡之部に入った頃に高校で同級の丸山一郎君(身障者の社会参加の向上に生涯をささげた。平成20年3月没時は埼玉県立大学教授)を大学に訪ねた際に「合祀と習合」を褒められた。天権之部の調査の際には浦和で落ち合う話をして別れたが、約束の頃に彼は大学に無理して通っては体力を失って病院に戻るという状態になっていた。残念な思い出である。 宮仕えの傍らで5年~7年の年月が必要と計算していた。平成20年6月にリタイアして以降は調べ損ないのフォローに何度も出かけることも容易で、目的を達したら帰りは電車を使わないなどして、1年半で約4000kmを走った。しかし、後半に残した地域は、前半の地域よりも明治以降の変遷だけでなく図会以前の変遷も多いこと、かつ多くの人が関心を持って調べた結果諸説入り乱れているものが多いことなど、アップに耐えうるだけの調査と理解に難渋した。 それでも計算よりずっと早く平成21年12月にワンラウンドを走り終え、サイトとしての暫定完成となった。 しかし、3年8ヶ月かけての作業の結果表現方法などが異なってしまっていること、その後判明したり変化した個所があること、調査ミスなど閲覧された方からのご指摘に応えるべきことなどから第二ラウンドを始めた。結局さらに3年2ヶ月近くかかり、まあまあ恥ずかしくないものは当初の計算だけ時間が必要だったのだと自分勝手な辻褄合わせをしている。 |