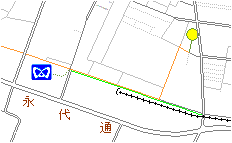江戸名所図会自転車探訪(揺光之部)
| 船橋大神宮周辺 |
揺光之部の巻末は茂侶神社(現茂侶浅間神社:左上図)である。京成電鉄の船橋競馬場と
JR東船橋駅の中間に位置するが、折りたたみ自転車の広げ易さと道の判り易さは後者になる。
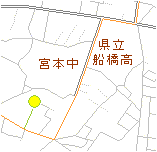
南口に出て350m南(左上図右上)、信号を右折して県立船橋高校の西側の道を左折して南に入っていく。道は細くなって突き当り気味に変則五差路に出たら右折する。100mほどの右(北)側に茂侶神社の参道入り口があるが、公衆電話ボックスが有るだけで鳥居はない。境内にかけての樹木には古木もあり、夏は涼しい。境内の手前の段差を上がると鳥居があり、「茂侶神社」と刻んだ額が掲げてある。境内の北、中学校との間の道路に出る裏参道が社殿の左右に付いている。
図会では、海浜の砂山の神社で、富士の白雪も房総の山々も眺望に入り、「風光最も秀美なり」と書いている。しかし、周囲の白砂青松の砂山は現在ではすべて住宅地となっていて、風光を鑑賞する余地はない。もちろんかつての海辺は京成電車が走り、その先には船橋競馬場、湾岸道路、大規模な工場倉庫街と海ははるかなたである。
茂侶神社の参道入り口に戻ってさらに西に進む(左上図左下)と、道は緩やかに左に曲がる。道なりに下っていくと2車線の道路に出る。右折して見えてくる五差路の信号のところに意富日(おおひ)神社(現船橋大神宮意富比神社:左下図①)の鳥居がある。
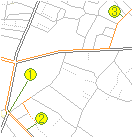 境内の碑に明治維新の戦災(戊辰戦争)で焼失した後、地域の寄付で再建されたことが記されている。
図会に記されている秋の大祭の前日の奉納相撲は、現在では少年少女主体となっているが継続している。また、神社境内の広さが船橋〜行徳ルートでは最大であるうえに、36の神社が境内に合祀されている。
境内の碑に明治維新の戦災(戊辰戦争)で焼失した後、地域の寄付で再建されたことが記されている。
図会に記されている秋の大祭の前日の奉納相撲は、現在では少年少女主体となっているが継続している。また、神社境内の広さが船橋〜行徳ルートでは最大であるうえに、36の神社が境内に合祀されている。
常盤御宮(現常磐神社)は、ほぼ図会の配置通りに本殿右奥にあるようだが、祭礼の時以外はだれも立ち入らせていないとのことである。なお、図会は常盤御宮の東に付注で 東光寺(左図②)は、大神宮の直ぐ東にある。山形の天童で弘法大師が始めた天道念仏踊りの由緒が図会に書かれているので、伺ってみようと思った。しかし、寺は近代的な新興宗教の会館風でドアを開けるのがためらわれた。 船橋大神宮前に戻り、境内西の通り(旧上総海道)を進み、大神宮下交差点で船橋通りへと左折、海老川を渡り、本町4丁目の次を左折して100m余の右に東光寺とともに天道念仏踊りを行っていると 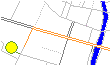 図会が記した不動院(右図)がある。イメージマップの写真にあるようにお年寄りの日向ぼっこの場所になっていたが、境内はそれなりの広さがあった。
図会が記した不動院(右図)がある。イメージマップの写真にあるようにお年寄りの日向ぼっこの場所になっていたが、境内はそれなりの広さがあった。図会は記していないが、門前には右下の「私の推察」に書いた地震と漁場争いに起因した追善供養の説明板とその碑が立っている。 JR船橋駅は北北西(京成船橋駅は手前100m)にあるので戻りを急ぐ方はこちらに向かうとして、再び海老川を東に渡る。 大峯山慈雲寺(左下図③)へは、大神宮下を直進して坂を上がり、最初の信号を過ぎて左に入る二つ目の道を入って行く。冒頭の茂侶神社と同様住宅地の中に埋もれているうえに入口に別の宗教施設があり、見つけにくかった。国府台の「鐘ヶ淵」の地名の由緒の寺と図会に書かれている。 図会で慈雲寺の前の項が遠ヶ澪(別名御菜ノ浦)で、慈雲寺はここから2丁と書いている。遠ヶ澪の場所ははっきりしないが、現海老川ではないかと思う。
そのまま進んで峰台小学校校門から100mほどを左折して昔の成田(海)道を進む。 江戸時代まで西から上総に向かう道と成田に向かう道の分岐点に出来た宿場として船橋は下総の中心地だった。一帯の地域としての「総名」の船橋は海神村、九日市場村、五日市場村などに及んでいると書いている。しかし、戊辰戦争で街が壊滅的打撃を受けたことに加え、明治以降県庁が千葉市にできたこともあって、地域でのイニシアティブは弱まってしまった。
埋立地の活用で競馬場を始めとする遊興施設ができて、第二次大戦後は東京郊外の都市的遊び場所としての印象の強い街になっていった。その後東京都心に直結する地下鉄東西線が西船橋駅まで延びたり、総武線が東京駅地下に入り込んだりして急速に東京の郊外住宅都市の性格を高めてきている。 |
| 船橋駅北東部 |
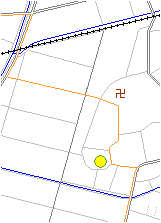
道は一旦低くなった後、JR総武線を越え、緩やかに下っていく。農業用水路を渡って緩やかに上る向こうの小高い住宅地に
ぶつかるように道は右に曲がる。この曲がるところを左に入ると、正面に意富比神社(現東町意富比神社:左図)がある。大神宮について「比を日としたのは天正の台命(=家康の仕業)」とあり、こちらが気になり訪れた。
北に進んで突き当たりに不動院というこれも前節に登場したのと同じ名の寺がある。その前を西に下り、直線の土地改良道路を走って海老川にぶつかり、右折する。 東葉高速鉄道の下を抜けて次の信号を左折、緩やかに上っていき、ぶつかり気味に左折して進む。この右手の台地が古く夏見厨(郷・村)と呼ばれた意富日神社のための農業地帯であったと図会は書いている。 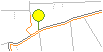 左折して500m、信号の手前に夏應山薬王寺(右図)と彫られた白い石柱が立っている。図会はここでも天道念仏踊りを行っていると書いている。正面の階段は急で、下からはお堂は見えない。先の信号を右に入って坂を上がっての脇参道から入ると、イメージマップの境内風景の写真のように踊るための広場はなさそうだった。
左折して500m、信号の手前に夏應山薬王寺(右図)と彫られた白い石柱が立っている。図会はここでも天道念仏踊りを行っていると書いている。正面の階段は急で、下からはお堂は見えない。先の信号を右に入って坂を上がっての脇参道から入ると、イメージマップの境内風景の写真のように踊るための広場はなさそうだった。 夏見郷は農業が主要産業だった時代において、上総海道と成田海道の分岐点に市場村を形成し船橋駅や大神宮を擁していた湊郷に負けない重要な地域であった。その中心の薬王寺の往時の隆盛の面影は廃仏毀釈を経ても残されていたようだが、米軍の空襲を受けて失われた。当初の探訪時には気づかなかったが、他の郊外社寺のフォローを終えてみると米軍は「町並みから離れて存在する屋根の大きな建物は武器弾薬格納庫の可能性あり」としていたかのようである。
街道に戻って右折して間もなく道なりに左(南)に曲がって市街地のほうに進む。
|
| 海神 |
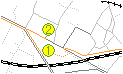
前節の道は、直ぐに船橋市中央卸売市場にぶつかる。これを右折して600mほどで船橋駅北口からの道と交差する。そのまま300m進むと左に東葉高速鉄道の地下駅である東海神駅への道があるので、これを入る。東海神駅出口、東武野田線の高架下、京成本線の昔ながらの狭いガードを抜けると、130mほどでJR総武本線にぶつかる。地下道を通らずに線路沿いに右に進むと、左図の右下に出てくる。 目の前に現れる跨線橋は、船橋街道である。これに沿って線路から離れ、跨線橋が降り切ったところを跨線橋の反対側に回り込む。 線路から1宅地ほどのところに意富日神社初鎮座地(現入日神社:左図①)への案内看板が立てられている。道が下っているのは、図会が描いた鳥居前の小川の痕跡であろう。辿りついてみると本殿は南向で鳥居は南の千葉街道の法面の下にある。
海神交番前から西も元来は船橋街道で、千葉街道はかつては上総海道だった。しかしこの分岐が当時も船橋駅舎の入口と言われ、船橋街道がここから東の短区間で、西は千葉街道として国道14号と一致した現在のほうが判りやすい。
海神交番前を50m船橋街道に入った左に大覚院(左図②)がある。図会は、阿須波明神祠(現龍神社:右図)の項で「禅宗大覚院奉祀す」と書いている。
その龍神社へは、国道14号を西へ400m、自家製作の家具屋になって直ぐ先のマンションの角を左に入る。  細い下る道が心もとない十字路を作っているところを右折した突き当たりに入口はある。こちらにも羽黒山由緒の碑があり、別当が大覚院だったこと記している。
細い下る道が心もとない十字路を作っているところを右折した突き当たりに入口はある。こちらにも羽黒山由緒の碑があり、別当が大覚院だったこと記している。千葉街道に戻って、船橋中央病院の大きな交差点を右向こうに渡り、ひとつ西を北に上がっていく道が洗川の河道(現大刀洗川は暗渠化。図会は血洗川も紹介)だったところとのこと。さらに浅間より東の山より発して源を蛇ヶ淵とも注記しているが、現存する浅間神社裏は住宅地に取り巻かれていて探しあてようがないのでルートから外しておく。 国道14号船橋街道を西船橋方面へ進む。 |
| 西船橋駅西北(栗原本郷) |
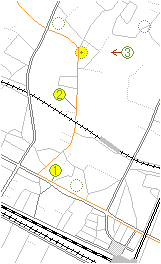 ガードを過ぎて300m、右側に児童公園がある。ここに万葉集にも詠まれた名勝
ガードを過ぎて300m、右側に児童公園がある。ここに万葉集にも詠まれた名勝その西側に葛飾明神社(現葛飾神社:左図①)が600mほど北から移転してきている。その経緯は、ここは熊野三所権現
神社西の道が栗原本郷の街道であろう。これを北に進んで京成電鉄を潜って直ぐ左の小高い所に宝成寺(左図②)がある。 図会に記述が無いのは、継嗣を失って
お家取り潰しになった栗原城主の成瀬家の菩提寺は縁起が悪いと齋藤長秋が考えたのだろうか。でも雪旦は葛飾明神社をとりまく景色の中に取り込んで描き、「寺前に4間四方に広がった椿の大樹がある」と
キャプションまで付けている。
さらに北に200mほど進んだ右の民家と民家の間の狭いところに葛の井(現葛羅の井:左図③←先)がある。図会は「くず」としているが、永井荷風が埋もれていたのを広めた際に
「羅」を付けて「かずら」と読ませたのが現在の名になっている。
図会は 台地の上の南北の道が京葉道路の原木インターから中山競馬場へ抜ける県道180号である。こここに出て100mあまり北に「寺内」というバス停がある。この「寺」と言い、その東の印内の印も元は「院」だと思われるので、それなりの寺が存在したはずである。 |
| 中山北東部 |
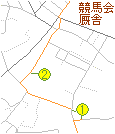 前節末から県道180号線をそのまま渡って歩車分離のない道を進む。右手の無線塔の下の外務省船橋分室をやり過ごすと住居表示が若宮になり市川市に入る。
その先右にあるのが若宮八幡宮(現若宮八幡神社:左図①)である。
前節末から県道180号線をそのまま渡って歩車分離のない道を進む。右手の無線塔の下の外務省船橋分室をやり過ごすと住居表示が若宮になり市川市に入る。
その先右にあるのが若宮八幡宮(現若宮八幡神社:左図①)である。若宮八幡のところでこれまでの道から左に折れていくと、奥の院への道標が有るので右折するとその先右に閑静な雰囲気の法華経寺の支院である奥の院(左図②)がある。 奥の院の前の道を北に突き当たるまで進んで左クランクに寂れた商店街を抜けて行く。この商店街の東隣は中央競馬会中山競馬場の厩舎である。
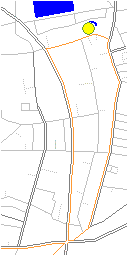 北方十字路を45度に分割している旧道で交差点を渡って100m、左に入っていく。700mあまりに信号があり、
左の坂を上った右に妙正社(現妙正寺:右図)がある。
北方十字路を45度に分割している旧道で交差点を渡って100m、左に入っていく。700mあまりに信号があり、
左の坂を上った右に妙正社(現妙正寺:右図)がある。図会は、妙正社を示しているものの、説明では妙正池と妙正大明神(姥神)として説明しているだけなので、 一巡目の時には通り過ぎてしまった。改めて古い石垣を見ると、大明神の名があり、境内左奥にそれと思われる祠があった。 説明をもう一度読むと、別ウィンドウ(日蓮法難時のアジト)に書いたように、神仏習合(合祀と習合参照)の極致とも言える祀り方で、図会で神社とも寺とも書いてないことが正しい表現と理解できた。 妙正池のほうは、寺の裏側に半分以上コンクリートで固められた姿で残っている。寺の北側の団地の北に市の調整池があり、これがむしろ往時の妙正池ではないかと思われたが、何の表示も見つけられなかったので、ルートには入れてない。
|
| 中山 |
十字路から1.2kmほどで左図右上寄りの分岐路になる。ルートから外れて道なりに100mの左にこの地に住んでいた東山魁夷の記念館があるので、汗をぬぐって暫時現代の文化に接するのも良い。 右へ分岐して下り始める坂の途中右に「子之神社参道」と書かれた鳥居があるが、これは脇参道である。下りきっての信号を右折して300mの右が子之神社(左図①)の正面である。急な石段で、脇参道が強調されていたのが理解できる。上がってみると、北側にも脇参道がある。 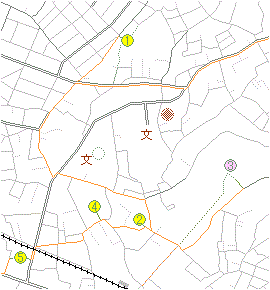 今来た道を戻り、信号をそのまま直進して250m、道幅からすると右に曲がりたくなるが前の細い道を進むと木下街道に戻る。30m左の細い道を東に入る。左の急な坂の上に小学校があり、ここに次に訪れる安房須明神社(現安房神社:左図②)があったのだが、明治時代に小学校の開設に伴って移転した。その安房神社へは、道が左に折れる十字路を右に入り、急な坂を(自転車を押して)上がる。
上がりきった少し右にある鳥居がそれである。鳥居脇に立て札があり、江戸名所図会を図示して明治以降の移転と合祀の経緯を書いてある。図会では、おどろおどろしい由緒と「淡島明神」との俗称が紹介されているが、船橋市教育委員会は淡々と書いているのみである。
今来た道を戻り、信号をそのまま直進して250m、道幅からすると右に曲がりたくなるが前の細い道を進むと木下街道に戻る。30m左の細い道を東に入る。左の急な坂の上に小学校があり、ここに次に訪れる安房須明神社(現安房神社:左図②)があったのだが、明治時代に小学校の開設に伴って移転した。その安房神社へは、道が左に折れる十字路を右に入り、急な坂を(自転車を押して)上がる。
上がりきった少し右にある鳥居がそれである。鳥居脇に立て札があり、江戸名所図会を図示して明治以降の移転と合祀の経緯を書いてある。図会では、おどろおどろしい由緒と「淡島明神」との俗称が紹介されているが、船橋市教育委員会は淡々と書いているのみである。鳥居の前を東に進むと本妙法華経寺(現法華経寺:左図③は寺のサイトへのリンク)の「山門」との説明板がある。図会は仁(二)王門と付注している。自転車を曳いて入っていくと、左右に支院(右図版で寺中)が並んでいる。図会は支院三十六宇今破壊せしものありて、僅かに十六宇存せりと書いているが、現在は境外を含めると20ほどありそうだ。
右図版の鬼子母神堂の位置には、「刹堂」という初めて見た名の堂があり、十羅刹女と大黒天が鬼子母神と合祀されているようだ。その南側の東山魁夷記念館への案内がある西門の先に右の其二右端の 境内北部の客殿は往時からかなりの規模に描かれている。現在はさらに規模を大きくしており、「刹堂」とは別に「鬼子母大神尊堂」という標柱が正面に建てられている。庫裡や方丈の役割もここが果たしていて、妙見堂前の案内板には「本院」とも表示されている。 図会では境内北部に三十番神堂が置かれていたが、原状は叢林状である。五層塔(現五重塔)は往時の姿で国指定の重文となっている。 図会が境内中央に本堂と付注しているのが祖師堂で国指定の重文である。本堂の東に描かれている常唱堂は原地不在だが、山門北の支院間(案内板では客殿横)にある「常修殿」が何らかの役割を継承しているのかも知れない。 泣銀杏樹と境内の間の道を南に上り右折すると山門前に戻る。ルートは直進するが、ここで左折して(虎斑ルート) 京成中山駅及びJR下総中山駅からの参道を200mほど下ると図版の大門(現総門)がある。 安房神社まで戻り、左の細い道に入って直ぐ右奥に廟碑らしいものが立てられている。右の「其二・・」の図版で描かれている日祐墓または日高墓と思われるが、締切って公開していないようだ。 突き当たり気味に左に曲がった右に泰福寺(左図④)が樹林など殆ど無い敷地に築地本願寺に良く似たデザインで建っている。次の訪問先の高石神社の別当をしていたこの寺は、「妙法華経寺其二」なり「高石神社」の図版(共に半裁だが見事に繋がって一枚の全幅図になる。つまり「妙法蓮華経寺」からの連続絵巻になる。)のどちらかに納まる位置にあるのだが、描かれていない。 寺の周囲が「高石神」という図会に使われている村名であることに安心して、舗装面が滑らかになっている(良く使われている)道を選んで進むと再び木下街道に戻る。と同時に京成本線の踏切になる。踏切を渡って50mもない右に高石神社(左図⑤)の入口があり、鳥居と石段が見える。南向きの社殿の左奥に観音堂が残っており、神仏混淆の名残のある例となっている。 神社の西側に出て、左に下り鬼越2丁目交差点で千葉街道に出て右折西へ向かう。 |
| 本八幡〜曽谷〜下総国分寺 |
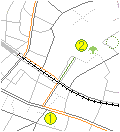
千葉街道をそのまま1kmほどで右手が市川市役所になる。その先の筋向いに
八幡不知森(現別称不知森神社:左図①)がある。図会では立ち入ると祟りが起こる狭い「深林」と表しているが、現状は密集した竹林で、
平成10年に更新された白い石の鳥居が目立つ。祟りの由縁は、尾ひれもついて拡大傾向にあるようなので、地元任せにして雑学に入れない。
西側に歩道橋があり、その先右の鳥居が立っている道は、葛飾八幡宮(左図②)の参道である。この辺は交通量が多いので市役所の正面の信号に戻って道路を渡る。 参道は京成本線で切られているが、踏切を渡ると境内である。図会が神木と書いている銀杏は「千本公孫樹」と呼ばれ、図会に描かれたより風格を増して本殿右側に現存している。
線路沿いに京成八幡駅の東の踏切まで進み、右折する。以下北に向かってバス停のある通りを3kmほど進む。途中右手に道路に背を向けた観音立像のある所願寺から左に入っていくのが昔の道と思う。 目的地手前の集落内の道がアップダウンが激しいのと、あまりにも使われていない道の感じがあって不安になる。ルート案内としては、約700mほど遠回りだが近道せずにそのままの道とする。 徐々に上り坂になり曽谷三差路で左に曲がり、台地の上に出る。  右図の右端に出てきて右に(春日)神社があるところを左に入って右に緩やかに曲がりながら下ると、安国寺(右図)が右にある。
日蓮上人が立正安国論を出した直後の中山に避難していた頃に開山した寺で、上人の銅像が建っている。本堂右手には鬼子母神堂があるが、日蓮上人自身が鬼子母神に救われたということから日蓮宗の寺では合設しているところが多い。でも扁額に尊を入れているのは見たことがない。
右図の右端に出てきて右に(春日)神社があるところを左に入って右に緩やかに曲がりながら下ると、安国寺(右図)が右にある。
日蓮上人が立正安国論を出した直後の中山に避難していた頃に開山した寺で、上人の銅像が建っている。本堂右手には鬼子母神堂があるが、日蓮上人自身が鬼子母神に救われたということから日蓮宗の寺では合設しているところが多い。でも扁額に尊を入れているのは見たことがない。上記の所願寺からの近道は、寺の南側に辿りつく(斑に強調してある)。次へは、寺の北の住宅地に入って次の辻を右折しバス通りを左折して進み、台地を一気に下りる。 下りきって用水路を渡ると正面に金光明寺/国分寺(左下図: 図会の記述では本当の国分寺の時代とは宗派が異なるとして「金光明寺」と書いているが、絵のほうは「国分寺」としている。)の杜が見え、T字路を左折すると「国分」というバス停がある。 バス停の向かいを国分寺に入っていく道が小高くなったあたりが図会が言う内膳山なのだろうが、単なる台地の住宅地になっていて山の地形も定かでないのと横切るには抵抗のある交通量なのとで右折を遠慮して直進する。  次のスーパーマーケットのところの信号で右に渡って入ると、階段が見える。この階段を自転車を下げて登ると近道である。左下図でお分かりのように左斜めに行くのが車用の道なのだが、自転車に坐り疲れた時など樹間の階段を歩けば風も吹き渡って汗も出ない。
次のスーパーマーケットのところの信号で右に渡って入ると、階段が見える。この階段を自転車を下げて登ると近道である。左下図でお分かりのように左斜めに行くのが車用の道なのだが、自転車に坐り疲れた時など樹間の階段を歩けば風も吹き渡って汗も出ない。上の道に出て右を見ると国分寺仁王門が見える。南門と本堂東の正門は儀式用なのか、普段は間にある通用門が入り口になっている。図会に「開創時世の古佛のある稀有な楼門」と書かれた仁王門は、明治以降火災になったが古佛は難を逃れたと立て札に書いてある。
南門の前から右に坂を下りてそのまま前方の道を辿る。 |
| 弘法寺・真間 |
左図の右上は、前節の国分寺の図の左下と繋がっている。
この間さしたるランドマークもなく、二か所ほどは迷い易い。上り始めて最初の分岐は右、その後の左分岐は道なり優先で良い。
千葉商大にぶつかったら左折、墓苑に出たら、右折する。墓苑が切れたら裏口からで申し訳ないが、弘法寺(ぐほうじ: 元来は「求法」だったようである:左図②)の境内に入る。 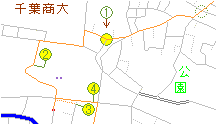 弘法寺の仏閣の多くは洗練されたデザインで作り直されている。図の■ ■にある仁王門が最も古色を漂わせているが、これも江戸名所図会に描かれているものとは異なり、明治になって他の寺から移築したものである。仁王門の隣の伏姫桜を始め境内の樹木は樹高
の大きいものが多く、夏場は格好の納涼の場所である。
弘法寺の仏閣の多くは洗練されたデザインで作り直されている。図の■ ■にある仁王門が最も古色を漂わせているが、これも江戸名所図会に描かれているものとは異なり、明治になって他の寺から移築したものである。仁王門の隣の伏姫桜を始め境内の樹木は樹高
の大きいものが多く、夏場は格好の納涼の場所である。入ってきた道を挟んで本堂の反対側に赤い門がある。この奥に図会の時代には本堂があった。
弘法寺を出て直ぐの交差点を渡ると、路面がデザインされた舗装に変わり、先方に復元された赤い継橋(左図左下赤表示)の欄干が見える。万葉以来日蓮までもが詠んだ「真間の継橋」であり、図会もしっかりと右の「真間 弘法寺」の景色に描いているのでクリックしてみていただきたい。
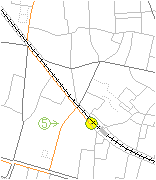 交差点の手前に戻って右に手児名旧蹟(左図③)への入り口がある。図会では手児名明神とも書いてあるが、当時から弘法寺と一体のものと扱われており、現在は「手児奈霊神堂」とさすがに「明神」は付けていない。
交差点の手前に戻って右に手児名旧蹟(左図③)への入り口がある。図会では手児名明神とも書いてあるが、当時から弘法寺と一体のものと扱われており、現在は「手児奈霊神堂」とさすがに「明神」は付けていない。細い参道の先の石柱の門を入って直ぐ左に万葉集の山部赤人の歌の「玉藻刈りけむ手児奈し思ほゆ」の立札がある。 図会では赤人の別の歌と高橋連虫麻呂の歌とを紹介している。 手児奈堂の南側稲荷神社との間に長方形の蓮池がある。小ぶりの蓮が池一面に繁っており、夏の早朝の壮観さを思わせた。 北の道に出て、斜向かいに当時から別途亀井院と呼ばれていると書かれている鈴木院(左図④)があり、手児奈が水を汲んでいたという真間井がある。 亀井院東の十字路を右折(南へ)、真間京成電鉄の踏切を過ぎて、鉄道の側道に入る(右図左上部参照)。 線路内が市川真間駅のホームになると、線路と側道の間(右図⑤→先)に九州都城「関の尾の甌穴」の出来損いのような石が置かれている。脇にある通常なら表示される設置者名も無い立札にはこれが
ところで図会には、記述無しで右の |
| 国府台・江戸川沿い |
しばらく街道を走らなかったので、自動車が脇を走る感覚を取り戻す。
市川広小路で右折して行徳と松戸を結ぶ松戸街道(千葉県道一号道路)に入る。400mほどで右に分岐する旧道を選ぶ。これを進んで国府台駅口を過ぎて200mの真間川に架かっているのが根本橋(左図①→先)である。 すぐ西に新道の橋があり、その向こうに真間川水門がある。 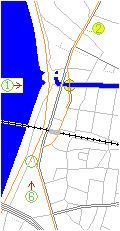 新道への合流は、次の目的地の都合と併せ右の狭い歩道で北に向かう。一つ先の信号から100m足らず先の右に鳥居があって急な階段がある。鳳凰大明神(現国府神社:左図②)である。階段の踊り場に説明板があるが、松戸街道脇に駐輪スペースすら無い状態で、氏子以外の参拝者は感じられない佇まいである。
新道への合流は、次の目的地の都合と併せ右の狭い歩道で北に向かう。一つ先の信号から100m足らず先の右に鳥居があって急な階段がある。鳳凰大明神(現国府神社:左図②)である。階段の踊り場に説明板があるが、松戸街道脇に駐輪スペースすら無い状態で、氏子以外の参拝者は感じられない佇まいである。松戸街道は交通量が多く、そのままは横切れないので前の信号に戻って長い坂を上がる。登りきったら国府台(弘法寺境内もその一部)で、道の両側は明治から敗戦までは軍用地になっていた。戦後の軍用地払い下げによる公共施設や大学が集中している。 松戸街道は、ガードレールの内側に歩道スペースがあるだけで車道は市川港などから内陸へのトラック輸送があり、自転車には快適ではない。 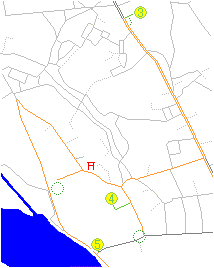 国府台病院(旧国立病院)から800mほどの右に明治末に猿江から移転してきた
国府台病院(旧国立病院)から800mほどの右に明治末に猿江から移転してきた戻って国立病院前までの三分の二ほどの信号を右折する。集落内を道なりに進むと左右の麓道にぶつかるので、左角を見ると道案内がある。左50mの案内通り 総寧寺(右図④)の門があり、下馬石標が立っている。しかしこの門はほとんど開閉されていないようで、手前の駐車場から境内に入る。 門前を南に150mほどのところに古戦場の由緒の国府城址があった。折り返して 住宅地を北へ抜けて坂を下りきり、逆V字に左に戻る。右手にポンプ場があるのは、洪水時に水没しかねない地区であることを示している。つまり、自然のままであったなら西から流れてきた江戸川がここまで押し寄せる場所である。
鐘ヶ渕の名は、「曲がった渕」の意味と思うが、冒頭の「船橋大神宮周辺」の説で紹介した慈雲寺に有った鐘を陣用に持ち出してここに落としてしまったからとの説を図会は紹介している。
ここから300mほどにも公園から下りる階段があり、川岸に消波ブロックが置かれている。その50mほど先に国府城址から下りてくる道があり、これを左折して上りかけた左に羅漢井(右図⑤)がきれいに整備されている。
さらに川沿いに南下して、左上の図に戻り、一旦京成線を潜って再び堤防上に上がるとその左に「市川関所跡」の柱(右上図⑥↑先)が立っている。図会は、利根川(現江戸川)の江戸側に関所を描き、市川側には描いていないので「渡口」と書くのが正しかろう。 ならばと図会の関所位置に相当する京成電鉄江戸川駅の南側を走り回った。
次節へ向けてしばらく江戸川左岸を南下する。 |
| 原木経由本行徳 |
前節からは江戸川堤防上を行くのと松戸街道を行くのと二つルートがある。堤防上は、風の強い日があるのとバイクなどの進入防止装置(バリカー)が煩わしいが、
車に気を遣わなくて良いし安全で見晴らしが良い。松戸街道はとくに信号が多いわけでないが重車両の横を走らねばならなかったりする。しかし、南(東)部ほど歩道が広くて歩行者が少ない傾向にある。
訪問地が離れているのでルート全部を図示するのは省略し、ランドマークのはっきりしている街道筋で説明する。 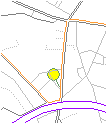 前節市川関跡から松戸街道に下りて南下、市川広小路で千葉街道を横切って2kmの左に大洲防災公園があり、その先で松戸街道は右に分岐する。右に入って1kmほどで京葉道路にぶつかるので左折する。
次の信号をもう一度左折するとこれが本八幡からの行徳街道である。信号から50mほどに甲宮(現甲大神社:左図)がある。
説明板では別当寺が火災に遭って詳細は判らないと、図会が記した兜起源には触れていない。大正9年に村内の祠などを合祀したとあり、「大神社」の名称が付いた由縁が伺える。
前節市川関跡から松戸街道に下りて南下、市川広小路で千葉街道を横切って2kmの左に大洲防災公園があり、その先で松戸街道は右に分岐する。右に入って1kmほどで京葉道路にぶつかるので左折する。
次の信号をもう一度左折するとこれが本八幡からの行徳街道である。信号から50mほどに甲宮(現甲大神社:左図)がある。
説明板では別当寺が火災に遭って詳細は判らないと、図会が記した兜起源には触れていない。大正9年に村内の祠などを合祀したとあり、「大神社」の名称が付いた由縁が伺える。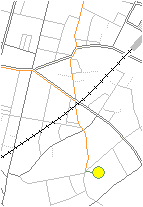 北に400m余りで原木方面に右折、京葉道路市川インター北を過ぎて1km余りの右に複合ショッピングセンターがある。さらに200m先の信号を右折して京葉道路を越えて原木中山のほうへ入ると右図上部になる。
高架になっている地下鉄東西線を潜って二つ目の辻の左に了極寺(右図)がある。図会はここを「海浜」と書いているが、現在では真間川河口まで2km以上離れている。
北に400m余りで原木方面に右折、京葉道路市川インター北を過ぎて1km余りの右に複合ショッピングセンターがある。さらに200m先の信号を右折して京葉道路を越えて原木中山のほうへ入ると右図上部になる。
高架になっている地下鉄東西線を潜って二つ目の辻の左に了極寺(右図)がある。図会はここを「海浜」と書いているが、現在では真間川河口まで2km以上離れている。戻って東西線高架を抜けたところの信号を左折、ひたすら道なりに走ると新行徳橋北詰に出る。堤防に上がると、階段があり、自転車を押して橋の歩道に上がれるようになっている。
渡る川は、1919(大正8)年に完成した江戸川放水路で、現在ではこれが河川法上の江戸川となっている。その際に設けられた橋は200m上流の行徳橋で、放水路ができるまでの行徳街道もこの位置にあった。
そのため、バスルートのほとんどは今でも新行徳橋ではなく、行徳橋を使っている。その他詳細は右の「図会の新利根川」をお読みいただきたい。
新行徳橋を渡り終えて500m、二つ目の信号(直ぐ先に歩道橋あり)で右折する(左下図右下)。現在通りの名は寺町通りとなっているが、当時は行徳と船橋を結ぶ幹線だった。
曲がって100m余りから右に続く塀の向こうが徳願寺(左下図①)である。
行徳は高潮や水害に度々襲われている。ほぼ一街区を占めてゆったりとしているこの寺は、山門も鐘楼も罹災せずに古いままのようである。
山門に置かれていた鎌倉時代の仁王像は、かっては人々の邪気を払ってくれていたが、現代では雨風の吹き込む山門から空調つきの保管庫で人間によって劣化から守られている。
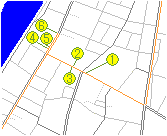
図会では、現在常蓮寺がある位置に「長勝寺」とキャプションしている。長松禅寺門前の説明板に津波に遭って移ったなどは書かれておらず、名称ともに雪旦のミスの可能性は高い。
西へ進んで本八幡からの行徳街道直ぐ右の西側の参道とは言い難い路地を入ったところに自性(姓)院(左図④)がある。
この寺は、本節最初の甲宮のほか右下図で説明する二つの神社の別当をしていたという面倒見の良い寺であった。
通りに戻ったところにあるのが、行徳徳願寺の図で神明(現行徳神明神社:左下図⑤)である。 その北、旧江戸川との間にあるのが大徳寺(左下図⑥)で、以上の近接した3寺社の配置は図会の描くままである。 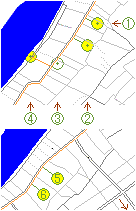 行徳街道を南へ500m程のバス停「行徳3丁目」の左に行徳八幡宮(右下図①←先)がある。そして80m南に神明宮(右下図②↑先)がある。この両神社は別当が前述した自性院であったことも影響してか、配置と言い境内に銀杏の古木が有るところと言い良く似ている。
行徳街道を南へ500m程のバス停「行徳3丁目」の左に行徳八幡宮(右下図①←先)がある。そして80m南に神明宮(右下図②↑先)がある。この両神社は別当が前述した自性院であったことも影響してか、配置と言い境内に銀杏の古木が有るところと言い良く似ている。
次の辻を右折して旧江戸川に突き当たったところに同じ図版に描かれている常夜燈(右下図④↑先)がある。長いキャプションにある「日本橋小網町から3里8丁」というのは、 小名木川と新川という運河を使っての距離で、東京湾を経ない安全な夜間就航が行われていたことが判る。 行徳街道に戻って南下すると右クランク状のカーブが二度繰り返される。矢や鉄砲の玉が通らないようにしたためとの俗説があるが、ここの場合は長すぎる宿場の役割を仕切るためのデザインと考えられる。 二度のクランクカーブを過ぎると、東西線行徳駅(右下図右下矢印方向)に通じる押切交差点になる。ここから200m足らずの左に円明院(右下図⑤)がある。 すぐ南には善照寺(右下図⑥)がある。両寺とも図会では描かれていないが、円明院の弁天祠は市杵島姫神が祭神で、明治以降各地の弁天社を厳島神社系統に組替えたのと逆のことが記されている。 善照寺のほうは挿絵入りで古鈴を紹介している。
行徳の製塩に関して図会は塩濱の項で家康とのかかわりを記し、2枚の図版を残している。風景は現在の東西線妙典駅付近から南東を眺めたものになっている。
行徳の製塩は関東平野の淡水が大量に流れ込んでいる東京湾の海水に寄っていたから消費地立地ではあったが他の地域より条件が悪く、明治以降全国統一の専売制の普及とともに急速に衰退した。
現在「塩浜」という地名が宮内庁の鴨場(行徳駅南方1.5km)の南の埋立地に付けられている。昭和の半ばまで海だったので図会が記すところとは全く異なる。図会の汐濱はむしろ現在の塩焼地区である。 図会は第二十冊の甲宮と市川根本橋の間で、逆方向にある「長島湊」を記している。行徳との関係が深かったと思われるので、そちらに向かって行徳街道をさらに進む。ルートとしては車のさらに少ない旧江戸川沿いの道でも、車道がしっかりしている新行徳街道でも、さらには一旦行徳駅で自転車を畳むのもお好み次第である。
|
| 長島 |
図会の長島湊の記述は短く、その位置は明確でない。私なりの推測を右の「長島湊の位置」に詳述するが、私の筆力の不十分さもあり一度このルートを訪れてからのほうが判りやすいと思う。 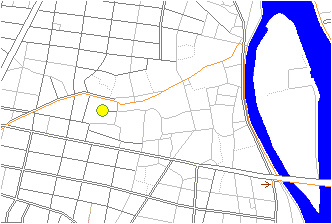 街道を道なりに進むと徐々に旧江戸川堤防に近付き、相之川で堤防道路と一緒になる。前方の川に架かっている橋は今井橋で、本篇中で対岸の今井を訪れることになる。
街道を道なりに進むと徐々に旧江戸川堤防に近付き、相之川で堤防道路と一緒になる。前方の川に架かっている橋は今井橋で、本篇中で対岸の今井を訪れることになる。橋の下を通って川はこの先左に曲がり、川の中に垂直の護岸と目いっぱい建築されている工場とで軍艦のような妙見島が見える。左図の右紡錘形の島がそれである。
橋の下の交差点を対角側に渡り、堤防道路に出て北上する。妙見島側はさらに護岸が立ち上がっていて車高の低い自転車では良く見えないので、ときおり立ち上がったり止めて船宿用の階段に上がればよく見える。 堤防道路が右に曲がり始めるところに一般道路に下りる階段があり、公衆トイレの案内も付いている。江戸川区はお年寄り向けの河岸ウォーキングを推奨しているようで、該当者である私も納得できるところである。 ここから北250mに新川(運河)の江戸川出口がある。 道を渡って左に入っていく。微妙に蛇行したこの道は、明らかに昔ながらの道である。そして左図で確認すると、葛西橋通りの北側のこの地域だけが歩車区分のない道路のネットワークになっていて、街区も不整形である。 隅田川から江戸川までの範囲は、関東大震災と米軍の空襲によって広い範囲が2度焼け野が原になった。震災復興と戦災復興で街には区画整理が施され、大部分が左図に見られる矩形の街区の街になった。その中で残ったこの地域は震災と戦災の被害が小さかったことを示している。 その西端の場所に梵音寺(左図)がある。右の「長島湊の位置」で原文を紹介したように、地名を名乗っていた長島一族が祀った観音堂がこの寺の前身だったが、図会はその限りの説明で絵は無い。 西の環七通りに出て400m南下すると、東京メトロ東西線の葛西駅である。図会の第二十冊は次々節の「新宿渡し口」から始まっているが、なんとも順路がとりにくいので連続ルート紹介は一区切りとする。 |
| 松戸 |
| 水元(含む金町北部) |
葛飾橋を渡って道なりに葛飾大橋の下を潜って直線250mほどの東金町五丁目左に桜堤という現代の名所があるので、シーズンにはそれを眺めるのも良い。
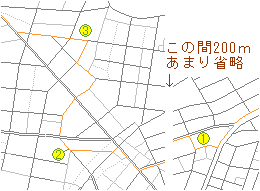 直線道路が終わる分岐交差点の「東金町交番西」の右側が目的地なので、手前の信号で右歩道に移っておくと楽である。葛飾橋西詰から堤防道路を5、600m来て下の道を渡って住宅地を抜けてこの交差点に出ても良い。
直線道路が終わる分岐交差点の「東金町交番西」の右側が目的地なので、手前の信号で右歩道に移っておくと楽である。葛飾橋西詰から堤防道路を5、600m来て下の道を渡って住宅地を抜けてこの交差点に出ても良い。交差点の分岐の所にガソリンスタンドがあり、その南が半田稲荷社(現半田稲荷神社:左図①)への道である。 境内入口に着いてみると、1街区南に鳥居があり、参道はそこからであった。
この神社について図会では記述が無く図版のみである。その図版には「拾遺に記す」と刻まれている。他の名所でも「詳細は拾遺に委ねる」旨の記述がいくつか出てくる。最後の改訂版は明治中期とのことで100年に及ぶ親子三代の私的事業であったことを慮ると事情変更已む無しだろうが、拾遺篇が刊行されなかったのは残念である
神社北側の道路を西に進んで二つ目の信号で右折、次の信号で左折して次の辻を右折して突き当たり気味の交差点に関東大震災後駒形橋東詰から移転してきた
東江寺の前の道を南東に行けばJR金町駅北口に出る。逆に北西に進んで道なりに右に曲がって北東に向きを変え、バス通りを渡る。突き当たり、左折して次の十字路を右折すると、これも関東大震災後業平橋近くから移転してきた
南蔵院前を西に進んでバス通りに出て右折、1kmほど走ると水元小学校が左にある(右図左下)。次の「水元そよかぜ園」を左折して次の信号で右折、40m先で道が右に曲がる角を左に入ると和銅寺(左図)の参道入り口である。 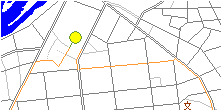 左折し損なってもすぐに「遍照院ようち園」があり、その向こうにいかにも寺の本堂という屋根が見え、幼稚園の北に寺の駐車場があるのでここから入ることもできる。
左折し損なってもすぐに「遍照院ようち園」があり、その向こうにいかにも寺の本堂という屋根が見え、幼稚園の北に寺の駐車場があるのでここから入ることもできる。 図会では、和銅寺廃址と項立てして、荒れ地で何もないと書いている。その前の項の猿ヶ股の地名を調べ、明治以降「水元猿町」になりさらに新住居表示で「水元5丁目」になったことが判った。地図を広げたら「遍照院和銅寺」が目に飛び込んできた。寺の名は開山の年号であるとのことで、東大寺より古い。
境内の石碑、石像には古色を帯びたものがあるが、区や寺が確実に判断できるのは石の手水鉢くらいのようで他にはなんの説明もない。いつ再興したか尋ねようとしたが、法事中であった。 図のように西の広い道路に出て南下する。 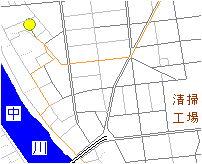 1km弱走って左に見えてきた清掃工場の煙突が左直横になったところに「清掃工場北」交差点がある。これを西に入り、十字路二つ目の広い道路を渡って突き当り気味に右に曲がってなんの変哲もない住宅地を進んでいくと、夕鶴観音堂の置かれている安福寺(左下図)に突き当たる。数百メートル南の図会に書かれている位置から「故あって移転」と石碑に彫ってあるが、図会が「なぜ夕顔というのだろう」と投げかけた疑問への答えともども知りたいことが刻まれていない。
1km弱走って左に見えてきた清掃工場の煙突が左直横になったところに「清掃工場北」交差点がある。これを西に入り、十字路二つ目の広い道路を渡って突き当り気味に右に曲がってなんの変哲もない住宅地を進んでいくと、夕鶴観音堂の置かれている安福寺(左下図)に突き当たる。数百メートル南の図会に書かれている位置から「故あって移転」と石碑に彫ってあるが、図会が「なぜ夕顔というのだろう」と投げかけた疑問への答えともども知りたいことが刻まれていない。
住宅地を西に抜けて飯塚橋より北で中川の堤防道路に出る。飯塚橋の下を潜り、管橋や水道橋の下、そしてJR常磐線の下を通って南下する。 |
| 新宿の渡〜題経寺(柴又帝釈天) |
中川左岸は、平成18年初夏に初めて走ったときよりは走りやすくなっていたが、車道の横に設けられた歩道はいかにもおざなりだし、車道も自転車が明らかに邪魔なほどの幅しかない。
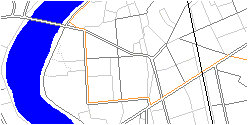 中川橋の架け替えとその前後の河川堤防の改修は終わっており、当時残っていた釣り船の係留地は撤去されていた。
中川橋の架け替えとその前後の河川堤防の改修は終わっており、当時残っていた釣り船の係留地は撤去されていた。半幅の絵に旅人や渡し船のほか川魚を扱っている店が描かれ、キャプションで鯉が美味しいと書いている新宿渡口は、現在の中川橋の位置そのままである。中川を渡って間もなく右(南)に曲がり、突き当たって左折して同じくらい進んでさらに左折するのが松戸街道で、 街道整備から遅れてここに設けられた宿場が新宿であった。図会の記述では前節の夕顔観音堂の位置をここの渡しから半道(=0.5里)ばかりと書いているだけで新宿の社寺の紹介は無い。
東京で「新宿」の二文字は、都庁の有る副都心の「シンジュク」が余りにも有名だが、こちらは「ニイジュク」である。
中川橋を渡って北西方向に行けばJR亀有駅である。本篇のルートは逆方向で橋を渡らない。新宿の旧道は、も往時の面影が無くなっていたが、橋からストレートに水戸街道に出る道の整備が進み、さらに通行量が減った。シャッターの閉じた店舗や事業所の並ぶ道を猫がのんびりと横切っている。
枡形の二辺を走ると現在の水戸街道に出る。松戸方向に進んで貨物線(常磐線と総武線を繋いでいる)の踏切を渡り、亀有警察前で右に入っていく。 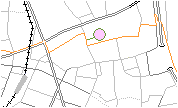 新宿公園前で平行する左の道に移ればその後1kmほどで右図左の京成金町線の踏切に出る。踏切を渡って柴又街道との交差点を左折、40mにある柴又帝釈天参道商店街に入っていく。
新宿公園前で平行する左の道に移ればその後1kmほどで右図左の京成金町線の踏切に出る。踏切を渡って柴又街道との交差点を左折、40mにある柴又帝釈天参道商店街に入っていく。映画「男はつらいよ」で有名になったここは、平日でも人通りが絶えない。門前の商店主は、山田洋次監督の家と渥美清の墓のほうには足を向けて寝れないだろう。なぜなら帝釈天、つまり題経寺について図会は、描いてないし文の量も前節の夕顔観音堂の半分もないのである。 帝釈天は、釈迦の守護を努めた弟子がその後守護神と扱われるようになったのが仏教としての経緯であるが、元来はヒンドゥ教の神である。
題経寺は開祖が造った板本尊の裏面に帝釈天が描かれていることから、本尊を拝む本堂の裏に帝釈殿が設けられている。また庚申の日が縁日なのは、中興の祖が板本尊を発見した日が庚申であるためとされているが、図会では千年前の開山の四天王寺でも庚申の日が縁日だとさりげなく書いている。 現在の堂宇はほとんど明治以降の建築だが一気に造ったものでないので帝釈堂への二天門と鐘楼は、本堂よりも組み物、彫り物とも手が込んでいる。 都心から柴又駅は、高砂駅で乗り換えて一駅(JR金町駅からも)である。乗り換え時間で日中は10分ほど待たされるから、自転車なら京成金町線に乗らずに降りて走り出したほうが早い。 次の明福寺へは、柴又街道をひたすら走っても9kmある。江戸川堤防を南下していくと総武線と千葉街道を渡る付近が未整備で回り道を余儀なくされる。 自動車と付き合わなくて良い走行を長時間過ごせる後者を取ることにして寺の裏に回ると、幼稚園があり、これほどの寺でも宗教活動外で経営してきたことが判り驚く。 |
| 旧江戸川右岸(今井〜新川口北)及び環七沿い |
柴又から今井までの柴又街道は一直線の道路で信号が多く、1時間近くかかる。時間に余裕のある人には江戸川の堤防道路が良いが、市川橋から総武線の前後が未整備で、判りにくい堤下の道路を一旦は走らなければならない。それでも途中幅広くジョガーも少ない区間があり、自転車天国である。また、放水路を過ぎると狭くなるが旧江戸川の区域は水生植物が茂っていて都鳥などが群れていたりして豊かな生態を楽しめる。そして対岸は4節前で走った行徳河岸である。
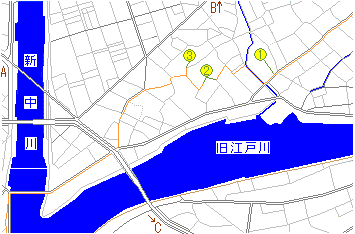 時間に余裕のない人など改めて出直す場合には都営地下鉄新宿線の一之江駅(左図A方向)と瑞江駅(左図B方向)からは1kmほど、東西線の南行徳(左図C方向)からは2kmほどである。橋上の強い風が嫌いな人は、道が判りにくいが瑞江駅になる。
時間に余裕のない人など改めて出直す場合には都営地下鉄新宿線の一之江駅(左図A方向)と瑞江駅(左図B方向)からは1kmほど、東西線の南行徳(左図C方向)からは2kmほどである。橋上の強い風が嫌いな人は、道が判りにくいが瑞江駅になる。江戸川(旧を含む)右岸堤防を来ると左図の旧江戸川の北の道になり、第一目的地を少し行き過ぎるので最短の柴又街道でルートを説明する。柴又街道が篠崎街道にぶつかるのは今井地区に入っての鎌田小学校の先の角である。これを右折すると左図右上に出てくる。
道路に面しては大きな幼稚園兼保育所があり、図会が記した太子堂や親鸞聖人御影堂は参道奥の門を入ってからである。教育行政論で戦後文部省をサポートした持田教授の蔵書などの図書館に御影も移されている。経堂(蔵)は僧侶にとって図書館だから寺の施設として受容範囲なのだろう。 さらに本堂裏には鏡ヶ池と袈裟掛松も健在である。前者は小さな池故に波が立ち難いのだと変に納得させられた。また、後者は植え直した若木であると図会が指摘したものらしく、200年生ほどである。 篠崎街道が河岸に出るところは、歩道も車道もさほど広くなく信号も複雑なので、これを避けて明福寺の西の水路付きの道に右折する。最初に左折できるところを曲がり次いで右クランクに進んで右にある伽藍が、図会が妙福寺の本院と書いている金蔵寺(左図②)である。そこにある門は東門で境内を通って本堂の正面を出て遊歩道を右折して一般道に出ると幼稚園が見える。 幼稚園にぶつかって右奥に図会が北條氏康とのゆかりを詳細に紹介している浄興寺があり、幼稚園は浄興寺経営であることが判る。図会が描いた本堂よりも背の高い 昔からの漁村集落の道筋がそのまま残ったようなこの地区は、戦災の被災度が低く、戦災復興区画整理から外れていたのだろう。結果的に急速な人口増にはならず地域の風習なども残ってもいるだろう。しかし、檀家信徒もそれほど増えない状況下で寺は競うように幼稚園を経営してきたが、少子化時代を迎えていよいよ寺の経営は容易ではない。 幼稚園の角から左クランクに進んで道なりに徐々に左に曲がって行くと今井橋西詰の交差点に出る。橋の下、つまり川と平行に進んで新中川に架かる瑞穂大橋を渡る。 なお、右図版の 瑞穂大橋を渡りきると川沿いには自転車用の車線幅も歩道も無い。橋詰の信号を渡っての左折、つまり右の側道を進む。一旦車道より低くなった後上がると信号がある。一応2車線の道路だが余りにも幅が無いのでこの信号から川沿いの細い歩道を行く。 道はガソリンスタンドにぶつかってクランクに曲がる。江戸川五丁目のT字路信号があり、その左が水神宮(右図)である。洪水や水難のないことを願って祀っているもので、ここまでにもいくつか見かけてきた。  図会は水神宮を独立の項で説明していないが、次の妙勝寺の項の中でそのゆかりを紹介している。現状は、水神宮前のスペースに町内会館があり、注意札に「神社部」と書かれていることからして自治会で管理してきたようだ。神仏分離後の維持の一形態である。しかし天保年間の刻みのある石の鳥居には合祀されている稲荷神社の額だけが上がっているし社殿も見劣りがする。
図会は水神宮を独立の項で説明していないが、次の妙勝寺の項の中でそのゆかりを紹介している。現状は、水神宮前のスペースに町内会館があり、注意札に「神社部」と書かれていることからして自治会で管理してきたようだ。神仏分離後の維持の一形態である。しかし天保年間の刻みのある石の鳥居には合祀されている稲荷神社の額だけが上がっているし社殿も見劣りがする。ここから200m南は小名木川の続きの新川の旧江戸川への出口で、その先に妙見島の北端が見える。4節前で折り返した地点まではさらに同じくらいの距離である。 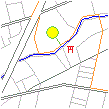 江戸川五丁目信号を広い右歩道を使って西に進む。最初の信号を過ぎて右に入る二つ目の道を右折する。突き当たるまで進むと古川親水公園沿いの道路に出るので左折する。
曲がって150m程の右に妙勝寺(左上図)がある。
江戸川五丁目信号を広い右歩道を使って西に進む。最初の信号を過ぎて右に入る二つ目の道を右折する。突き当たるまで進むと古川親水公園沿いの道路に出るので左折する。
曲がって150m程の右に妙勝寺(左上図)がある。図会には描かれていない開山堂があり、その前の立て札にひっかかたままになっている水神宮についての手がかりが書かれている。
以上で妙勝寺を済ませていた。10年以上経って古川親水公園を挟んで寺に背を向けて建っている二之江神社が気になって調べてみた。「三十番神」のその後は判ったがまたも疑問点は増えた。 西に進み、右に曲がって交番のところで環状七号線に出る。ここで信号のタイミングが合えば左へ渡るのが良いが、右歩道も広いのでそのまま進んでもかまわない。 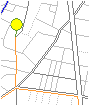 1kmほど進むと道路の左に一之江駅バスターミナルがある。環七はこの部分本線が陸橋になって浦安街道と交差している。この交差点の次の信号で左折、200mほど先で道が40度ほど左に曲がるところを直角に右に曲がる。
1kmほど進むと道路の左に一之江駅バスターミナルがある。環七はこの部分本線が陸橋になって浦安街道と交差している。この交差点の次の信号で左折、200mほど先で道が40度ほど左に曲がるところを直角に右に曲がる。
戻って先ほど直角に曲がったところで右へと広い道を辿り、新大橋通りに出たら右折し、新船堀橋で中川と荒川を渡る。 |
| 旧中川下流部 |
図会は正順で前節妙音寺に至る前、中川の流域の地域を紹介している。その一覧は次の通り。 猿ヶ股:葛飾区/猿町を経て水元に地名変更。バス停に名を残す。既訪和銅寺所在 飯塚:葛飾区/現在の西水元及び南水元。橋、小学校に名を残す。既訪安福寺所在 大谷:足立区/現在大谷田。飯塚橋の西 亀有、新宿、青戸、奥戸:葛飾区/いずれも現在も地名として健在。亀有はJR駅名も。青戸は新中川の分岐部 平井:江戸川区及び葛飾区/荒川放水路で分断され、葛飾区側は西小岩に。JR駅名も 木下川:墨田区及び葛飾区/荒川放水路で分断され、葛飾区側は木根川を経て東四つ木に。 小村井:墨田区/現在の立花。京成駅名に名を残す。 逆井:江戸川区/小松川2丁目の一部。 明治以降右の「東京東部水害と治水工事」に説明する大規模な治水工事でこれらの地域の構造や性格が変わった。しかし、最も変わったのは地域の真ん中に大水路を抱えた木下川と小松川であった。
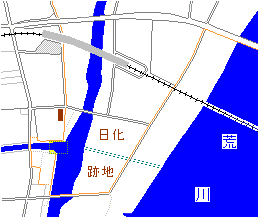 そんなこともあって以下暫く図会の逆順と云う原則から外れて現在の辿りやすいルートで探訪を続ける。
そんなこともあって以下暫く図会の逆順と云う原則から外れて現在の辿りやすいルートで探訪を続ける。 新船堀橋の西詰信号の手前で階段を下りて放水路右岸堤防沿いの道を南下する。殆ど歩行者はいないので右歩道を気楽に進む。都営地下鉄の高架下を過ぎて次のT字路を過ぎると道は上り気味になり右手は小高く土を盛った公園になる。
渡って直ぐ右の散策路に入って行けるところまで行くと、雪旦が中川口を描いた場所になる。左から小名木川が来ており、現在も土石や産廃を積んだ平船などが出入りしている。北にあった船番所から三人の役人が正座してこの水面を見張っている様を図会は描き、右の先ほど通った小高い公園のところに新川(船堀川)があって、
荒川放水路の設置に伴い旧中川との間の新川は埋められ、日本化学工業の工場敷地になった。この工場の跡地から六価クロムが検出された事件については右下の「亀大小防災拠点」で触れる。
散策路を戻って途中から右の階段を上がって街区の西に出て右折、右歩道のまま番所橋を渡り、20m程のところの階段を右に降り、小名木川の北側を東に進んで道なりに北に行くと中川船番所資料館がある。資料展示は図会の二つの絵をテーマにしており、関心と余裕のある人にお勧めである。
交差点で右歩道に移って北に進む。
道は首都高速道路が乗っている道路にぶつかる。そのまま右歩道で右折して進むと逆井橋である。  橋を渡って右に図会が、「逆井渡口より8、9町東の方」に善通寺があると書いた逆井渡についての説明板(右図)が設けられている。また、微妙なニュアンスの違いがあるが、右図鳥居印の小松川神社入り口にも説明板が立てられている。
橋を渡って右に図会が、「逆井渡口より8、9町東の方」に善通寺があると書いた逆井渡についての説明板(右図)が設けられている。また、微妙なニュアンスの違いがあるが、右図鳥居印の小松川神社入り口にも説明板が立てられている。善通寺の位置がここから8、9町東ということは、ちょうど現在の京葉道路小松川橋と首都高速中央環状線が交っているあたり(前節の妙音寺の西1.5km)であるが、当然移転しているのでその移転先へ向かう。 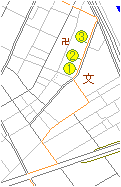 小松川神社の説明板を見て首都高速7号小松川線の下を東に進み、次の信号の小学校の先を左折すると300mほどで京葉道路に出る(左下図下部)。渡って右折し、次の小松川四丁目(交番がある)を左折、100mほど先の広めの道を右に入って行き、都立小松川高校の敷地の間を抜けて右に曲がり、左にカーブしたところの左に
小松川神社の説明板を見て首都高速7号小松川線の下を東に進み、次の信号の小学校の先を左折すると300mほどで京葉道路に出る(左下図下部)。渡って右折し、次の小松川四丁目(交番がある)を左折、100mほど先の広めの道を右に入って行き、都立小松川高校の敷地の間を抜けて右に曲がり、左にカーブしたところの左にここは、移転してきた寺院の団地のようになっている。善通寺は既に説明したとおりで大正初めに移転した。その荒川寄りには本所大平町から なお、最勝寺は黄色い目の(現代では五色不動のひとつとしているが、図会は触れていない)不動尊を本尊とし、江戸時代は向島の総鎮守牛嶋神社の別当だった。 荒川右岸沿いの道路に出て左折、直ぐこの道路から左に入り、JR総武線の平井駅のほうに向かう。 |
| 平井〜新小岩 |
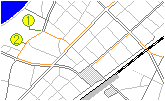 前節からの道は、JR総武線のガードで広い道に出る(左図右端部)。そのまま右歩道で進み、次の信号で左折して平井駅北口広場に出たところで右折して蔵前橋通り(千葉街道)を横切る。
前節からの道は、JR総武線のガードで広い道に出る(左図右端部)。そのまま右歩道で進み、次の信号で左折して平井駅北口広場に出たところで右折して蔵前橋通り(千葉街道)を横切る。左正面に平井聖天宮・燈明寺(左図①)の堂宇のスカイラインが見える。山門以外境内の建物はすべてRC造になっている。図会は平井の渡の向こうに兼帯の諏訪神社(左図②)を含めていくつかお堂を描いているが、建て替えの際に本堂に移すなどして残っているものは聖天堂とこの神社だけである。
将軍お立ち寄りの御膳所だったにもかかわらず図会は何のコメントもしていない。巷間評判の「聖天」すなわち歓喜天は守護神で、本尊は不動明王ということからインテリの長秋には書きにくかったのかもしれない。
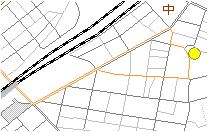
不動尊の寺としての特色ある節分会の行事のためだろうか、諏訪神社との間には広い空間が残されている。
諏訪神社前を南に出て平井駅方面に左折し、蔵前橋通りを左折して、新小岩へ向かう。 蔵前橋通りを2kmほどで平和橋通りとの交差点になる。これを右折してガードを潜って新小岩駅前に出る(右図左端)。直角に左折して約500m、中学の角で右に入り、次の十字路を左折してぶつかり気味の右分岐先の左に岩本町から江戸末期に移転してきた 当時は郊外だったろうが、境内は決して広くない。 戻るのだが、そのまま進んで広めの道に出たら右折して進み、五叉路に来たら左折して駅前から平和橋通りをひたすら北西に進む。 |
| 四つ木地区 |
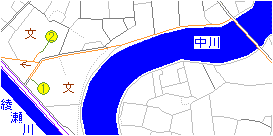 新小岩駅前からまっ直ぐに走ること1.6kmで中川に架かる平和橋を渡り終える(左図右端)。堤防道路を左折して進み、700m余りのところで下りて右斜めに下の一般道に入る。中川中学入口を過ぎ、幼稚園を左に見て曲がると
新小岩駅前からまっ直ぐに走ること1.6kmで中川に架かる平和橋を渡り終える(左図右端)。堤防道路を左折して進み、700m余りのところで下りて右斜めに下の一般道に入る。中川中学入口を過ぎ、幼稚園を左に見て曲がると浄光寺は、現在地の西北西600mほどにあり、明治時代の陸軍測地部の地図でもすぐ分かるほど大きな境内を持っており、地域のさまざまな行事もここで行われていた。
戻って右折(左図←)して出る首都高の高架下道路を右歩道で北西に進み、次の信号で高架の真下に入って木根川橋に通じる歩道を上がって行く。 荒川に沿って流れてきた綾瀬川が、浄光寺の南400mほどで中川に合流する。荒川と中川の仕切り堤防を北上してきた首都高速道路中央環状線は、この合流点で綾瀬川左岸に移っている。そのため小菅までの3.5kmは窮屈な交通動線になっている。
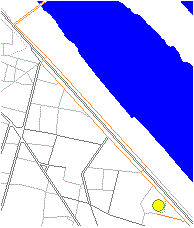
400mほどで木根川橋東詰の信号になるので橋を渡り、対岸の堤防道路を南下する(右図上端部)。
800m先の堤防下に既述した白髭神社がある。堤防からの下り口は100mほど手前である。鳥居は荒川のほうにあるのだが、社殿は南向きである。加えて社殿前の駐車場との間は狭く段差があって鉄線が張られている。何とも無粋だが、訪れた時は早咲きの寒桜の小さな株が満開だった。社殿の軒下に大正4年の移転の経緯を記した碑がある。 図会は、他にも天照大神宮、山王権現宮と弁財天祠が薬師堂境内に存在したことを記しているが、帰趨は不明である。 四ツ木地区に戻るので木根川橋に向かう。堤防下の道路を進み、信号になったら堤防上に戻っておく。橋の西詰も狭い中で自動車の右左折を捌くのを優先しているので、それなりに神経を使う。 渡ったら高架下側道東の歩道で左折、200mあまりで京成押上線を潜り、直ぐを右折して商店街に入っていく。最初の信号の分岐型交差点の左に西光寺(左下図①)への広めの道(参道?)がある。 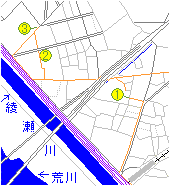 山門を入っての右(後ろ)に
山門を入っての右(後ろ)に
頼朝などの知恵袋で名領主としての家系を確立した葛西三郎清重の墓に設けられていた稲荷である。本家筋は秀吉に滅ぼされたが、今も残る葛西姓の人の多くは先祖を清重としている。
北の門を出て道なりに左に進んで水戸街道の四つ木橋が立ち上がるところの交差点に出る。ここを渡って斜めに首都高速のほうに向かう。
高架下の道路に出る手前40mのところの路地を右に入る。途中クランクに曲がって直ぐ右に若宮八幡宮(左下図②)が西向きで建っている。図会の時代すでに古松老杉嬌々として寥々たる状態だったようだ。
怠けていると思ったから名前を間違えたではないだろうが、北に進んで通り抜けたところに東向きで建っている善福寺(現善福院:右下図③)を別当と書いている。 この後自転車は、図会では平井と一之江の間に綴じている南蔵院ほかに向かうため、先ほどの水戸街道の交差点を渡り直して東へ進む。 荒川の西を除く本節の区域は、荒川放水路工事から東京市への合併まで(ほぼ18年間)本田村となっていた。今も各所に残る「本田」の看板や施設名はその名残で苗字の本田ではない。読みは「ホンデン」である。
|
| 立石〜堀切 |
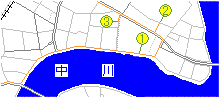 京成押上線にぶつかったら平和橋通りで踏切を渡って奥戸街道に入り、立石駅南の仲見世出口を過ぎて300mで中川を渡る本奥戸橋になる(左図左端)。
京成押上線にぶつかったら平和橋通りで踏切を渡って奥戸街道に入り、立石駅南の仲見世出口を過ぎて300mで中川を渡る本奥戸橋になる(左図左端)。渡らずに堤防沿いの道路か堤防上を辿っていくと左に南蔵院(左図①)が見える。堤防上道路の場合は、付いているスロープが寺の東西60mほど離れたところにそれぞれあるので、それを使って下りる。 熊野(権現)祠(左図②)は、図会の記述では境内艮の隅となっているが、絵ではほぼ現在位置に南蔵院とは別境内のように描かれている。寺の東の道を回って信号を渡り、右歩道左折で30mに立派な参道と石柱でその存在を示している。 こちらの御神体が円錐形の石とのことで、次の立石祠(左図③)と妙に符合しているのは気になる点である。
図会は壹尺ばかりと記述し、合わせて石質弱にして「冬には欠け、春には復元する」という言い伝えを記述しているのは、長秋は「熊野神社の御神体がその上部で、何かで折れたから慌てて祀ったんじゃないの」と言いたいのを我慢して書いているように感じられる。
さらに、この石も南蔵院の寺境にありと記述している。  次の普賢寺(右図)は、右上の表のように前後かなり離れている。地図をかなり省略させていただき、その分記述で補うこととする。
次の普賢寺(右図)は、右上の表のように前後かなり離れている。地図をかなり省略させていただき、その分記述で補うこととする。立石祠から戻って信号を左に進んで京成押上線を潜って150mほどで道が左に曲がる。曲がって最初の信号を右折する。そのまま700mほどで水戸街道に出て、渡る(白鳥交差点)。左、右の順に道が分岐する右の道を直進すると高圧線の鉄塔が見える。近づくと右に都立高校左に幼稚園があり、その先の六叉路交差点(葛西用水跡の道路)で進んできた直角左方向の道に入る。 この道もほぼ直線で、信号の先が見通せないのは、右図の普賢寺最寄りの交差点が最初である。この交差点で右歩道に移ってすぐに普賢寺入口の表示ある。平成22年のページ再編まで3回ルート探しをしたが、これが一番判りやすい。別の道で迷った場合は、図会の時代の村の名前を継いでいる上千葉小学校(右図文マーク)がランドマークである。 さて、普賢寺の表示を絵の無い分類にしたが、右の
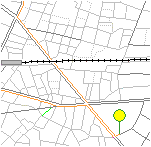 バス通りに戻って西に進み1km足らずで小菅2丁目交差点に出たら左折、300m足らずで平和橋通りに出て(左下図左上)左折、京成本線のガードを抜けると「
バス通りに戻って西に進み1km足らずで小菅2丁目交差点に出たら左折、300m足らずで平和橋通りに出て(左下図左上)左折、京成本線のガードを抜けると「街区の南が寺の入り口で、交差点は「妙源寺裏」と言ったほうが正確である。普賢寺からこの交差点の東100mに抜ける上千葉村時代の名残のような道があり、500mほど近道である。横からの人や車の出入りに注意して走っていると、時間的には紹介したルートとさして変わらないので、このページを参考にウォーキングで辿る人のためのルートである。 妙源寺前の信号を西に進んで100m弱のY字分岐の左の遊歩道を抜けてそのまま道なりに前に進んでいくと500mほどで堀切菖蒲園である。しかし、図会に登場しないのでパスし、Y字分岐を右に採って堀切橋を渡る。 本節をもって荒川以東を完了するのだが、江戸名所図会をもっと詳しくチェックしている人からは、次の2点を指摘されそうである。 第一は、右の絵である。街はその名残を消し去っており、葛西と言っても広いのでどこを指しているか不明なのだが、
二つ目は、青砥左衛門尉藤綱 第宅旧跡である。地名は青戸だが駅名は青砥で、それだけでも雑学の対象である。夜分に小川に落とした小銭を松明を灯し人を使って探し出したという話を子供のころ聞かされ、その不合理さは今もって理解しがたいが、その主人公が青砥藤綱である。 図会も懐疑的な記述をし、しばらくいひ伝ふるにまかせとしている。青砥藤綱ゆかりという場所は、他にも横浜や千葉県南部にあるようだが、現在の歴史研究では藤綱の存在も怪しいという。 徳川幕府が廃城とした後しばらく使っていた葛西城跡(青砥駅の北800m)のことだろうとのことだが、ならば歴史好きな長秋がもう少しコメントしていても良さそうである。葛西城跡はオリンピック関連の環状七号線整備でバタバタと調査して「埋設保存」として道路区域になってしまったようだ。そんなわけでルート地図やイメージマップ写真を省略する。
|
| 北千住〜鐘ヶ淵 |
図会のパノラマで現代の堀切橋西詰は中央部になるので、まずは北千住駅南5,600mの関屋天満宮(左図)に行って鐘ヶ淵方面に戻る。
堀切橋西詰で左折して100m近く先でV字に戻ってガードをくぐり(右図右上参照)、次の信号を左折して西へ進む。北千住駅の南で東武鉄道の踏切と地下鉄、つくばEXそして常磐線のガード(左図右端上)を過ぎて200m足らずのT字路に左折する。曲がって300m足らずの左に鳥居があり、氷川神社(左図)の標柱が立っている。 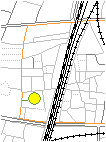
境内を出て南へ50m足らずのところを墨堤通りが東西に走っている。氷川神社から出ると、その側道に出るので左折してJRなどの階段付きガードをくぐる。東へ進むと、道は鉄道に挟まれる。左の踏切をきた道が合流した左に東武牛田駅、右に曲がって踏切を渡っての左が京成関屋駅である(右図左端)。 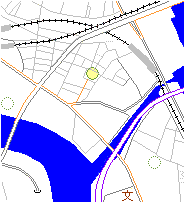 ここでほぼ平行している2線は、東武は東行きが押上を経て営団地下鉄で都心へ行くのに対し、逆に京成は西行きがターミナルの上野である。
ここでほぼ平行している2線は、東武は東行きが押上を経て営団地下鉄で都心へ行くのに対し、逆に京成は西行きがターミナルの上野である。この先の堀切橋から来た道との千住曙町交差点を右に行けば、平成18年2月竣工の千住汐入大橋である。橋の上流側の隅田川沿いは風景写真を海外に出しても恥ずかしくないほどの綺麗なマンション開発がなされている。ここに 墨堤通りに戻って鐘ヶ渕方向の次の交差点を左折、20mほどの左斜めを見ると牛田薬師堂・西光院(右図)の山門が見える。なお、「牛田」はこの地域の旧村名であり、東武の駅名はこれによる。 また墨堤通り右折し、綾瀬橋を渡る。つまり、旧綾瀬川の合流点であり、隅田川は直角以上に鋭角に南へと流れの向きを変えている。ここをさして鐘ヶ潭だと図会は書いている。 図会が記している
さらに図会は、庵崎を隅田河原と絡めて詠んだ和歌を3つ引いて名所の要件を満たしていることを示し、この辺のはずだが慥(たしか)でないと書いている。 |
| 白髭東 |
前節の図の最下部の鐘淵中学校を過ぎると、墨堤通りの右は高層の都営住宅列が屏風のように立ち並んでいる。鐘淵陸橋の交差点を右折し、屏風の最初の切れ目のゲートを抜け、首都高速道路沿いの道を左折する。
此の辺の大型建築と大型構造物ばかりの地域も明治以降鐘紡の工場だったが、図会が「頗る美景色」と讃えた 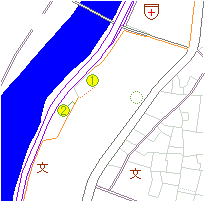 左折するところは若干低くなっていて、水神大橋の関係のように見えるがそうではない。ここに東から
左折するところは若干低くなっていて、水神大橋の関係のように見えるがそうではない。ここに東から左折して200mほどのところに
木母寺を抜けると東白鬚公園である。園内車両通行禁止で西が正門のようだが、こちらが正門のほうが参詣者には心穏やかであろう。公園の中を南西に進むと直ぐに水神宮(現隅田川神社:左図②)がある。こちらは図会の時代には高速道路の下ぐらいに在った。
図会は正順で水神宮などに至る前、隅田河について概念を明確にしようとしている。しかし、古へに違ふ事もありなんと、地域と時代によって呼称が変化するものと半ば諦めている。実際に東京湾北部での川の流れは、熱帯大河川のデルタ地帯と同様に洪水や人為的な治水工事の都度変化してきている。隅田川以外もひっくるめて総称すれば「綾瀬川」と表現するのが最も適していると言える。
須田河原:隅田河原におなじと書いている。 隅田河堤:北條氏が築いたもので深堀橋から上流熊谷までの16里(63km弱)としている。
隅田宿:図会自体が往古の奥州街道の駅舎なるべしとし、この宿のことが書かれた史料が、隅田川をずっと北東の川(綾瀬川?)を指していたころのものだから、隅田川の近くではないとしている。 都鳥:五首の和歌を引き、隅田川固有の鳥のように詠まれているが、伊勢物語が影響したもので、カモメのうち大型がウミネコで小型がミヤコドリだからどこにでもいる鳥なんだと記している。 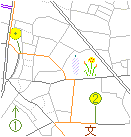
首都高の側道に戻って南下、白髭橋にぶつかって左折する。
白髭橋東詰交差点で対角に渡り、南へ200m、二つ目の信号のところを斜めに左に入るとその下り坂の左が白髭明神社(現白髭神社:右図①↑先)である。 キチンと南面しており、当初の配置のままと思われる。住所表示は東向島になっているが、橋や公園の名の元になった神社である。境内の碑からもこの神社の別当が西蔵院で、他の文献からもすぐ隣に在ったようだが見当たらず、明治以降の経緯は不明である。 神社前を東へ進んで向島百花園の脇を通って左クランクに曲がって南下すると隅田川高校にぶつかる。
戻って先の信号で鋭角に左折して水戸街道に出る。 |
| 向島 |
水戸街道の交差点は東向島3丁目であり、これを右折して左側(歩道)を行く。
秋葉大権現社(現秋葉神社:左図①↑先)の入り口は判りにくい。東向島3丁目から二つ目の向島5丁目という信号を左折して40mほどのところから石の柵垣がはじまる。それを左に入ると鳥居がある。 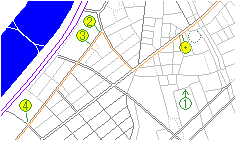 鳥居に向かってから振り返ると、水戸街道までの間が飲み屋街になっていて、これが参道の体となっている。この飲み屋街の入り口は一度通り過ぎているのだが、余程注意深くないと気付かない。
また図会では周辺は「俗間請地」で、「酒肉店」が多いというキャプションつきで庵崎という地域図を設けている。
鳥居に向かってから振り返ると、水戸街道までの間が飲み屋街になっていて、これが参道の体となっている。この飲み屋街の入り口は一度通り過ぎているのだが、余程注意深くないと気付かない。
また図会では周辺は「俗間請地」で、「酒肉店」が多いというキャプションつきで庵崎という地域図を設けている。
この神社は図会の記すとおり、千代世稲荷を相殿しているが、別当の 水戸街道に戻って都心に向かう。二つ目の信号の交差点(左に交番がある)で右折して、隅田川の方向に向かう。なぜかまた向島五丁目と書いてある信号の左向こうが長命寺(左図②)である。
長命寺の直ぐ南が弘福禅寺(左図③)である。山門の様式は禅寺の趣とも図会とも異なっている。図会はこの寺は須崎にあると記して絵も少し離して描いている。
長命寺と弘福寺の前の道を南西に進み、左図の④が三囲(稲荷)神社である。本殿前に建てられている其角の霊験あらたかな雨乞いの句の碑は、図会が紹介している田中稲荷の名とともに周囲が水田で農業主体の地域であったことを認識させてくれる。別当は延命寺だったとのことだが、移転か廃寺かも不明である。 なお、三囲神社の北側の地域にあった 三囲神社前から引き続き同じ道を進んで200mの言問通りに出る。これを渡るのだが、なかなか信号が変わらない。かといって目いっぱい大きく見えるスカイツリーを眺めていると、再び信号が赤になってしまうので要注意。渡って右の隅田公園の一角に牛嶋神社(右図)がある。  図会は右の「牛御前宮」と次節の「大川橋」の図版で、上記二つの寺の隅田川側に牛御前宮を描き、キャプションからは牛頭天王社を伺わせる。
記載では、牛御前王子権現社は「牛島の総鎮守」であって別当は本所の最勝寺(本所の牛島神明宮も兼帯)であると書いている。関東大震災で、1km近くの移転をして名前を「牛嶋神社」と変え、同時に神明宮を摂社とした。神社の構造改革としては珍しくダイナミックで、裏話を知りたいところだが立札には一切書かれていないし、先輩諸氏の神社由緒のWEBでも触れられていない。
図会は右の「牛御前宮」と次節の「大川橋」の図版で、上記二つの寺の隅田川側に牛御前宮を描き、キャプションからは牛頭天王社を伺わせる。
記載では、牛御前王子権現社は「牛島の総鎮守」であって別当は本所の最勝寺(本所の牛島神明宮も兼帯)であると書いている。関東大震災で、1km近くの移転をして名前を「牛嶋神社」と変え、同時に神明宮を摂社とした。神社の構造改革としては珍しくダイナミックで、裏話を知りたいところだが立札には一切書かれていないし、先輩諸氏の神社由緒のWEBでも触れられていない。隅田公園東の道を進んで、源森橋南詰で右折して墨堤通りに戻り、墨田区役所側に渡る。 |
| 本所 |
墨田区役所手前で渡った川は北十間川で、右手の隅田川との水門には源森水門と名が付いているがこの橋は枕橋で、源森橋はも一つ東の橋である。
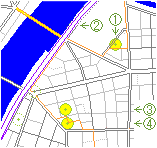 枕橋は、スカイツリーがビルに邪魔されずに見えるポイントのひとつである。
枕橋は、スカイツリーがビルに邪魔されずに見えるポイントのひとつである。この枕橋の南から源森橋の南の地域(左図右上)が瓦町で、図会はここで営まれていた瓦製造の様子を描いている(右「瓦師」)。 流通体制の整備された現代では材料立地型の産業であるが、当時は流通途上での破損のリスクが大きく消費地立地産業であった。 墨田区役所の南の次を右折して40mの右に如意輪寺(左図①↓先)の入り口がある。
そのまま進んで、道なりに浅草通りに出、アサヒビールの本部ビルを過ぎて隅田川にかかる橋が
右歩道で橋を往復し、高速下の道を隅田川に沿って進み、250mほどで駒形橋東詰交差点に出る。ここに、水元に移転した
駒形橋東詰交差点で東から南へ三つに道が分かれているうち、東南に進む道を進み、左に入る二つ目の道を入ってすぐ左に本久寺(左図③←先)がある。 この寺も古地図と対比すると微妙に南下している。また、建物も寺院以外に用途転換できそうなデザインである。 本久寺の反対側に路地があり、これを入った突き当たりに小さな最勝稲荷(左図④←先)がある。
 これに対して堀切へ移転した
これに対して堀切へ移転したまた、図会は荒井町に中郷八幡宮があり、その北隣に上記の普賢寺が別当の大六天祠があるとしている。中郷八幡宮の別当だった 最勝稲荷を東へ出て右折、車線区分のある通りに出たら左折して次の信号で右折して南下する。右が小学校左が公園になったら次の角を左折し、
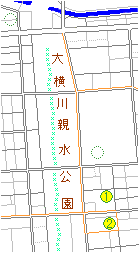
右の絵はよく判らない。
加えてキャプションの「世の中は 蝶々とまれ かくもあれ」は、芭蕉の師匠の西山宗因の句である。評価の分かれるこの句と絵の内容とがどう関係するのか、理科系の私にはお手上げである。 |
| 北十間川沿 |
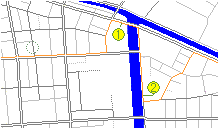 日本たばこの西北の角で右折し、400mほどで左図左端に出てくる。四ッ目通りを渡って左の街区に戦災に遭って八王子の山懐に移転した
日本たばこの西北の角で右折し、400mほどで左図左端に出てくる。四ッ目通りを渡って左の街区に戦災に遭って八王子の山懐に移転した図会は、最教寺について蒙古鎮静の際の日蓮上人真蹟とされる日の丸曼荼羅を寺宝とし、半幅2枚、全幅2枚もの絵図を使って紹介している。(右の4図参照)
横十間川の手前右にあるのが柳嶋妙見堂・法性寺(左図①)である。近松や北斎の墓が残っており、訪問者は多い。境内の一部はマンション化し、寺の一般的風貌とは程遠くなっているので、どこが建物の入り口かよくわからない。影向、星降と優雅な名の松のその後を訪ねたりすると怪訝な顔をされそうだ。
柳嶋橋で横十間川を渡ると江東区亀戸になる。次節の亀戸(蔵前橋通り北)と一緒にしたほうがよいかもしれないが、図会の順を逆に辿ることを優先して扱う。
なお、図会の時代には北十間川は、単に十間川と言い、後発の横十間川に横を付けていたようだ。 右折、横十間川左岸の道を南に200m余りの左に
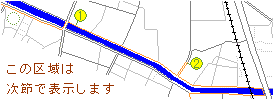 右折してから250mほどの信号を渡ったブロック(右図左上)に
右折してから250mほどの信号を渡ったブロック(右図左上)に北十間川に架かる明治通りの福神橋で川の左岸沿いに移ってすぐに吾嬬権現社(現吾嬬神社:右図①)がある。日本武尊(図会では記されていない)と弟橘媛を祭神とするとあるが、昭和20年の戦災まであったという相生の樟への信仰が発端かもしれない。
この神社の別当寺の宝蓮寺は次節で紹介する。
さらに川沿い400m左に、旧日本住宅公団が市街地で面的に再開発をした最初のプロジェクトである立花一丁目団地の最南端の住棟が聳えている。その東側に慈光院(右図②)がある。悠仁君(ぎみ)ご誕生のしばらく後に訪れたところ、住職のお嬢さんから「高野槙が有名になっちゃいました」と言われた。
紡錘状の樹形で生育力の強そうな若樹が墓地への入り口で天を目指していた。
さらに下流に進み、東武鉄道亀戸線の踏切を渡って丸八通りに出て川を南に渡り、右岸を戻ってくる。 |
| 亀戸(蔵前橋通り北) |
都立江東商業高校の西の街区に常光寺(左図①)がある。寺の入り口は南なので、街区の間の道へと左折して鋭角に右折するとすぐに門がある。来迎、龍燈のペアの老松を名所とし、江戸六阿弥陀参りとともに賑わっていたようだが、老松は失われ代わりに露座の石仏が目立っている。
100m足らず南に走っている蔵前橋通に出て右歩道を都心方向に進む。歩道橋のところに、前節の吾嬬権現社の別当だった宝蓮寺(左図②)がある。 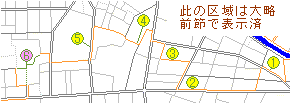 宝蓮寺西の道路を北に入って二つ目の十字路を左折した右に
宝蓮寺西の道路を北に入って二つ目の十字路を左折した右に
東覚寺西の小さい街区の向こうは、前節で渡った福神橋から南下している明治通りである。
神明宮は、先祖が漁民など舟人だった氏子から「入神明」として祀られていたが、梅屋敷が廃園となった水害で、この境内の南寄りに社殿を移された。図会が名所として評価した網干榎も水害で失われ、東京市民を経て都民になった氏子たちに船玉様を超える御加護を求める動機がなくなり、社殿が劣化したのを機会に後から合祀された神様と一緒に扱われたようだ。
参道口に戻って直ぐ右折して進み、ぶつかって左折すると普門院(左図⑤)である。江戸初期に幕命により鐘淵にあった千葉氏の城内からこちらに移転したという。緑豊かというか、伸び放題の樹木が夏の涼み場所を提供している。
なお、左の図版は風俗画であって、名所を紹介したものではない。私の生まれ育った松本平も道祖神の多い地域だった。それぞれがひと月に一回くらい簡単な供え物をして安全祈願をする日があったような記憶があるが、年に一度の祭礼行事は無かった。 |
| 小名木川北(猿江) |
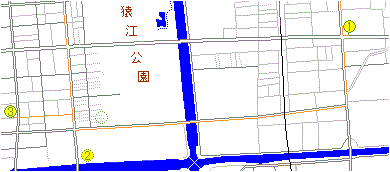 さらに左岸を進んで首都高速道路の下を抜けてすぐの丁字路を左折し、途中貨物線の下を抜けるなどして600mほどで明治通りに出る。これを右折する(南下)。400m余りで新大橋通りとの交差点になり、交差点を左に曲がったところに
羅漢寺(左図①)がある。あると言っても、羅漢像のほか本尊等を含め五百三十有余体の木彫を
さらに左岸を進んで首都高速道路の下を抜けてすぐの丁字路を左折し、途中貨物線の下を抜けるなどして600mほどで明治通りに出る。これを右折する(南下)。400m余りで新大橋通りとの交差点になり、交差点を左に曲がったところに
羅漢寺(左図①)がある。あると言っても、羅漢像のほか本尊等を含め五百三十有余体の木彫を
元の羅漢寺は、安政の大地震で羅漢像を陳列していた建物のほか松雲禅師から百年余り後に造られた三匝(さざゐ)堂が壊れ、修復できないまま寺は衰微し、残った羅漢像や本尊を抱えて明治20年に墨田区緑に移転し、さらに目黒区に移転した。 図会の時代には双方とも健在で、文化的な名所としては最大級だったから、娯楽の名所の浅草寺に匹敵するスペースを使って紹介している。 五百羅漢の尊号は目黒のほうで紹介する。
現在の羅漢寺は、禅宗ではあるが曹洞宗で、残された檀家のために後を継いだものであろう。
さらに明治通りを南下し、次の信号を右折する。500mほどの右にある都立科学技術高専の前に「釜屋通」の碑がある。確かに嘉永年間の切絵図には「釜屋通リ」と書き込みがある。図会は五本松の項で、小名木川が鍋屋堀とも呼ばれることのいわれを説明している。釜屋は通りに並ぶ鍋匠の筆頭だったというから通りの名はそうだったかもしれない。 横十間川の堤防に上がって大島橋を渡らずに左折して150m進むと、小名木川との川の交差があり、四つの岸をX字に結ぶクローバー橋という現代の名所がある。大島橋をそのまま渡ると右は猿江恩賜公園である。
次の交差点は四ツ目通で、これを左折して小名木川橋北詰めの左に 折り返して先ほどの交差点からさらに一街区先で左折して進むと、赤い鳥居が道路際べったりに立っているのが見える。摩利支天宮(日先神社:左図③)である。図会に比べてあまりにも規模が小さく祠然としており、150年の歴史にいろいろあったことを感じさせる。 四つ目通りに戻って北に2街区進むと、住吉駅の東京メトロ半蔵門線入り口がある(都営地下鉄はこの先新大橋通りとの交差点)。さらに1kmほど進めば錦糸町駅であり、その手前で渡るのが京葉道路である。
|
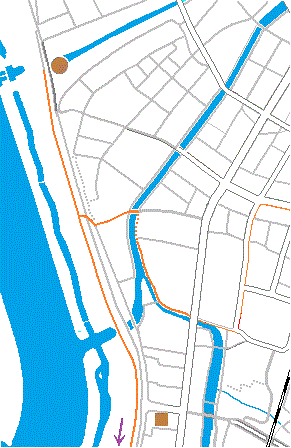
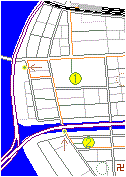 勤め先が神田の人にとっては、東に進む靖国通りを自転車15分で両国橋(左上図左)を渡る。渡ると通りは京葉道路と名を変える。前節から続けて錦糸町駅の南で京葉道路を左折して来れば10分程度である。
勤め先が神田の人にとっては、東に進む靖国通りを自転車15分で両国橋(左上図左)を渡る。渡ると通りは京葉道路と名を変える。前節から続けて錦糸町駅の南で京葉道路を左折して来れば10分程度である。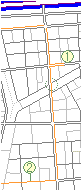
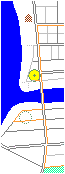
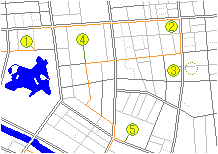
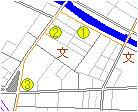
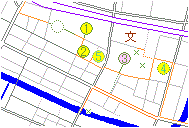
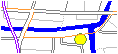 100mも進めば、正面に鳥居が見え、洲崎弁財天(現洲崎神社:右図)である。図会の描くところでは境内の南側は波打ち際になっているが、現在海岸は直線でも3kmほど南である。これに対して鳥居の脇から北側の大横川を渡る朱塗りの欄干の歩行者専用の新田橋(一旦廃されていたのを大正時代に新田医師が復元した)は、太鼓橋が描かれた位置にある。
100mも進めば、正面に鳥居が見え、洲崎弁財天(現洲崎神社:右図)である。図会の描くところでは境内の南側は波打ち際になっているが、現在海岸は直線でも3kmほど南である。これに対して鳥居の脇から北側の大横川を渡る朱塗りの欄干の歩行者専用の新田橋(一旦廃されていたのを大正時代に新田医師が復元した)は、太鼓橋が描かれた位置にある。