江戸名所図会自転車探訪(天
| 最新更新箇所へ |
| 横須賀中心部〜深浦 |
本編のスタートは京浜急行電鉄横須賀中央駅である(左図左下)。駅前通りを左に行き、最初の交差点を右折、ぶつかって左クランクに進むと横須賀警察署のところで横須賀街道(国道16号)に出る。これを左に行き小川町交差点を渡る。変形五叉路で信号が複雑なので、タイミングによっては右歩道で渡った方が早いこともある。
渡って前に入ると北側に学校の並ぶ三笠公園通りにぶつかるので右折する。
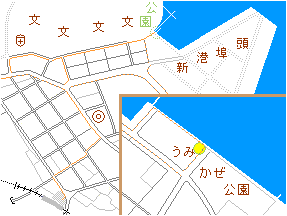 学校の先の公園の海岸には日露戦争日本海海戦の旗艦であった三笠が置かれており、その反対側(右)に三笠桟橋がある。ここから猿島への連絡船が出ている、夏の海水浴シーズン以外の平日は閑散としている。
学校の先の公園の海岸には日露戦争日本海海戦の旗艦であった三笠が置かれており、その反対側(右)に三笠桟橋がある。ここから猿島への連絡船が出ている、夏の海水浴シーズン以外の平日は閑散としている。 図会天セン之部の最後の名所の記録は、猿島と裸島で、地理的にはこのどちらかが最南端である。
右の「経緯など」に書いた曖昧さを無人島に渡ってまでして解明することはその道のプロに委ねることにして乗船せず、猿島が最も良く見える場所を探した。三笠桟橋から戻って直ぐを左折すると左が新港埠頭だが、道路は港湾施設扱いで適当に遮断されたりしているのでパスした。横須賀港の各埠頭をつないでいる「よこすか海岸通り」を1km程行った左にある「うみかぜ公園」が猿島に最も近そうなので、島の遠景写真を含むイメージマップを左図右下に挿入し、そのコースは左図中で虎斑で示した。
うみかぜ公園から次へは同じ通りを戻って上述の小川町交差点で横須賀街道に入るのが良い。 「横須賀まで来てこれだけ?」という向きには、ついでに観音崎や浦賀を周遊するコースをお勧めする。走水への登り坂で振り返って猿島を眺めると島の南北が長いのが判る。ウォーキング専門の方、とくにかつての横須賀を知っている人には、街中ウォッチングでその変貌(山口百恵・宇崎竜童ですらいかに古くなっているか)を実感することをお勧めする。
三笠桟橋から直接深浦港へは、三笠公園通りを戻ってそのまま進み、米軍横須賀基地入口のところで左折、横須賀街道に出て右折する(以下8kmほどはルート図示を省略)。一つ先の信号を左クランクして入る通りは「ドブ板通り」である。相変わらずのスカジャン、アーミールック、サバイバルグッズの店やスナック喫茶でがんばっている店があるが、跡地やシャッター閉め切りが増えており、英語の看板は少なくなっている。 通りの突き当りのEMクラブ(旧海軍士官休養所)跡の再開発は、計画段階で少しかかわりのあった私が懸念した通り、市の重荷になっていることを感じさせる。横須賀街道の横断歩道橋も、好意的には旧海軍のガントクレーンをイメージしたデザインのように見えるが、この道を走るドライバーの99%には意味不明であろう。
汐入駅前で横須賀街道に戻って高速道路沿いに右に入るとJR横須賀駅があり、その先はわが国自衛隊の横須賀基地で行き止まりである。横浜からは京浜急行よりも15分以上余計な時間をかけて200円近く高い運賃を払って乗る人は稀有で、まして地域外の大部分の人は間違って到着したら途方に暮れるだろう。高速道路から離れてすぐにあるトンネルに始まって以下国道を離れるまでの六つのトンネルはいずれも分離型の一方通行なので、追い越す自動車は右車線を走ってくれて有り難い。トンネルがこんなにあるのは、東京湾に向かっての尾根があり、尾根と尾根との間が浦になっているからである。この尾根に沿って断層痕があり、南のものほど新しく地震危険度が大きいとの調査研究結果が発表されている。 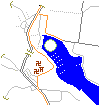 フィリピン海プレートが地殻変動を伴って相模湾に沈みこむ度にこのような尾根が盛り上がったというように受け取れるが、そこまでは言い切っていないのはなぜだろうか。
フィリピン海プレートが地殻変動を伴って相模湾に沈みこむ度にこのような尾根が盛り上がったというように受け取れるが、そこまでは言い切っていないのはなぜだろうか。六つ目のトンネルを抜けると、道は大きく左に曲がり、船越1丁目交差点になる。ここで右のバスが通う通りに入って道なりに進んで坂を登ると対面通行トンネルになる。注意してこれを抜けると先ほどとそっくりに道が左にカーブして右図の下部に出る。すぐの信号付き交差点を右に渡り、広くなっている歩道の先を右に入る。突き当りは小高くなっていて寺社がくっついて建っている。これを回り込んだ所が、榎戸湊(現深浦港:右図)である。狭い敷地に建物が建ち並んで直接海岸には出られないので、一旦バス通りへ戻って200m程先から右へ入り直すと湾の全貌が良く見える。 対岸にはヨットやプレジャーボートが係留されていている。先ほど通った道に建ち並んでいた建物群は、これらのボート所有者の別荘のように思えてきたが、確信は得ていない。 右図の範囲は、現在の住居表示では「浦郷」で、地区内の郵便局を始め店舗名などに「浦郷」が付けられている。図会の図版「浦の郷」(次節)は、ここ榎戸湊を埒外にしており、謎である。
再びバス通りに戻り、右折してトンネルを抜ける。
|
| 埋立てられた追浜湾 |
本節では、先ず左の二つの図版をご覧頂きたい。
雀ヵ浦は、天神を祀って安全を祈願するほど岩礁の多い危険な海岸である一方、奇岩が名勝でもあり峠越えせずに済む浜通りの道の必須の通過点であったことを示している。この絵は夏島西部の海の中(現追浜高校グランド)から北を見て描いたことになる。なお、記述では項を立てており、同所(前の項の室木村)の南の出崎で浦の江と云ふと書いている。 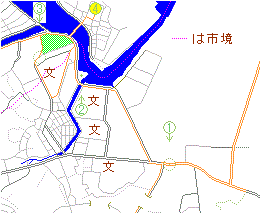 前節から短いトンネルを抜けて左は通常の集落だが、右は工場街である。直ぐにぶつかる東西の広い通りを右歩道のまま200mほどの信号まで来ると、右手に緑の丘が出現する。これが先ほどのトンネルの山続きの岬か独立の島かと思うとさにあらず、旧海軍航空隊が気象観測を兼ねた基地内公園として造成し、後に地下壕を設けた人工の地形で、現在は市の「貝山緑地」という公園である。500m程先に入口があるので時間に余裕がある人は上がってみると、前節の猿島が意外に近く見える。
前節から短いトンネルを抜けて左は通常の集落だが、右は工場街である。直ぐにぶつかる東西の広い通りを右歩道のまま200mほどの信号まで来ると、右手に緑の丘が出現する。これが先ほどのトンネルの山続きの岬か独立の島かと思うとさにあらず、旧海軍航空隊が気象観測を兼ねた基地内公園として造成し、後に地下壕を設けた人工の地形で、現在は市の「貝山緑地」という公園である。500m程先に入口があるので時間に余裕がある人は上がってみると、前節の猿島が意外に近く見える。その入口の手前の信号を北に1km進んで道なりに直角に右に曲がって150m程先の南(右)に、「伊藤博文明治憲法起草記念碑」が(昭和50年日産の用地になったので)移設されている。その後ろは古代遺跡「夏島貝塚」として小高い岡がある。これが夏島で、図会に長三丁横一丁と書かれているのと図版の絵から、北西から東南の尾根筋と縦横2/3ほどが残されている。状況からして伊藤博文が帝国憲法を起草した別荘は岡の西南の日産工場内にあったのだろう。 ここまでの道は京急追浜駅前からの「夏島海貝塚通り」で標識もある。現状確認程度の目的しかないので、ルート図などは省略して通りを戻る。なお、さらに進んで右折しての行き止まりに深海探査船の開発などをしている独立行政法人海洋研究開発機構の本部がある。 戻って東西の通りなってしばらくのあたりに 前節から出てきたときの信号の一つ先を右に入り、横須賀スタジアム東の直線の道路を進む。この道の左、鷹取川までの間は公園、学校などの公共施設が殆どである。再び入り江に出て200mほどで鷹取川を渡ると左は横須賀市営住宅天神アパート、右がエンジンメーカーの出荷倉庫になる。この辺が雀ヵ浦の岩礁があって天神崎とも称すと書かれた場所(左図②↑先)だったと思われる。 アパート群を通り過ぎてガソリンスタンド先を左へ鋭角に入ると自衛隊用を主体とした国家公務員住宅の室ノ木宿舎がある。この団地の南端を回って戻ると左側が追浜県営住宅になり、右は県警追浜公舎、そして横浜創学館高校(旧横浜商工高校)になる。すぐに左右とも公務員住宅の区間になって関東学院大学等のキャンパスにぶつかると道は右に曲り、公園(野島公園室ノ木分区)内を抜けて海岸道路に出る。 この公園の入口一帯(左図③↓先)が昭和18年に軍に接収されて金沢文庫駅北に移転した太寧寺(2節後の金龍院の図版遠景に付注されている)の境内だった。 室木村にありと書かれている筥根権現社は手掛かりがない。 上の段落で施設の地名をいちいち書いたのは、当時の人たちが残した地名とその記録が通じなくなる懸念を具体例に照らして右下の雑学メモにまとめる伏線である。
海岸道路を右歩道で200mあまり(夏島方向に)戻ったところの信号で道を渡ると野島への夕照橋になる。これを渡り、信号先を30mほどを右に曲がって50m弱の左が善應寺(図④:現染王寺)である。
染王寺の北にあるのが野島公園の本体で、その北海岸の西に伊藤博文金沢別荘が保存されている。
|
| 金澤八景駅西部 |
内川橋を渡って300m六浦中学校入口交差点を左折、京急本線を潜り、侍従川を渡って突き当り気味に右折して京急逗子線の踏切を渡る。200mあまり道なりに進んでバス通りに出て左折すると400mほどで六浦駅前に出る。そのまま逗子線の北側を平行して進む。
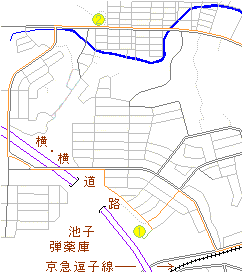 行く手に高架の横浜横須賀道路が見えてくる(この辺から右奥が「朝比奈地区である」)。勾配が上がり始めるところの信号付きT字交差点を右折して踏ん張って坂を上がっていく。緩やかに左に湾曲して最初の信号付き交差点を左折して突き当たりは
行く手に高架の横浜横須賀道路が見えてくる(この辺から右奥が「朝比奈地区である」)。勾配が上がり始めるところの信号付きT字交差点を右折して踏ん張って坂を上がっていく。緩やかに左に湾曲して最初の信号付き交差点を左折して突き当たりは千光寺の横の道も坂だが、いずれはこうして蓄えた位置のエネルギーを爽快に放出できると考えて上っていき、幅の広い道路に出たら左折、三信センター前交差点で右折していよいよ坂を下る。 直ぐに横浜市の環状4号線でもある鎌倉街道に出るが、右折して200mも行かないところの左の崖が磨崖仏の界地蔵があった場所(左図②)である。
引き続いて海のほうに向かっていく。 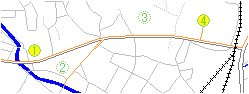 右から左に見送った侍従川を再び左から迎えて渡るあたりからが六浦の中心地で、直ぐ左に光伝寺(右図①)がある。門前の石碑に「並木天満宮」(図版では寺の裏山に天神と付記されている)と神仏習合を堂々と示している。
右から左に見送った侍従川を再び左から迎えて渡るあたりからが六浦の中心地で、直ぐ左に光伝寺(右図①)がある。門前の石碑に「並木天満宮」(図版では寺の裏山に天神と付記されている)と神仏習合を堂々と示している。光伝寺から200m先の信号からV字に戻るように南西に伸びる道が本節の始めに六浦駅に向かった道で、本節当初に向かった専光寺はこの道の右にありと図会は記している(昭和58年移転時は既に「千光寺」)。 この地域には照天姫物語が伝説になっている。侍従川の名は、姫の乳母の侍従が身を投げたことから付いたとされており、その身投げの場所はこの付近(右図②付近)と図会は書いている。また、寺の本尊は姫が火焙りになったときに身代わりになり、姫はこの本尊を念持仏としたとも書いている。
さらに先の左に上行寺(右図④)が現存している。この寺は図会が称名寺(次々節)の項で扱っている「賭碁に勝って二王像を身延山に運んだ」という伝説の当事者日荷上人が住職だったとという寺で、伝説は境内の説明板にもしっかりと書かれている。 |
| 金沢八景駅東 |
京急のガード手前を左に上がっていった所の住宅街は、図会が旧跡紹介をしている
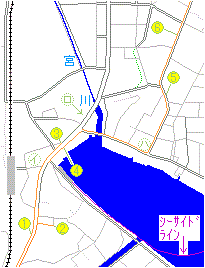 ガードを抜けて出た横須賀街道六浦交差点で左折、左歩道で200m先に泥牛庵(左図①)への石段がある。位置も役割も図会の時代のままである。
ガードを抜けて出た横須賀街道六浦交差点で左折、左歩道で200m先に泥牛庵(左図①)への石段がある。位置も役割も図会の時代のままである。泥牛庵の先50mの信号で道の反対側に渡り、40mほど戻って左に入っていった突き当りが金龍院(左図②)である。 一見普通の家のような門扉の向こうに広がる境内は鬱蒼としている。
 金龍院から横須賀街道に出て、さらに南下し、六浦交差点の70m先に六浦川・六浦橋(右図▼左上)がある。前節の侍従川・内川橋よりもメジャーな名がまさかと図会は驚いて小溝・小橋と書いているように思える。
金龍院から横須賀街道に出て、さらに南下し、六浦交差点の70m先に六浦川・六浦橋(右図▼左上)がある。前節の侍従川・内川橋よりもメジャーな名がまさかと図会は驚いて小溝・小橋と書いているように思える。 現代の私は10年前の当初アップの際、前節千光寺跡地北に「六浦川」郵便局があるのに引きずられて「侍従川の支流だったが遠の昔に埋められた」と決めつけていた。改めて全巻の地名のチェックをしていて六浦村(字:アザ)川の有力者(もしかすると千光寺)が他の字に負けじと設けた郵便局名ではと今は思っている次第。
折り返して金龍院先まで行き、横須賀街道の西側に戻り北上する。金沢八景駅前東口は明治初期に廃寺した円通寺の境内(左図イ:図版は「瀬戸弁財天」)が京急線路敷にまで広がっており、西の岡に東照大権現(図版は同前。2節前の図版浦の郷で坂を上がって来る旅人を描いたのもその辺か)があったと思われる。一部は廃藩置県後冒頭に書いた米倉陣屋と一体に管理されていたようだが、今ではいずれも何の痕跡もない。
図会は沢庵禅師の鎌倉紀行から「弁天の島へ渡る橋は二連だ」との記述を引用しているが、右の「弁財天」、「瀬戸明神」や次節の「勝概一覧」の各図版ではそのように描いていない。直截さを憚りながらも、読者に高僧のミスを気付かせようとしているようだが、もしかすると図会の200年前は弁天の方にあって宮川には橋が無かったかもしれない。
駅前を通り過ぎてもう一度信号を渡った先が瀬戸明神社(左図③:現瀬戸神社)である。図会描く蛇木蛇混柏が現在では鳥居の横に移されているが、350年を越えて形を留めていると言うのは驚異である。 道幅こそ違え、社前の道を隔てて瀬戸弁財天(図④:現枇杷島神社)になっている。現代は道を横切れず、駅前まで戻って信号を2度渡る必要がある。
旅亭・東屋は、図会の時代には瀬戸橋の手前にあったが、安政年間に火災に遭って橋から100m余先の洲崎交差点のところ(左図(ハ))に移転した。明治になって伊藤博文が夏島の別荘(2節前参照)で立案した帝国憲法の案をここの東屋で閣僚らに示して意見交換をしたとのことで、「憲法発祥の地」という碑が建てられている。
この道を直進すると、前々節の染王寺に行くのだが、洲崎交差点を左折する。200m余り、道が緩やかにうねるところに龍華寺(左図⑤)がある。
なお、右の図版で寺の東の遠景には汐濱とキャプションが入っていて、その左後の海中に低い松の茂みが水平に描かれているが、これが現在の「八景島」であろう。また、寺の手前には舟運が描かれているが、この川の痕跡は、一街区西側にある緑道である。 天然寺(左図⑥)は、同じ道を100mほど北へ行った左である。入口の参道は狭められているが、山門の向こうには結構広い境内がある。 |
| 金沢文庫駅東部 |
| 能見台南 |

金沢文庫駅前交差点から300m、「谷津二の橋」という信号を過ぎて左の道に入って踏切を渡る。右の線路沿いに大型マンションの前を過ぎるといかいにもデザインしましたという感じの広い階段が現れる。
自転車をぶら下げてこれを上がりきったら開発された住宅地の左端を辿って進む。左の山への入口があるので自転車を押してこに入っていく。
能見堂からの北斜面は、谷津という地名だった。第二次世界大戦後にここを住宅地開発した京急グループは、「能見台」という名をつけて売り出した。能見堂の最寄り駅は金沢文庫駅だが、東京寄りで金沢文庫駅までの2倍遠い「谷津坂駅」を能見台駅にしてしまった。
ネーミングライトの意識もなかったし、明治初年に廃寺になっていた能見堂の立場で異論を唱える人は少数だった。平成になって横浜市などが史跡の扱いを始めたが、「擲筆松」の由来まで生じさせた金沢八景の絶好のビューポイントは、荒れ果てた樹林によって失われてしまった。
図会本文にも記されている「八景」をメモすると、洲崎晴嵐、瀬戸秋月、小泉夜雨、乙艪帰帆、称名晩鐘、平潟落雁、内川暮雪、野島夕照である。 自転車をぶらさげて能見堂跡の西の急坂に設けられた階段を踏み外さないようにして降り切り、住宅地内を右へ進み、途中左の広い道に出、引力のなすがまま下ると、先ほど上った線路際の階段の北に出る。左にヘアピンで線路際に下り、北の集落に入ってへ入っていき、上りになったところの分岐を右にとってもう一度線路沿いに出ると、道が線路の下に潜る手前の左正面に軍によって室ノ木から移転させられた
一般に寺の移転は長年培った檀家との関係を希薄にし、檀家の寺替え(宗旨変え)を生ずる。この寺は檀家との事前の打合せもなかったので一時は無住にまでなったが、同一宗派の檀家移しなどの支援で、現在に至っている。 線路の下を通って横須賀街道に出て、北、杉田へ向かう。一旦都心へ戻る場合は、金沢文庫駅に戻るのが特急電車などが停まるので便利だが、せめて1kmはまともに走り切っておきたい向きには横須賀街道1km余り先の左に能見台駅に上がる道がある。 |
| 杉田から上大岡 |
図会にはこの区間の記述はなく、図版(絵)だけである。手持ち(活版印刷)の編集ミスかと思い、図書館の復刻版などを見たが記述で弘明寺と金沢は一枚の版の中で続いている。図版は「青木明神社」が「弘明寺」の前に置かれているので微妙だが、少なくとも杉田については長秋は訪れず、雪旦だけが訪れたように見える。
地域紹介の記述の中で触れているものなど記述のみというのはいくらでもあるし、鳥瞰図の中で主体に隣接して描かれただけのものも少なくないが、絵だけでまとまった区間になっているのは例外的である。
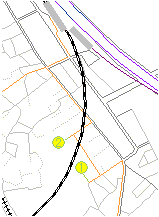
横須賀街道を15分足らずで、富岡トンネルがある。
妙法寺境内の直ぐ東の道を北に進んでJR根岸線の下を通って突き当り、左を見ると神明宮(左図②:現杉田八幡宮)がある。  例によって幼稚園併設パターンである
例によって幼稚園併設パターンである横須賀街道に戻って300m足らずの聖天橋交差点を直進して3.8kmの八幡橋交差点で横須賀街道から右に岐かれて本牧に行くルートも設定できる。 右折すればJR新杉田駅(金沢八景駅までのシーサイドライン起点でもある)であり、左折すれば京急杉田駅(左図左外)であるので、選択肢は多い。 上大岡へは、直進して1kmあまりで左折して屏風ヶ浦バイパス側道(歩道)を行く方法もあるが、今回は屏風ヶ浦バイパスへの坂より緩やかな京急杉田駅前をかすめての峠道を採る。上り切っての下りは「逆コースはご勘弁を」と言いたい急坂で、すぐに大岡川上流の笹下川に沿った道になる。 大岡川は、横浜の中洲部で東京湾に出ている。「横浜」の地名の源になった立派な砂州は、主にこの川が供給していた土砂で形成されたものであった。流域の都市化で頻繁な土砂崩れは無くなっている代わりに、雨水の短時間流出は大きくなっている。このため東京湾への短絡水路として上述した八幡橋が渡る堀割川、4節後の「横浜都心部」で触れる堀川に加えて昭和50年代に「大岡川分水路」が整備された。
大岡川分水路の分水地点は、屏風ヶ浦バイパスとこのルートとの交差点手前で、バイパスの下に1.4kmほどの水路トンネルが掘られ、磯子の埋め立て工業団地内で東京湾に出ている。 右図下部の日野川合流部近くで横浜からの鎌倉街道に出るが、そのまま直進する。
次のまともな十字路を左折すると、大岡川を渡る青木橋の左袂に青木明神社(現青木神社:右図)がある。
上大岡駅は、快速特急も停車する駅なので、徒歩や小刻みにフォローしていく人には便利である。駅前の混在を避けるには先ほどの十字路で左折し、駅の北へ出て鎌倉街道に合流し、北へ向かう。 |
| 南区(蒔田〜弘明寺) |
横須賀街道に出て15kmに、市営地下鉄弘明寺駅のある弘明寺交差点がある。左折してアーケード商店街を抜けると弘明寺にぶつかるが、後回しにして進む。同じくらい走ると、左から横浜環状一号線道路が来ている通三丁目交差点になる(左図左)。
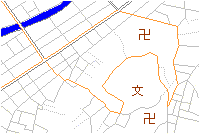 さらに三つ先の信号(宮元町:左折して大岡川を渡る橋は現在も蒔田橋。この先の信号までの間に市営地下鉄蒔田駅がある)で右折し、道なりに右へ右へと辿ると勝国寺の門前になる。ここで右へ鋭角に折れて、左の岡を取り巻いている道を上がっていく。この岡が、天キ之部の世田谷中央部で登場した吉良氏が世田谷へ移る前に館にしていた蒔田城跡で、堅守の山城だったと図会は紹介している。
さらに三つ先の信号(宮元町:左折して大岡川を渡る橋は現在も蒔田橋。この先の信号までの間に市営地下鉄蒔田駅がある)で右折し、道なりに右へ右へと辿ると勝国寺の門前になる。ここで右へ鋭角に折れて、左の岡を取り巻いている道を上がっていく。この岡が、天キ之部の世田谷中央部で登場した吉良氏が世田谷へ移る前に館にしていた蒔田城跡で、堅守の山城だったと図会は紹介している。現在は横浜英和学院(旧成美学園:有島武郎通学の頃は横浜英和学校)のキャンパスになっている。正門近くに遺跡についての説明板があり、右の横須賀通街道側は、木々の間から市街が見える。 南側に下り口があり、これを右に向かって道なり下りていくと、先ほど走り抜けた通三丁目交差点に出る。 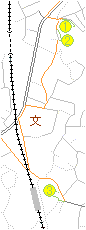 今通ってきた地区に延伸されるべき向かいの環状一号道路を進み、大岡川を渡り井土ヶ谷交差点を左折する。
今通ってきた地区に延伸されるべき向かいの環状一号道路を進み、大岡川を渡り井土ヶ谷交差点を左折する。
左折して500mあまり先、三つ目の信号(住吉神社入り口)を左に入り、直ぐの斜路を上がっていくと住吉明神社(現住吉神社:右図①)である。 住吉神社と乗蓮寺・二位禅尼影堂(右図②)は境内が続いている。しかし、右の図版でも柵が設けられていること、その記述もないことから別当関係はなかったように思われる。現在も両者の間は寺が設けた幼稚園が遮っており、一旦下に下りて大通りに出ずに左折すると上る斜路がある。幼稚園が出来るまでは寺のためだったが、最近は幼稚園を優先しているようである。 二位禅尼とは尼将軍とも称された北条政子のことで、乗蓮寺の開基でもある。お手植えの榧、影堂と立体墓地を統合した霊堂には寺宝の禅尼像も保存されている。地名「井土ヶ谷」は元来「井戸ヶ谷」で、その井戸は、寺の境内で政子が愛用した井戸であるとのこと。 自転車をぶら下げて境内の西の階段を下り、南へ向かうと中学校にぶつかるので右折、大通りに出て左折、京急高架の手前を左に入っていく。京急弘明寺駅前を左に商店街を下りていくと途中右に弘明寺本堂(右図③)への階段があり、その先ほぼ下りきったところに観音堂への仁王門(イメージマップの写真はこちら)がある。仁王門から振り返ると、本節冒頭で書いたアーケード街の入口が見える。 駅裏は市の公園や図書館になっているが、行基大士や弘法大師が霊感を受けた麻耳山という山で、 次節へは、弘明寺駅前で京急線を渡り、大通りに出て4kmほど先の平戸に向かう。 |
| 旧東海道最遠の江戸名所 |
平戸桜木通りは峠道である。逆Sの字を描いて上った後は東海道(国道一号)の山谷交差点に向かって直線状に一気に下る。東海道を戸塚方面に左折して右に湾曲すると平戸立体交差点である。
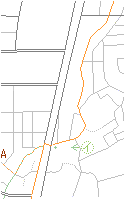 環状2号道路の高架を過ぎての信号で右に渡り、側道を上がっていくと左図下部になる。
環状2号道路の高架を過ぎての信号で右に渡り、側道を上がっていくと左図下部になる。800m余り上がったところに環状2号を跨いでいる歩道橋があり、その下に案内板があ、ここから西南に下る道が旧東海道であることを示している。これを150mほど下った交差点で右折して左図A方向400mに品濃町交差点があり、その北80mがJR東戸塚駅(改めて都心から出向く場合の出発点)である(左図の虎斑ルート)。 自転車を降りて歩道橋を渡ると「品濃坂上」の案内板がある(左図(イ)←先)。図会が坂上にて右を望めば芙蓉の白峰玉をけづるが如く、左を顧れば鎌倉の遠山翠黛濃にしてとその風光を称えているポイントは、どう探してもこのへんしかなかった。
図会が旧東海道で紹介している最も遠い江戸名所がここシナノ坂である。しかし、右の図版でも記述でも「権太坂」を別称としている。さらに用字も記述の項は「品野」、注で「信濃」「科野」を紹介、図版は「科濃」である。そして現在の住居表示では旧東海道が「品濃」と「平戸」の境になっている。 もう少し話をややこしくすると、JR東戸塚駅から出発して旧東海道に入って100mほどの左に「品濃坂下公園」がある。明かにバブル経済期以降に整備されたもので、新住居表示下で行政当局が勝手に付けた名前と思われる。 北へ延びる旧東海道を辿ると、左図上部から緩やかに下り、再び上り坂になる。上り坂の途中に「牡丹餅坂」との案内板がある。右の境木の図版や記述では、坂の上の武相国境に店があるようになっており、そこで食べ残して懐に入れた牡丹餅がこの坂を転げ落ちたりしたのだろうか。
坂の上は不思議に広い交差点になっており、図版に描かれた地蔵堂(右図①)がその北側に現存している。 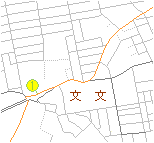 地蔵堂の境内と広い歩道を含めた道路との境が武相国境で、現在は保土ヶ谷区と戸塚区の区界である。この不思議に広い道路空間は界木・・立場の跡とも思われるが、現在では戦後の宅地化で形成された境木商店街が縁日に出店(でみせ)をする広場になっている。
地蔵堂の境内と広い歩道を含めた道路との境が武相国境で、現在は保土ヶ谷区と戸塚区の区界である。この不思議に広い道路空間は界木・・立場の跡とも思われるが、現在では戦後の宅地化で形成された境木商店街が縁日に出店(でみせ)をする広場になっている。道を東に進むと、右に小学校と中学校が並んでいる。この中ほどの向かいに権太坂から上ってきた道が来ている。つまり坂の上なので、図会が権太坂を品野坂と誤解したどうかを富士山や鎌倉の山が見えるかどうかで確認したかったが、校舎が遮っている。校舎が無くても、図版「境木」の背景などから品濃坂の稜線の上に出た部分だけが見えるに過ぎず、記述ほどの感動は無かったのではないかと思われる。 この左分岐の道を下っていく。はじめは緩やかでやがて急になり、一旦勾配が小さくなった後、分岐から800m先の権太坂小学校と県立光陵高校の間あたりでまた急になる。元来の坂はこの先保土ヶ谷バイパスで分断され、地図の位置を変えずにバイパスの上を橋で渡っている。
下りきってぶつかり、左折して100m、帷子川を渡って東海道本線手前が本節里程表の元町ガード交差点である。 |
| JR保土ヶ谷駅山側 |
元町ガード交差点から東へ進んだ旧東海道は、一旦現東海道に合流し、保土谷本陣前跡という交差点で左に入って再び単独の旧東海道になる。JR東海道本線を渡って300mあまりで保土ヶ谷駅前広場(左上下部)からの広い道が合流する。
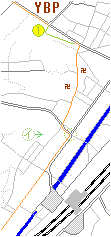 次の交差点は、交通違反の金を集めやすくするためだけに付けられた名前と思われる「反則センター」という無粋な名前の交差点である。ここに右の「帷子里」図版の左下隅に描かれている
次の交差点は、交通違反の金を集めやすくするためだけに付けられた名前と思われる「反則センター」という無粋な名前の交差点である。ここに右の「帷子里」図版の左下隅に描かれている後で訪れる冨士浅間祠の別当は保土ヶ谷の真言宗・天徳寺と書いている。
また、前節の境木地蔵堂の説明板はここ(左上図右の卍マーク:入口は旧東海道側)にある「見光寺」が立ており、図会の時代以前からの名刹らしいが、とりあえずは対象でないのでパスした。 東からのバス道り(大門通り)に出て左折すると、神明宮(現神明社:左上図①)の鳥居があり、細長い境内になる。神主が専管しての神社で、格式があり右の図版でも10社ほどが境内に付注されているが、現在神社のサイトでは十数社になっている。(個別紹介省略) 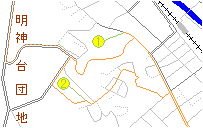 神明社本殿前から横浜ビジネスパーク前に出て大門通りを上って行く。
相模鉄道の星川駅入り口から80mのところに、杉山明神社(現星川杉山神社:右図②)の別当と記され、図幅にも描かれている法性寺(右図①)がある。
神明社本殿前から横浜ビジネスパーク前に出て大門通りを上って行く。
相模鉄道の星川駅入り口から80mのところに、杉山明神社(現星川杉山神社:右図②)の別当と記され、図幅にも描かれている法性寺(右図①)がある。法性寺から杉山神社への道は、図会が描くとおり寺の境内のすぐ東の道であるが、絵よりもはるかに勾配がきつく、私は漕ぎ上がることができなかった。右図の上へ突き抜けて星川小学校で左折して横浜新道入口から明神台団地内の道で上る方法(虎斑のルート)もある。しかし、楽ではないし自転車を押して上がるのと時間は変わらない。 ぐるっと東正面にまわると「都筑第一座」と延喜式に明記されているとの説明板がある。横浜を始め神奈川県内には他にも杉山神社がいくつかあるが、あまりの山の険しさに摂社や遥拝所があちこちに設けられたと考えられる。
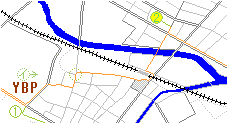 鳥居の前から,ブレーキだけで下りていくとT字路に出る。左折すると先ほどの大門通りに出るので、右折して戻る。
鳥居の前から,ブレーキだけで下りていくとT字路に出る。左折すると先ほどの大門通りに出るので、右折して戻る。横浜ビジネスパークの東端の角を左折して50m先、右の歩道の広い道に入る。(左下図参照。一部左上図と重複)T字路で突き当ったのは古町街道である。左折して40m弱に左から出てくる湾曲した道は、図会の時代の
ここを右に入って相鉄天王町駅前に出ると旧東海道であり、 なお、3節後で紹介する「神奈川総図其三」の最遠景に天王という付注がある。これは現天王町駅の北200mにある(左下図②)橘樹神社の前身の「牛頭天王社」のことである。神社本庁の圧力での変更だが、神仏分離令から50年もかかった。しかしその前に地名は定着し、駅名もこれを継承している。 この神社ゆかりの方と知り合った。質問をし始めたら、「私は分家筋で、あまり聞いてないので判りません」と話題を避けた。50年の間に姓は戸籍に残ったが、かえって一族ご一統のタブーになっているのだろうと感じた。
「橘樹神社」は、天キ之部の「橘樹郡中心地」で登場している。橘樹郡の北寄りの地と南端の地とは交流はほとんどなく、この地も昭和2年に橘樹郡を離れて横浜市になったから、お互いの氏子たちは同名の神社が生じたことに気付くことなく経過したのだろう。 その橘樹神社は、ガードを抜けてすぐ左クランクして駅北で復活している旧東海道に入り、現在の古町橋(古町街道でないのだから変)を渡って信号を越えた左(左下図②)である。信号に戻って左折、現東海道を横切り、橋上駅の相鉄線西横浜駅の階段を上り下りしてひたすら東南東へ1km、藤棚町交差点で南へ向かう。
|
| 本牧 |
図会の第六分冊には、第五分冊で項立てされている横浜村関係の図版2枚が綴じ込まれている。私の当初の探訪記録では、三節前の蒔田城址から本牧を経て横浜都心を済ませた後改めて旧東海道部分に入るルートにして記述順を動かした。再編にあたっては、第五分冊に集録すべきものだった2枚の図版が手違いで第六分冊に含まれたと理解して記述順を尊重してみた。しかし、よく考えて見ると本牧までが第五分冊のはずだったのかもしれない。 藤棚町から2km弱、黄金町駅のところで京急を潜って大岡川を渡ると本編最初の方でお世話になった横須賀街道に出る。これを渡ると、交通量に応じて道は細くなり、高速道路(中村川)にぶつかる。歩道橋を使って川を渡って同じ方向に進むと看護学校先で左図上部になる。 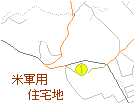 右先に進むが、やがてギアを落としても上り切るのはきつい坂が100mほど続く。押して上がった道の向こうは、「おもいやり予算」で運営されている米軍住宅地である。Googleで見た限りだが首都圏の米軍住宅地の中で最大の一戸当たり敷地面積になっており、おもいやりへの見返りなのか広域避難地にもなっている。詳細は右下の「本牧根岸接収地」でどうそ。
上りきって山手通りへ鋭角に左折して、右に見えてくる樹林が
右先に進むが、やがてギアを落としても上り切るのはきつい坂が100mほど続く。押して上がった道の向こうは、「おもいやり予算」で運営されている米軍住宅地である。Googleで見た限りだが首都圏の米軍住宅地の中で最大の一戸当たり敷地面積になっており、おもいやりへの見返りなのか広域避難地にもなっている。詳細は右下の「本牧根岸接収地」でどうそ。
上りきって山手通りへ鋭角に左折して、右に見えてくる樹林が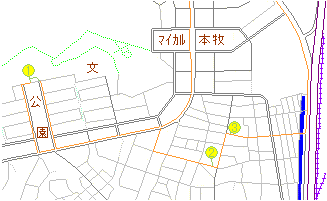 ここでは、この地への移転後の戦後に奉納された高村光雲の観世音菩薩像が、参拝者用駐車場から入って右手の四阿風のお堂に置かれていることだけ触れておく。自転車を押して参拝者用駐車場から境内に入り、観音像などを拝み、正門に出て裏から入った非礼を詫びる一礼をして自転車に乗る。
ここでは、この地への移転後の戦後に奉納された高村光雲の観世音菩薩像が、参拝者用駐車場から入って右手の四阿風のお堂に置かれていることだけ触れておく。自転車を押して参拝者用駐車場から境内に入り、観音像などを拝み、正門に出て裏から入った非礼を詫びる一礼をして自転車に乗る。増徳院前を右(南)に進み、根岸海岸に下りるルートもある。しかし、極端に道が細くなったり、ヘアピン状に道を選ばねばならないのでパスし、山手通りを進む。 山手通りを進んで1km余りにある打越橋(高さ20m弱)で横浜駅根岸道路を跨ぐ。続いて両側が横浜共立学園になって突き当たる。右折して山手本通りの地蔵坂上交差点に出て左クランク状に渡って下っていく。信号がわずらわしいのであえて本牧通りに出ないで、通りから1宅地裏(左)の道を1km余り進む。 先に信号が見えたら本牧通りに出て、さらに右歩道に移って進む。山手警察署前の信号から区画整理された区域が始まる。
図会は、本牧十二天宮を訪れた参拝者が鳥居の前で、宮を背にして海を見ている様を描いている。騒ぎ始めた波の上で、岬の岩にぶつからないよう必死で舟を操っている帆掛け舟とこぎ舟の舟びとを心配そうに見ている。つまり、現在の本牧通りは海の中だったのである。
現在の本牧神社は神社林などが整備されていない。誰しもの疑問に応えるかのように、摂社や合祀している神社が未整備であることの説明板が掲示されている。右の吾妻権現の図版に描かれている 本牧通りに戻って左折し、最初の信号で通りの反対側の道に入り、次の十字路を左折する。二つ十字路を過ぎると赤い山門が目印の多聞院(図②)がある。この寺は、十二天宮の別当として図会に記されている。 多聞院の角を左折して北へ向かって最初の信号交差点の右向こうが吾妻明神社(権現宮)(現吾妻神社:図③)である。図会は、東京湾の向こうの木更津の吾妻神社のご神体が漂着したという伝説を紹介しているが、現在この神社に建てられている説明板には、伝説より古い時代からあったので妄説であるとしている。 神社前を東に進んで産業道路に出ると、首都高速道路湾岸線が頭の上を走っている。大型トラックなどが轟々と走っているが、路側帯は余裕があるし、一部では歩道もたっぷりあって歩行者が少ないのでこれを左折、北上する。 |
| 横浜中心部 |
首都高湾岸線は間もなく本牧埠頭方向に遠のく。産業道路をそのまま2kmあまり走ると、首都高が右から道路の上を跨いでいるのが見える。手前に左が元町方向との案内が出ているのでこれに従って左折する(左上図右端)。
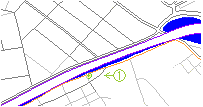 入って200mほどの交番のところで首都高の下の中村川沿いの道を選ぶと、次の角の駐車場の上に増徳院の薬師堂(左上図①←先)が残されている。つまりこのへんが増徳院の境内だった。
入って200mほどの交番のところで首都高の下の中村川沿いの道を選ぶと、次の角の駐車場の上に増徳院の薬師堂(左上図①←先)が残されている。つまりこのへんが増徳院の境内だった。1923年の関東大震災で増徳院は殆どの堂宇を失うが、これをきっかけとして元町の墓地と寺の拠点を平楽に移し、跡地は一般市街地になった。元町に残した檀家向けの連絡所も1945年米軍の空襲で焼かれ、現地に残った僅かな土地に薬師堂を立体化して増徳院の痕跡を留めることとなった。 現地の駐車場の壁には、父がフランス人で、波乱万丈の人生を送った平野威馬雄の歌詞が張られている。歌詞は言外に国際協力に貢献した増徳院を称えているようにも思える。
平日も女性客で賑わう元町商店街を敬遠して、そのまま進み、広い通り(本牧通り)に出たら右歩道で西の橋を渡り、JR関内駅方向に向かう。 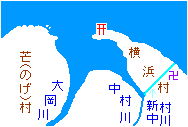 中華街西門や横浜スタジアムを通り過ごすと市役所と関内駅との間は歩道だけになる。これを抜けて市役所の西に出る。
西の橋からここまでのルートは、中村川の自然流路跡で、元町裏の首都高速道路が乗っている中村川は、開港に伴って外国人居留地を明確に区分するために掘削されたものである。(右上図参照)
中華街西門や横浜スタジアムを通り過ごすと市役所と関内駅との間は歩道だけになる。これを抜けて市役所の西に出る。
西の橋からここまでのルートは、中村川の自然流路跡で、元町裏の首都高速道路が乗っている中村川は、開港に伴って外国人居留地を明確に区分するために掘削されたものである。(右上図参照)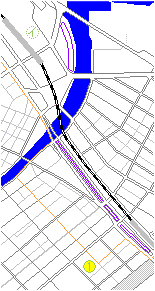 市役所西から関内駅ホーム下のガードを潜って「石の広場」の前に出る(左下図右下)。右折して広い歩道を行き、地下街出入り口の手前の左の路地を見ると、赤い鳥居が建っている。
市役所西から関内駅ホーム下のガードを潜って「石の広場」の前に出る(左下図右下)。右折して広い歩道を行き、地下街出入り口の手前の左の路地を見ると、赤い鳥居が建っている。
神社の鳥居には「横浜弁天」の額がかかっていて図会の時代からの呼称を尊重している。 神社の境内には、社殿のほかに弁天の祠も設けられており、その岩の形状は、むしろ図会が描く 神社前をJR根岸線に平行に進む。まずは国道16号が横須賀街道と呼ばれる最後の区間を横切り、往年の面影がほとんど消滅した伊勢佐木町商店街を横切り、西公園のところで大岡川に出て右岸を下流に進む。桜川橋で川を渡り、300mほどの花咲町2丁目交差点を右折するとJR桜木町駅である。 横浜弁天の旧地と姥島の旧地は「みなとみらい21地区」内である。ともに面影はないのでルートを設けない。しかし地区内は歩道幅が広いので、JR桜木町駅を起点として現代の名所をあちこちを眺めるポタリングには、車道走行を義務付けられていない70歳以上の私などの世代には最適である。
 交差点を渡って交番前を右歩道で進んで直ぐ右クランクで旧東海道を天王町方面に進むと右に赤い神社掲示板と鳥居があり、浅間神社/富士浅間祠(現浅間神社:右下図①:次節「神奈川総図其三」で人穴社)への登り口である。私が最初に訪れた日は祭りの日で、旧東海道の松原商店街は出店が並び走り抜けられなかった。掲示板に自転車をくくりつけるのもはばかられ、ぶら下げて石段と旧坂を登った。イメージマップの写真も境内写真で、プライバシーに障る参拝者もいるかもしれない。
交差点を渡って交番前を右歩道で進んで直ぐ右クランクで旧東海道を天王町方面に進むと右に赤い神社掲示板と鳥居があり、浅間神社/富士浅間祠(現浅間神社:右下図①:次節「神奈川総図其三」で人穴社)への登り口である。私が最初に訪れた日は祭りの日で、旧東海道の松原商店街は出店が並び走り抜けられなかった。掲示板に自転車をくくりつけるのもはばかられ、ぶら下げて石段と旧坂を登った。イメージマップの写真も境内写真で、プライバシーに障る参拝者もいるかもしれない。二の鳥居の向かいには図会が「富士の人穴に通じているという古い言い伝えは疑問だが省けない」と書いている人穴(現在では古墳跡と調査確認されている)がある。ここを右に回って降り、また右に進み、宮ヶ谷小学校入口交差点を渡って左に上がってすぐ右に入っていく。交差点付近は形を変えているが、この道は江戸への旧東海道である。 |
| 神奈川驛(向軽井澤、台町、青木町) |
旧東海道左側は「南軽井沢」、右側は「楠町」が首都高速の下まで続く。図会は向軽井沢と云ふ地迄、すべて神奈川驛と書いている。この上がり坂の区間にはその名残は殆どない。首都高速を潜った後のほぼ直線になっている神奈川台町の海岸が他の錦絵になっている袖の浦で右の図版神奈川総図其三の海岸、同其二の中央部の岡が道灌山と思われる。
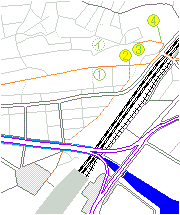 ペリーの二度目の寄港は横浜だったから、この沿道は野次馬や幕府のあたふたでごった返していたに違いない。また、本節登場の現存名所は開港当時のエピソード付きのものだらけである。右の「神奈川台」の図版に他を圧して描かれているさくらやは、飯綱神社入り口から100m手前の右に「田中家」として現存し(左上図①)、説明板も立っている。「さくらや」以降明治時代の名士や異人さんを接遇したおりょう(竜馬の妻:仲居づとめをした)のことなど田中家を巡る160年間の激動の歴史は同家のサイトに詳しい。
ペリーの二度目の寄港は横浜だったから、この沿道は野次馬や幕府のあたふたでごった返していたに違いない。また、本節登場の現存名所は開港当時のエピソード付きのものだらけである。右の「神奈川台」の図版に他を圧して描かれているさくらやは、飯綱神社入り口から100m手前の右に「田中家」として現存し(左上図①)、説明板も立っている。「さくらや」以降明治時代の名士や異人さんを接遇したおりょう(竜馬の妻:仲居づとめをした)のことなど田中家を巡る160年間の激動の歴史は同家のサイトに詳しい。飯綱権現社(現大綱金毘羅神社:左上図②)は右の神奈川総図其一から二に渡って描かれており、往時の社殿はいくつもの参道の石段を上がった左上図の(イ)の位置にあった。
三寶寺は、飯縄権現等の別当のように飯綱権現参道東に並べて描かれているが、別当は本節で後述する普門寺だった。三寶寺は描かれている街道沿いの地はマンションになっていて、後ろの急斜面に鉄筋コンクリート造の威容を誇っている。アクセスは以下の本覚寺の山門前を権現社旧地のほうにがった左が正門になっている(左上図③)。 一旦東海道(第二京浜:旧国道一号)に出て青木橋交差点まで上がり、さらに国道と併行している少々きつい坂の上に本覚寺(左上図④)の山門が見える。脇には、下田に決まるまでの間この寺がアメリカ領事館として使われたことの碑と説明板がある。また、境内には図会が虚無僧寺として紹介している西向寺 「本覚寺の南にあり」との 
神奈川湊の支配をもくろむ伊勢氏(後の北条早雲)の策略に乗せられた相模守護代の上田氏は、1510年に本覚寺周辺に陣を敷いて主家の上杉に謀叛を起こす。上杉の勢力圏を通らずに湊と小机方面とを繋ぎ、上杉の軍勢を引き込むことを兼ねてここに切通しを作り、切通しの東側には城郭まで築いた。これが本覚寺の北東部の本覚寺切通であり、熊野権現山城(本覚寺山門前から鉄道越えに森が見える)である。早雲は、勢力温存を決め込んで上田氏を見殺しにした。この切通しは、明治になって東海道本線敷設の格好のポイントとなった。
青木橋を渡り京急神奈川駅の南を真東に向かうのが旧東海道である。駅前からほぼ100mのところに、上述した飯綱権現と次の洲崎明神の別当をしていた普門寺(右図①)があり、先80mに洲崎明神祠(現洲崎大神:右図②)がある。この間の小路を上がっていくと熊野権現山城址(現幸ヶ谷公園:右図⑤。公園東半分が後述する観音山?)がある。幕末の開港時の埋め立て用に山頂が削られ、低くなった。
東へ進んで第一京浜に出、左折して200m、滝の川に架けられていた滝の橋の現在の姿であるが、轟音とともに一瞬に走り抜ける自動車に圧倒されて橋の存在感は全くない。この橋の手前を川沿いに左に入り、最初のT字路を左に入ると宗興寺(右図③)である。ヘボン式ローマ字のヘボンが逗留していたとの説明板がある。そのせいではないだろうが、寺は現代の建築様式になっている。 右の図版観音山からすると、宗興寺の正門から真っ直ぐに上がる数十段の石段の上に観音堂があり、その後ろは「熊野旧跡」としている。現在もこの地形は残っているが、幼稚園やグランドがあって遺構らしいものはない。
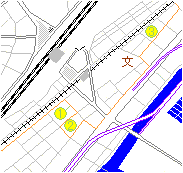 慶運寺から京急のガードを戻ってすぐ左折し、300mほどで塀の上から墓石が覗き、その向こうが本堂になる。金蔵院東曼陀羅寺(左下図①)である。入口は本堂をやり過ごして境内に沿って右折したところにある。そのまま進んでもう一度右折できる道は、旧東海道らしくデザインしてある。この道に図会の時代の山門が残されているが、山門の際まで墓が広がっていて、閉じられたままである。
慶運寺から京急のガードを戻ってすぐ左折し、300mほどで塀の上から墓石が覗き、その向こうが本堂になる。金蔵院東曼陀羅寺(左下図①)である。入口は本堂をやり過ごして境内に沿って右折したところにある。そのまま進んでもう一度右折できる道は、旧東海道らしくデザインしてある。この道に図会の時代の山門が残されているが、山門の際まで墓が広がっていて、閉じられたままである。その先を左折し、次の角をもう一度左折すると、大きな狛犬が鳥居の前に建てられている。熊野権現社(現熊野神社:左下図②)である。鳥居のほうが新しいから、鳥居が狛犬の後ろに立てられたというべきかもしれない。別当は今見てきた金蔵院だった。そして現幸ヶ谷公園の線路側の位置にあったこの神社は図会の時代に既にここに移転していた。 第一京浜に出て北進し、JR東神奈川、京急仲木戸の両駅から出てくる道を横切って200mほどの神奈川小学校正門前の次の角を左折する。地名「神奈川」の語源となったと図会が説明している上無川の流路跡がこの道である。 直ぐの右折できる道を入って街区一つで能満院満願寺(現能満寺:左下図③)になる。この寺はこの後小机まで行って子安に戻って来る際に訪れる白旗八幡宮の別当だった。 |
| 神奈川補遺 |
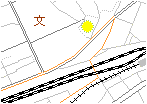
能満寺前をそのまま進むと、T字にぶつかるので左折し、そのまま京急の下を潜る。図会に登場してもよさそうな神社が正面にあるが、載ってないのでパスして右折し、京急の西北側を進む。神奈川新町駅のところで左クランクに京急の操車場線を渡って再び京急の西北側を進む。T字にぶつかって左折し(左上図中央下)、JR横浜線の下を潜って京浜東北線の踏切を渡り、右に坂を上がる。第二京浜の七島町交差点に出て向かい側に渡り、右歩道で鋭角に戻る。50mほどの右に蓮法寺がある。
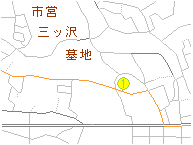 第二京浜は500mほど先で右も左も国道一号と言う奇妙な立町分岐がある。右歩道のまま行くのがルートだが、左車線で行って桐畑交差点を右折して、200mほどの反町交差点へ戻るのがマナーかもしれない。ここから西への道は、駐留米軍が昭和23年に占領地支配のための道路として作らせたものである。地図上に水平に線を引いての指示どおり、ガーデン下交差点から約1.5kmはアメリカ本土によく見られる緯度に平行な直線になっている。
第二京浜は500mほど先で右も左も国道一号と言う奇妙な立町分岐がある。右歩道のまま行くのがルートだが、左車線で行って桐畑交差点を右折して、200mほどの反町交差点へ戻るのがマナーかもしれない。ここから西への道は、駐留米軍が昭和23年に占領地支配のための道路として作らせたものである。地図上に水平に線を引いての指示どおり、ガーデン下交差点から約1.5kmはアメリカ本土によく見られる緯度に平行な直線になっている。直線を700mほど走ると、三ツ沢中町の信号付き交差点がある(左下図右下)。続く先の信号を右、急坂を尾根に上がって行く。最初のまがりなりにも十字路になっているところを左に入って行くと、右手に鮮やかな群青色に塗られた門があり、これが図会の時代本覚寺の南にあった 寺の塀の角を西へ出ると、右手に広大な横浜市営三ツ沢墓地がある。掌を上に向けたような緩やかな谷が樹影ひとつなく、一望できる。しかし、図示したルートで陽光院から100mほどのところに茶屋があるくらいで、駐車場、トイレ、休憩所はない。そもそも交通手段も南の急坂の下の国道1号にある市営地下鉄三ツ沢上町駅と茶屋の対極の北側の尾根の上のバスの終点があるだけである。老人が先立った配偶者の墓参りをするなどという状況には全く対応できていない。真夏や真冬に親を亡くしたらただでさえ気が滅入っているのに、納骨に立ち合いたいという親族への気遣いで喪主は供養の気持ちもそぞろになるだろう。 左下図のルートを左へ進んでいくと道なりに右に曲がり、2kmほどで片倉町に出る。墓地の中を北へ抜ける方が距離は短いが、きついアップダウンをものともしない姿を仏様に見せたい人に限られるような気がする。 |
| 小机周辺 |
片倉町の坂を北へ下り、新横浜方面の表示のまま進んで環状2号線に出て次の信号の岸根交差点を左折する。岸根交差点から1kmで右図の右端のJR横浜線小机駅になる。 駅前の信号の先を左に入って突き当り、左に通用門と山門があるのが雲松院(左図①)である。歴史的には神奈川区の寺などよりは古く、寺格も上であったようだ。北條氏滅亡以降発展から残されてきたおかげで、震災や米軍の空襲対象地域を免れて落ち着いた風情がある。 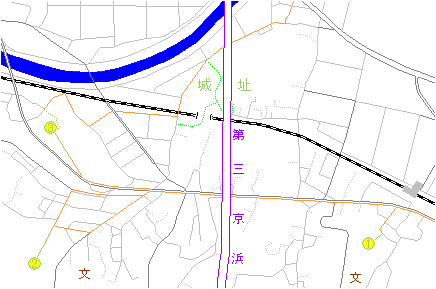 戻って商店街を西へ緩やかに上って行き、第三京浜を潜って坂を下り、泉谷寺という信号付き交差点を左に入って行く。左が小机中学校入口になっている反対側の右の道に入ると、泉谷寺(左図②)の山門に出る。
戻って商店街を西へ緩やかに上って行き、第三京浜を潜って坂を下り、泉谷寺という信号付き交差点を左に入って行く。左が小机中学校入口になっている反対側の右の道に入ると、泉谷寺(左図②)の山門に出る。
ところで、雲松院の裏には小机小学校があり、小机では小学校と中学校はそれぞれ寺領を使って設けられたものと推察される。 参道を真っすぐ出てマンションと団地の間を抜けてぶつかった道(JR横浜線の南を小机から長津田まで走るバス通り)を右に進んで先ほどの泉谷寺交差点に出る。北側に渡り、右歩道で折り返すように坂を上がる。上り切って広がる台地が住吉原で、 右へのカーブが終わる位置に住吉神社(左図③)の石碑があり、参道が分岐している。図会が城山の東の山觜にと記した白山権現(図版では2カ所に付注がある)は明治末からこの神社で合祀されている。 神社の右にある私道を抜けて坂を下るとJR横浜線にぶつかる。横浜線を渡らずに東へ進み、ぶつかった道の少し右に小机城址(御殿山)へ上がる散策路入口があるが、雑草が生い繁っていたり無粋な第三京浜のの遮音壁で視界が遮られていて快適ではない。(というのが当初訪問時であったが、その後崩壊対策もあってか、コンクリートで固めた階段道に整備されたがなおのこと自転車を伴っては訪れにくい)踏切を鶴見川のほうに渡って道なりに走り、第三京浜の下を抜け、新横浜と港北インターやニュータウンをつなぐ道路に出て、この道で鶴見川を北へ渡る。
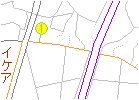 鶴見川を渡って300mの右に第三京浜の港北インター料金所がある。その先で東西の「緑産業道路」を渡ると左はイケアである。イケア先の信号付十字路の名になっている右向こうの折本交番の東に淡島明神社(現淡島神社:右図)の鳥居が建っている。
鶴見川を渡って300mの右に第三京浜の港北インター料金所がある。その先で東西の「緑産業道路」を渡ると左はイケアである。イケア先の信号付十字路の名になっている右向こうの折本交番の東に淡島明神社(現淡島神社:右図)の鳥居が建っている。神社の境内の説明や土地改良事業の記念碑の記録で、この地域が水害の常襲地域であったことが判る。
|
| 綱島街道の岡 |
前節の図から外れてすぐ道は「緑産業道路」に合流して低い丘を越える。市営地下鉄新羽町駅をかすめて新羽橋で北へ向かって流れる鶴見川を渡る。
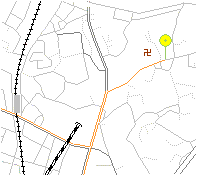 東南東に向かって進み、東急大倉山駅を過ぎ(左上図左端)、新幹線を潜って綱島街道に出たら、左折して200mほど坂を上がる。なかなか変わってくれない信号だが、これを右に入っていくと、師岡熊野権現宮(左上図:師岡熊野神社)がある。
東南東に向かって進み、東急大倉山駅を過ぎ(左上図左端)、新幹線を潜って綱島街道に出たら、左折して200mほど坂を上がる。なかなか変わってくれない信号だが、これを右に入っていくと、師岡熊野権現宮(左上図:師岡熊野神社)がある。右の図版で神社西隣に「別当」と記されただけの寺は「法華寺」であることが判る。
平成27年正月TVでこの神社で「凶」の御神籤を引いた人に「禍転為福」と書かれたお守りを渡していると報じていた。ネット検索をして確認したら、喜んでツイートした人のブログがたくさん出てきた。正しい四文字熟語は「転禍…」である。7年ほど前にアップした本文の「星祭り」が習合の残像かと思ったが神職の水準が原因のようだ。
また前節で触れた「市民森」がここにもあるがこれは日本一の人口を誇る市の問題。 戻って綱島街道を南下する。菊名駅前を直進するのが旧綱島街道だが、左に入って現綱島街道の結構きつい坂を登る。登りきった法隆寺交差点で綱島街道と岐れ前方左の道を下っていく。
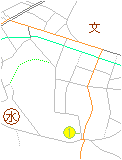 内路交差点で左折し水道道を進み、横浜市立東高等学校入口(右図左上)を右に入る。校門を過ぎて最初の右に入る道に入っていく。
内路交差点で左折し水道道を進み、横浜市立東高等学校入口(右図左上)を右に入る。校門を過ぎて最初の右に入る道に入っていく。右手が墓になり、その向こうの高い所にあるのが松隠寺(現松蔭寺:右図①)である。最後は自転車を押すほどの坂である。図会が坂を下り廻りて・・・・岡の上三丁半先だと書いてある慈眼堂(右図版義高入道墓)も境内に移設してある。寺が経営している幼稚園のさらに西には横浜市の水道配水池(タンク)があるが、この辺までひと山全部境内であったのではと思わせる。 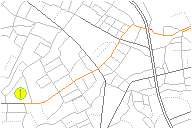 寺の前を南に向かってブレーキ頼りに急坂を下って住宅地を抜けて2車線道路に出て右折、500m先の2車線道路を横切って西寺尾小学校専用のようなJR横浜線の狭いガードを抜け、左クランクすると大口通りに出るので南下(一宅地路左が横浜線)する。JR大口駅前を過ぎて二つ目の大口通り交差点を右折する。
寺の前を南に向かってブレーキ頼りに急坂を下って住宅地を抜けて2車線道路に出て右折、500m先の2車線道路を横切って西寺尾小学校専用のようなJR横浜線の狭いガードを抜け、左クランクすると大口通りに出るので南下(一宅地路左が横浜線)する。JR大口駅前を過ぎて二つ目の大口通り交差点を右折する。500mほどで道は細くなり自動車一方通行出口になる(左下図右端)。これを抜けると綱島街道に再会する(西大口交差点)。横切って突き当り気味に左折して道なりに進み、信号を渡ると体調によっては上れないくらいの坂になる。これをなんとか上がっていくと頂点近くの右に白旗八幡宮(現白幡八幡神社:左下図①)がある。
次節へは鶴見方向に向かうのだが、第二京浜を使わず来た道を戻り、大口駅南の踏切で横浜線を、新子安交差点で第二京浜を渡る。JR新子安駅手前の新子安小前の交差点で左折、鉄道の騒音に交じって潮風の匂いも感じられる道をルートとする。 |
| JR鶴見駅西南部 |
右向こうの京浜急行線花月園前駅からは花月園競輪開催日には人でいっぱいになる跨線橋が東海道線と道路を渡っているところには東福寺前よいうバス停もある。
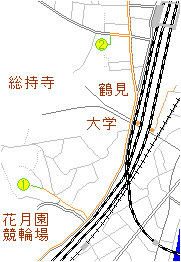 その先にある花月園前駅への踏切は、開催日には閉鎖される。当初は競輪帰りの客を待たせることも考えて競輪場に通じる道路を広幅員にしていたが、日本第二位の「開かずの踏切」での競輪で負けこんだ客のトラブルは多く、「歩ければのろのろでも我慢できる」として跨線橋を設けて当日は踏切を閉鎖している(左図下部の位置)。
その先にある花月園前駅への踏切は、開催日には閉鎖される。当初は競輪帰りの客を待たせることも考えて競輪場に通じる道路を広幅員にしていたが、日本第二位の「開かずの踏切」での競輪で負けこんだ客のトラブルは多く、「歩ければのろのろでも我慢できる」として跨線橋を設けて当日は踏切を閉鎖している(左図下部の位置)。一つ先の狭いほうの道を左に入っていき、ほぼ突き当りに子安観音堂/東福寺(左図①)がある。鎌倉時代初期の開基以来懐妊・安産さらには健育のご利益が着実として身分の上下を問わず一貫して信仰を集めてきている。 山越えしての次への近道はあるが、距離差は大したものではないので、戻って線路沿いを進む。
すぐ先の分岐交差点を左に進み、次の信号を左折して直ぐに成願寺(左図②)がある。図会は本尊も薬師像も作者不詳と書いているだけだが、総持寺に寺領を分けたのがこの寺である。 信号に戻って北に進むと三角交差点に出る。左斜め向こうのアーケード商店街を通り抜け、 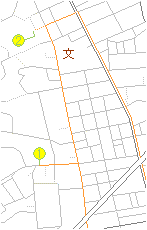 そのま進むと国道一号(第二京浜)になる(右図下部)。
これを突っ切って次の信号を左に曲がると、宝泉寺(右図①)がある。東海道が整備される前からの古刹で、図会には直接登場しないが、3節後で登場する川崎宗三寺の項で本山がここと記されている。
そのま進むと国道一号(第二京浜)になる(右図下部)。
これを突っ切って次の信号を左に曲がると、宝泉寺(右図①)がある。東海道が整備される前からの古刹で、図会には直接登場しないが、3節後で登場する川崎宗三寺の項で本山がここと記されている。戻って昔からの末吉街道を北上し、右側の末吉小学校を過ぎると左に末吉不動堂と書いた碑が建っている。この参道を入っていき、階段を上がって寺の碑の後ろに集会所風の建物がある。訪れた時に、たまたま地域の人たちが神輿の準備をしていた。 怪訝に思い尋ねたら、ここは昔から500m北西にある末吉神社の土地だとの返事。別当関係を聞いたが仲間の顔を見て「分らない」とのことだった。 末吉不動堂/真福寺は、右の図版同様左の赤い仁王門からさらに階段を上がった奥にある(右図②)。 次は鶴見駅の東口に行くのだが良いルートがない。一つ東側の現代の末吉街道を使っても鉄道の下は歩道は右側におざなりに付いているだけで、右に渡るとすればそれは駅東口へ行くことを前提とした道路設計になっている。左車線幅は最小限に設計されていて自動車と変わらないスピードで右カーブしながらの凹部走行をこなす必要がある。 結局は三角交差点で来た道を戻ることになる。当初の訪問の際は日本一の開かずの踏切を体験しようと総持寺踏切を利用し、ルート説明では跨線橋用エレベータ(左図●)の使用を紹介した。その後市は高齢者向けのバリアフリー化としても評価できるとして鉄道側の踏切閉鎖要請を平成24年度から受け容れた。
|
| 旧東海道(鶴見川前後) |
総持寺前の旧踏切跨線橋経由の場合は、京急沿いの道を経て駅広の京急鶴見駅北の信号まで来る。ここから北に向けて概ね旧東海道のルートである。
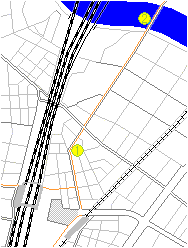 JR鶴見駅自由通路を使うと70mほど先の旧東海道に出る。
JR鶴見駅自由通路を使うと70mほど先の旧東海道に出る。右図版のしがらき茶店は、「生麦村」とタイトルが付いているが、他の文献では「鶴見村」であり、旧東海道が鶴見神社へ直進せずに30度右に曲がる角にあった(左図①)。
明治以降も蕎麦屋をするなどしていたが廃業し、現在のラーメン屋はマンション化の際に他の場所で成功していた別の経営者が出店したものである。図版を良く見ると、本格建築とはいえない掘立柱にせいぜい萱の屋根で、縁台の横には籠が乗りつけている。つまり、ドライブスルー様式で、他の図版には見当たらない。 直進して鶴見川を渡る橋(左図②)は現在「鶴見川橋」と名付けられているが右図版の鶴見橋はここにあった。そして現在では京急線の東の第一京浜の橋が「鶴見橋」と名付けられている。 7節前の「帷子橋」は、元来の橋が一旦別名になったうえで消滅したのだからやむをえない。
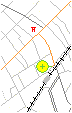 ここでは地物として存続しているものの名を横取りした感があり、地域文化の継承を無視した暴挙と言える。第一京浜の橋はせいぜい「新鶴見橋」であるべきだ。
ここでは地物として存続しているものの名を横取りした感があり、地域文化の継承を無視した暴挙と言える。第一京浜の橋はせいぜい「新鶴見橋」であるべきだ。 鶴見橋の図版中に橋より此方(市場町側)に米饅頭を売る家と書かれている。鶴見駅東駅広を北に渡った左の和菓子店が平成の初めにその製法を復活している。
鶴見川を渡って700m、熊野神社前を右折して市場銀座商店街に入る。京急の踏切の手前の細い道を右に入って京急鶴見市場駅の入り口の向かいに専念寺・観音堂(右図)がある。商店街の活気がいまひとつなうえに線路沿いは夜間営業の飲食店が多いためか、寺は固く門を閉ざしている。 旧東海道に戻り、川崎へ進む。 |
| 川崎区海寄り |
熊野神社から300mの市場上町の信号を以って横浜市に別れを告げ、川崎市に入る。
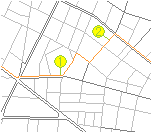 京急八丁畷駅の踏切を過ぎて次の信号の「日進町交番前」で右折して市電通りを進み、第一京浜を渡って700mのところに渡田交差点がある(左図左端)。
図会の時代にはこの辺に新田義貞重臣の一人亘新左衛門尉早勝の住居跡として
京急八丁畷駅の踏切を過ぎて次の信号の「日進町交番前」で右折して市電通りを進み、第一京浜を渡って700mのところに渡田交差点がある(左図左端)。
図会の時代にはこの辺に新田義貞重臣の一人亘新左衛門尉早勝の住居跡としてこの五叉路(?)の左向こうに入る道を入って100m先の左に成就院無動寺(左上図①)がある。
角を左に曲がり、この先十字路を右鍵の手に曲がっていくと、上で触れた新田神社が左にある。新田義貞が討たれた越前足羽の泥の中から上記の亘早勝が主君の剣などを探し出して自分の領地のここに祀ったとの言い伝えを図会も紹介している。しかし、太平記では足羽城主が持ち込まれた遺骸、具足ともども尊氏に届けたとされている。 この辺の地名「渡田(ワタリダ)」が、「亘の田」由来であることは容易に推し量られる。
新田神社の北で右折して東南方向に進み、市電通りに出たあたりから首都高横羽線までの付近が図会の時代の波打ち際で、
潮風にさらされてまともな作物もできなかった海浜の地にわが国の高度成長の起爆剤となった重工業が立地し、直線を原則とする区画街路で形成された街に前時代の遺物を保存する気持ちが育たなかったのは、同じ時代の空気を吸った者として理解できる。
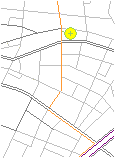
川崎臨港警察署付近から先には道路海側にも昔からの集落の名残があったりする。右図版の塩浜が地名として残っているが、その先はやはり大工場用に埋立てられており、往時の痕跡はない。そんな訳でこの1.8kmあまりに関連するルート紹介は省略する。
川崎臨港警察署前交差点を左折する(右図右下)。最初の信号を右折して北上して250mほどで、信号付交差点の向こうが児童公園と広場になっている。公園の先に石観音堂(右図)がある。境内は図会に記されている霊亀石を始め、石碑がいくつもある。図会は、「石観音堂=明長寺」と記述しているが、ここは無住のお堂だけで、明長寺は本節最後に登場する。 図会は、7合入る蜂龍盃が大師河原村池上氏の家にあり、末廣松のある稲荷新田石渡氏のところにも大盃があって、江戸と南武地域の酒豪による呑み合戦が行われたことを書いている。前者は、保有していた子孫が平成16年に川崎大師に奉納したとのことである。後者は、前者より海寄りの地域とのことだが不明である。
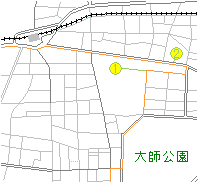 石観音前をそのまま北へと進み、富士見通を横切って150mほどを右折すると、大師公園にぶつかる。公園の園路側を走らせてもらうと、左分岐路の向こうに駐車場と塔が見える。川崎大師・金剛山平間寺(左下図①)である。塀に沿って進むと不動門前を経て大山門前に着く。境内の堂宇はほとんどが空襲で焼け落ち、昭和の後半にひとつひとつ造営を重ねたものであるので殆どが鉄筋コンクリート造である。
石観音前をそのまま北へと進み、富士見通を横切って150mほどを右折すると、大師公園にぶつかる。公園の園路側を走らせてもらうと、左分岐路の向こうに駐車場と塔が見える。川崎大師・金剛山平間寺(左下図①)である。塀に沿って進むと不動門前を経て大山門前に着く。境内の堂宇はほとんどが空襲で焼け落ち、昭和の後半にひとつひとつ造営を重ねたものであるので殆どが鉄筋コンクリート造である。右の図版右端の建物にいなり、青龍権現、神明と付注されている。一堂に習合して祀られて描かれているが、現状は「福徳稲荷堂」の名称で本堂と不動堂の間に境内で唯一米軍機の焼夷弾が当たらなかった木造文化財として残されている。堂前(?)の潜り鳥居がコンクリート造で、場違いか愛嬌かはお任せする。コンクリート造の清龍権現堂は大山門を入って直ぐ右にある。神明は見当たらない。いずれにしても明治以降別々に扱われてきたようだが、戦後は習合的な社祠も寄進があれば受け入れて復元しているようだ。 毎年正月には社寺の参詣客ベストテンが報じられる。図会に登場する名所ではこの川崎大師がトップで、明治神宮、成田山新勝寺に次いで第三位というのが定位置化している。正月に限らず「厄除けといえばお大師様」というのが京浜地区に定着しており、平日も参詣客が絶えない。大山門前から東への参道商店街は、浅草ほど多様性はないが連日売り声呼び込みが響いている。 参道商店街を出て左へヘアピンに戻る京急川崎大師駅への通りにも参拝客目当ての商店街が形成されている。この商店街に出て直ぐの北側に慧日山明長寺(現在は慧でなく恵を使っている。左下図②)がある。
西へ向かって大師通りを進む。 |
| 川崎都心部+戸手 |
京急川崎大師駅前から1km余りで左側は広大な川崎競馬場となる。この辺は
行く手に見えてくる高架道路は、多摩川を渡ってきた第一京浜である。この高架道路をくぐらずに、側道の歩道で左折する(左図右部)。 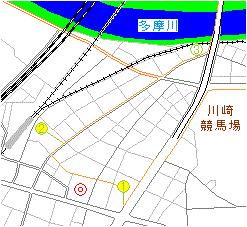 高架が地上に降りて次の交差点(宮本町)で右歩道に移る。
高架が地上に降りて次の交差点(宮本町)で右歩道に移る。交差点を渡って100mのところに堀内山王権現(河崎山王)社(現稲毛神社:左図①)の通用口があるが、さらに南の正面から入る。 五神合祀だったこの神社には図会の時代に宮司が置かれていて別当の世話になっていなかった。
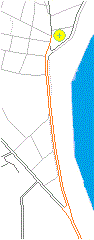 市役所側の鳥居を潜って市役所裏を通り、旧東海道に向かう。旧東海道に出る手前右JAの辺りに上記の佐々木宮と下記の養光寺があったらしい。旧東海道に出たら右折し、次の交差点の手前左が宗参寺(現および図版は宗三寺:左図②)である。寺の南の墓地の向こうに京急川崎駅のホームが見える。墓地の一角に右の「河崎」図版中の佐々木塚があるかもしれないが立ち入ってない。なお、この寺の斎場を兼ねた会館に「養光閣」の名が付いている。
図会は養光寺について、宗参寺に属すと書いているので佐々木宮の稲毛神社合祀の頃合併し、その由緒で付けた斎場の名前であろう。
市役所側の鳥居を潜って市役所裏を通り、旧東海道に向かう。旧東海道に出る手前右JAの辺りに上記の佐々木宮と下記の養光寺があったらしい。旧東海道に出たら右折し、次の交差点の手前左が宗参寺(現および図版は宗三寺:左図②)である。寺の南の墓地の向こうに京急川崎駅のホームが見える。墓地の一角に右の「河崎」図版中の佐々木塚があるかもしれないが立ち入ってない。なお、この寺の斎場を兼ねた会館に「養光閣」の名が付いている。
図会は養光寺について、宗参寺に属すと書いているので佐々木宮の稲毛神社合祀の頃合併し、その由緒で付けた斎場の名前であろう。旧東海道を北に進み、本町交差点で左折し大師通りを西に進む。平面のままの京急大師線は良いとして、京急本線とJRとのガードは恰も自動車専用の観があり歩道もまともに整備されていない。平日は渋滞していることも多いのでドライバーの反感を買わないよう遠慮がちに脇を走る。河原町の分岐交差点(右図下部)で右、多摩川堤防道路に移る。 次の戸手町の信号も分岐交差点で、その挟まれたところに下で説明する妙光寺(右図)がある。 図会は六郷の渡しについて「昔は長さ百二十間の橋があって東路四大橋、江戸三大橋に数えられていたが、享保年間に田中丘隅が提案して渡しになった。丘隅の墓は上平間村日蓮宗田中山妙光寺にある」と書いている。ところで田中家は渡舟業でもあったというから話はややこしい。
他の文献では「丘隅が渡舟業の田中家に養子に入る前に六郷は渡しになっていた。養子に入ってから川崎宿の振興や多摩川だけでなく他の河川の治水で業績を挙げた」と書いている。
この手前の河原町は、戦前戦後を通じて工場地帯だった。工場群と妙光寺の間は工場労働者等の密集住宅地だった。高度成長後の工場跡地には県や市の公的住宅が建設されたが寺との間は長い間被災危険度の高い地域として残され、いまでもここの堤外地は整備されないままである。本町交差点への折り返しはできるだけ堤防に設けられた歩道を使い、京急・JRのガードは往路と同様にして走る。本町交差点へ戻った(左図)左折し、再び見えてくる第一京浜の六郷大橋高架に向かう。
新六郷橋を渡って神奈川県から東京都に入る。 |
| 六郷から羽田 |
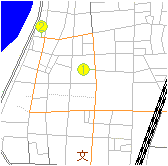 平成9年に完成した新六郷橋の車道は橋の実長の2倍以上を高架専用道化してあり、この間自転車はアクセスできない。西の側道は、川崎側が階段、東京側が急こう配のループで自転車は降りろと書いてある。まして車いすの散歩は不可能である。ループを降りた橋の下を公園として、旧橋の遺構を飾ってあるが、昼なお暗く真夏の日よけ以外は快適性はない。
平成9年に完成した新六郷橋の車道は橋の実長の2倍以上を高架専用道化してあり、この間自転車はアクセスできない。西の側道は、川崎側が階段、東京側が急こう配のループで自転車は降りろと書いてある。まして車いすの散歩は不可能である。ループを降りた橋の下を公園として、旧橋の遺構を飾ってあるが、昼なお暗く真夏の日よけ以外は快適性はない。ループ歩道橋をぐるりと回って京急六郷土手駅前を通ってJRのガードを抜け、右折する。
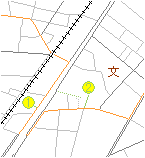 安養寺のところから南に戻り、左へ100m以上見通せる道路の二つ目を左折する。先ほど通った交差点を直角に横切り、東海道線の踏切を渡る。
安養寺のところから南に戻り、左へ100m以上見通せる道路の二つ目を左折する。先ほど通った交差点を直角に横切り、東海道線の踏切を渡る。右図のように途中右分岐路を選んで京浜急行線を渡って第一京浜に出て右折する。右歩道で200mほどの横断歩道橋のところに宝珠院(右図①)がある。手前50mほどの道路の反対側には別当をしていた六郷八幡宮(現六郷神社:右図②)の脇参道の鳥居が見える。 六郷神社へは、目の前にある歩道橋を渡っても良いが、100mあまり先の信号で道路を渡ると、旧東海道が一宅地裏側に残っている。再び第一京浜に呑みこまれる100m先(横断歩道橋の反対側)を右折すると神社の正面が左にある。頼朝寄進の手水鉢や明治になって最初の六郷橋の橋標が残されている。 右奥は区立六郷小学校である(右図文)。明治初期に現在は京急の用地になっている宝珠院の境内で設立されたが、10年余りで八幡宮境内の
図会は「御園」という地名に着目して行方弾正の梅林がこの辺にもあったのではないかと推測している。しかし、数百年に及ぶ荘園の歴史からは「ミソノ」の地名の由緒を極めることは非常に難しい。
また「八幡塚(やはたづか)」は一方で、六郷渡手前の東海道沿いの地域を指す八幡宮を超えた広い概念にもなっていた。 神社前を東に進み、信号付交差点に出たら左折して羽田方向に向かう。
江戸時代からの道筋を感じさせるこの道を2Kあまり、緩やかに右に湾曲した後道が直線状になってすぐ都南小学校を過ぎての交差点を左折する。 次の十字路に長照寺(左下図①)がある。図会の時代には、次の龍王院の南にあって山号は「朗羽山」だったが、明治時代に多摩川の洪水に遭いこの地に移転して「羽田山」に変えた。 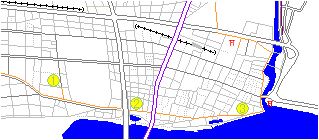 戻って再び東へ。産業道路の下を抜けて直ぐの左に次の羽田弁天の別当をしていた龍王密院(現龍王院:左下図②)がある。この寺もなぜか山号を金生山から医王山に変えている。この辺からはバス通りではなくなり、忘れられた道の雰囲気になるとともに潮風を感じるようになる。
戻って再び東へ。産業道路の下を抜けて直ぐの左に次の羽田弁天の別当をしていた龍王密院(現龍王院:左下図②)がある。この寺もなぜか山号を金生山から医王山に変えている。この辺からはバス通りではなくなり、忘れられた道の雰囲気になるとともに潮風を感じるようになる。首都高横羽線の下を通って約500m、多摩川の堤防道路に上がりかけた左に階段がありこれを降りたところに
左下図のように、弁天旧地、現穴守稲荷神社を経由して、ヤマト運輸(荏原製作所本社跡)の角から北へ向かう。 |
| 森ケ崎から大森東・中 |
ひたすら進むと左図下で(新)呑川を渡る。
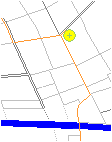 街の雑学としては、ここの橋も途中首都高速道路の下で南前堀を渡る橋もともに「旭橋」と名付けられている。
街の雑学としては、ここの橋も途中首都高速道路の下で南前堀を渡る橋もともに「旭橋」と名付けられている。渡って右に曲がって出た道を左折すると、森ヶ崎十字路という交差点に出る。この交差点の直ぐ東、森ヶ崎下水処理場に向かう道に面して大森寺(左図)がある。次の貴船明神の別当だった。入母屋に宝珠窓ではあるが、通常の角材を用いての100年は経過していない建物(戦災後の再建?)である。神社近くから移転した可能性は高いが、民家風の入り口なのにインターフォンもなく引き戸は閉まっていた。 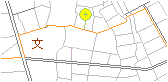 信号一つ西の2車線通りを北上すると、大森東5丁目交差点を経て左図右に出てくる。突き当たる手前を左折し、行き止まり気味を左に入っていく。途中少し右に曲がるが、150mあまりの右に貴船明神社(現貴舩神社:右図)がある。図会の記述の通り、産土神としての折節の祭事が一覧で掲げられていた。
信号一つ西の2車線通りを北上すると、大森東5丁目交差点を経て左図右に出てくる。突き当たる手前を左折し、行き止まり気味を左に入っていく。途中少し右に曲がるが、150mあまりの右に貴船明神社(現貴舩神社:右図)がある。図会の記述の通り、産土神としての折節の祭事が一覧で掲げられていた。右図の東200m先は往時は海だった。現状は運河の向こうに昭和島が見えるだけなので紹介しないが、
大森の海苔養殖は、明治以降海岸埋立で沖へ沖へと追いやられ、戦後の京浜二区埋立と江東区側からの23区のごみ処分地で壊滅状態になり「伝統産業」の旗印のもと港湾区域ギリギリで細々と行われている。平成29年話題になった江東ー太田の埋立地帰属争いは漁協が一時補償を受けて決着したとして江東有利の裁定を都は示した。歴史の古さからは大田区だろうが、近年の実態を優先するとなると、日本は対ロシア、対中国、対韓国とも大田区の立場に近い。
引き続き西へ進んで産業道路へ出、左折して大森東中学交差点で西へ渡ってそのまま進んでいく。
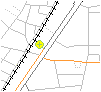 車線区分がなく微妙に蛇行しているこの道を500m足らずで旧東海道を呑みこんでいる第一京浜国道に出る。この辺が大森宿(合の宿)で、右図版の「和中散(幕府御用達)」や「麦藁細工」を並べた店があったらしいが、何の痕跡もない。
車線区分がなく微妙に蛇行しているこの道を500m足らずで旧東海道を呑みこんでいる第一京浜国道に出る。この辺が大森宿(合の宿)で、右図版の「和中散(幕府御用達)」や「麦藁細工」を並べた店があったらしいが、何の痕跡もない。この交差点を渡って右60mに貴菅神社というのがある(左下図)。説明板には、「大森村の鎮守の貴舩神社と道の反対側の菅原神社とを明治42年に合祀したもの」と書いてある。構えは先ほど見てきた貴舩神社(右図)よりもみすぼらしい。図会には大森村海道より右にありと書かれているが、 「大森村海道」とは東海道のことか別の浅草海苔を運んだ道のことかも不明である。祭礼の日にちは3ヶ月ほど違う。図会も来由詳ならすと書き、図版を設けるほどの名所とは扱わなかったので深入りせずにそのまま第二京浜を右歩道で南下する。 |
| 蒲田 |
第一京浜を南へ右歩道で500mの大田区立体育館前交差点を過ぎると右は梅屋敷公園である。前節の和中散の店がここに確保してあった梅園に移ってきた場所で、明治時代に要人が休息に訪れた旨の説明板が立っている。
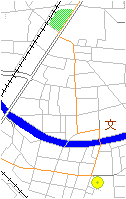 公園の南端で道を反対側に渡って入る。道なりに右に曲がって進み、道が折れるように突き当たるところを左折し、東蒲中学にぶつかったら右折して呑川を渡る。
渡って最初の十字路のところに高輪から明治時代に移転してきた
公園の南端で道を反対側に渡って入る。道なりに右に曲がって進み、道が折れるように突き当たるところを左折し、東蒲中学にぶつかったら右折して呑川を渡る。
渡って最初の十字路のところに高輪から明治時代に移転してきた寺前の十字路を西に第一京浜のほうに進み、分岐路をインターロッキング舗装の狭いほうの道に入っていくと、高架化した京急羽田空港線が第一京浜を渡るところに出る。正月の箱根駅伝で選手と電車とどちらを優先するかで長年双方の懸案であった蒲田踏切は平成24年秋には廃止されることになっている。 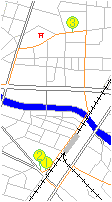 高架下から100mほど南を右折して、京急本線を渡ると右に妙安寺(右図①)があり、その左隣に蒲田八幡宮(現蒲田八幡神社:右図②)がある。神社は、次の円頓寺近くの稗(本来は草冠が付く)田神社から勧請されたとの伝えがあるが、図会は記述していない。
高架下から100mほど南を右折して、京急本線を渡ると右に妙安寺(右図①)があり、その左隣に蒲田八幡宮(現蒲田八幡神社:右図②)がある。神社は、次の円頓寺近くの稗(本来は草冠が付く)田神社から勧請されたとの伝えがあるが、図会は記述していない。京急蒲田駅西口前を線路沿いを北に戻っていくと「弾正橋」で呑川を渡る。多摩堤通りを渡ってそのまま入って200mほどの十字路を左折すると、右に円頓寺(右図③)がある。先ほど渡った橋の名になった行方弾正(親子?三代?)のうち北条氏に従って秀吉に滅ぼされた直清の墓があり、図会は直清の屋敷だったと書いている。 行方弾正忠明連という豪族が「六郷」に居館を構えていたと図会は記し、円頓寺の項では六郷時代に信玄の侵攻を防いだと書いている。16世紀後半の文書には「行方」を名乗る実力者の名がいくつも登場する。上記の妙安寺も山号は「行方山」であり、信玄と戦って死んだ義安の妻が尼になって開いたというのだが、この尼の子が直清との記録はないようである。明連と義安が同一人か、直清の父は誰なのかも確たるものはない。
なお、円頓寺は右上の図版の最も手前に描かれており、その筋向いに「八幡」が描かれている。この八幡は、現蒲田八幡神社ではなく稗田神社のことではないかと私は思う。稗田神社は「蒲田八幡」と呼ばれていたこともあるとのこと。 寺の前を西へ向かうと(東は梅屋敷公園の北に出る)直ぐ稗田神社の鳥居で分岐するが、左を採り広い通りに出て南(左)に進む。多摩堤通りとのあやめ橋交差点を右折し、呑川を斜めに渡った次の信号でJR蒲田駅方面に直進せずに、右折する多摩堤通を辿ってJR東海道線のガードをくぐる(つまりあやめ橋交差点からは右歩道が良い)。JRの西へは左歩道の地下道で階段をを下って上がるしかないが、出て50m先にある最後のオウムサリン犯が捕まった漫画カフェ前を通る。
|
| 西蒲田 |
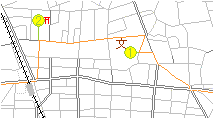
JR下地下道から100mあまりにJR蒲田駅からの斜めの道路を含む複雑な交差点がある。これを北へ渡って駅からの道の延長の斜め左の道に入って200mあまりの左に女塚神社(左図①)の石碑があり、路地の向こうに鳥居が見える。
図会には私有地の塚として書かれているが、明治以降JR蒲田駅東にあった八幡神社をここに移設合祀して女塚(オナヅカ)神社とした。言い伝えは次節で・・・・・。 神社北側の相生小学校の北東の角の交差点に出て西へ進む。400mほどの右(北)側に蓮花寺(左図②)がある。図会は、「往古は、巍々たりし巨藍なりしが」行方弾正の宗教弾圧で仁王像を池上本門寺に移したと記述している。手前(東隣)には熊野神社があり、別当関係があったと思われるが図会にはその記述はない。 南下して多摩堤通りに出て東急池上線蓮沼駅前から西へ向かう。 |
| 東急多摩川線沿線 |
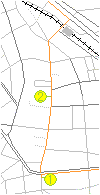
環状八号線、東急多摩川線を横切って走ること1.5km、左上図右下に出てくる。
矢口南交差点を左に曲がったところに十騎社(現十寄社:左上図①)がある。図会は、次の新田大明神(現新田神社:左上図②)と道路を挟んで向かい合っていると書いているから、移転したのだろうが、現地の立て札には一言も触れていない。言い伝えは新田神社の祭神である新田義興の家臣十名なのだが、現在の社名はそのことへの連想を避けているような表現である。尤も図会も新田義興より昔の大和武尊東征の際の旧跡で、多摩川対岸の矢向と対になっているここの地名の矢口は、その際の古戦場を示していると書いている。
武蔵新田駅のところの踏切を通って環状八号線に出て、左折、北へ向かう。 環八を600mほど北へ進むと左図下部に出てくる。さらに信号三つめの藤森稲荷前を過ぎて左斜めに入ったところに光明寺(右図)がある。 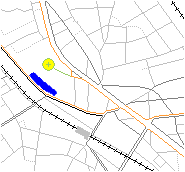 関東の高野山と称されたという図会の紹介はいくつかあるが、こちらもその一つである。現在は境内を一部環八に取られた形跡もあるが、図会が多摩川の残流湖と説明している光明寺ヶ池は残されている。しかし、訪問時の平成21年8月には池のまわりがすっかり高い塀に囲まれて大工事が行われている様子だった。3年後の再訪では工事車両用の出入り口の扉が錆び着いていた。
関東の高野山と称されたという図会の紹介はいくつかあるが、こちらもその一つである。現在は境内を一部環八に取られた形跡もあるが、図会が多摩川の残流湖と説明している光明寺ヶ池は残されている。しかし、訪問時の平成21年8月には池のまわりがすっかり高い塀に囲まれて大工事が行われている様子だった。3年後の再訪では工事車両用の出入り口の扉が錆び着いていた。図会が1行だけ紹介している鳳来寺峰の薬師は、現在では「観蔵院」と称されている。観蔵院へはさらに環八を400m弱進んで左前方に分岐して行く「新田道」を入って400mほど緩やかに下がって右へ上がったところの右への岐路を少しクランクに曲がった左に観蔵院の門がある(左下図)。 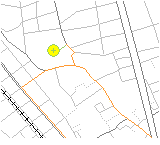 図会は寺名を「正雲寺」としているが、本堂や庫裡が別にあったのではなく、薬師堂だけだった。
図会は寺名を「正雲寺」としているが、本堂や庫裡が別にあったのではなく、薬師堂だけだった。多摩川の北側の断崖(ハケ)の最下流部になるのがこの丘の南斜面である。南に丘越えをすると、ここでは形だけの2車線道路になっている多摩堤通りに出る。これを左折して東急鵜ノ木駅に入る鵜ノ木交番交差点から300mで、再び光明ヶ池を囲む工事囲いになる。この間道は東急多摩川線の1街区北を併行して走っている。東急電鉄発祥の路線の目蒲線は、地下鉄南北線との相互乗り入れによりその路線名は消え、
次節本門寺へは、環八へ出た目の前の区民プラザ交差点でそのまま東に進んでも良いが、環八をもうひとつ南の千鳥三丁目交差点で左折すると池上通りである(右図参照)。 |
| 池上本門寺 |
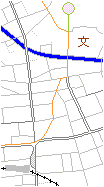
途中東急池上線、第二京浜を横切って池上通を1.5km進むと、池上駅交差点になる。変形している交差点で、右の池上駅前広場も無理やり広げた感がある。左斜め前方に入っていくのが駅からの本門寺への参詣客が辿る旧参道で、これを辿って広い参道に出ると、左、呑川越しに本門寺(左図)の山が見える。
旧参道が新参道と合流するところを東西に通じている道が、右図版で(呑)川と平行に描かれている旧道(池上道)であると考えられる。
本門寺は、日蓮上人入滅の霊場で、布教活動を兼ねた行事が盛ん(広い境内を活用したライブコンサートもしている)である。しかし訪問日は縁日でなかったので閑散としており、惣門前の柵に自転車をくくりつけて、境内を歩いた。石段を上がっての仁王門は、米軍が焼く(市街地からの延焼ではない)までは前々節の蓮花寺から移設されたものだった。五重塔は、被災しなかったが、戦後修理はされているとのこと。 惣門前の新参道東側と境内西側には合せて20近くの寺院がある。殆どは坊舎三十六宇と記されているもので、右の図版で「塔中」と付注されているものであろう。古跡四院と書かれているうち學蔵坊は現存が確認できないでいるが、大坊(本行寺)、南坊(南ノ院)、照栄院は現存している。(図等表示省略) 惣門前北西100mほどの右の車坂を上がると自転車のまま大堂と本殿の間の寺務所に行ける(イメージマップの境内図左の道路に合流)。直進して300mには大坊本行寺(右図版「其四」の上人荼毘所の場所は宝蔵になっているが硯井などは新しく造り直されて管理されている)への入口がある。さらに100m余り先の都営地下鉄車庫線の下を抜けると第二京浜国道である。直ぐ右の交差点の信号には「本門寺入口」という札が付いており、車坂からの道はその右に出てくる。 |
| 馬込 |
第二京浜の本門寺入り口から都心方向は、直線の登り坂である。右折予定なので右歩道をゆっくり上がっていく。逆にハイスピードで降りてくる自転車に要注意。
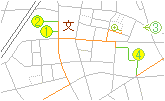 300mあまりの馬込中学前交差点で右折、梅田小学校入口を過ぎての十字路を左折し、左に東急ストアのある交差点を右折し、緩やかに登り切ったところの十字路(左図下部)を左折する。
300mあまりの馬込中学前交差点で右折、梅田小学校入口を過ぎての十字路を左折し、左に東急ストアのある交差点を右折し、緩やかに登り切ったところの十字路(左図下部)を左折する。信号付き交差点の右向うが馬込小学校で、左が馬込八幡神社(左図①)である。その北隣が、長遠寺(左図②)である。
小学校の角を東へ進み、坂が下り始めるとすぐゼブラマークがある。そこを左に入った十字路右先に神明社(左図③←先)がある。入口は東へ回り込んだところ、囲んでいるのは幼稚園の柵で、どう見ても「園の一角に神社」といった風情である。 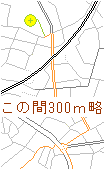 戻って左クランクに向かい側に上がり、左手の万福寺(左図④)の墓苑入り口から入っていく。
戻って左クランクに向かい側に上がり、左手の万福寺(左図④)の墓苑入り口から入っていく。北条家の下でこの地を支配していた梶原氏の創建で、現代もその墓が残されているほか、寺は近代の名士の墓も積極的にPRして墓地を公開している。また、明治以降次節で触れる桃雲寺を合併している。境内南側の表門はかなり石段を下ったところにある。 寺の前を左に進んでいくと、馬込八幡から下りてきた道と鋭角に交わる。その延長の道へ鈍角に右折していくと、環七の馬込銀座交差点に出る(右図下部)。横切れないので歩道橋に自転車を持ち上げて渡り、アンツーカー舗装の狭いほうの道に入り、100mほど先で歩道付き商店街へと左折する。 新幹線の下を抜けて、ゼブラマークの十字路を左折すると右に、明治末泉岳寺のそばから移転した如来寺と、さらに大正末に上野駅北から養玉院が移転合併した 馬込銀座交差点に戻って環七を南下する。 |
| JR大森駅西と東 |
馬込銀座から1kmで環七は春日橋交差点の立体交差になる。跨いでいる池上通を北へと左折する。
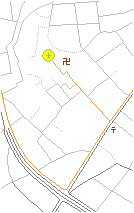
左上図で幹線道路がV字に受けている地区は北からの山王の台地で、江戸時代「新井宿村」と呼ばれた地域である。図会は、木原山の項で木原氏がこの村に封じられたことを注記しているが、前項戸越八幡に続いて同後の丘山をいへりとなっているので、混乱しやすい。加えて当時も存在していた山王神社(現日枝神社)や古刹善慶寺を無視して熊野社に触れているだけである。
ここを訪れた齋藤長秋・月岑が右の「義民六人衆」のことを聞かされなかったはずはなく、図会独特のなぞかけではないかと思う。
池上通に入って200mの信号のところに「義民六人衆」の碑がある。これを入っていくと、突き当たりに善慶寺の山門があり、その向こうの本堂の先がさらに小高くなっている。
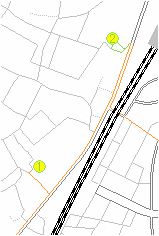 池上通に戻り、300mほど先を左に入って坂を上がり、右に入ったところに
池上通に戻り、300mほど先を左に入って坂を上がり、右に入ったところにJR大森駅に近づいていくと道は少し下って山王二丁目の信号が底になっている。80m手前に左から道が下りてきていて、右のJR線路方向への下りこう配などは、右の八景坂の図版描くところにそっくりである。描かれている鎧掛松はその先の岬状の岩の上、となると現在の大森駅前かさらに上の段の天祖神社のあるところ(右図②)にあったと思われる。松の根元で旅人が江戸湾を眺め、その旅人目当ての茶店が並んでいる様を図会は描いているが、駅周辺はもちろん現在の天祖神社境内には松はない。でも、急峻な地形は現在は石段に置きかえられ、神社裏には「八景坂」の名の付いた小公園もある。 自転車を曳いて駅構内を抜けても良いが、山王二丁目の信号に戻って左折、JR東海道線をくぐって大森アーケード商店街を抜け、第一京浜方向に向かう。アーケード街を抜けて、信号を渡って1街区過ぎると広場に出る。広場の対角線の位置で東西の道路に出る。東へ進んで八幡通入り口交差点(左下図左端)で旧東海道を横切り、2街区目に入ると右先の3街区目に墓苑が見えてくる。 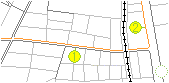 鈴の森八幡宮(現磐井神社:左下図②)の別当だった密巌院(左下図①)である。入り口は目立たないが、ちゃんと八幡通に面している。二階通路で相互に繋がっている現代建築が本堂と会館になっている。
鈴の森八幡宮(現磐井神社:左下図②)の別当だった密巌院(左下図①)である。入り口は目立たないが、ちゃんと八幡通に面している。二階通路で相互に繋がっている現代建築が本堂と会館になっている。
図会は「鈴の森」は、宇佐八幡宮で鈴石(打てば鈴のような音がする石)を管理していた石川年足が武蔵の国の国司になった際に神石としてここの八幡宮に祀り、境内林を「鈴石の森」と言ったと書いている。その後、石清水八幡宮を総元締として八幡宮体制を整備した際にここが武蔵総社になったとも書いている。
江戸時代さらに「鈴ヶ森」に転じて周辺の地名になって、「北の小塚ヶ原、南の鈴ヶ森」は刑場を意味するようになり、良くないイメージが付いてしまっていた。 一方、天キ之部の石井神社(世田谷区大蔵)の項では、延喜式に書かれた通りに水が出る磐井神社はここだと記述している。延喜式由縁の名は、当時すでに神社の格付を左右していたので「石」繋がりの線で荏原郡東端のこの八幡宮を「磐井神社」と呼ぶ力が強くなっていたようだ。天キ之部で書いた明治以降の経緯から大蔵説を頑張る人はいなくなった。 100m東の海は、平和島競艇場で、その向こうは流通団地である。万葉集に登場する荒藺崎、笠島(神社)が当時既にその場所が曖昧になっていたようだし、東海道の海側にあった
第一京浜を北へ向かい、京急大森海岸駅付近から品川区になる。その先で首都高の鈴ヶ森ランプが右へ湾曲して離れ、同時に旧東海道も右に分岐している。鈴ヶ森刑場はここから先の旧東海道と京急線の間にあった。 |
| 大井 |
第一京浜が京急高架線の下を抜けて最初の信号を左折すると左図右下に出てくる。
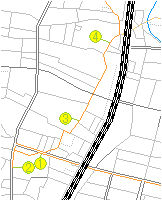 JRのガード下は半地下であり、時間雨量5、60ミリの豪雨が30分も降ったら通れないだろうと思いながら、漕ぎ上がる。と、その左に古い感じの道が分岐し、寺の入り口がある。鹿島大明神社(現鹿島神社:左図②)の別当だった常林寺(現来迎院:左図①)である。お堂は震災戦災を潜り抜けた木造である。
JRのガード下は半地下であり、時間雨量5、60ミリの豪雨が30分も降ったら通れないだろうと思いながら、漕ぎ上がる。と、その左に古い感じの道が分岐し、寺の入り口がある。鹿島大明神社(現鹿島神社:左図②)の別当だった常林寺(現来迎院:左図①)である。お堂は震災戦災を潜り抜けた木造である。往時の鹿島神社は、寺と入り口を並べていただろうが、
池上通りを鹿島神社前交差点まで戻り、右折して来迎院前に出、北側の古道に入っていく。この道は、図会が上古海道と書いている道である。突き当たって右鍵の手に進むが、古道がこの形になったのは結構古いような気もする。 すぐ左に弘福寺(図会のミス?光福寺:左図③)がある。この寺本堂裏の了海上人産湯井は現在ではコンクリートと石で要塞の様になっている。図会はこれとは別に地名の源となった大井という別の泉があると書いてあるが、品川区の説明板などは同じものとして書いている。 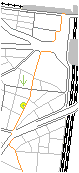 光福寺から300m北に西光寺(左図④)がある。光福寺同様入口は奥まっているが、境内は結構広い。
光福寺から300m北に西光寺(左図④)がある。光福寺同様入口は奥まっているが、境内は結構広い。ここまでの3つの寺社は、いずれも桜の名所として知られており、図会もそれぞれに一言付け加えている。 西光寺の先を道なりに進むと階段でJR東海道線の下を潜ることになる。この先古道は立会川の谷に下りて上るヘルマン坂を上がり「見晴らし通り」になる。次節を飛ばしてこのルートを採るのも魅力的なので、虎斑で示しておいた。 JR線の手前で左折して北西の方向に進む(左図上部)。大井中央病院前を過ぎて作守稲荷のところで左分岐(小左クランク)をすると右図下部に出てくる。 池上通に出たら右の大井三ツ又交差点(細街路を含めると五ツ又)で左に渡り、左側の細街路に入る。80m余りの左(右図↓先)に納経塚(現庚申堂)がある。次々節で大井町に戻って真っ先に訪れる来福寺の本尊所縁の地として当時から現代まで同寺が管理してきている。 道を下って大井町駅広場に出て東急大井町線に乗る。図会では池上や馬込の名所の間に挟んでいるがルートが設定しにくい(何十年もかけての沿線道路の整備が進行中)東急大井町線沿線地区を次節として挿入する。 |
| 東急大井町線沿線三八幡 |
東急大井町線の北千束駅で電車を降りると、改札はガード下である。広場も無い道路際で自転車を広げても、平日の日中は昇降客が少ないのであまり迷惑にならない。
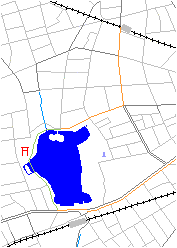 南に道を採り、三つ目の十字路を右折すると1分もしないで左が洗足池(図会では千束池)になる。池の周りは公園になっているので自転車を曳いていく(のがマナーだが、平日は時間帯によってはひと気が無いので・・・・)。池の東は勝海舟の晩年の庵があったところで、現在は墓碑などが置かれている。
南に道を採り、三つ目の十字路を右折すると1分もしないで左が洗足池(図会では千束池)になる。池の周りは公園になっているので自転車を曳いていく(のがマナーだが、平日は時間帯によってはひと気が無いので・・・・)。池の東は勝海舟の晩年の庵があったところで、現在は墓碑などが置かれている。池の中の弁天は、右の図版左側の鳥居であろうが付注していない。海舟墓所と池を挟んで対称的な位置の千束八幡神社の前にある松は、往時からは3.4代目という袈裟(腰)掛松とされている。
中原街道を都心に向かう。左上図右端が尾根になってのアップダウンと環七との交差点を過ぎると、中原街道を跨ぐ大井町線の高架が見えてくる。 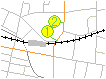 高架手前右の稲荷通りに右折し、途中旗の台駅を左に見、荏原町駅のところで左折して踏切を渡る(右図)。
高架手前右の稲荷通りに右折し、途中旗の台駅を左に見、荏原町駅のところで左折して踏切を渡る(右図)。踏切のすぐ北に法蓮寺(右図①)の入口がある。境内を接して北に別当関係だった中延八幡宮(現旗岡八幡神社:右図②)がある。寺も神社も端正さを感じさせる造りである。 そのまま道を北に進み、西中延3丁目交差点を右折、大井町線の南に移り、第一京浜を渡って400mほど先の交番のある交差点を左折する。 戸越公園駅のところでまた大井町線の北に出てしばらく進むと、広い幅員の割に交通量の少ないのに信号間隔だけは大幅員並みの道路に出る(左下図左端)。 これを横切って三つ目の十字路を右折してすぐを左に入ると突き当りが行慶寺(左下図①)である。 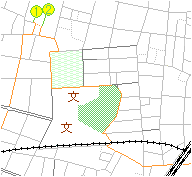 ここも別当配置がそのまま残っており、東隣の戸越八幡(左下図②)へは門前から寺経営の幼稚園の脇を抜ける通路がある。もちろん往時は境内は一つでこんな道はなかっただろう。
ここも別当配置がそのまま残っており、東隣の戸越八幡(左下図②)へは門前から寺経営の幼稚園の脇を抜ける通路がある。もちろん往時は境内は一つでこんな道はなかっただろう。
神社参道を南に出て左折して進むと、工事用フェンスに囲まれた国立国文学研究資料館跡にぶつかる(平成24年9月現在)。3年前は丁度整備計画の策定中とのことだったが、とりあえず古い建物は撤去されたようだ。反時計回りに南に回ると小学校があり、その東が戸越公園である。公園に沿って行ける所まで行く。左下図での緑色の網掛けと学校マークの範囲は、江戸時代に細川侯の下屋敷なって以来、諸侯、財閥が別邸を構え、昭和になって公有地化が進んだ地区である。 鋭角に曲って直ぐ右の細い道に入って大井町線の下を抜け、ひとつ右の道路工事区域の南の囲いに沿った道を辿り、十字路に出たら前の道を進んで東海道新幹線の下で踏切を渡る(左下図右下)。
左に大井町線を確認しながら進むと、前節末で見慣れた場所に出る。 |
| 東大井〜青物横丁 |
前々節で自転車を畳んだ東急大井町駅前を過ぎて次の信号がJR北駅舎の東口2番から出て南の交差点である。この交差点を南に下がって品川区民会館(きゅりあん)の北側を下っていく。
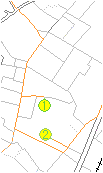 左図左上は、区民会館の東で池上通りに出たところになる。そのまま信号を渡り、次の分岐で右の狭いほうの道に入り、見晴らし通り(大井上古海道)に出たら右折する。
左図左上は、区民会館の東で池上通りに出たところになる。そのまま信号を渡り、次の分岐で右の狭いほうの道に入り、見晴らし通り(大井上古海道)に出たら右折する。200mほどのところのT字路を左に入って100mほど緩やかに上がった右に小さな鳥居と赤いのぼりがはためく「梶原稲荷神社」(左図①)がある。 右の来福寺図版で寺の境内北側にいなりとキャプションされたものとその後ろの梶原塚とを一体化して、梶原家の末裔の人々が守ってきたことを伺わせる。
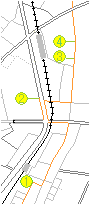 来福寺から第一京浜に出て大井消防署前交差点で東に渡る。京急の下を抜けて60mを左折し、突き当たる左に鮫頭明神祠(現鮫洲八幡神社:右図①)がある。旧東海道の西側であることは、海浜にありとの記述と違う。でも「明神=御林八幡」という扱いがあるので、別の所のものでなく図会の説明不足としておく。
図会は、地名は砂水、明神は鮫頭とし、地名は昔佐美津(=白水:cf白湯<サユ>)だったとの説も紹介している。
来福寺から第一京浜に出て大井消防署前交差点で東に渡る。京急の下を抜けて60mを左折し、突き当たる左に鮫頭明神祠(現鮫洲八幡神社:右図①)がある。旧東海道の西側であることは、海浜にありとの記述と違う。でも「明神=御林八幡」という扱いがあるので、別の所のものでなく図会の説明不足としておく。
図会は、地名は砂水、明神は鮫頭とし、地名は昔佐美津(=白水:cf白湯<サユ>)だったとの説も紹介している。旧東海道に出て北に300m進むと、右図中央の交差点に出る。左折して大井町駅方面に進み、第一京浜を対角にわたって60m都心方向に海晏寺(右図②)の山門がある。東は東海道から西は坂上の東照権現までを境内にしていた。東照権現のあった紅葉の名所(左図版参照)は、国家神道体制や神仏分離に精力を注いだ岩倉具視の厳重に管理された神式の墓地になっている。
都心方向へ100mほどで、池上通(第一京浜まで)の延長の道に出る。この道は「ジュネーブ平和通り」と表示されている。江戸末期に行方不明になっていた品川寺の鐘が大正時代にジュネーブ美術館で見つかり、返還されて60年後の友好都市提携を機にこう名付けられた。目黒蟠龍寺の銅像もいつの日かパリから戻されればいのだが。 |
| 南品川 |
タイトルを「南品川」としたが、前節末の2寺は江戸時代も現代も南品川である。また本節荏原神社の現在の住居表示は北品川だが当時は南品川だった。
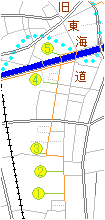 ジュネーブ平和通りを横切って左図下に出て100m、左に天妙国寺(左図①)がある。
ジュネーブ平和通りを横切って左図下に出て100m、左に天妙国寺(左図①)がある。
続いて民家数戸を隔てて長徳寺(左図②)があり、さらに次の小路を左に入ると常行寺(左図③)がある。 図会の記述からは、長徳寺がもっと北東にあり、常行寺も本光寺(右図①)の地続きのように読める。しかし両寺とも現在位置であり、現在の鉄道や道路が感じさせ方を変えているのかもしれない。 常行寺前から、旧東海道のひとつ西の道を北に進む。
先に見えていた赤い欄干の橋は、貴船明神社(現荏原神社:左図⑤)の祭礼用に近年設けられた橋である。右の同じ図版で、川は神社の手前を流れているが、現在の川筋を図版に挿入すると、中央奥から左手前に描くことになる(旧河道は左図●をつないだルート)。 つまり、昭和初期の目黒川河道変更工事の結果、南品川の鎮守であった神社が川の北側になり、住居表示も北品川になってしまった。図版にある 荏原神社から旧東海道に出たところの橋が中の橋(現品川橋)である。南品川の鎮守である貴船明神も次節で紹介する北品川の鎮守もともに牛頭天王であったから、両社の祭礼は「天王祭」と呼ばれて同日に行われていた。両社の神輿はこの橋の上で神輿の交歓が行われ、それ故に俗称「行逢橋」だと図会も紹介している。 魔よけの神として身近な信仰の対象として定着していた牛頭天王が国家神道政策に馴染まず、素盞鳴尊への祭神の変更や神社名の変更が行われたことは既に十社ほどに関して説明してきた。 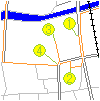 こちらでも天王神輿を海に担ぎこむ海中渡りは賑わっており、その海浜が埋め立てられて超高層ビルの大部分は「天王洲」の名を付けており、多くの人は「東品川2丁目」とは言わず「天王洲アイル」と呼んでいる。
こちらでも天王神輿を海に担ぎこむ海中渡りは賑わっており、その海浜が埋め立てられて超高層ビルの大部分は「天王洲」の名を付けており、多くの人は「東品川2丁目」とは言わず「天王洲アイル」と呼んでいる。品川橋を南に渡って川沿いに右折、先ほどのルートと交差して進み、京急新馬場駅のホーム下を抜けると第一京浜である。次の目的地は道の向こうだが横断できないので南160mにある交差点で渡って北へ60mほどの左に本光寺(右図①)と図会では寺中と付注して描かれている清光寺(右図①)の共通の入り口がある。街道の喧騒に耐えて寺の雰囲気を保つためか、手入れが回らないのか境内の樹木密度が高い。 Uターンして交差点を直進し、次の小路を入り、直ぐ西向きの小路に入った突き当たり左に図会が海竜寺と記している海蔵寺(右図②)がある。
北入りの参道を戻り、第一京浜との出入り交通が多い道を西へ進んで直ぐの左クランクの交差点の北の細い小路に入って突き当たりが大龍寺(左図③)である。 交差点のところは天龍寺(左図④)である。当初の訪問と再訪の間に山門が改修され真新しい。 図会は日蓮宗の重要な寺として本光寺だけを項立てて記述し、本光寺(清光寺を含む)を一番手前に配置して4寺を一枚の図幅に納めて描いている。しかし、海蔵寺が「海竜寺」と名乗った時期はないようなので、図会のミスと考えられる。 天龍寺の南を西に進み、次の十字路で北に進む。 |
| 新馬場駅西部 |
前節から進んで目黒川を渡る橋の名は要津橋である。前節末で右折した付近にあった東海禅寺南門と北門(左図文マークの北東にあった)とを結ぶ通路に架かる橋として右の図版(その3)の中央右寄りに描かれている。現在は橋を北に渡って右に寺はあり、本堂の東側に描かれている図版とは配置が異なっている。
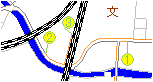 地理的には順路とは言えないが、図会は東海禅寺を天セン之部の冒頭に挙げている。家光と親交のあった沢庵禅師が開いたこの寺は、江戸時代を通じて権勢を誇っていたからである。東海寺の正面の額門は現在の山手通りと第一京浜の交差点にあり、描かれている奥の山は、東海道新幹線と東海道線が分かれる地点である。この広い境内に塔頭十七宇が散在していた。明治以降境内の大部分は公有地化され、現在東海禅寺は山手通りからの北入り(左図①)となっている。
そして、近年は寺の北側に超高層賃貸マンションを建てるなどして寺の運営を支えているようである。
地理的には順路とは言えないが、図会は東海禅寺を天セン之部の冒頭に挙げている。家光と親交のあった沢庵禅師が開いたこの寺は、江戸時代を通じて権勢を誇っていたからである。東海寺の正面の額門は現在の山手通りと第一京浜の交差点にあり、描かれている奥の山は、東海道新幹線と東海道線が分かれる地点である。この広い境内に塔頭十七宇が散在していた。明治以降境内の大部分は公有地化され、現在東海禅寺は山手通りからの北入り(左図①)となっている。
そして、近年は寺の北側に超高層賃貸マンションを建てるなどして寺の運営を支えているようである。
信号を北側に渡り、山手通りの歩道を西に向かう。S字状に曲りながら下ってJR東海道線などを潜り、車の出入りの多い製薬会社の倉庫を過ぎると、東海禅寺の開祖の沢庵和尚が住んだという「春雨庵」を引き継いだ春雨寺(左図②)の標石がある。高層の女性専用(?)の賃貸住宅があり、その一角が寺への入口になっている。米軍の空襲などによって檀家数20の小さい寺になったが賃貸住宅を設けて運営をやりくりしていると寺のサイトに書いてある。結果的に東海禅寺のまねのようだ。 戻って直ぐ、JR東海道線などの手前に「東海寺大山墓地」の案内看板が置かれている。春雨寺へ向かう時には気付かなかったのは、看板が西向きにしか置かれていないためであった。線路に沿って100mほどで墓地になる。図会が特記し、描いている沢庵和尚廟(品川区の説明板は「沢庵の墓」)、縣居大人墓(賀茂真淵墓)、南郭先生墓はここに集められている(左図③)。沢庵和尚の墓は存置縮小かも知れないが、後二人の墓は描かれている配置では無い。 管理していた塔頭少林院のその後が不明でかつ現在の管理者東海寺は東海禅寺と異なるような春雨寺のサイトを読むと、江戸時代の日本人の思想に大きく影響したこの人たちの墓地がこのような電車の騒音が絶えないこの場所に置かれることになった明治以降の過激な変革については、中韓の領土主張の因縁とは別の意味でその歴史的な認識を深める必要を感じざるを得なくなる。 続いて山手通りを戻っていくと、左に品川学園(左図「文」)がある。  200m余りで第一京浜の北品川2丁目交差点である。これを左折して50mを左に入ったところに清徳寺(右図①)がある。図会に東海禅寺の塔中の名称は殆ど登場しないが、この寺は右の午頭天王社(彫師が「牛」を「午」と間違えた?)の図版に描かれかつ光巌寺の記述の中に書かれている。光巌寺は、現在の京急新馬場駅の北側にあったが、現在は痕跡もない。
200m余りで第一京浜の北品川2丁目交差点である。これを左折して50mを左に入ったところに清徳寺(右図①)がある。図会に東海禅寺の塔中の名称は殆ど登場しないが、この寺は右の午頭天王社(彫師が「牛」を「午」と間違えた?)の図版に描かれかつ光巌寺の記述の中に書かれている。光巌寺は、現在の京急新馬場駅の北側にあったが、現在は痕跡もない。清徳寺から第一京浜に戻って左60mに牛頭天王社(現品川神社:右図②)の鳥居がある。本殿へは長い石段になっているので、右手の女坂を押し上げるか、持って行かれないよう国道のガードレールに結びつけるかである。神社の性格は前節で詳しく書いたが、合祀社は図版とはだいぶ異なっている。 神社前の信号で現東海道を渡って旧東海道北品川宿からの参道を進んでいく。 |
| 東+北品川 |
前節から道なりに前へ進むと、旧東海道に出る。左向こうが本陣跡ととのことだが、右図版の「品川駅」は背景からして本節末の「問答河岸」であろう。現在は「聖蹟公園」と格調高い名称になっているが、たぶん明治維新で天皇が東京に移る際にでも宿泊したことと勝手に推測している。
山手通りとの東海道北品川交差点を左折して聖跡公園入口を経て山手通りのひとつ東の信号(八ッ山通り)まで行き、筋向いに渡る。 八ッ山通りを南50mほどの小路に入り、通りの東50m足らずを併行している道を南に行くと右に
 目黒川は中の橋から東50mほどで左へ曲がり、ほぼ現在の八ッ山通りを北に向かって流れていたが昭和初めに付け替えられたことは前節で触れた。
目黒川は中の橋から東50mほどで左へ曲がり、ほぼ現在の八ッ山通りを北に向かって流れていたが昭和初めに付け替えられたことは前節で触れた。
神社の名のいわれは、弟橘媛が遭難したときの船の木材がここに流れ着いたと言うものだが、媛が身を海神に捧げたので船は無事上総に着いたのではなかったっけ?でも「船団の一部が破船した」と反論されそうだ。 砂州の一本道だったと思われる神社前の道を北に進んでも、山手通りが渡れないので神社脇の路地から八ッ山通りに出て右歩道のまま北進し、先ほどの交差点を渡って300mほどで左下図右下に出る。 歩道橋を過ぎて右に入り、直ぐに左を見ると突き当たりに洲崎弁天(現利田神社:左下図①)がある。自転車(イメージマップ写真)の先を右に曲った辺りにあったと思われる 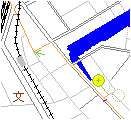
神社南の交差点を渡って旧東海道の品川宿の通りに出て南へと左折する。100mほどの右に、図会の時代には深川にあったが、明治になって品川に戻った 向きを変えて旧東海道を北に進む。北品川郵便局を過ぎて右の辻に問答河岸跡の標石(←)がある。この辺の海岸は目黒川の流れは無く、砂州のおかげで波が穏やかで河岸の適地だった。 北品川の旧名所は、地物として残っているもの少なく、町内会や区役所が立てた説明板や碑があちこちにある。磯の清水に関しては、「清水横丁」の説明板(北品川駅と第一京浜の間)でこの通りの奥(たぶん西端)とのことだが、第一京浜(当時無かった)が道路交通の幹線になっていることなど道路網が変わっているので、どこに湧いていたかは不明である。 そのまま進んで、東海道方面の交通の要衝の八ッ山橋交差点に出る。この交差点は、品川村と谷山(ヤツヤマ)村の境で図会はこの村境を天セン之部と天枢之部の仕切にし、現在の行政も品川区と港区の境にしている。 現在、谷山村の区域に品川村の区域の御殿山の冠を付けたマンションが建っているが、明治時代に谷山村の区域に品川駅を作ったのがお手本かもしれない。 |
| 天セン之部を巡り終えて |
|
天セン之部は、図会7篇の中で図版が最も多い。図版のコピーをアップしないまま当初の探訪を始めていたのだが、この篇のアタックの際に「図会」と言う以上は図版を欠かせないと気付き、再編のための2ラウンド目を実施する決意をした篇であった。 図版に小さく付注されているだけで本文記述のないものが多く、これまでの篇以上に100%フォローすることの不可能さを実感させられた。 この篇の地域は、品川からの東海道沿いと三浦半島方面である。他の六篇と異なり、都心を起点としていない。私の実際の自転車コースも、町田の我が家から八王子街道、鶴見川サイクリングコース、尻手黒川道路、多摩川サイクリングコースそれにJR横浜線、南武線の活用で現地と行き来をし、都心を走る機会が少なくなった。都心からのアクセスを前提とした編集方針と節の設け方などとが合致してない部分も生じていると思うが、お許しいただきたいところである。 |
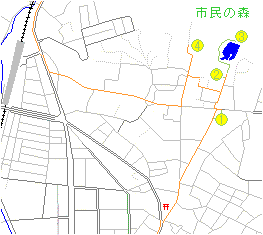 こちらが山門も付いて正面と思うが、自動車主体の現代、称名寺側(北)のほうが入りやすくなっている。
こちらが山門も付いて正面と思うが、自動車主体の現代、称名寺側(北)のほうが入りやすくなっている。