江戸名所図会自転車探訪(玉衡之部)
| 最新更新箇所へ |
| 新荒川大橋前後 |
玉衡之部の巻末は、豊島になっている。その前が赤羽・川口で、さらに前が王子である。現代の順路として不自然であるので、東京メトロ南北線で赤羽岩淵駅のひとつ先の埼玉高速鉄道川口元郷駅まで自転車を運んでこの篇をスタートさせる。
JR川口駅東口から産業道路でも判りやすいのでそれも選択肢である。 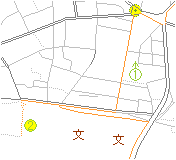
川口元郷駅の南口を出ると、岩槻街道である。400mほど赤羽方面に戻ると、JR川口駅東口から直線で南東に進んできた産業道路がぶつかる本町ロータリーになる(左上図右上)。
この大交差点は、自由な自転車走行のことは全く念頭になかったと思われ、長い信号間隔を覚悟して遠回りをしてぐるっと南回りでJR川口駅方向に進む。手前で右へ渡ると、次に南に渡りたくても、200mほど先まで行かないと渡れない。
この辺から旧岩槻街道西側の地域が河口鍋匠が何軒もあった地域である。旧岩槻街道沿いは、往時の佇まいを残しているところもあるが、マンション業者のターゲットにもなっているようである。
図会が描いた右図版には多くの仏神の堂祠が描かれているが今はない。当初訪問時には、寺の駐車場には復元工事の完成予想図には、図会の絵さながらの反り屋根の本堂が描かれていたがいつのまにか外されたようだ。 善光寺へ車で行くための仮設道路は階段のところからJR線の方までぐるっと回って堤防上に出て東へ戻ってきている。寺から新荒川大橋に出る堤防道路は、進入できないようになっている。3年半前に訪れた時からの変化を確認に行ったがなんら変わっていない。と書いて5年半、平成28年に再々訪したが寺の完成予想図が無くなって道路等の状況はそのままだった。国交省の河川整備での堤防道路補償に絡んで話がこじれっ放しにでもなっているのだろうか。 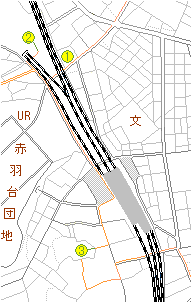 階段下に戻って小中学校用の道路堤防を斜めに上る道を使って橋の北詰に出て隅田川を赤羽方向に渡る。渡り終えても交番の脇を右歩道のまま信号を渡って進む。
階段下に戻って小中学校用の道路堤防を斜めに上る道を使って橋の北詰に出て隅田川を赤羽方向に渡る。渡り終えても交番の脇を右歩道のまま信号を渡って進む。二つ目の大きな交差点(右図上)が赤羽交差点で、羽田空港から東京都区部の西部をぐるっと回ってきた環状八号線道路が右からきてここが終点である。左はその続きではなく、北本通りと言い、途中環七と交差し、王子駅で本郷通りに繋がっている。 この交差点からやや幅員が狭くなっている道を真っ直ぐ200mあまり進んでJR線のガードの手前右が宝幢院(右図①)である。 図会は記述していないが、次の赤羽山八幡宮(現赤羽八幡神社:右図②)の別当だった。 ガードを潜ってすぐ右折して100mほどの高架下に八幡神社入り口がある。この高架は、JR埼京線と新幹線で、すぐ先でトンネルに入る。高架の手前の坂道に鳥居が建っており、トンネル上の神社の駐車場に繋がっている、つまり自動車用の参道である。高架を潜っていくと急な石段があり、年寄りが自転車を下げて登るにはいささかリスクがある。 境内には軍関係の碑が多く、赤羽が、URの赤羽台団地にあった陸軍補給廠を中心とした軍の街として発展してきたことを物語っている。 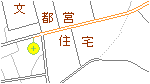 神社入口の南40mの丁字交差点を西に1.2km進んで住宅団地街が終わりそうなところに、関東大震災で被災して旧新寺町(開陽之部)から移転してきた
神社入口の南40mの丁字交差点を西に1.2km進んで住宅団地街が終わりそうなところに、関東大震災で被災して旧新寺町(開陽之部)から移転してきた
戻って線路沿いにJR赤羽駅西口の駅前広場に出て、南下する道を100m程進むと、駅南口から西に向かって延びる道と交差する。 この辻を右に入ると静勝寺(右図③)の階段にぶつかる。赤羽八幡の階段よりは短いが急な石段であるし、左の坂も急で自転車を押して上がるしかない。上がり切った正面に影堂がつつましやかに佇んでいるが、
境内の南(こちらが正門)から住宅地の中へ出てブレーキだけで下りて行き、下り切ったら左折し、先ほどの道へ出て戻るように左折して次の場違いな感じの広い道路を右折して鉄道のガードを東へ抜ける。 ここにも左右前後いかにも道路拡幅を諦めたような交差点があり、これを右折して緩やかな直線の坂道を上っていく。約1kmで環状七号線に出る。 |
| 豊島 |
前節からは3km近く何もないので、私のルートを徒歩でトレースする方は、一旦赤羽駅に戻り、改めて王子駅か王子神谷駅を使っていただくのが合理的だと思う。 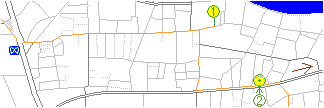
環状七号線に出たところかひとつ東の信号で右歩道(南側)に移っておく。神谷陸橋が北本通りを跨ぐ宮越交差点を使わずに、地域の殆どの歩行者や自転車が使っている交差点手前の旧道を右折するためである。
神谷陸橋途中で旧道に右折してくると左図の左端東京メトロ南北線の王子神谷駅の北口で北本通りに出る。ここで信号を東に渡り、庚申通と書かれている商店街を抜けてひたすら東に進む。
清光寺から少し戻って南に向かい、次の広い道路を東に向かって200mあまりで紀州明神社(現紀州神社:左図②↑先)である。
神社前を左図右端の→のほうに進むと、豊島橋で隅田川を渡り、開陽之部「荒川左岸・隅田川右岸」で荒川を渡った江北橋になる。 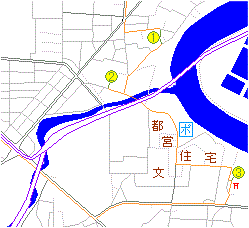 神社の東の信号で南に渡り、豊島商店街に入っていく。駅や幹線道路から遠いせいか大型店は立地しておらず、昔ながらの店が中心の街である。この通を抜けると広い道が斜めに交差してきている。(右図上部)
神社の東の信号で南に渡り、豊島商店街に入っていく。駅や幹線道路から遠いせいか大型店は立地しておらず、昔ながらの店が中心の街である。この通を抜けると広い道が斜めに交差してきている。(右図上部)この広い道を北東に進み、上で江北橋に出ると書いた紀州神社前の道とが合流する500m余先に その信号を南に進んで、左二つ目の道を入る。直線から緩やかに右に曲がる付近の家と家の間を抜けると、児童公園に出る。この公園の中に豊島清光の霊を祀っている 公園の南に出て南西に進み、T字路としてぶつかったら右に進む。100m足らずの右(北)に西福寺(右図②)がある。図会には禅宗にしてとあるが、現在は真言宗豊山派で仁王門や露座の仏像が華やかに彩られている。
梶原塚は、図会では西福寺と豊島川の間に描かれ、文でも梶原堀之内、豊島川の河曲堤の本にありと書かれている。 「豊島川」という名前は、「紀州神社ほか」と「西福寺」の図版それぞれの遠景に描かれた水面にキャプションされている。他の地域の記述などや他の文献でも見かけない。隅田川の地域限定の名と思われる。
梶原塚にあった古碑などは福性寺(右図③)に移転されているが、塚は西福寺から福性寺への途中で潜る首都高速中央環状線の下あたりにあったらしい。
福性寺を南に出た広い通りを東へ500mほどで、上述した開陽之部の節で訪れた船方神社(十二天森:あらかわ遊園隣)である。逆に西に進んで明治通りに出る。明治通りを左400mにある都電の梶原駅の名の由来は説明するまでもないだろう。これにも背を向けて再び首都高を潜り、溝田橋交差点で明治通りを渡って進む。 |
| 王子周辺 |
溝田橋交差点を渡ってすぐ左に入って200mほどの信号の次の十字路を右に入ると、左先に装束稲荷神社(■写真アリ)がある。往時この辺は装束畠と呼ばれ、中央にあった
入ってきた道に平行に進み、北本通に出て左折して北とぴあ前交差点に出る。右のビル(左図E)には東京メトロ南北線王子駅のエレベーター付き出入口がある。都心から直接王子へ来て地上に出る場合はこれが便利である。 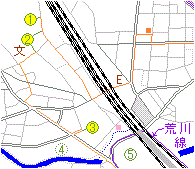 右折してガードを潜った先に信号がある。図会がこの地の繁華は都下にゆづらずと記した店々はこの交差点の左右に立ち並んでいたと思われる。
信号を左へ進んでいくと、左に王子稲荷社(現王子稲荷神社:左図②)があり、続いて当時は現北区役所の分庁舎のあるところ(左図④)にあった
右折してガードを潜った先に信号がある。図会がこの地の繁華は都下にゆづらずと記した店々はこの交差点の左右に立ち並んでいたと思われる。
信号を左へ進んでいくと、左に王子稲荷社(現王子稲荷神社:左図②)があり、続いて当時は現北区役所の分庁舎のあるところ(左図④)にあった
境内を上がって左の門を出、坂を右へ上がり次の角を左に曲がって広い通りに出たら左へ進む。
道路の反対側に渡って少し入った北区役所の分庁舎があるところ(左図④)にあった前出の金輪寺は権現、稲荷両社の別当だった。右「十八講」の絵は氏子たちの僧侶への感謝の行事である。 石神井川を渡る橋には昭和初期のアールデコデザインの欄干がついており、音無橋と名付けられている。図会の時代この下に堰があり(右図版「音無川」参照)、隅田川からの船はここで止められていた。昭和30年代の治水工事で橋の上流から飛鳥山公園の地下を抜けるトンネルが掘られた。
飛鳥橋は、「飛鳥山」の図版の右手前に描かれており、現在のガード下の位置である。改修前の石神井川は、現在の東武ストアから印刷局にかけて流れて左図右端付近で現在の河道に繋がっていた。
明治通りは次のT字路で右に曲がり、再び首都高速道路環状線を抱えて西巣鴨方面に進む。これを渡り、再び都電を渡って次の信号が飛鳥山(現在は同公園:右図①)の本郷通り口である。明治初期から欧米に負けない公園のひとつとして整備されてきたためか、江戸の風情を残しているものは殆どない。 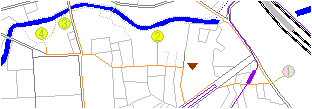 噴水はあっても夏は日比谷公園のほうが涼しい。博物館や都電の廃車が並んでいるのも何となく安っぽい。金輪寺が納めた漢文の飛鳥山碑だけが図会と合致している。桜も吉宗が植えた桜は半分の本数になり、ランキングは都心の新しい公園に負けている。いつからそうなったかは判らないが、昭和40年までは都の公園だったのが区の公園に所管替えされたのとも関係がありそうだ。
噴水はあっても夏は日比谷公園のほうが涼しい。博物館や都電の廃車が並んでいるのも何となく安っぽい。金輪寺が納めた漢文の飛鳥山碑だけが図会と合致している。桜も吉宗が植えた桜は半分の本数になり、ランキングは都心の新しい公園に負けている。いつからそうなったかは判らないが、昭和40年までは都の公園だったのが区の公園に所管替えされたのとも関係がありそうだ。同じ信号を戻ってそのまま細い道路を行くと右に飛鳥山停留所を見て明治通りに出る。通りの北側に渡り、右歩道で進んだ後歩道橋先を右に入る。100m余りの右に独立行政法人になって酒類総合研究所東京分所と長く聞きなれない名前になってしまった旧醸造研究所が右図▼の位置にあり、これを西(左)にはいっていく。100m弱の右に滝不動尊/正受院(右図②)の参道がある。 開山の言われ、千島列島探検の近藤重蔵の墓、木立に囲まれた明治時代建造の中華風の鐘楼門、戦火に耐えた樹林など由緒を重ねてきているこの寺は、赤ちゃん供養の寺としても知られ、悲運に遭った若い夫婦の姿を見かける。
西へ進んで滝野川病院前交差点を右に進むと直ぐに左手に金剛寺(別称紅葉寺:右図③)がある。寺と石神井川の間の遊歩道を入っていくと川沿いの半円形の低地(もみじ緑地)に降りる。この寺側の崖に 緑地の南斜面を上がり、南へ進み、バス通りに出たら左折し、滝野川病院前交差点に戻ったら右、南へ進む。 |
| 古石神井川上流部 |
本節のタイトルの「古石神井川」をご理解いただくため少々説明を加える。
有史以前のことだが、石神井川は現在の流れから正受院の東で南に曲がり、前節で明治通りを北に渡った付近、本節の昌林寺前、本郷通り霜降橋、JR駒込駅東を経て本駒込図書館付近から不忍通りに沿って流れ、御徒町付近で海に注いでいた。 古文書の記録では現在の流路で、飛鳥山台地の西側に発して不忍池に入る川は谷田(戸)川、藍染川と呼ばれる別の川で、昭和末期まで石神井川の下流だったいうのは学説の一つに過ぎなかった。しかし、バブル経済で低層建築地帯だったこの流域にも高層建築が建ち、数多くのボーリング調査のデータが得られた。その分析の結果、現石神井川の上流部から続いていた川であることが実証され、谷の広さも十分に説明できるものとなった。
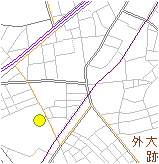
前節から進むと首都高併設の明治通りに出る。その信号を渡って右折、バス停を過ぎて同じくらい走ったらマンションの間の道を左折する。
次の信号を渡るといかにも旧道というこの道を行くと、右手にお寺が3刹並んでいる。その真ん中が鉄道の敷設で上野から移転してきた 都電を渡って直ぐの信号を左折し、次のT字路の信号を右折して150mほどに、周囲と不釣り合いの大型賃貸マンションがある。その先は公園になっているが、ここが東京外語大の跡地である。 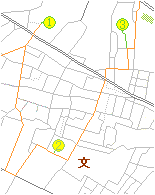 20世紀最後の東京の国立大学の移転としてここから調布飛行場の近くの米軍返還地に移ったものである。国有地の活用としては何ともつまらない姿は、外語大OBにとっても悲しい思い出の地になってしまったのではなかろうか。その西から南にかけての古石神井川の南西の斜面である下瀬坂を降りてゆき、染井銀座商店街を横切って進み、ぶつかった先の左に昌林禅寺(右図①)の小ぶりの石碑がある。
これを入ると今度は古石神井川の北東斜面である坂を上がり、突き当たりが境内である。
20世紀最後の東京の国立大学の移転としてここから調布飛行場の近くの米軍返還地に移ったものである。国有地の活用としては何ともつまらない姿は、外語大OBにとっても悲しい思い出の地になってしまったのではなかろうか。その西から南にかけての古石神井川の南西の斜面である下瀬坂を降りてゆき、染井銀座商店街を横切って進み、ぶつかった先の左に昌林禅寺(右図①)の小ぶりの石碑がある。
これを入ると今度は古石神井川の北東斜面である坂を上がり、突き当たりが境内である。戻って道を渡り、次の分岐で左に進んで再び染井商店街を横切って坂を上っていくと、信号が右にある交差点まで辿りつく。ここを右折して200m足らずが染井霊園だが、順路は左折である。次左のスクールゾーンと書いてある細い道を入る。 道なりに右に曲がると染井稲荷社(現染井稲荷神社:右図②)と西福寺(右図②)が並んでいる。当時は当然習合で、図会は西福寺の境内にあるように記している。この寺の前は桜並木で、樹種は言わずと知れている。そのまま進んで突き当りは駒込小学校である。 小学校の前で左折して再び坂を下る。道が平らになり、バス通りを横切って突き当ったところを右70mのところに無量寺(右図③)の入り口がある。こちらは昌林禅寺より緩やかな坂である。寺域は図会の絵よりもずっと大きく育った杉が立ち並び、静寂を保っている。 図会の時代から動いていないと思われる山門(惣門)を出て、
右の図会の絵と見比べて見ると、何のことはない、旧古河庭園は無量寺の境内だったことが判る。なかでも無量寺が別当をしていて境内(ほぼ現在の大谷美術館の位置)にあった |
| 平塚村〜田端 |
無量寺と旧古河庭園との間の坂を上がりきって本郷通りに出ると平塚神社前交差点である。(左中図)
 この神社を後回しにして、交差点から600mあまり飛鳥山方面にある
この神社を後回しにして、交差点から600mあまり飛鳥山方面にある 無量寺境内にあったときからの「七社」という名は、祭神が7柱であったことを表している。本殿前の説明板は、移転先のこの場所が既に5社合祀の神明宮の境内だったがこれらを末社としたこと、
古河・岩崎両豪商から青年団集会所を寄贈されたことを書いている。本通りからの参道設置も含めて神仏分離を行うとこんなにメリットがあると政府がモデルを示した以上の破格の扱いであったと言える。
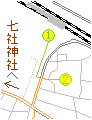
戻ってきて平塚神社前交差点手前の公園の中を通っても行かれるが、公園の中を乗り回すのは良いマナーとも言えないので、交差点を左折してJR上中里駅に降りる道をしばらく行き、東にある鳥居から平塚明神社(現平塚神社:左下図①)境内に入る。
平塚神社の北は、大きな崖であり、その下をJR京浜東北線などが走っている。豊島氏の祖先が八幡太郎義家から拝領した鎧を低い塚に埋めて祀ったのが神社と地名の由緒とのこと。
しかし室町末期に古河公方に組して二度にわたり太田道灌に攻められて城跡になった。この周辺は江戸時代は平塚村と呼ばれていたが、現代では地名から消えている。 入った鳥居のところから反対側に渡ると平塚明神の別当と図会が記している城官寺(左下図②)が真正面にある。 本郷通りに戻って左折し、次の信号で左の田端方面を選んで本郷通りと岐れる。 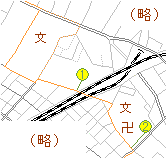 400m先の女子聖学園前で道を渡ってそのまま(この道は下校時には生徒でいっぱいになるので、その場合は一つ先の中里三丁目で道を渡った方が良い)坂を下る。下りきったところで左折して進むとタイミングが良いと踏切の音が聞こえる。
JR山手線唯一の踏み切りがこの先にあるからである。近づくと右手に大きなゴルフボールのモニュメントがある。その反対側(左)が円勝寺(右上図①)である。
400m先の女子聖学園前で道を渡ってそのまま(この道は下校時には生徒でいっぱいになるので、その場合は一つ先の中里三丁目で道を渡った方が良い)坂を下る。下りきったところで左折して進むとタイミングが良いと踏切の音が聞こえる。
JR山手線唯一の踏み切りがこの先にあるからである。近づくと右手に大きなゴルフボールのモニュメントがある。その反対側(左)が円勝寺(右上図①)である。円勝寺から踏切を渡って真っ直ぐ進んで滝野川第7小学校にぶつかる。 図会が1行余りで書いていて絵でも祠然としている 神社の角を右、南西へ進むと信号付交差点があり、これを東南、左に進む。
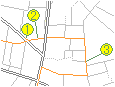 仁王の姿なのかも判らない)の向こう側に入り口がある。
仁王の姿なのかも判らない)の向こう側に入り口がある。 当初訪れた時(3年前)、それなりにスペースのある東覚寺の正面を避けて中途半端な位置になぜ仁王像が置かれているのか疑問だった。今回の再訪で未供用の道路内からゆっくりと写真を撮り直すことができたのと同時にその疑問も少し解けた。
神仏分離令で都合が悪くなって図会の位置から暫定的に移したままというのは、神社が自分の財産だと言ったり寺が嫌がったりしたのかはたまた神仏分離令が廃されるのを待ったのかと思ったのだが、どうやら、一旦寺の正面に移されたが、道路計画でやむを得ずこの位置に再移転したのだろうと思っている。
田端八幡宮は、平塚神社同様参道脇に御輿庫が並んでいる。そして、本節の4神社とも参道が長めに確保されているのが印象的である。
神社東はJR田端駅から都心に向かう通りである。これを横切って進み、ぶつかって右折して100mに與楽寺(右下図③)がある。
JR田端駅からの通りに出て左折、本駒込に向かう。 |
| 本駒込 |
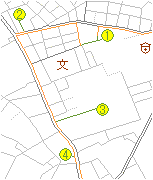
動坂下で不忍通りを渡り、坂を上がっていくと交番が左右に道を岐けている。これを右にとり、都立駒込病院を通り過ぎてまもなく左に入る小路がある。
これを入ると駒込神明宮(現天祖神社:左図①)の境内に直結している。図会では、境内から本郷通り(図会では岩ふち街道)までの間に広大な芝生が描かれている。第九中学校はその一部であろうが、
その他は一般市街地になっている。残された境内は街中でのつつましやかなもので、往時からの土地転用の経緯を知りたくなるのは、携わってきた仕事による習性だろうか。
鳥居の前に出て右に行って元の道に出たら左折する。
富士神社境内は、小山のようになっているが、これが自然地形ではない可能性は高い。その理由は右の「浅間社と富士講」で・・・・・。 本郷通りを南に向かうと、誰も見落とさないほど大きな字の石碑が立っているのが吉祥寺(左図③)である。学僧の宿坊ばかりか天神や秋葉なども備えていたこの寺の境内は今も広大で、本殿前には本郷通りの喧騒も届かない。 「吉祥寺」は、東京23区を西に出て最初の街、武蔵野市の中心地のほうが知られている。災害のたびに多くの寺社は境内を縮小させて被災者を救済してきた。
さらに都心に向かい、道が緩やかに右に曲がった右側に南谷寺(左図④)があるので吉祥寺前の信号で右歩道に移る。
五色不動巡りの一つ「目赤」であるが図会は、最初に動坂(この名は不動坂の「不」が略されたもの)上にお堂を立てた僧侶が修行の地の伊賀赤目山の名を使ったが、後年目黒目白に引きずられて変えられたものだと書いている。 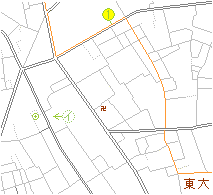 東京メトロ南北線の本駒込駅がある駒本小学校前の交差点を過ぎると向丘2丁目交差点になる。
東京メトロ南北線の本駒込駅がある駒本小学校前の交差点を過ぎると向丘2丁目交差点になる。右図や右の「浄心寺坂」をご参考頂くことにしてあえてルート紹介せず、向丘2丁目交差点を団子坂方面に左折する。左側は寺が続き、その最後に光源寺、駒込大観音(右図①)がある。消失した江戸時代の木造のお堂より2メートルほど低いとは言え、伝統の形より観音像にあわせた形のデザインで、大きな屋根が寺院だとの先入観からは斬新である。 ここから400m先で道は右に曲がりながら急な下り坂になる。これが団子坂だが、詳しくは次節に譲る。 寺の先の信号を右折、400n余りで次節の根津神社裏門に行ける広い道に出る。遠回りでも正面から入ることにしてこれを横切り、200mほど進むと左先が高いコンクリート塀で囲まれた東京大学地震研究所になる。この手前を左に入っていく(右図右下)。
|
| 谷根千 |
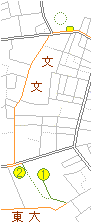
東大野球場入口から60mほどの急な下り坂を曲がり、坂を降り切った左に朱塗りの鳥居が立っているのが根津権現社(現根津神社:左上図①)である。主祭神は素盞鳴命であるが、18世紀初頭の千駄木坂(現団子坂)上からの移転以前から「権現」であった。別当について図会の記述はないが、絵には描かれており昌仙院神宮寺という名も他の文献に残されている。本尊を祀る本堂らしきものがないことから、いわゆる「兼帯」ではなく、神社のマネージメントのみで檀家を持たない別当だったのではないかと思われる。もちろん現在の境内に何の痕跡もない。
本殿に向かって左に徳川家宣胞衣塚があるなど当時から由緒もあったと思われる。
胞衣塚との間を北に進むと乙女稲荷神社がありさらに先に
最後少し下ってのバス通りとの交差点を右に下る。この坂は上に述べた団子坂(千駄木坂)だが、図版では別名に潮見坂と七面坂を紹介している。前者は先ほどの小学校の名の由来である。また後者は坂下に付注付きで描かれている この坂上の北に区の施設があるが、この辺りが 七面堂があった交差点には東京メトロ千代田線の千駄木駅がある。この交差点をそのまま渡って前の道へ入っていく。
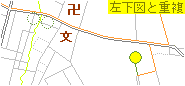 この先の三崎坂がカラーンコロンとお露の幽霊が下ってきた坂であるが、団子坂より緩やかな分長い。上がりきっての幼稚園前の信号を右に入り、200mほど先を右に入って突き当った右が瑞林寺(右図:瑞輪寺が正しく、図会のミス)である。図会ではこの辺を上野の周辺としているが、現在は谷中の地番表示となっている。また、この寺を身延山の触頭と紹介しており、現在も広闊な境内となっている。
この先の三崎坂がカラーンコロンとお露の幽霊が下ってきた坂であるが、団子坂より緩やかな分長い。上がりきっての幼稚園前の信号を右に入り、200mほど先を右に入って突き当った右が瑞林寺(右図:瑞輪寺が正しく、図会のミス)である。図会ではこの辺を上野の周辺としているが、現在は谷中の地番表示となっている。また、この寺を身延山の触頭と紹介しており、現在も広闊な境内となっている。信号まで戻って一つ東の信号を左折する。150mほどの右に平成24年に改築落慶した功徳林寺の入口がある。この入口の真正面奥に稲荷神社固有の赤い幟が立っている(左下図①)。
 さらに50mほど進んだ左が同じ図版の左手前に描かれている長安寺(左下図②)である。
さらに50mほど進んだ左が同じ図版の左手前に描かれている長安寺(左下図②)である。長安寺の前を東に入っていき、霊園の十字路で左折する。そのまま進むと正面が感応寺(現天王寺:左下図③)である。
此の寺の裏はJR京浜東北線などが走っており、日暮里駅がある。駅へ向かっての細い道が芋坂口の現在の姿である。鉄道敷設以来位置も形も変っており、工事仮設も度々なので、自転車を引くなどして橋上改札の日暮里駅西口へ出る。 |
| 日暮らしの里(含む道灌山) |
通りに出たところの信号の向こうに本行寺(左図①)がある。門に「月見寺」と書いてあるこの太田道灌ゆかりの寺から日暮里(ひぐらしのさと:ニッポリ)が始まる。左の図版には
以下日暮里惣図全四版には20ヶ所以上に付けられている。しかし、記述は少なく注の多くは確認できていない。 本行寺の西が経王寺(左図②)で、明治維新の際に彰義隊を匿って官軍の攻撃を受け話題になり、現代ではその名所である。 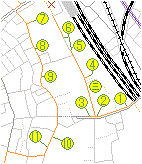 さらに西へ諏訪台通り入り口を過ぎたところに延命院・七面大明神社(左図③)がある。近くの「夕焼けだんだん」が現代の名所になっているが、その南(左側)の七面坂の名はこの延命院の七面堂に由来している。
さらに西へ諏訪台通り入り口を過ぎたところに延命院・七面大明神社(左図③)がある。近くの「夕焼けだんだん」が現代の名所になっているが、その南(左側)の七面坂の名はこの延命院の七面堂に由来している。
その先に朱塗りの仁王門のある養福寺(左図④)がある。さらに100m余りで正面に鳥居があるのがこの地域唯一の神社とも言える諏訪明神社(現諏方神社:左図⑥)である。諏方神社の祭神は諏訪大社上社と同じで、神社庁の格式は高い。 鳥居のところで、右を見ると門があり、こちらはこの神社の別当をしていた浄光寺(左図⑤)である。
諏方神社の北は西日暮里公園で、園内に図会を始めとした江戸時代の文献を引用したパネルが掲示されている。図会は その手前に青雲寺のえびす堂と観音堂が、先にはこんぴらとほていが描かれているが、もちろん今は無い。 公園北端に階段があり、これを下りると道灌山通りを渡る歩道橋がある。そのむこうのビルの後ろは図会の時代には一繋がりの台地で屈指の風雅の地と言われた道灌山なのでこちらを探訪して日暮しの里に戻る。
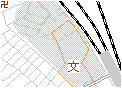 マンション団地の北を左(西)に下る道の向こうには3節前に訪れた與楽寺がある。
マンション団地の北を左(西)に下る道の向こうには3節前に訪れた與楽寺がある。適当に切り上げて開成学園の間の道で下に降りる。左折して道灌山通りに出て右の信号で通りを地上で渡り返してそのまま進む(左図左上)。この道は、六阿弥陀道と言われ、前篇の荒川左岸の性翁寺にまで至っていた。50mほどで左に入ると坂の上に青雲禅寺(左図⑦)がある。裏山が区の公園になっていることは前述のとおり。 六阿弥陀道へ戻って100m弱に青雲寺とともに「花見寺」と呼ばれてきた修証院(現:左図⑧)があり、さらに同じくらい進むと南泉寺(左図⑨)がある。両寺の間に図会は 月、雪、花を分担しての名所づくりは、江戸の風流にマッチしていたように思う。しかし、図会ではどのひとつも触れていない。
さらに進んで夕焼けだんだんの下で右の谷中銀座をやり過ごして100m弱に長相寺(現長明寺:これも図会のミスかもしれない。左図⑩)が左にある。
宗林寺の先を右に入って130mでよみせ通りに出て左折する。この通りは藍染川(前節「法住寺」図版では蜆川とも付注)を埋めてできた古くない道なのだが、今風レトロの街並みになり谷中銀座と併せ平日も遠くから訪れた人で賑わっている。左折してから250mほどで前節の妙林(蓮)寺跡と法住(受)寺跡の間に出る(前節右図黄緑色の道)。さらに南は河道そのままの曲がりくねった通称へび道で、これを抜けて真直ぐな道を400mで言問通りに出る。 |
| 上野公園とその周辺 |
言問通りを左折して上っていく坂は善光寺坂である。すぐ左にある玉林寺について図会は、善光寺が宝永二年に青山の外れに台命で移転させられるまでここにあったと天キ之部で記している。「善光寺前町」は明治初期まで残っていた。
上がって二つ目の谷中六丁目信号で右折する(左図左上)。そのまま進んで突き当りに護国院(左図①)がある。境内は手入れの形跡が見えないほど樹木が生い繁っている。 護国院の東は芸大(正式には東京藝術大学。国語審議会が常用を認めていない「藝」が使われている。)美術学部のキャンパスである。寺の前を右(東北東)に進むと信号があり、その先右は同大音楽学部である。道路の左側、長州藩所縁の圓珠院の隣のブロックに 道が突き当った先に 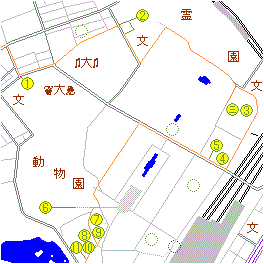 戊辰戦争で殆どの伽藍を失った寛永寺が、明治になって宿坊の一つ大慈院の土地に開祖天海大僧正(慈眼大師)所縁の川越喜多院から中堂を移築して再興したものである。現在の国立博物館前広場の噴水のところに旧中堂はあり、博物館の敷地には本坊があった。
戊辰戦争で殆どの伽藍を失った寛永寺が、明治になって宿坊の一つ大慈院の土地に開祖天海大僧正(慈眼大師)所縁の川越喜多院から中堂を移築して再興したものである。現在の国立博物館前広場の噴水のところに旧中堂はあり、博物館の敷地には本坊があった。
線路と平行(南)に進んでの交差点を左折して線路を跨ぐのが現在の「車坂」だが、右図其三で付注されている
150mほど先に国立博物館入口があり、信号があるのでここで道を渡る。広場は歩行者が多いので遠慮して芸大方向に100m余り進んで都立博物館の方へと左折する。そのまま進むと上野動物園入り口になるが、これを横切って突き当り、左に曲がると右に鳥居が立っており東照大権現宮(現上野東照宮:左図⑥)である。階段があるので自転車をひいて入っていく。霊廟は、寛永寺霊園の中に非公開で囲ってあるそうで、ここは祭殿である。 戻って中間の門を出てすぐ右に出て左先に壊れて上半分になってしまった大石燈籠(現お化け灯篭:左図⑦)がある。その先道が下り始めた右の小高い所に鯨鐘(時の鐘)(左図⑧)がある。芭蕉の「花雲や鐘は上野か浅草か」の時鐘であるが、喧騒著しい現代では殆どの人が気付かない。 道の反対の左の丘の上には仏塔があり、そこに文殊楼後ろに(右図版其三参照)あった 大仏は関東大震災まで道を下りきった左の低いところに南向きに坐っていたが、震災で壊れ胴体部分は戦時の金属供出で処分された。昭和42年に現在地への仏塔(薬師堂)の整備と併せて顔面レリーフが設置されたが、小さな子は怖がっている。また、現在の向きは北向きになっている 南へ戻って園路の交差広場に出て右に忍岡稲荷祠(穴稲荷)(現花園稲荷神社:左図⑩)がある。
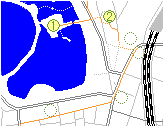 鳥居を出て坂を下って100mほどの信号で不忍池のほうに渡るのだが、その手前に公園地下の駐車場からの自動車の出口があるので要注意である。
鳥居を出て坂を下って100mほどの信号で不忍池のほうに渡るのだが、その手前に公園地下の駐車場からの自動車の出口があるので要注意である。不忍池と中島弁財天(右図①)は現在も名所である。蓮の花は図会に描かれた以上に増え、暑い夏の時期人々に安らぎ(最近は「癒し」と言わないと通じないかもしれない)を与えてくれている。同じ信号を渡り戻ってそのまま階段を上がる。学生時代通学に使い、踏み面幅の違う二段を一組にした階段に、東京は結構変な所だと思ったことが蘇えった。 上りきると目の前に柱が朱塗りのお堂が見える。清水観音堂(右図②)である。京都の清水寺を模して西側に舞台を設けてあり、不忍池から湯島方面を眺めている花見図が図会に描かれている。
この南の階段のところに黒門と御成門があったが、図会は黒門前の広場を描いただけで触れていない。現在は地下が京成上野駅になているが地上は広場である。その広場を東に出てJR上野駅方向に戻り、ガード下の信号で中央通りを南側に渡る。 上野駅の大部分は右の図「山下」で描かれた火除け地だった。寛永寺に一般市街地の火災が及ばないよう設けたものだったが、広い空地は格好の興行場所であったし露店も設けられた。幕府はたびたび規制したようだが、図会の時代は規制が緩んでいた時期で、この絵は貴重な江戸風俗史料と言われている。 その左端に半分消えたような付注があり、辛うじて啓運寺と読める。gooの古地図で「慶雲寺」というのがJRのガード東側(右図右端)にある。当初見落としていたが、平成26年に始めた詳細な索引表作りの過程で気づきWeb検索したらあっさりと見つかった。戊辰戦争で焼かれて15年ほど仮設状態だったが、上野駅の開設に伴って西日暮里へ移転していた。 ガードの西側に先ほどの ここで再び中央通りを渡り、不忍通りの一つ南の道に入る。この通りが仲町通りで、本郷に至るメインストリートとして栄えていた。通りに入って150m余りの右にパークホテルがあるが、その手前に開陽之部浅草みやげのトップに書かれていた 本節終のほうは現存しない名所ばかりになってしまった。しかし、寛永寺に関して図会が記したり描いてあっても、焼失したもの移転再興が不明なものは本節で挙げただけではない。以下項目のみリストしておく(名木を除く)。竹台、廊門、雲水塔、三十番神社、転輪蔵、吉祥天・七面、鐘楼、法華堂、常行堂、勅額門(中堂入口)、弁天、児稲荷、宝光堂、牛頭天王社、常念仏堂。
|
| 湯島〜外神田 |
不忍通りを左折して50mで天神下交差点になる。これを右歩道で右折して坂を上がる。
道路の反対側に後で訪れる湯島天神の夫婦坂入り口がある。こちら側は白っぽいマンションがあり、その先左に入ると国の出先機関の合同庁舎が奥にあることを案内している。マンションのあたりもかつては湯島天神側同様石積みの擁壁で、湯島切通しと呼ばれていた。寛永寺などとの連絡の便のため幕府が坂を切り開いて道を設けたものである。 この辺りに 根生院のあった場所はスキャンダラスな歴史が伴っている。その詳細は右の「不運」で・・・・・。 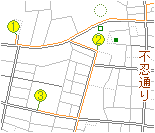 坂を登りきってしばらくすると右手に100m足らずだけ分離帯のあるような不思議な道路がある。麟祥院(左図①)の入り口である。春日の局の墓所であり、天神下から上がってきた道路が「春日通」と呼ばれる所以である。
坂を登りきってしばらくすると右手に100m足らずだけ分離帯のあるような不思議な道路がある。麟祥院(左図①)の入り口である。春日の局の墓所であり、天神下から上がってきた道路が「春日通」と呼ばれる所以である。根生院跡の方へ道を戻り、坂が始まる所にある「湯島天神入口」の信号で道路の反対側に渡って入っていく。湯島天満宮(現湯島天神社)の正門は信号から入って100mほどのところにある。
夫婦坂の降り口にある戸隠神社は、図会では俗に戸隠明神と云うが本来は湯島神社だと書いている。 湯島天神から南に伸びる道を辿る。三組坂上という信号のある交差点で右折する。150mほどで右手に立派な山門と本堂が現れる。霊雲寺(左図③)である。関東真言律の惣本寺と図会が書いている体制は維持されているようで、震災や戦災に遭っても慌てずに着々と復元をしてきている。当初訪問時に復元計画が掲示されていた鐘楼は平成26年末には落慶した。しかし、図会の図版の本堂の後ろの境内は一般市街地化され、平成30年には介護付き高齢者マンションが完成しそうである。 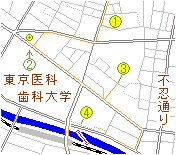 霊雲寺から三組坂上に戻って右折し、清水坂を下る。うっかりすると通り過ぎてしまうが、左の歩道に赤い鉢巻のようなものが付いている道標があるのに注目する。赤い線を追うと信号から150mほどで左に入り、その左に妻恋大明神社(現妻恋神社:右図①)がある。起源は揺光之部の吾嬬神社などと同趣で、祭神は弟橘媛である。
霊雲寺から三組坂上に戻って右折し、清水坂を下る。うっかりすると通り過ぎてしまうが、左の歩道に赤い鉢巻のようなものが付いている道標があるのに注目する。赤い線を追うと信号から150mほどで左に入り、その左に妻恋大明神社(現妻恋神社:右図①)がある。起源は揺光之部の吾嬬神社などと同趣で、祭神は弟橘媛である。図会は万治年間に火災に遭って坂の下から上に移ったと書いており、元は神社前を東に下る妻恋坂を降りきった現在の妻恋坂交差点付近にあったのだろう。 清水坂下に出て蔵前橋通りを右折して坂を上がっていく。ほぼ上がりきって道が左に曲がると前方の信号が見えるところに来る。信号まで行かずに左にあるビルの間の細い道を本郷通りに出て右歩道方で右折する。目の前の濃いめのベージュ色のビルに円満寺(右図②↑先)という看板が付いている。都心にいくつかみられるビル内寺院の典型で、2階が喫茶店になっている。 戻ってそのまま本郷通り(板橋街道神田明神社図版参照)を下って行き、次の信号(湯島聖堂前:現本郷通りはここから聖橋のほうに右折している)を過ぎると左に大鳥居があり、神田大明神社(現神田明神社:右図③)の入口である。
本郷通りに戻って道路の反対側が聖堂(現湯島聖堂:右図④)である。直線で下っているこの付近の本郷通りは、自動車のスピードが出過ぎて危ないせいか信号はもとより横断歩道もない。次の信号まで行って右折して外堀通りに出ると左向こうに昌平橋が見える。 玉衡之部の書き出しに昌平橋が登場するが、詳細は天枢之部に譲って外堀通りを右歩道で坂を上がっていく。 100m余りのところ右に仰高門がある。しかしこの門は貧相な感があり、構内に入ったところの舗装もボロボロである。訪れた時、修学旅行の自由行動のグループがいたが、彼らもこれが本当の入口だろうかと訝っている様子だった。 正門である入徳門へは構内を塀に沿って70m進む。オイルショックの前頃に一度訪れた時には木が茂っていなかったが、現在は手入れができていないようで梢と梢が重なるほどになっている。 林羅山が創設した孔子廟が聖堂の起源で、幕府は付設された林羅山の私塾を江戸時代の価値基準の基礎である儒学の最高学府として経営させた。図会でも「本邦第一の学校」と書き、聖堂を取り巻く霞の上に此辺学問所と注記している。徳川嫌いの明治政府も高等教育の骨格をここの関係者に委ねるしかなかった。
いくつかの国立大学のルーツはここにある。現在は東京医科歯科大学が現地に残っておいるが、東京女高師移転後設立された東京高等歯科医学校が発展したものでかえって最も由緒が新しい。その前の東京女子高等師範学校は関東大震災後に大塚二丁目に移転していたが、戦後の新学制移行の際にルーツに因んで「お茶の水」女子大学(駅名などは御茶ノ水)となったものである。
都心に戻るには自転車を曳いて通り抜け、聖橋出入り口の階段を上がって聖橋を渡る。橋の上からは、外堀通りからは見えなかった神田川を渡る東京メトロ丸の内線を見ることができる。渡りきったところは天枢之部の縄張りだが、本篇の終点としての電車駅は、橋の南詰の右JR御茶ノ水駅とする。
|
| 開陽之部と玉衡之部を走り終えて |
|
この両篇はそれぞれ比較的短く、平成19年は猛暑で手抜きをしたにもかかわらず9ヶ月余で回った。揺光之部だけで9ヶ月近く要したのと対象的である。
残りの4篇は、いずれも広範囲で長編かつ明治以降の経済発展の中で早くから新住民が移り住み、開発され地域の生活や文化が変貌した地域である。これまでとは違う要因で現状不明の箇所が多くなるのではと懸念している。なので7篇中3篇終わったというより3分の1に達したかどうかというところである。 一方で、江戸名所図会シリーズを始めた頃よりWEB情報活用の智恵が付き、事前の準備で効率的に探せるようになった。とくに殆ど土地勘がない地域でも地図検索で駅の出入口が判ったり、航空写真で幹線道路の横断歩道の位置まで判るのがありがたい。(平成19年10月) 3年前の調査でもやはり揺光之部よりはこの両篇のほうが手慣れていたようだ。揺光之部の再訪調査には7か月を要したのに対し、平成19年にも勝る猛暑だった今年に6か月で再訪再編できたのは前回不十分だった箇所が少なかったことが大きい。(平成22年12月) |