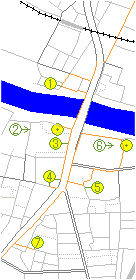| 土手通り〜今戸 |
<開陽之部の巻末は、現代の足立区竹の塚東部から浅草裏の橋場に戻って今戸へ来て新吉原で終わっている。当初の長秋のルートには無かったのを月岑が付け足したかのようである。本節はその部分である。>
本篇の出発地は東京メトロ日比谷線の三ノ輪駅とする。自転車をぶら下げて駅北口地上に上がると、昭和通り(日光街道)と明治通りの交差点、大関横丁である。北北東から南南西の日光街道は後日の探訪ルートになるが、今回は明治通りで左(東南東)に進む。
200m余りの三ノ輪2丁目交差点で明治通りは広幅員のまま東に30度ほど曲がる。自動車と共に車線で直進するのはリスクが高いので、交差点先のゼブラマークでこれを渡って土手通りを東南に進むと左上図の上に出てくる。
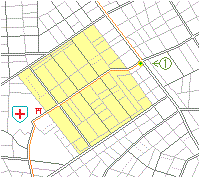 吉原大門交差点を過ぎて右に渡ると何代目かの移設された見返へり柳(左上図①←先)が街路樹風に立っている。移植されたと案内板にあるが、図会の絵でも土手通り沿いである。旧土手通りはひとつ北の通りかもしれない。
吉原大門交差点を過ぎて右に渡ると何代目かの移設された見返へり柳(左上図①←先)が街路樹風に立っている。移植されたと案内板にあるが、図会の絵でも土手通り沿いである。旧土手通りはひとつ北の通りかもしれない。ここから1街区入って左上図で黄色く塗った範囲が新吉原遊女町の跡である。吉原大門は道が斜めになっているところにあった。
現在では、仲之町通に面して大門から100mほどは高級キャバレーなどとなり、昼間から黒服が表に出て客を引いている。それを過ぎると表は飲食店もあるが、一歩左右に入るとソープランド街である。さらに奥は安宿と言ってよいホテルがいくつもある。 仲之町通を通り過ぎて道は再び曲がっているが、ここは明治以降公立の吉原病院という性病対策の専門病院が設けられていたところである。平成18年に訪れた時は、何もなかったがその後区立台東病院が開設されている。その手前には、吉原神社がある。往時遊女たちが身請け人の出現を祈ったであろう小さな稲荷神社が郭内あちこちにあったのを明治になって統合して設けたものである。 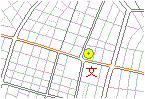 この先道なりに進んで二つ目の信号が六差路の北千束三丁目交差点である。左鈍角の道を進んで500mに浅草警察署がある。その対角に本頁末の図版金竜山浅草寺(五)の中央遠景に「富士」と付注された浅草富士浅間神社(現代の名:右図)がある。因みに同図版の左遠景には大きな築地塀が描かれている。先ほど通り過ぎてきた「新吉原」であるが付注してなくてもだれでも判ると言うことだろう
この先道なりに進んで二つ目の信号が六差路の北千束三丁目交差点である。左鈍角の道を進んで500mに浅草警察署がある。その対角に本頁末の図版金竜山浅草寺(五)の中央遠景に「富士」と付注された浅草富士浅間神社(現代の名:右図)がある。因みに同図版の左遠景には大きな築地塀が描かれている。先ほど通り過ぎてきた「新吉原」であるが付注してなくてもだれでも判ると言うことだろうなお、現在の浅草5丁目から6丁目は、長らく「富士町」と名乗っており、神社前には富士小学校が健在である。 図会は日本堤という項を立てている。荒川・利根川水系の洪水から江戸を守るために、日本中の大名を動員して2ヶ月で土手を築いたのでこの名が付いたとの説に加えて、小塚原から南千住から橋場にかけての低い堤と合わせて2本だからとの説も紹介している。万葉集で「亦打山」と書かれ、待乳山、信土山とも記される山が堤防工事で削られたと次の真土山・聖天宮の項で書きしるしている。
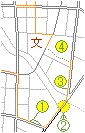
富士浅間神社から300mほどで広い道は左に折れるが、正面のガソリンスタンド左の一方通行出口の道に入る(左下図左上)。200m先で吉野通りを渡る(左下図中央)と、道の左が山谷堀公園になる。150mほどで右に園地への道があるのでそれを辿っていくと道路へ出るところに待土山聖天宮(左下図①)への上り階段がある。
本殿の前に出ると右に観音像がある。続く右手が社務所かと思うと本龍院という看板がかかっており、地蔵尊の案内がある。
ここの祭神は密教の系統の大歓喜天と毘沙門天で、管理運営している本龍院は墓を持たず、信徒のみのの寺である。いわば密教の神社とでもいう形態で、現在神社庁の管轄から外れている。しかし明治以降の十倍近い期間、弁財天、牛頭天などインド伝来の仏教の守護神を祀る場合はもとよりで、山王(権現)信仰などの土着の宗教、さらには高天原に本籍があって明治以降我が国の国教として扱われた神道の神社ですら別当寺に管理運営を委ねていた。
図会は何の不思議もなく、別当は、天台宗金龍山本龍院と号くと書いている。
「本龍院庫裡」との看板が覗える街区東南の角で石浜通りに左折して山谷堀公園のところに出ると、堀の埋め立てで役目を終えた
次の分岐信号で左に曲がったところに黒塗りの仁王像が立っている。慶養寺(左下図③)である。弁財天の境内と図会は書いているが、これは現存しない。 その北の街区に今戸八幡宮(現今戸神社:左下図④)がある。本殿東にあった別当の 境内を西に出て、都立浅草高校を反時計回りに回って裏のT字路(左下図上)を北に入っていく。 |
| 橋場 |
左の図で、下のほうに黄色く塗ってあるところは、前節の図の再掲部分である。車線区分のある東西の道路は交通量が少なく、そのまま北に突っ切れるが、マナーとしては西の吉野通りの東浅草三丁目交差手まで行って戻る。二つ目になる露地へ左折すると、左に窮屈そうに熱田明神(現熱田神社:左図①←先)がある。
図会は、本節で後述する駿馬塚とともに4節後の三ノ輪の仲間に入れて編纂している。しかし、熱田明神の南に駿馬塚があると書いており、これは現代の両者の配置とはまったく異なっている。絵で鳥居の前の通りに「千住通り」と書かれていることから熱田神社が泪橋近くにあって後に現在地に移転した可能性は残るが、調査未了である。
北に一街区進んで先を右折し、自動車一方通行を逆進する。150nほどの交差点に出て消防署の右に入り、次の十字路を左折すると、長昌寺(左図②)の入り口がある。
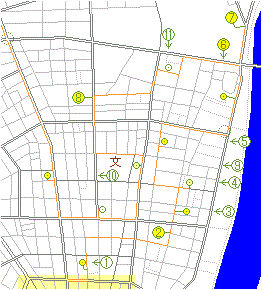 北に進んで100m弱の右に法源寺(現保元寺:左図③←先)がある。
北に進んで100m弱の右に法源寺(現保元寺:左図③←先)がある。
図会は、ここから石浜神明宮までを全幅4枚と半幅1枚の続き絵で描いており、名所地帯と認識していたようである。 保元寺から北へ1街区先の交差点の右向こうに福寿院(左図④←先)がある。東野先生之墓があると図会は書いている。(若くして柳沢吉保に引き立てられた儒学者で、結核で死んだ後に知己がまとめた遺稿集が評価されたとのこと) その交差点を左折、次の十字路を右折して150mほどの右に妙亀塚(明神)(左図⑤←先)がある。小高いところにベンチが置かれ、近所のお年寄りが時間を潰している。階段が運動になって街中を散歩するよりも健康の維持増進ためには良さそうだ。
隅田川右岸道路を北へ100m余りの左に砂尾不動(現橋場不動:左図⑥↓先)の入り口がある。図会では「橋場寺」とも言うと書いてあるが、現状は神社化して「橋場」の名が使われている。
明治通を渡って100m余り、当初探訪したときは工事中だったが、歩道と一体の観もある石浜城址公園が整備され、石浜神社(左図⑦)への参道の体もある。関東大震災後の大正15年に仏教の守護神である牛頭天(天王)も合祀していた朝日(石浜)神明宮に真先稲荷明神社合祀して「石浜神社」とした。さらに戦災復興で昭和29年にここに造営し直したと鳥居脇の碑に記録されている。60年経っても図会が描いているほどにも樹木が育っていないが、図会の風景とは良くフィットしている。 図会が記している天神(天満宮)、水神、手置帆負命・彦狭知命(現麁香神社)、さんけい石(現御百度石)や記述にない疱瘡神まで姿を変えて祀られている。招来(おいで)稲荷も図会が客観的に狐窟と付注したものかもしれない。 左歩道を西に進み、「平賀源内顕彰碑」が建っている辻を左に入り、二つ目の路地を右に入ると普段固く門を閉ざしている平賀源内の墓がある。 そのまま西に進んで石浜通りに出て南下しゴルフ練習場の手前を右折して突き当たると玉姫稲荷神社(左図⑧)である。玉姫稲荷から南下、 200mほどの十字路右先に保育園がるが、この十字路を左に入ったところに石浜小学校がある。 この小学校の敷地の大部分は、いくつもの伝説があった
鏡ヶ池に祀られていると図会が記した弁財天は付近に見当たらない。南下して今戸二丁目交差点を右折して次の信号を石浜小学校のほうに戻ったところの宝蔵院に弁財天があるが、これが鏡ヶ池から移設されたものであるかどうかは明示されていない。
吉野通りを北上400mで泪橋交差点(左図左上)であり、400mで南千住の駅である。
|
| 谷塚駅〜竹ノ塚駅 |
前節南千住駅から日光街道を来ると8kmで保木間の陸橋になる。西保木間交差点で右歩道に移り、そのまま分岐して旧四号国道(本来の日光街道)を300mで都県境になるが、その手前の毛長川沿い道に右折する。
出直しての谷塚駅スタート(里程表はこちら)は東口広場である。東の日光街道を横切って東へと進み、潮崎東横断歩道のかかっている交差点を右折し、都県境の毛長川を渡る。都側の広大な旧日本住宅公団の花畑団地との間に西から来ているのが日光街道経由のルートである。 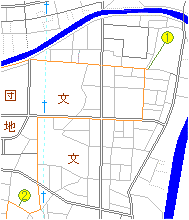 ほどなく左図の左になり、高圧線(左図の†が目の前を横切っている。その手前で川沿いを離れて高圧線の下を通ってひたすら進めば鷲大明神社(現大鷲神社:左図①)である。
ほどなく左図の左になり、高圧線(左図の†が目の前を横切っている。その手前で川沿いを離れて高圧線の下を通ってひたすら進めば鷲大明神社(現大鷲神社:左図①)である。
鳥居のやや西寄りの道を南に進んで突き当り、右折して再び高圧線を潜って信号手前の公園沿いの道に左折する。やがて団地の直線道路から旧い集落道路に替わると右が寺の塀になるので、時計回りに沿っていくと、正覚院(左図②)の入り口がある。 図会は鷲大明神の別当と記しながら、神社の風景に含まれておらず、当時から境内は離れていたようだ。 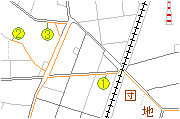 寺の西の十字路の一つ先の信号を左折(南下)し、300mほどの花畑中前交差点を右折、ひたすら直線状に進む。日光街道との交差点をそのまま直進すると右手向こうに清掃工場の赤白の煙突が見える。やがてアパート団地にぶつかるようにY字交差点になる(右図右下)。これを右へ進み、東武鉄道伊勢崎線のガードを潜る。ガード手前右には清掃工場の出口がある。
寺の西の十字路の一つ先の信号を左折(南下)し、300mほどの花畑中前交差点を右折、ひたすら直線状に進む。日光街道との交差点をそのまま直進すると右手向こうに清掃工場の赤白の煙突が見える。やがてアパート団地にぶつかるようにY字交差点になる(右図右下)。これを右へ進み、東武鉄道伊勢崎線のガードを潜る。ガード手前右には清掃工場の出口がある。ガード西の変則交差点を左にに入ってすぐ右に曲がると左の公園の中に八幡太郎義家東征に由緒を持つという白旗塚(右図①)がある。公園の利用者に荒らされないよう塚の周囲はフェンスで閉鎖されている。 そのまま西へ進んで、二重になっているような尾竹橋通の交差点を右側で渡り、北20mほどのインターブロック舗装の道に入る。右側に寺が続くようになり、その3番目が 尾竹橋通に戻り、北に進むと、左手に谷中三崎町から移転してきた 谷中三崎町では図会が清浄無塵の仏界にして、六時礼讃の声は、松風と共に寂々たりと書いている。寂れが進んで明治を迎え、その様子を見た円朝が怪談牡丹灯篭の舞台に仕立て、現在ではこれがこの寺の売りになっている。 花畑の大団地を始め、竹の塚は中層住宅団地の街である。熟知していれば団地内通路をうまく通り抜けて近道ができるが、初めての者にとっては、没個性的な羊羹型のアパートが殆ど同じ建築密度で繰り返されると、土地勘が働かなくなって不安になる。 これらの団地は、第一次ベビーブーマーの世帯形成と東京への人口集中の受け皿として建設された。少し前の世代の私もこのタイプの団地で5年ほど生活をした。建物床面積の敷地面積に対する割合(なぜか業界では「容積率」という)が76%とという建設基準で作られたこれらの団地は、現在では居住者の高齢化で諸活動の負担力が低迷し、建物の維持費の捻出も困難になりつつある。いっそのこと床面積を増やして新しい入居者の購入費で建設費を出せないかと花畑団地を含むあちこちの団地で建て替え計画が提案されている。しかし、高齢の入居者には生活環境や生活様式の激変を受け容れ難いうえに人口が減ることがはっきりしている以上安定的な住宅需要が見込めないことから、この提案をビジネスチャンスと見るプロは少ない。 尾竹橋通りを南下、700mほどでX字に交わる道路を左に採ると東武鉄道竹ノ塚駅である。
|
| 竹ノ塚駅〜西新井駅 |
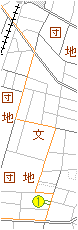
前節竹ノ塚駅の南のガードから100mほどの信号で右に入り(左図上)、300m余りの次の信号(竹ノ塚小学校)を左折し、学校の東角で南に曲がる。250mほどで突き当るので左に進み、次を右折する。
すぐ右に八幡宮(現六月八幡神社:左図①)と其別当と図会が記す炎天寺(左図①)が鳥居と山門を並べている。境内はほとんど一体である。 炎天寺は、小林一茶の「瘠せ蛙負けるな一茶これにあり」が炎天寺で詠まれたことを由緒として、句碑が建てられ、句会が盛んなようだ。一茶は図会初版のころに江戸に出てきて活躍していたが、評価が確定していなかったのか図会は書いていない。 炎天寺の東南東500mほどに「島根鷲神社」がある。図会は記していないが前節の大鷲神社の末社だったようで、こちらでも酉の市が行われている。
一街区南の道路に出て右歩道のまま右折、車道とは別に緩やかな勾配の跨線橋で東武伊勢崎線を越える。すぐの交差点で南北に走っているのが尾竹橋通りで、これを左折し、適当なところでブロック一つ西の道路に移ってさらに南下すると右図右上に出てくる。 東武鉄道大師線の下を潜ると環七(環状七号線道路)が東西に走っている。
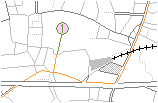 この寺の現代の売り物の自動車本体への交通安全祈願を受けに裏門から境内へ盛んに車が入ってくるので、要注意である。また、大師前駅からの門もオープンになっており、境内の東側は賑わいというよりも雑然、騒然と言ったところである。
この寺の現代の売り物の自動車本体への交通安全祈願を受けに裏門から境内へ盛んに車が入ってくるので、要注意である。また、大師前駅からの門もオープンになっており、境内の東側は賑わいというよりも雑然、騒然と言ったところである。イメージマップは寺のサイトにお任せするが図会が付注して描いている 都心に戻るには、環七を東へ(右歩道で)進んで東武伊勢崎線の鉄橋の手前を右へ100mで左に西新井駅の西口が見える。 続けて走る場合は、右図左下の環七から左斜めに岐れる道を進む。 |
| 荒川左岸・隅田川右岸行ったり来たり |
前節の環七から南西へ1km弱で、日暮里舎人ライナーが上空を走る尾久橋通りに出る。ここで左折してまた1km弱南下しての信号(二つ目:東西の道路は江北橋通り)の向こうに扇大橋駅への階段がある。都心からの出直しで日暮里からこの電車(新交通システム)でここに来ることもできる。
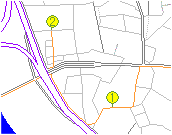 この交差点を江北橋方向(西)に向かい、300m弱の信号(左図右端)を左に入り、次の辻を右に曲がったところに性翁寺(左上図①)がある。行基が延命寺の本尊を含む六体の阿弥陀像を創った際に余材でこの寺の阿弥陀如来をも創ったとのことで、余木寺とも呼ばれてきた。
この交差点を江北橋方向(西)に向かい、300m弱の信号(左図右端)を左に入り、次の辻を右に曲がったところに性翁寺(左上図①)がある。行基が延命寺の本尊を含む六体の阿弥陀像を創った際に余材でこの寺の阿弥陀如来をも創ったとのことで、余木寺とも呼ばれてきた。
戻って江北橋を渡り、すぐ右折して下りて行く。途中分岐信号を右に行くのだが、交通量が多かったら少し先の堤防から降りる歩行者用信号まで行き、階段を下りるか折り返してヘアピンで車道を下りるかである。道なりに進むと小台橋である。 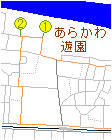 小台橋を右歩道で渡りきったらすぐ右折する。ぶつかったら左、次は右を繰り返すと荒川区立あらかわ遊園の正面に出る(右図)。荒川区の西端で、拡大地図を見ると一部の土地は北区になっているようである。
小台橋を右歩道で渡りきったらすぐ右折する。ぶつかったら左、次は右を繰り返すと荒川区立あらかわ遊園の正面に出る(右図)。荒川区の西端で、拡大地図を見ると一部の土地は北区になっているようである。通り過ぎてすぐの右に参道があり、図会が船方村の鎮守と記した十二天森(現船方神社:右図①)である。足立姫伝説で侍女たちの骸は上がったが姫は不明とのことで、侍女たちの塚(十二天塚)が御神体ということになる。 鳥居の前を左に細い道を進んでいくと、図会が記していない「延命寺」(右図②)がある。右上の雑学で書いたように、船方神社の別当だったから足立姫とは関係はあっても六阿弥陀とは関係がないようだ。 図会は富士浅間祠の項を立てて足立姫伝説などを紹介している。しかし、足立姫よりはるかに後の富士講信仰の名が付いた祠はこの辺に見当たらないし、船方神社に合祀されたのかどうかも判らない。 寺の前を南へ進むと都電通りに出、左折して尾久橋通りの熊野前交差点まで東進する。ここは橋を間近にした立体交差になっているので、左折して側道を進んで尾久橋の南詰で階段を上がって本節冒頭で紹介した日暮里舎人ライナーとともに隅田川を渡る。 扇大橋を渡らずに扇大橋南交差点で右折、荒川と隅田川に挟まれたところを東へ進む。久しぶりに車道を避けて荒川の河原の道を自由に走るのも一法である。  西新井橋まで来たらこれを北に渡る。渡り終わって堤防の上の交差点を右へ行き堤防下へ降りると梅田排水機場交差点である。そのまま川を離れる道に入って300mの手前に本節冒頭に登場した江北橋通りの未完成部区域がある(当初訪れた平成18年末は先行買収済みの空地ばかりだったが、9年近く経った平成27年夏でも重車両を除外しての地域の人達が通行できる部分舗装が市松模様である)。完成後は北側歩道に相当するところを入るとすぐに左が寺の塀になる。
西新井橋まで来たらこれを北に渡る。渡り終わって堤防の上の交差点を右へ行き堤防下へ降りると梅田排水機場交差点である。そのまま川を離れる道に入って300mの手前に本節冒頭に登場した江北橋通りの未完成部区域がある(当初訪れた平成18年末は先行買収済みの空地ばかりだったが、9年近く経った平成27年夏でも重車両を除外しての地域の人達が通行できる部分舗装が市松模様である)。完成後は北側歩道に相当するところを入るとすぐに左が寺の塀になる。
図会の絵では、「梅田天神祠」「不動堂」「別当明王院」とキャプションが付き、文では萬徳山明王院、梅林寺と号すとなっている。八幡太郎義家のひ孫が造った祈願所を原点とし、興廃の末徳川幕府から寺領を得たとあり、神仏混交の典型である。現在境内で目立つのは赤い不動堂である。 寺の正面を東へ向かうと、道が広くなるがすぐ突き当る。左クランクに進んで梅田街道(日光御成り道)に出る左角に「石不動」という小さな祠がある。北の梅島駅から御成り道を南下してきたときには、これが明王院への目印である。南へ150mほどで左から江北橋通りの完成部分が来ている(左下図右端:右側は未買収地も残っている)。これを400mほど東へ進むと、日光街道梅田交差点である。ここを右折すると千住新橋なのだが、まったく自転車を考慮していない橋の取り付けになっている。バイクと一緒に車道を行くには側道に進む車に注意して織込み走行をすることになるし、側道を行くと折返し100mもある歩道を歩行者と一緒に一旦東のほうまで歩くしかない。 |
| 北千住と南千住 |
| 国際通北部〜根岸 |
日光街道に戻って南へ500mほどで常磐線を潜り、さらに150mで本篇の出発地点だった東京メトロ三ノ輪駅の北口がある大関横丁交差点になる。
ここから右2kmほどの地区が三河島だが、三河守が住んでいたのでこの地名が付いたと推測、併せ萬里居士もこの辺に住んだようだとしているだけで、特定の名所を紹介していないので、ルートに入れずにパスする。 日光街道は大関横丁から昭和通りになる。しかし、120mほど先の三ノ輪交差点で昭和通りと分れ、左向こうから合流してきている国際通に入る(左図右上)。 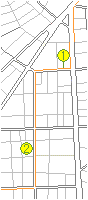 次の交差点で右歩道に移ると直ぐに「一葉ゆかりの千束稲荷」の看板があるのでこれを右に入る。
次の交差点で右歩道に移ると直ぐに「一葉ゆかりの千束稲荷」の看板があるのでこれを右に入る。千束稲荷(現千束稲荷神社:左図①)は、千束郷の叢祠と図会は書いているが、現在では街中の明るい神社として立派な社碑が立っている。
正燈寺の前をそのまま南へ進み、次の信号で右折する。昭和通りに出て渡り、更に進んで次の信号を過ぎた右に安楽寺(右図①)がある。
さらに進んで根岸四丁目交差点を右(北)へ50mのところ右への分岐路の角に時雨岡不動堂(右図②←先)がある。あるといっても、 図会でコメントされている「御行の松」は枯死、後に掘り起こした根が飾られて説明の立て札が立っている。 道を南に戻って交差点を過ぎて右に塀の外側を有料駐車場にしている「西蔵院」(右図③)がある。 時雨の岡不動堂はこの寺の境外の堂宇ということである。 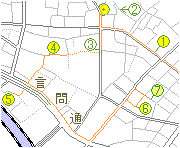 西蔵院の南に「根岸の里公園」があるが、これが図会が描いた右の絵(根津の里)の場所とは思えない。
西蔵院の南に「根岸の里公園」があるが、これが図会が描いた右の絵(根津の里)の場所とは思えない。公園の寺側の道を西に通り抜けて出た道をそのまま前に進んで50m、右に円光寺(右図④)がある。 俗称「藤寺」は図会の時代からで、現存する藤棚の藤は蔓というよりも木である。訪れたのは藤の季節ではなかったが、適期にはさぞかし素晴らしい景観だろうと思われた。現代は、図会に描かれていない屋外の観音像が目印にもなっている。 寺の少し西を南に入る道を辿って言問通に出ると、上野桜木町から鉄道を跨いで下りてくる言問通りの高架がある。この下を向こう側に渡る歩道がるので、これを使ってJR鶯谷駅側に渡る。そのまま飲み屋街(というよりも風俗店街に)を抜けて駅北口に抜ける小路があるので、これを入っていくと場違いな感じで「元三島神社」(右図⑤)がある。 ここは、駒形で記されている三島神社の旧地とのことであるが、神社の風情は移転先よりもしっかりと残っている。しかし、駅のほうへ進んで裏から見ると、本来参集殿として計画されたであろう本殿下は飲食店に賃貸されていた。 戻って言問通りの高架下を抜けて右折、根岸一丁目交差点で金杉通りに左折する。気付きにくいが、次の信号の右向こうに小野照崎明神(現小野照崎神社:右図⑥)への入り口がある。
入ってきた並び鳥居を出て右に進んで次の右ブロックに小野照崎神社の別当と記されている小野山嶺松院(現小野照山嶺照院:右図⑦)がある。当初文字違いもあって見落とし、再訪時(平成22年8月)は工事囲いに包まれていた。改めて訪れてみると経営する幼稚園と一体の建築になっており、左右の門柱それぞれの山号と院号にはいずれも「照」の字が彫られている。神仏分離令への反発か図会のミスか。 次節へは、金杉通りに戻って左折、言問通りを渡って上野駅方面に向かう。 |
| 坂本〜新寺町西部 |
根岸一丁目交差点で言問通を横切ると間もなく、前方に新幹線をはじめとするJRの電車が走るのが見える。いよいよ近づくと道は左に曲がり、上野郵便局になる。
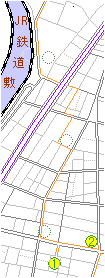 この郵便局から南へかけての位置に
この郵便局から南へかけての位置に道路を挟んで線路敷になっているところには、 左へ曲がって首都高速の下を抜けて左寄りの狭くなった道を進み、二つ目の左に入る小路に入る。ぶつかったら左クランクで上野学園大学の西の道を進む。
ぶつかって左へ進んでバス通りに出たら右折する。保健所と区役所があるこの通りの浅草通りに出る手前に 左図の幡随院から広徳寺を結ぶ線から浅草寺の西までの区域が、明暦の大火(振袖火事)で罹災した寺の集団移転先となった「新寺町」である。この地域の西が「(上野)山下」であった。図会は山下を開陽之部に収録している。しかし、紹介する名所は現御徒町駅西側が主体であるので、この探訪記録としては上野公園(東叡山)と一緒に玉衡之部で収録する。
以上4連続移転済み旧地になった。それだけ、時代の波の大きかった地域とご理解いただきたい。
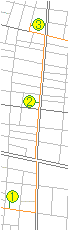 明治新政権の国家神道政策に添って近くにあった歳神(元来は土俗信仰)の祠を合祀し、事業成就の祭神白狐の姿は影をひそめてしまった。図会が別当と記している正法院はさらに痕跡を残していない。
明治新政権の国家神道政策に添って近くにあった歳神(元来は土俗信仰)の祠を合祀し、事業成就の祭神白狐の姿は影をひそめてしまった。図会が別当と記している正法院はさらに痕跡を残していない。浅草通りに戻って右折、稲荷町駅の入り口の先を左へ曲がったところに永昌寺(左図②)の入り口がある。 稲荷町交差点で浅草通りと交わっている清洲橋通りで南へ三つ目の小路を左折し、二つ目の小路の角に長遠寺(右図①)がある。図会は日蓮大士像を名所としているが、像は現存しない。 2街区東の2車線道路を北へ向かい、松ヶ谷2丁目交差点で浅草通りを渡って北へ進む。二つ目の東上野六丁目信号先左に
図会では東本願寺の東隣として記し、描いている。次節でリンクする新寺町総図を参照されたい。
北へ250m余りの松が谷二丁目信号を左折、次の右の小路を入ったところに赤城山燈明寺(右図③)がある。信州善光寺の燈明にいわれがあり、赤城明神を併設していると図会にあるので中に入りたかったが、門は閉じられひっそりとしていた。塀越しに墓地の上空全面に立派な藤棚が見え、シーズンはさぞやと思われた。
東西の通りは合羽橋通りで、これを東(合羽橋交差点方向)へ進む。 |
| 新寺町 |
松が谷二丁目の次の信号を過ぎると、図会には登場しないが霊梅寺というゆかしい名前の寺があり、その先左の奥まった所に海禅寺(左図①)がある。明暦の大火で湯島から移転したとの記述。
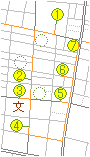 実相寺は、道を戻って信号を左折する角の街区の位置に描かれているが、消息不明である。同様に除厄太子堂が紹介されている慈眼院が曲がって100m程先の右のブロックの位置に描かれているが、不明である。
実相寺は、道を戻って信号を左折する角の街区の位置に描かれているが、消息不明である。同様に除厄太子堂が紹介されている慈眼院が曲がって100m程先の右のブロックの位置に描かれているが、不明である。その南の本覚寺(左図②)は健在である。その南の街区に本尊聖徳太子像で明暦の大火で馬喰町から移転したと書かれている聖徳寺(左図③)は南が正面である。 この街区の東側に隆光寺が描かれているが、これも消息不明である。
松葉小学校の南に祝言寺(左図④)がある。江戸城近くの祝言村にあったと図会が書いているのも、一般に「祝言」は結婚式を指すので寺の名として不思議だからだろう。 その先の十字路を左折して100mほどで「合羽橋道具街」に出る。さらに左折して、100m程の合羽橋南項s店を左折してすぐ北側に正定寺(左図⑤)がある。幼稚園の一部が寺と言う風情で、学校法人の立場のほうを宗教法人の立場より重んじている雰囲気である。 一街区挟んで北に松源寺(左図⑥)がある。正定寺同様南向きで、鉄骨可働フェンスの門(というか入り口)である。 合羽橋道具街の中央がこの先の合羽橋交差点である。その手前に、慈覚大師直彫りの観音像が本尊との清水寺(左図⑦)があるが、境内後方のマンションと道路の間の小さなビルが寺で、看板も寺らしくないのでうっかりすると見落としそうだ。この寺は浅草橋からの振袖火事移転組である。 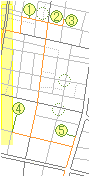
右図の左、黄色くなっている範囲は、左図と重複表示になっている
合羽橋交差点を東(右)に入る。次の左の道に入り、次の十字路を右に曲がった左に東光院(右図①)がある。小伝馬町からの振袖火事移転。
その東の街区に、関東大震災後世田谷の北烏山に移転した その東が天嶽院遍照寺(右図②)で、図会は宋伝来の本尊で清水寺と一緒に移ってきたと書いている。 さらに東の街区に西を正面にしている日輪寺(右図③)がある。図会のスタートの地、千代田区(芝崎村)から移転してきたため「神田山」と名乗り、かつては神田明神の別当であったり、平将門の法要をしていたと記されている。 天嶽院の西に戻って左折、南下する。200mほど先の左の広い範囲に、振袖火事で神田から移転した そのまま進んで次の信号の右向こうの街区が東本願寺の街区(右図④)である。浅草通りからの参道があるので街区南側に回り込む。150年前で来訪が途絶えていたにもかかわらず朝鮮通信使の旅館と図会は書いている。現在の境内には軍国主義の兆しを憂えている昭和始めの「憲政の碑」が残っている。
勢力分散のため秀吉から東西に分けさせられた浄土真宗本願寺派であるが、明暦の大火でそれまで浅草にあった西本願寺が築地に移り、神田にあった東本願寺が浅草に移った。東本願寺派は、京都の本山が宗派抗争で消滅し、平成になってこの東京の東本願寺を本山として浄土真宗の正統として再構築された。 正面前を東に折り返してそのまま200m程進み、国際通りに出る。左折してすぐ左に清光寺(右図⑤)の入り口がある。昭和の名優長谷川一夫の墓が現代の名所?小さめの藤棚が品良く色を添えていたが、境内は立体駐車場を業としているかのようだった。
図会は清光寺の北側に前節紹介した報恩寺を描き、東本願寺の東と記している。 国際通りを右歩道のまま南に向かい、寿4丁目交差点(地下は東京メトロ田原町駅)で浅草通りを渡る。 |
| 田原町〜浅草橋 |
田原町駅のある浅草通りの寿四丁目交差点の次の小路を右に入る。
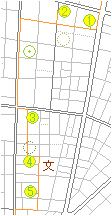 すぐ右に金竜寺(左図①)がある。 東伊興の寺町に昭和の始めに移転した
すぐ右に金竜寺(左図①)がある。 東伊興の寺町に昭和の始めに移転した一つ西の十字路を過ぎて浅草通りから南へ一方通行の道を右に入って直ぐ右の本法寺の境内に、浅草神社(当時は三社権現:2節先参照)境内にあった 西へ進んで、菊屋橋交差点からの新堀通り(浅草通りから北は合羽橋道具街)に出て左折(南下)する。前節の東本願寺辺も含めて新堀川沿いを新堀端と呼び、その中心部として右の図版が描かれている。 まずは龍宝寺であるが、直線距離で200m南北に離れて二つ同名の寺がある。北は通称鯉寺(浄土宗)、南は通称川柳寺(天台宗)である。
龍宝寺前の狭い小路をそのまま南に進んで突き当る手前に東漸寺があったようだが、その後のことは判らない。突き当りが浄念寺(左図④)である。
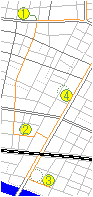 新堀通りに戻って南へ100m足らずで蔵前橋通りに出る。右歩道のまま西へ向かって100m余りのところに鳥越明神社(現鳥越神社:右図①)がある。東京にある名称に鳥が入っている神社では最も古く、大川(隅田川)を自由に越える鳥に憧れた人々が祀り始めた神社とのことである。
境内には震災復興区画整理の測量原点の碑があるほか、蔵前橋通りに面した鳥居に鳩山一郎の戦後の寄贈と彫られている。
新堀通りに戻って南へ100m足らずで蔵前橋通りに出る。右歩道のまま西へ向かって100m余りのところに鳥越明神社(現鳥越神社:右図①)がある。東京にある名称に鳥が入っている神社では最も古く、大川(隅田川)を自由に越える鳥に憧れた人々が祀り始めた神社とのことである。
境内には震災復興区画整理の測量原点の碑があるほか、蔵前橋通りに面した鳥居に鳩山一郎の戦後の寄贈と彫られている。神社前の交差点を渡ってJR浅草橋に向かう。道なりに南へ進み、浅草橋の高架駅が見えたら、一つ手前の交差点を左折する。ぶつかってもう一度左折すると銀杏八幡宮(現銀杏岡八幡宮:右図②)である。名前のとおり境内は銀杏の樹ばかりであるが、揺光篇の本八幡の千本公孫樹のような大木はなく、いずれも百年未満の樹である。 江戸通りへ出て右の浅草橋駅は都営地下鉄の駅もあり、雛人形や玩具のブランドメーカーが近くにあることから夏の盛りを除いては人ごみが絶えない。駅前交差点で道を渡りガードを潜って橋北の信号のところ左折する。1街区目には 2街区目の東南角には篠塚稲荷社(現篠塚稲荷神社:右図③)がある。
戻って江戸通を北上する。左歩道ぴったりに鳥居があり、須賀神社とある。図会の時代には祇園社(牛頭天・十王天)(右図④)と言っていたが、明治以降スサノオの尊を祭神として名称を変えたものである。別当の大圓寺は手掛かりがない。 その北というか同一境内にあったはずの 江戸通りをさらに北に進む。 |
| 蔵前〜駒形 |
前節須賀神社の直ぐ北の信号が須賀橋交番前交差点である(左図左下)。この信号で江戸通りを東に渡って入っていく。この交差点には隅田川に向かって向きを変えていた新堀川を南西から北東に渡る橋があり、その橋の名が残っているものである。

この一角から隅田川までの200m前後の幅の川沿いで厩河岸渡までの間には、江戸時代幕府の米蔵が建ち並んでいた。その西の一般市街地を含めて図会は前節図版など「大倉前」と書いている。「御蔵前」と書くこともあり、これが現在のこの地域の地名「蔵前」のゆえんである。
江戸通りへ戻って右歩道のまま北へ向かう。第六天社は100年余り前まで次の蔵前一丁目交差点の左にあったと図会は記している。この交差点を隅田川に向かっての中ほど北に昭和59年まで国技館があった。(以上の補足は右「蔵前河岸の変遷」参照)。 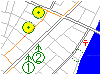 次の蔵前二丁目交差点は左へ国際通りが分岐して大交差点になっている。右歩道のまま走ってきたのは、自転車には右分岐しにくいこの交差点を避けるためである。次の蔵前三丁目交差点で江戸通りを西へ渡る。(右図左下端)
次の蔵前二丁目交差点は左へ国際通りが分岐して大交差点になっている。右歩道のまま走ってきたのは、自転車には右分岐しにくいこの交差点を避けるためである。次の蔵前三丁目交差点で江戸通りを西へ渡る。(右図左下端)30mほど入っての角を右(北東)に曲がって2街区進むと、石清水正八幡宮(現蔵前神社:右図①↑先)が左にある。この神社には、蔵前国技館時代の力士の奉納したものが残っている。 なお別当の
春日通りで隅田川を渡るのが厩橋である。右図でルートにしてないが、橋の手前を右に入って100mほどのところに東京消防庁のビルがある。その手前左に 春日通りと江戸通りの厩橋交差点には、大江戸線の蔵前駅がある。ところが同じ都営地下鉄の浅草線の蔵前駅とは構内では全く繋がっていない。浅草線の蔵前駅は榊神社の後渡った蔵前3丁目交差点にあり、両駅は約300m離れており、地上に出て12分歩いて乗り換えることになっている。おのぼりさんや高齢者の戸惑いが必至の駅である。 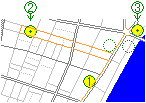 諏訪明神社(現諏訪神社:右下図①)は、厩橋交差点から江戸通りを北(東)へ250mにあるが、自転車でも一瞬で通り過ぎてしまうほどの小さな神社である。図会の時代にも小規模だったようだが、至って久遠にして来由詳ならずとなっている。
諏訪明神社(現諏訪神社:右下図①)は、厩橋交差点から江戸通りを北(東)へ250mにあるが、自転車でも一瞬で通り過ぎてしまうほどの小さな神社である。図会の時代にも小規模だったようだが、至って久遠にして来由詳ならずとなっている。諏訪神社の北にそびえるビルの角にウルトラマン人形が建っている。おもちゃのトップメーカーバンダイ(+ナムコHD)の本社である。この北の街区にはすでに図会の時代に創業していた「駒形どぜう」がある。その先を左に入り、ひたすら西に進んで300m付近の右に三島明神社(現三島神社:右下図②↓先)がある。 しかし、こちらも注意していないと気付かずに通り過ぎて国際通りに出てしまう。
現在の上野動物園のあたりにあった弘法大師ゆかりの稲荷が、元禄時代に三島神社とともに移転してきたと文でも絵でも紹介している清水稲荷社は、江戸通りに出る角にあったはずだが痕跡もない。現在は銀行になっている。 駒形西詰交差点は変則五叉路なので、信号サイクルが長い。次を考えるとまず江戸通りを右歩道に渡り、そして左(北)に渡る。そこにある駒形堂(右下図③↓先)は、清水稲荷と道路を挟んで向かい合わせの位置にあったが、駒形橋の架設に伴う既存家屋の移転などで、100mあまり北の現在地に移動したものである。禁殺碑はかなり傷んではいるが、存置されている(右図版の私的コメントをどうぞ)。 同じ交差点を左よりの雷門正面に向かって入っていく。 |
| 浅草寺とその周辺 |
前節から入ってきた通りは、図会で並木町と記されており、1966年まで浅草並木町として町名は残っていた。図会の時代には、風雷神門(雷門は現在も通称らしい:左図①→先)を東へ100m余りの吾妻橋西詰交差点の一角(2020東京五輪マラソンの折り返し点)に
雪旦は半紙20枚分を使って浅草寺とその周辺の様子を描き、長秋は極めて詳細に記述しており、図会全七巻の第六巻冒頭が全体の焦点であるかのような印象になっている。浅草寺は、神仏習合の最も進んだものであったがその人気は絶大であったから、明治新政府の廃仏毀釈策にも苦心の跡が見える一方、多くのものが残されたり、被災しても復興されている。
雪旦の絵の番屋とほぼ同じ位置の道路際に交番がある。
交番に咎められるまでもなく、混雑時は仲見世の間は自転車を押して進むしかないが、仲見世の裏は乗って行ける。仲見世の裏に何があったかは、絵を見ていただけば判るが、これを現代の地図に落としてみたので、クリックしてみていただきたい。(これらを始め、以下記述の少ない境内の諸寺社のフォローは省略)
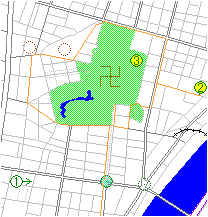
伝法院通りに出たら左折する。この通りは、商品配送の車も走る輻輳した道になっている。国際通りに出る手前の交番のある五(六)叉交差点は、六区の中心で、この南北は戦前わが国最大の興行街、娯楽街であった。
昭和40年代からの高度成長で、産業労働者の配置や労働形態の変化、マイカーブームなどによって娯楽の多様化が進みこの界隈は舞台芸人たちの修練の場や安キャバレーなどに変わっていった。しかし、国際通りにつくばエキスプレスの浅草駅(最初は「新浅草駅」と言っていた。)が設けられてから人通り(旅行案内片手のアジア系外国人が目立つ)が増え、街にはさまざまな新しい店が展開している。 この交差点を北に進んでの突き当りの東西の道から北が第五区だった。関東大震災まで日本一の高層建築だった凌雲閣(浅草十二階)はこの突きあたりに、広大な花屋敷の園地を背景に建てられていた。その花屋敷は嘉永年間の開業のため図会には登場しない。現在の言問通りや国際通りに及ぶ第五区の大部分を園地とし、上野動物園を凌ぐ人気動物園を併設していた時期もある。現在は10分の1以下の規模になっており、150年の有為転変はこの間のわが国のレクリエーション史を映して激しい。わが国最古のローラーコースターもイベントの企画次第で動かすようで、経営がイベント用施設賃貸業のようになっている。 花やしき前を通り抜けて言問通りに出て右歩道のまま東へ進む。すぐ右の浅草寺病院は、図会で楊弓などの娯楽が描かれていた場所である。寺の慈善事業として始まったものが独立した経営になっているようである。その東にお寺の団地(左図で白ヌキにしてある)がある。元来は次の信号(馬道)の北部にあった浅草寺の末寺群(坊?)を集約したもののようだが、調べきれていない。
二天門前交差点に戻って左折し、次の信号を右に入ると銭瓶弁天(現在は単に弁天堂)の裏にぶつかる。反対側に回ると立札があり、鯨鐘(時の鐘)も現存している(鐘楼は空襲で焼失)ことがわかる。 南側の伝法院通りに出て右折すると、浅草寺境内の外周を時計回りに回り終える。ここから二王門(現宝蔵門)までは図会の時代も東側は店(絵 宝蔵門の手前右に
宝蔵門の左の図会が地主稲荷とえびすを描いた場所には、図会が描いていない三宝荒神堂と境内東側から移された 五重塔の北は広場になっているが、図会の絵では、毘沙門天以下六神ほどの名前が小さく書かれている。その北側の本堂寄りに、本節冒頭に書いた さらに西の境内の外とも思える場所に淡島明神社(現淡島堂)があるのはほぼ当時のままで、ほっとする。でも図会にコメントのない阿弥陀如来や2菩薩が合祀されているようで、かえって習合が進んでいる感がある。小さく その北の図会で念仏堂のある位置に立派な影向堂が建っている。説明板では平成5年までここにあった薬師堂を三峰神社横に移したとあるが、念仏堂の役割を復元して影向堂を設けたのなら図会をフォローする立場からは判りやすいのだが・・・・・。 本堂の裏、浅草病院と間はバス駐車用の広場が広がっている。
広場を東に抜けると三社権現(浅草神社)(左図③)がある。詳しくは右の「浅草神社の扱われ方」を・・・・・。右上の図版其五には秋葉・熊谷稲荷が描かれているが、安政元〜2年に新門辰五郎が勧請した引被官稲荷が建てられ、熊谷稲荷は2節前の寿町の本法寺に引き取られた。 神社南の鳥居に出てくると、すぐ左に随身門(現二天門)がある。 隋身門は、東照宮の分社が境内に設けらた際に右大臣左大臣を配して設けられた。
家光が立てた本堂は、安政、関東の二大地震には耐えたが、米軍の空襲で焼けおちた。15年後に雷門と一緒にRC造で再建されたが、耐震性不足とのことで補強工事が行われた。
図会は、浅草寺の遠景に浅草川を描き、地誌として宮(三屋)戸川という旧名を持ち、その沖で浅草寺本尊が網に入ったと書いている。寺島、柳島、牛島、大島、猿江、永代島などの地名が往時の海面の広がりを示しているとも書いている。 |
| 開陽之部を巡り終えて |
|
開陽之部は、現代の足立区、荒川区東部、台東区をカバーしている。この範囲を大きくは反時計回りに巡った。
明治までに既に市街化が進んでいた台東区の範囲は、明治以降の災害や空襲、そして経済発展の影響を大きく受けており、図会の時代の姿を残しているもののほうが少ない。同様のことは台東区と隅田川を挟んで対岸の揺光之部の本所地区でもみられた。 これらの地域の社寺は、震災、空襲、水害でそれぞれの堂宇を失っている。加えて一般市街地の被災者の救済のために境内を割いており、規模の縮小は元よりこれを契機に郊外移転をしたものも多い。 浅草周辺の再訪は平成22年夏の猛暑にぶつかったうえに、単なる筋肉痛と思っていた痛みが骨盤変形に起因していたことが判り、その治療を始めたこともあって、再編更新が遅れ気味になってしまった。次の玉衡之部は、図会中最も短いが、あまり遅れを取り戻すことを意識しないで続けたい。(平成22年9月) |